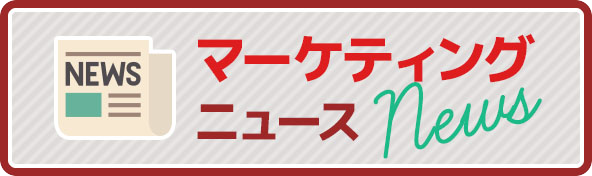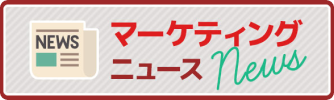- 検索
-
- テーマ別実施時期一覧
- カテゴリー別一覧
-
-
アルコール飲料・嗜好品145
-
非アルコール飲料209
-
その他19
-
-
住宅・住宅設備218
-
-
家電126
-
パソコン・カメラ・AV機器113
-
その他10
-
-
家庭用品・トイレタリー91
-
自動車・関連用品76
-
-
インターネット・情報通信327
-
携帯電話・スマートフォン180
-
メディア・広告66
-
その他7
-
-
ファッション68
-
交通・レジャー・娯楽161
-
季節行事・イベント241
-
時事・ニュース・トレンド51
-
企業ブランドイメージ246
-
広告・CM51
-
WEBサイトの利用91
-
顧客満足度100
- 実施時期別一覧
-
- 調査時期:
- 2022年10月
- 設問項目:
-
食事のデリバリーサービス利用頻度/利用しているデリバリーサービスの種類/食事のデリバリーサービス利用場面/食事のデリバリーサービスの店舗選定時の情報源/食事のデリバリーサービスへの注文方法/直近1年間に注文したデリバリーサービス/食事のデリバリーをする店舗選定時の重視点/新型コロナウイルス感染拡大によるデリバリーサービス利用状況の変化/今後デリバリーサービスを利用したい頻度/食事のデリバリーを利用したい場面/利用したくない理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■食事のデリバリーサービス利用者は全体の4割、そのうち月1回以上利用者は2割強。直近1年間デリバリーサービス利用者のうち「休日・夕食」が5割強、「休日・昼食」「平日・夕食」が各3割前後。過去調査と比べ「平日・夕食」が増加傾向。
■デリバリーサービス直近1年間利用者の注文方法は「店舗のWebサイト・アプリ」「デリバリーのWebサイト・アプリ」が各4割前後で、過去調査と比べ増加傾向。店舗選定時の情報源は「ポストに投函されるチラシ、ダイレクトメール」が3割強で、過去調査と比べ減少傾向。「デリバリーサービスのWebサイト・アプリ」「店舗のWebサイト・アプリ」は各26%。
■食事のデリバリー店舗選定時の重視点は「価格が手頃」が4割強、「味が好み」「手元にチラシがある」「メニューが豊富、注文可能なものが多い」が各3割弱。
■今後デリバリーサービス利用意向者の比率は5割弱、女性の方が比率が高い。デリバリーサービス利用者では8~9割、非利用者では2割弱。月1回以上利用意向者はデリバリーサービス利用意向者の2割強。男性や若年層での比率が高い。
-
- 調査時期:
- 2022年10月
- 設問項目:
-
ネットスーパー利用経験/ネットスーパー利用理由/ネットスーパー利用時の重視点/直近1年間の利用ネットスーパー/直近1年間の最頻利用ネットスーパー/直近1年間のネットスーパー利用頻度/新型コロナウイルス感染拡大によるネットスーパー利用状況の変化/ネットスーパー利用意向/ネットスーパーの不満点・改善要望(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■ネットスーパー利用経験は2割強、現在利用は1割強。現在利用者のうち、週1回以上利用者は1割強、月1回上利用者は5割強。コロナ禍により「以前はあまり利用していなかったが利用するようになった」「以前から利用しており頻度が増えた」「一時的に利用が増えたが以前と同程度に戻った」が利用経験者の各1割強。
■ネットスーパー利用経験者の利用理由は「重いもの・かさばるものを届けてくれる」が5割弱、「買い物時間を節約」「外出したくないときに便利」などが各3割強。
■ネットスーパー利用時の重視点は、「品揃えの充実度」が5割強、「送料の安さ」が4割強、「商品の価格」「品質の良さ」「配送の確実さ」が各30%台。
■ネットスーパー利用意向者は全体の2割強、現在利用者の8~9割、利用中止者の3割、利用未経験者の1割。
-
- 調査時期:
- 2022年10月
- 設問項目:
-
高齢家族との同居・別居状況/見守りサービス利用状況/利用したことがある見守りサービス/見守りサービス利用意向/利用したい見守りサービスの種類/利用したい見守りサービスの重視点/見守られる側になった際の、サービス利用意向/見守りサービス利用意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■離れて暮らす家族などの状態を確認・サポートする見守りサービスの現在利用者は約2%、利用経験者(現在非利用)は約4%。サービス認知・利用未経験者、サービス非認知者は各5割弱。別居している65歳以上高齢者がいる層のうち現在利用者は約4%。
■見守りサービス利用経験者のうち「定期的に訪問・電話などをし安否確認」「通報ボタンを押すと家族やサービス事業者へ通知」が各20%台。自治体サービス主利用者では「定期的に訪問・電話などをし安否確認」、民間サービス主利用者では「食事宅配サービスなどの配達時に安否確認し報告」「センサーを設置、異常時に通知」などが多い。
■見守りサービス利用意向者は全体の3割弱、非利用意向者は1割弱。利用意向者は、現在利用者の8割前後、利用経験者の5割強、サービス認知者・利用未経験者の3割強、非認知者の2割。利用したいサービスは「定期的に訪問・電話などをし安否確認」「要請があった際にサービス事業者が駆けつける」が利用意向者の各4割弱、「センサーを設置、異常時に通知」「食事宅配サービスなどの配達時に安否確認」が各3割強。
■見守りサービス利用意向者の重視点は「料金」が8割弱、「サービスの種類やプランの充実度」「料金体系のわかりやすさ」「緊急時対応のスムーズ・迅速さ」が各40%台。
-
- 調査時期:
- 2022年10月
- 設問項目:
-
冷凍食品利用頻度/利用する冷凍食品の種類/冷凍食品利用場面/冷凍食品利用理由/冷凍食品購入時の重視点/直近1年間に購入した冷凍食品メーカー/新型コロナウイルス感染拡大による冷凍食品利用頻度の変化/新型コロナウイルス感染拡大による冷凍食品利用状況の変化/気に入っている冷凍食品・気に入っている理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■冷凍食品利用者は全体の約85%。週1回以上利用者は5割強で、2019年調査より増加。コロナ禍により冷凍食品利用頻度が増えた人は3割弱で、減った人より多い。
■冷凍食品利用者のうち「中華系の軽食・おかず」「麺類」利用者が各5割強、「米飯類」が5割弱、「あげもの類」が4割弱。利用場面は「夕食」が利用者の7割弱、「昼食」5割強、「食事を簡単に済ませたい」「料理を作るのが面倒」「お弁当」「ふだんの食事のメニューとして」が各2割強。
■冷凍食品利用者の理由は「保存がきく」「すぐにできあがる」「手順が簡単」が各50%台、「調理や後片付けの手間が省ける」が4割、「少量必要なときに便利」が3割強。
■冷凍食品利用者の重視点は「味」「価格」が購入者の各7割前後、「容量、サイズ」が4割強、「原材料」「生産国・地域」「電子レンジ対応かどうか」「安全性」などが各20%台。
-
- 調査時期:
- 2022年10月
- 設問項目:
-
味噌汁を飲む頻度/市販の即席味噌汁を飲む頻度/即席味噌汁を飲む場面/よく飲む即席味噌汁のタイプ/即席味噌汁の好きな具/よく買う即席味噌汁のメーカー/即席味噌汁を選ぶ際の重視点/気に入っている即席みそ汁と、気に入っている点(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■市販の即席みそ汁を飲む人は約75%、そのうち週1回以上飲む人は4割弱。「個包装/生味噌」を飲む人が即席みそ汁飲用者の約75%。「個包装/フリーズドライ」は4割弱で、過去調査と比べ増加傾向。
■即席みそ汁の好きな具は「豆腐」「わかめ」「ねぎ」が各6割弱、「油揚げ」が4割強、「しじみ」「あさり」「なめこ」が各30%台。過去調査と比べ「なす」が増加傾向。
■即席みそ汁を飲む場面は「家での夕食」が4割強、「家での昼食」「家での朝食」が各20%台。「みそ汁を作るのが面倒なとき、作る時間がないとき」は2割強。「家での夕食」は若年層での比率が高い。
■即席みそ汁選定時の重視点は「具材の種類」「味噌の味・種類」「価格」が購入者の各6割弱。
-
- 調査時期:
- 2022年10月
- 設問項目:
-
アルミパック入りゼリー飲料の飲用頻度/直近1年以内に飲用したアルミパック入りゼリー飲料銘柄/直近1年以内に最もよく飲用したアルミパック入りゼリー飲料/アルミパック入りゼリー飲料飲用理由/アルミパック入りゼリー飲料飲用場面/アルミパック入りゼリー飲料購入時の重視点/アルミパック入りゼリー飲料の飲用意向/アルミパック入りゼリー飲料の不満点・非飲用理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■アルミパック入りゼリー飲料飲用者は全体の約35%、そのうち週1回以上飲用者は1割強。今後の飲用意向は全体の3割、月1回以上飲用者の8~9割、非飲用者の約5%。
■アルミパック入りゼリー飲料飲用理由は「エネルギー補給」「味が好き」が飲用者の各30%台、「摂りたい栄養成分が入っている」「価格が手頃」「食欲がない時や体調が悪い時でも飲みやすい」などが各20%台。「食欲がない時や体調が悪い時でも飲みやすい」は女性30~50代での比率が高い。
■飲用場面は「おやつ」「体調が悪い」「小腹がすいた」「食欲がない」などが飲用者の各2割前後。蒟蒻ゼリータイプを飲む人では「おやつ」「小腹がすいた」など、アミノバイタルゼリー主飲用者やヴァーム主飲用者などでは、運動・スポーツの前後や途中の比率が高い傾向。
■アルミパック入りゼリー飲料購入時の重視点は「味」が飲用者の6割強、「価格」が4割強、「フレーバー」「効能」が各30%台、「栄養素」「成分、添加物」などが各20%台。
-
- 調査時期:
- 2022年09月
- 設問項目:
-
1年前と比べた、生活全体の支出額の変化/1年前と比べた、生活全体の収入額の変化/1年前と比べた、購買意欲の変化/1年前と比べてお金をかけていること/今年お金をかけるのを我慢している分野/消費行動スタイル/消費に関する考え方・行動/今後1年間の購買意欲の変化/今後1年間の購買意欲変化の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■1年前と比べ生活全体の支出額が増えた人は4割弱で、2021年調査時より大きく増加。支出額が減った人は1割強。収入額が減った人は3割弱、増えた人は1割強、「変わらない」は6割強。
■1年前と比べ購買意欲が低い人は3割弱、購買意欲が変わらない人は6割弱。今後1年間の購買意欲が低くなると思う人が2割強で、2021年調査よりやや増加。購買意欲が変わらないと思う人は7割弱。
■1年前よりお金をかけていることは「食品・飲料」が3割強。「旅行、レジャー」「外食、グルメ」はそれぞれ約15%で、2021年調査と比べやや増加。また、1年前より収入が増えた層での比率が高い。
■今年お金をかけるのを我慢しているものは「旅行、レジャー」が4割弱、「外食、グルメ」が2割強、「映画、ライブ、演劇、美術展など」「友人知人とのコミュニケーション」が各8~9%で、いずれも2021年調査より減少。消費行動では「節約はしつつちょっとした贅沢も楽しむ」が約36%、「常に節約を意識」「必要なもの以外はなるべく買わないよう我慢」が各2割弱。
-
- 調査時期:
- 2022年09月
- 設問項目:
-
今年贈ったお中元の件数/贈ったお中元の内容/お中元を贈った相手/お中元の購入場所/お中元の平均単価/お中元の品物選定時の情報源/お中元を贈る理由/今年もらったお中元の件数/今年のお中元選定時の重視点・こだわり(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■今年お中元を贈った人・もらった人は各4割弱で、いずれも過去調査と比べ減少傾向。高年代層や、東北などでの比率が高い。
■今年のお中元に贈ったものは「お菓子類・デザートなど」が贈った人の3割強、「ビール類」が2割強。北海道、中国などでは「果物」の比率が高い。贈った相手は「その他親戚」が4割強、「兄弟・姉妹」「自分の親」「配偶者の親」が各2~3割。
■購入場所は「百貨店の店頭」「総合スーパーの店頭」「オンラインショッピングサイト」などが各2割弱。過去調査と比べ「オンラインショッピングサイト」「百貨店のオンラインショップ」などが増加傾向。参考情報源は「店頭の商品」「ギフトカタログの冊子」が各2割強。
■お中元を贈る理由は「感謝の気持ちを表す」が実施者の5割弱、「普段ご無沙汰している方へのご挨拶代わり」「相手に喜んでもらいたい」「相手からもお中元を毎年もらうから」などが各3割弱。
-
- 調査時期:
- 2022年09月
- 設問項目:
-
直近3年間に行ったアウトドアレジャー/直近3年間でのアウトドアレジャーの頻度/直近3年間でのアウトドアレジャーの同行者/直近3年間にアウトドアレジャーに行った理由/アウトドアレジャーに関する情報収集源/アウトドアレジャーの好意度/新型コロナウイルス感染拡大による、アウトドアレジャーの実施状況・頻度の変化/新型コロナウイルス感染拡大以降のアウトドアレジャーの楽しみ方/アウトドアレジャーの魅力・期待/やってみたいこと(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■アウトドアレジャーが好きな人は全体の4割強、好きではない人は3割強。アウトドアレジャー直近3年間経験者は全体の3割強、2017年調査より減少。直近3年間では「バーベキュー、アウトドア料理」「自然観察」が各1割強、「ピクニック、ハイキング」「登山、トレッキング」などが各8~9%。
■直近3年間に行ったアウトレジャーに「友人・知人」と同行する人は10・20代や70代で高い傾向。女性では家族と同行する人の比率が高い。「ひとりで」は2割強で、男性高年代層での比率が高い。情報収集源は「Webサイト」「家族や友人・知人」が、直近3年間経験者の各3~4割、「旅行関連雑誌・ガイドブック」「テレビ番組・CM」「SNS、ブログなど」が各10%台。
■直近3年間にアウトドアレジャーに行った人の理由は「趣味」「気分転換」「自然の中で過ごしたい」が各4割前後、「家族や仲間とのコミュニケーションの機会」「健康のため」「体を動かしたい」などが各3割前後。実施頻度が高い層では「趣味」「健康のため」「体力づくり、運動不足解消」が上位。
■新型コロナウイルス感染拡大により「頻度が減った」が全体の16%、「コロナ禍以降はやめた」は約9%。「以前からアウトドアレジャーをしており頻度は変わらず行っている」は1割強。コロナ禍以降のアウトドアレジャーの楽しみは「近隣の自然の中でできるアウトドアレジャーを楽しむ」「自宅敷地内の屋外でアウトドアグッズを使ってバーベキュー」「自宅近くの自然の中で食事やお茶など」が各8~9%。
-
- 調査時期:
- 2022年09月
- 設問項目:
-
健康に気をつけている度合/健康のために摂取を心がけている成分/摂取している成分に期待する効果/摂取している成分を摂取するきっかけ/成分の摂取方法/成分を摂取している飲食物/健康のために摂取したい成分/栄養成分に関することで気になっていること(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■健康のために摂取を心がけている成分がある人は全体の6割強。摂取成分の上位は「乳酸菌」「たんぱく質」「ビタミンC」「カルシウム」が各2割強、「ビタミンB」「鉄」「DHA」「ビフィズス菌」が各1割強。今後摂取したい成分上位5位は「カルシウム」「乳酸菌」「たんぱく質」「ビタミンC」「DHA」。現在・今後ともに、「たんぱく質」が過去調査と比べ増加傾向。
■成分を摂取するきっかけは「テレビ番組・CM」が4割弱、「家族や友人・知人のすすめ」「健康や栄養などに関するWebサイト」「新聞記事・広告」などが各10%台。
■摂取成分に期待する効果は「健康維持」が栄養成分摂取者の6割強、「免疫力・抵抗力向上」が5割弱、「体調不良の改善、病気の改善・悪化防止」「疲労回復」などが各3~4割。
■成分の摂取方法は「食べ物、飲み物」が成分摂取者の7割強、「サプリメント、プロテイン、健康食品など」が約56%。摂取している飲食物は「大豆加工品」「乳製品」「野菜、きのこ類」が各6割前後、「魚介類、水産加工品、海藻類」が各5割弱。
-
- 調査時期:
- 2022年09月
- 設問項目:
-
スマートフォン所有状況・主利用機種/スマートフォンで利用している機能・サービス/スマートフォン購入時期/利用スマートフォンの満足度/スマートフォン利用意向/スマートフォン選定時の重視点/スマートフォン購入時の携帯電話会社・通信事業者の変更意向/スマートフォン購入時の携帯電話会社・通信事業者の変更意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■スマートフォン所有率は全体の9割強で、過去調査より増加傾向。所有率は10・20代約96%、30~60代9割強、70代8割強。
■スマートフォンで利用している機能・サービスは「通話」が所有者の9割弱、「カメラ」が7割強、「スマートフォン用のWebサイト閲覧」「時計、アラーム」「Webメール、パソコンメール、フリーメールなど」「電卓」「電話帳、アドレス帳」「インターネット電話」などが各60%台。過去調査と比べ「インターネット電話」「チャット、トーク」「オンラインショッピング」「万歩計」などが増加傾向。「スマホ決済」「テレビ電話、ビデオ通話」などは2020年から比率が高い。
■スマートフォンの利用意向は全体の8割強、「とても利用したい」が55%で過去調査より増加傾向。スマートフォン所有者では9割弱の利用意向、非所有者では2割弱。意向者の選定時の重視点は「本体価格」が6割強、「バッテリー」が5割強、「画面サイズ・大きさ」「通信料金」などが各40%台。
■次回も「同じ携帯電話会社・通信事業者にしたい」は、スマホ利用意向者の6割、NTTドコモ主利用者で高い。「携帯電話会社・通信事業者にはこだわらない」は2割弱、大手キャリア以外主利用者で高い。
-
- 調査時期:
- 2022年09月
- 設問項目:
-
利用している音源・音楽コンテンツ/定額制音楽配信サービスの利用頻度/直近1年間に利用した定額制音楽配信サービス/直近1年間の最頻利用定額制音楽配信サービス/定額制音楽配信サービス選定時の重視点/定額制音楽配信サービスの平均利用月額/定額制音楽配信サービスを利用する機器/定額制音楽配信サービス利用意向/定額制音楽配信サービス利用意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■直近1年間の定額制音楽配信利用者は全体の2割強、そのうち、週1回以上利用者は7割強で、2017年以降増加傾向。10~30代での比率が高い。過去調査と比べ、Spotify利用者などが増加傾向。
■直近1年間の定額制音楽配信利用者の重視点は「月額料金」が5割弱、「楽曲の曲数」「無料版・無料お試しの充実度」各3割強、「好きなアーティストの楽曲の充実度」が2割強。1ヶ月あたり平均利用額が500円以上の比率は有料での利用者の5割強で、過去調査と比べて増加傾向。
■利用機器は、「スマートフォン」が直近1年間利用者の7割強、「パソコン」が4割弱、「タブレット端末」「スマートスピーカー」が各1割強。Amazon Music Unlimited主利用者では「スマートスピーカー」が3割弱。
■定額制音楽配信サービスの利用意向者は全体の2割強、非利用意向者は6割弱。利用意向率は2017年以降増加傾向。週4~5回以上利用者では各9割前後の利用意向、直近1年間非利用者では2割弱、利用未経験者は約4%。
-
- 調査時期:
- 2022年09月
- 設問項目:
-
所有している電子レンジのタイプ/所有電子レンジのメーカー/所有している電子レンジの機能/電子レンジの機能のうち、使っている機能/電子レンジ機能の利用場面/調理をする際の電子レンジ利用頻度/電子レンジで調理をする理由/電子レンジ購入時の重視点/電子レンジのメーカー選定理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■「オーブン・トースター機能付き」所有者は4割強、「スチームオーブンレンジ」は2割強。購入時の重視点は「価格」7割弱、「操作のしやすさ」5割強、「メーカー・ブランド」「本体の大きさ」などが各4割強。
■電子レンジについている機能は「飲み物を温める」「生解凍・半解凍」「ちょうどよい温度に自動で温める」が各5~6割。使っている機能は「飲み物を温める」「ちょうどよい温度に自動で温める」が各30%台、「生解凍・半解凍」「温度を指定して温める」が各20%台。
■電子レンジを使う場面は「家庭で作った料理やご飯の温めなおし」が所有者の7割弱、「レトルト食品、電子レンジ用食品などの調理・温め」「市販のお弁当等の温めなおし」「解凍」などが各6割弱。
■調理時に電子レンジを使う人は所有者の4割強。調理での電子レンジ利用者の調理理由は「短時間で調理ができる」が8割強、「下ごしらえに便利」「キッチンコンロと並行作業ができ効率的」「手順が簡単」が各4割前後。
-
- 調査時期:
- 2022年09月
- 設問項目:
-
食品・飲料購入時に気にする栄養素・成分/食生活で糖質を気にする度合/糖質の摂取に関する意識・行動/糖質を意識して飲食する理由/直近1年間に購入した低糖質商品/新型コロナウイルス感染拡大に伴う、低糖質食品・飲料の購入頻度の変化/低糖質商品の購入意向/低糖質商品の購入意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■普段の食生活で糖質を気にしている人は全体の4割強。女性や高年代層で高い傾向。糖質の摂取に関して意識していることは「糖質の多い食品・飲料を控える」が3割、「低糖質であることが表示されている商品を摂取」が2割弱。
■直近1年間の低糖質の商品購入者は全体の6割強。「パン類」「ヨーグルト」「ビール類」などが各2割弱、「飲料(お酒以外)」が10%。コロナ禍により低糖質食品・飲料の購入頻度が増えた人は2割強、「変わらない」が7割強。
■糖質を意識して飲食する人の理由は「生活習慣病、メタボの予防」が6割弱、「体型・体重が気になる」が4割弱、「血糖値の改善」「健康によさそう」「糖尿病などの病気の改善」が各25~26%。
■低糖質の商品の購入意向者は全体の4割強で、過去調査と比べ増加傾向。直近1年間低糖質食品購入者の今後の購入意向は6割強、直近1年間非購入者では2割弱、購入未経験者では約6%。
-
- 調査時期:
- 2022年09月
- 設問項目:
-
直近1年間での麺類を食べる頻度/直近1年間に麺類を食べるシーン/麺類を食べる理由/自宅でよく食べる麺類/自宅で最もよく食べる麺類/直近1年間での自宅でよく食べる麺のタイプ・準備方法/自宅で最もよく食べる麺類の材料・商品購入時の重視点/直近1年間に外食でよく食べる麺類/好きな麺類の食べ方やアレンジメニュー(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■麺類を週1回以上食べる人は全体の7割強。「週2~3回」「週1回」がボリュームゾーン。休日・平日の昼食に食べる人は各60%台、夕食は各3~4割。
■麺類を食べる理由は「麺類が好き」が麺類を食べる人の約65%、「調理が簡単」が約45%、「早く準備ができる」「食べやすい」が各3割強、「単品で済ませられる」「好きなメニューがある」が各20%台。
■直近1年間に自宅で食べる麺類は「うどん」「ラーメン、中華麺」が、麺類を食べる人の各7割強、「パスタ、スパゲッティ」「そば」「やきそば」が各6割前後、「そうめん」が5割弱。市販の商品購入・調理者の重視点は「価格」「麺のタイプ」が各5割前後、「容量、サイズ」「スープやつゆ、ソースがついているかどうか」「賞味期限 ・消費期限」が各20%台。
■直近1年間に外食で食べる麺類は、「ラーメン、中華麺」が麺類を食べる人の6割弱、「うどん」「そば」「パスタ、スパゲッティ」が各30%台。東日本では「ラーメン、中華麺」「そば」、西日本では「うどん」「ラーメン、中華麺」が上位2位。
-
- 調査時期:
- 2022年09月
- 設問項目:
-
ドレッシング利用頻度/利用している市販のドレッシングの数/よく使うドレッシングの種類/直近1年間に利用したドレッシングのメーカー/市販のドレッシング購入時の重視点/市販のドレッシングの用途/新型コロナウイルス感染拡大に伴う市販のドレッシングの使用に関する変化/野菜やサラダなどにかけて食べるのが好きなもの/ドレッシングのこだわりやおすすめ(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■ドレッシング利用者は8割強。「週に2~3回」がボリュームゾーン。週1回以上利用者は7割弱、毎日利用者は2割弱。市販のドレッシング利用者について、コロナ禍による変化は「市販のドレッシングを使う頻度が増えた」が1割強、「使ったことがない種類のドレッシングを試してみた」が約9%、「市販のドレッシングを使う頻度が減った」は約5%。
■市販のドレッシング所有数は「1種類」が利用者の約26%、「2種類」が3割強。よく利用する種類は「ごま(乳化タイプ)」が利用者の5割強、「醤油ベース」が約36%、「青じそ」「フレンチ:白」「イタリアン」などが各2割前後。市販のドレッシングを野菜やサラダ以外にも使うことがある・積極的に使う人は、ドレッシング使用者の2割弱。
■ドレッシング使用者の購入時重視点は「味」が8割強、「値段」「味の種類」が各40%台、「量」2割弱、「料理・食材との相性」約15%。2014年調査以降「ノンオイル」が減少傾向。
■野菜や温野菜、サラダなどの好きな食べ方は「市販のドレッシング」が7割弱、「マヨネーズ」が4割強、「塩、しょうゆ、などの調味料」が3割弱。2019年調査と比べ「市販のドレッシング」が減少。
-
- 調査時期:
- 2022年09月
- 設問項目:
-
直近1年間でのグミを食べる頻度/好きなタイプのグミ/直近1年間に食べたグミの銘柄/直近1年間に最もよく食べたグミの銘柄/グミを食べる場面/グミ選定時の重視点/グミの利用意向/直近1年間でのグミタイプのサプリ利用状況/グミの不満点/食べない理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■市販のグミを直近1年間に食べた人は、全体の4割弱。女性や、若年層での比率が高い傾向。直近1年間に食べた人のうち週1回以上が約15%、月1回以上が4割強。サプリタイプのグミを直近1年間に食べた人は約6%。
■直近1年間利用者が、市販のグミで好きなタイプは「ソフトタイプ」が6割強、「ハードタイプ」が4割弱、「パウダーつき」が2割弱。「小腹がすいたとき」「おやつのとき」に食べる人が各4割前後、「口寂しいとき」「仕事や家事の合間」「気分転換」が各2割前後。
■直近1年間グミ利用者の重視点は「味」が8割弱、「食感、噛み応え」が4割弱、「価格」「ジューシーさ」が各20%台。「味」「食感、噛み応え」などは女性での比率が高い。
■グミの利用意向は3割強、非利用意向は約46%。利用意向者の比率は女性や若年層で高い。グミを月1回以上食べる人では各80%台の利用意向、直近1年間非利用者では1割強、利用未経験者では約2%。
-
- 調査時期:
- 2022年09月
- 設問項目:
-
スポーツドリンク・機能性飲料の飲用頻度/直近1年以内に飲んだスポーツドリンク・機能性飲料/直近1年以内に最もよく飲んだスポーツドリンク・機能性飲料/スポーツドリンク・機能性飲料を飲む場面/スポーツドリンク・機能性飲料購入時の重視点/スポーツドリンク・機能性飲料に期待する効果/スポーツドリンク・機能性飲料飲用意向/スポーツドリンク・機能性飲料の不満点/飲まない理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■スポーツドリンク・機能性飲料飲用者は全体の7割強。週1回以上飲用者は2割弱、男性の飲用頻度が高い傾向。
■スポーツドリンク・機能性飲料を飲む場面は「汗をかいた」「のどが渇いた」が飲用者の各3割強、「脱水症状を防ぎたい」「スポーツの後」「スポーツをしている時」などが各20%台。アミノバリュー主飲用者、ヴァームスマートフィットウォーター主飲用者などでは「スポーツをしている時」、OS-1主飲用者では「脱水症状を防ぎたい時」が1位。
■購入時の重視点は「味」が飲用者の6割強、「価格」が約46%、「機能・効果」「飲み慣れている」「成分」「容量、サイズ」などが各20%台。期待する効果は「水分補給」が飲用者の約75%、「熱中症対策・予防」が6割弱、「運動時や前後に適切な栄養素やエネルギーの補給」「体調を整える」が各2割強、「風邪など体調不良の回復をうながす」「運動後の疲労回復」などが各15~16%。
■スポーツドリンク・機能性飲料飲用意向は6割弱、男性10・20代や40代で高い傾向。月に数回以上飲用者では9割以上の飲用意向、現在非飲用者では約4%。
-
- 調査時期:
- 2022年08月
- 設問項目:
-
犬・猫の飼育状況/犬のえさのタイプ/猫のえさのタイプ/直近1年間の市販のペットフード購入場所/直近1年間の市販の犬・猫のペットフードの月額費用/市販のペットフード購入時の重視点/市販のペットフード選定時の参考情報源/市販のペットフードのフードローテーション実施状況/犬・猫の食事やペットフードの悩みの対処法/市販のペットフードの悩み・困っていること(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■犬・猫のいずれかを飼っている人は全体の2割弱。犬のみを飼っている人は約9%、猫のみを飼っている人は約8%。
■市販のペットフードのタイプは「ドライ」が犬飼育者の8割強、猫飼育者の約95%、おやつ・スナックは犬・猫のいずれも5割前後。犬を飼っている人では半生、ウェット・缶詰が各2割強、猫を飼っている人ではウェット・レトルト、ウェット・缶詰が各3~4割。直近1年間の購入場所は「ホームセンター」が、犬や猫の飼育者の4割強。2019年調査と比べ「オンラインショッピング」が増加。
■ペットフード購入時の重視点は「対象年齢」「嗜好性(ペットの好みにあっている)」「成分」「安全性」が、直近1年間ペットフード購入者の各4割強、「製品特徴」「価格」などが各4割弱。
■市販のペットフード選定時の参考情報源は「商品パッケージの説明」「店頭の情報」「獣医師やブリーダーなど専門家の意見」が、直近1年間ペットフード購入者の各20%台。悩みの対処法は「獣医師、動物病院に相談」が4割弱、「情報サイトや、口コミサイトなどで調べる」「家族や友人・知人に相談」が各20%台。
-
- 調査時期:
- 2022年08月
- 設問項目:
-
身体の悩み/1日の平均睡眠時間/睡眠の質の度合い/睡眠の質の悩み・不満の程度/睡眠の質の生活への影響度/睡眠の質をよくするために行っていること/睡眠の質をよくするために利用したい商品・サービス/睡眠の質をよくするもので効果があった・おすすめのもの(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■1日の平均睡眠時間は「6時間くらい」が4割弱、「7時間くらい」が3割弱。6時間以上が7割強、7時間以上が4割弱、5時間以下は約26%。50代では他の層より睡眠時間が短い傾向。
■睡眠の質について、よい方だと思う人は30%、よくない方だと思う人は4割弱。睡眠の質がよい方だと思う人の比率は、女性10・20代や男女70代で高く、睡眠の質がよくない方だと思う人の比率は、男性10・20代、女性40・50代でやや高い。
■睡眠の質について悩みや不満を「慢性的に感じている」は2割強、「いつもではないが、感じることがある」が4割強。これらをあわせた悩みや不満を感じる人は約66%で、女性の方が高い。睡眠の質に悩みや不満がある人のうち、普段の生活に影響がある人は6割強。
■睡眠の質をより良くするために行っていることは「規則正しい生活」が3割弱、「運動、トレーニング」「ストレッチ、体操、マッサージ」「ふだんの生活の中で体を動かす」「ストレスをためない」などが各2割弱。利用したいものは「睡眠の質向上・快眠を目的とした商品」が1割強、「サプリメントや市販の薬、漢方薬」「睡眠の質向上・快眠効果をうたった機能性食品・飲料」が各1割弱。
-
- 調査時期:
- 2022年08月
- 設問項目:
-
年をとることへの抵抗感/実年齢より若く/年上に見られたい度合い/年をとることによるからだや心の変化で気になること/アンチエイジングへの関心度/アンチエイジング実施状況/アンチエイジングの実施内容/アンチエイジングの方法として行いたいもの/加齢に伴う心身の変化・衰えについての考え方/アンチエイジングに効果があると思う商品・サービス(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■年をとることに抵抗を感じる人は全体の6割弱。実年齢に対し「相応に見られたい」は3割弱、「若くみられたい」は6割弱。加齢によって気になる変化は、「髪の毛」「視力の低下・老眼」が各50%台、「顔のたるみ」「顔のしわ」「基礎体力の低下」「顔のしみ」などが各4割弱。
■アンチエイジング関心層は全体の5割強、男性4割強、女性約65%。アンチエイジング実施率は3割弱、女性50~70代では各40%台。
■アンチエイジング実施内容は「ウォーキング、散歩など」「エイジングケア用のスキンケア用品・化粧品、石鹸等の使用」「サプリメント・健康食品の摂取」などが各4割弱。女性30~50代では「エイジングケア用のスキンケア用品・化粧品、石鹸等の使用」「紫外線対策」が上位2位。今後行いたいものは「十分な睡眠」「ウォーキング、散歩など」「規則正しい生活」「体によい食事」などが各3割前後。
■加齢に伴う心身の変化・衰えについては「若々しさを保つために加齢に伴う心身の変化や衰えを改善・予防したい」が2割弱、「加齢による心身の変化や衰えをある程度受け入れつつ、健康的に年齢を重ねたい」が5割弱、「加齢による心身の変化や衰えも含めた、年相応の心身の状態を受け入れたい」が1割強。
-
- 調査時期:
- 2022年08月
- 設問項目:
-
朝の肌のお手入れに使う時間/行っているスキンケア/使用しているスキンケア・化粧品/スキンケア・化粧品選定時の重視点/スキンケア・化粧品購入時の参考情報源/スキンケア・化粧品購入場所/スキンケア・化粧品の1ヶ月あたり平均購入金額/コロナ禍によるスキンケア・化粧品の買い替え・選び方の変化/コロナ禍によるスキンケア・化粧品に関することの変化(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■朝の肌のお手入れをしている人は全体の6割弱で、2020年調査より微増。男性4割弱、女性9割強。そのうち、かかる時間が5分以下の人は7割強。「保湿ケア」実施者は4割強、「UVケア」が2割強、「ハンドケア」「美白ケア」が各1割強。
■使用スキンケア用品のうち、「口紅」は2020年調査より減少、「チーク」は2017年調査以降減少傾向。コロナ禍で買い替えたり選び方が変わったものは「洗顔料」1割強、「化粧水、ローション」「口紅」が各7%。男性10~30代では「洗顔料」の比率が高い。
■選定時の重視点は「肌との相性」が使用者の6割弱、「使用感・使いごこち」「効能・効果」が各5割弱、「価格の適正さ」が3割強。購入場所は「ドラッグストア」が使用者の6割強。「インターネット通販」は女性40~60代での比率が高い。
■購入時の参考情報源は「店頭のPOP」「テレビ番組・CM」「製品のパッケージ」「ブランド・メーカーのWebサイト」などが使用者の各2割前後。女性若年層では「Twitter、インスタグラム、YouTubeなど」などの比率が高い。
-
- 調査時期:
- 2022年08月
- 設問項目:
-
自動車保険の加入状況/自動車保険に加入している保険会社/自動車保険について、最も多く保険料を支払っている保険会社/加入自動車保険会社の満足度/自動車保険(任意保険)の加入経路/自動車保険加入時に参考にした情報源/自動車保険選定時の重視点/自動車保険契約先の見直し意向/今後自動車保険に加入(更新)したい保険会社/加入自動車保険への加入理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■自動車保険(任意保険)加入率は全体の7割強。契約先見直し意向は加入者の3割強。
■自動車保険の加入経路は「パソコンからインターネット経由」が加入者の3割強、「保険代理店」「自動車を購入した店」が各2割弱。参考情報源は「保険商品を扱ったホームページや比較サイト」が2割弱、「家族・友人などのクチコミ」「テレビ番組・CM」「自動車購入店」「保険を取り扱う企業のホームページなど」が加入者の各1割強。
■保険選定時の重視点は「保険料の安さ」「補償内容の充実度」が加入者の各5~6割、「事故時の対応力・サービス」「商品内容のわかりやすさ」が各3割強。「保険料の安さ」はSBI損保主加入者、チューリッヒ保険主加入者などでの比率が高い。
■今後加入したい保険会社は「ソニー損保」「東京海上日動火災保険」「損保ジャパン」「SBI損保」などが上位。「わからない」は5割強。
-
- 調査時期:
- 2022年08月
- 設問項目:
-
室内の匂いが気になる度合/室内用消臭・芳香剤の使用状況/直近1年間に使用した消臭・芳香剤/最も気に入っている消臭・芳香剤/室内用消臭・芳香剤の形状/室内用消臭・芳香剤の使用場所/室内用消臭・芳香剤選定時の重視点/スプレータイプの消臭・芳香剤使用頻度/新型コロナウイルス感染拡大に伴う、消臭・芳香剤の選定・利用に関する変化/消臭・芳香剤の使い分け/使わない理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■室内用消臭・芳香剤使用率は全体の5割弱。使用場所は「トイレ」「居間、リビング」が使用者の各5~6割、「玄関、くつ箱」「寝室」が使用者の各3~4割。
■室内用消臭・芳香剤の形状は「置き型」「スプレー式」が使用者の各6割弱、「スプレー式」は2015年以降増加傾向。スプレー式使用者の利用頻度は、「ほとんど毎日」「週2~3回」がボリュームゾーン。
■消臭・芳香剤使用者の選定時の重視点は、「好きな香り」「価格」が4~5割、「消臭力が強い」「効果の持続性」「無香、微香」「商品ブランド」「メーカー」などが各20%台。
■コロナ禍に伴う、自宅での室内用消臭・芳香剤の選定・利用に関する変化は、「除菌効果を重視するようになった」が使用者の2割弱、「消臭効果を重視するようになった」「無香のものを使うようになった」が各1割前後。
-
- 調査時期:
- 2022年08月
- 設問項目:
-
食生活の状況/完全栄養食の認知・利用/直近1年間に利用したことがある完全栄養食/完全栄養食直近1年間利用頻度/完全栄養食利用意向/完全栄養食を利用したい場面/利用したい完全栄養食のタイプ/完全栄養食についての考え方/完全栄養食利用意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■完全栄養食利用者は約3%、利用経験者は約6%。認知率は全体の6割弱で2019年調査より増加。直近1年間完全栄養食利用者のうち、毎日利用者、週2~3回利用者は各2割弱。「定期的に利用していない」「試しに数回利用」が各2割強。
■完全栄養食利用意向者は2割弱、非利用意向者は4割強。現在利用者の利用意向者の比率は8割強、利用中止者では4割強、認知・利用未経験者では3割弱、非認知者では約9%。利用意向者が利用したいタイプは「パン」が6割弱、「パスタ」が4割弱、「スープ」「カレー」「ラーメン」「シリアル」「クッキー」「チョコレート」などが各3割前後。
■完全栄養食利用意向者が利用したい場面は「朝食の代わり」「健康を維持」「栄養バランス・栄養不足が気になる」が各3割強、「小腹がすいたときや、おやつの代わり」「昼食の代わり」が各20%台。
■完全栄養食については「手軽」「栄養バランスについて考えなくてよいので楽」「合理的」「必要な栄養をとれるという点で安心」などが各20%台。現在利用者では「合理的である」「手軽」の比率が特に高く、この点に魅力を感じていることがうかがえる。一方非利用意向者では「おいしくない・おいしくなさそう」「食べる楽しみが減る」「食材そのものから栄養を摂った方が体によいと思う」などが上位。
-
- 調査時期:
- 2022年08月
- 設問項目:
-
夏を感じ始める時期/夏の味覚を楽しむ度合い/夏の味覚とは/夏の味覚を味わうときの重視点/夏の味覚にあうお酒/夏に飲みたくなる飲み物/夏によく食べる味/夏の味覚を使った料理のおすすめ(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■夏を感じはじめる時期は「6月下旬」「7月上旬」が各3割弱で、2018年調査より時期が早まっている傾向。夏の味覚を味わう際の重視点は「鮮度」「見た目(彩りなど)」「価格」が上位3位。
■夏の味覚といえば「スイカ」が7割弱、「トウモロコシ」が約46%、「枝豆」「トマト」「きゅうり」が各4割弱。「トウモロコシ」「枝豆」などは西日本での比率が低い傾向。
■夏の味覚に合うお酒は「ビール類」が6割弱、「チューハイ・サワー」が2割弱。夏に飲みたくなる飲み物は「麦茶」が5割強、「炭酸飲料・炭酸水」が約35%、「スポーツドリンク」「水、ミネラルウォーター」「緑茶」「コーヒー、コーヒー系飲料」などが各2割前後。
■夏によく食べる味は「さっぱり」「スパイシー」が各30%台、「すっぱい」「辛い」「薄い・あっさり」などが各2割強。「塩辛い・しょっぱい」は10~30代での比率が高い。
-
- 調査時期:
- 2022年08月
- 設問項目:
-
直近1年間に食べたタブレット菓子の銘柄/直近1年間に最もよく食べたタブレット菓子の銘柄/タブレット菓子を食べる場面/タブレット菓子の好きな味・風味/タブレット菓子購入頻度/タブレット菓子選定時の重視点/タブレット菓子の利用意向/新型コロナウイルス感染拡大に伴う、タブレット菓子を食べる頻度の変化/タブレット菓子の不満/食べない理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■タブレット菓子利用経験者は全体の約56%、直近1年間利用者は3割強。好きな味・風味は「ミント系」が6割弱、「強めのミント系」「柑橘系フルーツ」が各3割前後。コロナ禍に伴いタブレット菓子を食べる頻度が減った人は、タブレット菓子を食べる人の2割、変わらない人は7割強。
■直近1年間にタブレット菓子を食べる人のうち、「気分転換」「仕事中・会議中」「移動中」「すっきりしたい」などに食べる人が各3割弱、「眠気を覚ましたい」「通勤・通学」「口臭が気になる」「口寂しい」などが各2割弱。
■タブレット菓子購入者頻度は月1回以上購入者が全体の2割弱。2019年調査より購入頻度の減少がうかがえる。購入時重視点は、「味」が購入者の約65%、「価格」が3割強、「爽快感・刺激」が3割弱。
■タブレット菓子利用意向は3割強、非利用意向者は5割弱。直近1年間にタブレット菓子を食べた人の利用意向は8割強、食べていない人の約8%。
-
- 調査時期:
- 2022年08月
- 設問項目:
-
レトルト食品の料理での利用頻度/直近1年間に利用したレトルト食品の種類/レトルト食品の利用場面/レトルト食品購入場所/レトルト食品購入時の重視点/レトルト食品購入理由/新型コロナウイルス感染拡大に伴う、レトルト食品利用頻度の変化/新型コロナウイルス感染拡大に伴う、レトルト食品利用状況の変化/気に入っているレトルト食品とその理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■レトルト食品を利用して料理をする人は全体の9割弱。ボリュームゾーンは「月2~3回程度」。月1回以上は7割強で、2019年調査より微増。レトルト食品利用者のうち、コロナ禍において利用頻度が増えた人は2割強、「変わらない」は8割弱。
■レトルト利用者が直近1年間に利用したものは「カレー」8割弱、「パスタソース」5割弱、「料理の素」「惣菜」「丼もの」「ご飯:白米・玄米」などが各20%台。
■レトルト食品利用場面は「ふだんの食事のメニューとして」「作るのが面倒」「時間がない、すぐ食べたい」が、利用者の各40%台。過去調査と比べ「ふだんの食事のメニューとして」が増加傾向。
■レトルト食品購入者の重視点は「味」「価格」が各7~8割、「容量、サイズ」が4割弱、「賞味期限」「メーカー」などが各2割強。購入理由は、「すぐに食べられる」「簡単に食べられる」が各6割強、「価格が安い」「調理の手間が省ける」「長持ちする・保存がきく」が各30%台。
-
- 調査時期:
- 2022年08月
- 設問項目:
-
カレーを食べる頻度/カレーの準備方法/直近1年間でのカレーを食べるタイミング/カレーを食べる場面/カレーを自分で作る頻度/カレーを作る時に使う市販のルウのタイプ/直近1年間に使ったカレールウ/直近1年間の最頻使用カレールウ/市販のカレールウ購入時の重視点/カレーを作る時の工夫・こだわり(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■カレーを食べる頻度は「月に2~3回程度」「月に1回程度」がボリュームゾーン。月1回以上食べる人は8割。カレーを食べる人では「自宅で作ったカレー」が8割弱、「レトルトカレー」が6割弱、「外食」が3割弱。
■カレーを食べる場面は「カレーを食べたい」が7割弱、「調理や後片付けを簡単に済ませたい」「辛いものが食べたい」「家族の要望」「食欲を増進させたい」などが各10%台。直近1年間でのカレーを食べるタイミングは「平日:夕食」が7割弱、「休日:夕食」が4割強、「平日:昼食」「休日:昼食」が各3割前後。
■カレーを自分で作る人は全体の6割強、男性約45%、女性30代以上で各80%台。月1回以上作る人は男性約25%、女性5割強。使うルウのタイプは「固形タイプ」が9割弱、「粉末タイプ」「フレークタイプ」が各1割強。
■市販のカレールウ購入時の重視点は「味」が利用者の7割強、「辛さ」が約45%、「価格」が4割弱、「こく」「香り」「メーカー」などが各2割前後。
-
- 調査時期:
- 2022年08月
- 設問項目:
-
夏に飲む飲み物の量(1日あたり)/夏によく飲む飲み物/夏の定番の飲み物/夏に飲む物に期待すること/夏における、常温での飲用状況/夏に常温で飲む飲み物/夏に常温で飲む理由/夏の飲み物で気に入っているもの(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■夏によく飲む飲み物の上位は「コーヒー、コーヒー飲料」が6割、「麦茶」「水、ミネラルウォーター」が各5割強、「緑茶」が4割強、「ビール類」が3割強。夏に飲む定番の飲み物(1つ)は「麦茶」が4割強、「水、ミネラルウォーター」「ビール類」が各1割弱。
■夏に飲む物に期待することは「冷たい」が8割弱、「のどの渇きをいやす」が5割強、「脱水症状を防ぐ、熱中症対策」「スッキリしている」が各30%台「のどごしが良い」「糖分ゼロ、無糖」「リフレッシュ、気分転換」が各2割強。
■夏に常温で飲むことがある人は全体の4割強。常温で飲む人のうち「水、ミネラルウォーター」が5割弱、「緑茶」が約35%、「麦茶」「コーヒー、コーヒー飲料」が各20%台。
■夏に常温で飲むことがある人の理由は「体を冷やさないため」「冷たいものは胃に負担がかかる」が各3割前後、「冷たいものはおなかをこわしやすい」「健康のため」「夏に限らず、常温のものを飲むことが多い」が各2割前後。