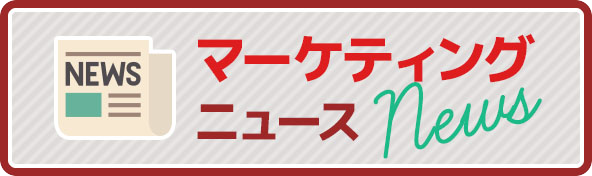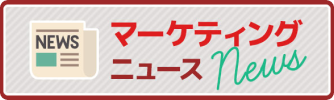- 検索
-
- テーマ別実施時期一覧
- カテゴリー別一覧
-
-
アルコール飲料・嗜好品145
-
非アルコール飲料209
-
その他19
-
-
住宅・住宅設備218
-
-
家電126
-
パソコン・カメラ・AV機器113
-
その他10
-
-
家庭用品・トイレタリー91
-
自動車・関連用品76
-
-
インターネット・情報通信327
-
携帯電話・スマートフォン180
-
メディア・広告66
-
その他7
-
-
ファッション68
-
交通・レジャー・娯楽161
-
季節行事・イベント241
-
時事・ニュース・トレンド51
-
企業ブランドイメージ246
-
広告・CM51
-
WEBサイトの利用91
-
顧客満足度100
- 実施時期別一覧
-
- 調査時期:
- 2022年07月
- 設問項目:
-
環境問題への関心度/使い捨てプラスチック製品の利用についての意識度/利用する使い捨てプラスチック製品/使い捨てプラスチック製品であった方がよいと思うもの/使い捨てプラスチック製品に関する考え方/使い捨てプラスチック製品に関して実施していること/レジ袋有料化で不便に感じる度合い/環境への負荷が少ないと思う容器包装/使い捨てプラスチック製品に関して意識していることや取り組み(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■使い捨てのプラスチック製品利用を意識する人は6割強。女性や高年代層での比率が高い。「使い捨てのプラスチック製品は便利」「過剰包装」が各4割強、「ゴミがかさばる」「プラスチック製の製品が多すぎる」が各4割弱。
■使い捨てのプラスチック製品や容器で普段使う・もらうものは「ペットボトル」が7割強、「食品トレイ」「プラスチック製の容器・袋の商品」が各60%台、「無料のポリ袋」が5割強。2021年調査と比べ、「プラスチック製ストロー」「かさ袋」「プラスチック製のスプーン・フォーク」などがやや減少。
■使い捨てのプラスチック製品のうち、あった方がよいと思うものは「ペットボトル」が5割強、「無料のポリ袋」が4割強、「食品トレイ」「無料レジ袋」が各3割強。レジ袋有料化で不便に感じる・感じない人TOP2は、いずれも4割強。
■環境への負荷が少ないと思う容器包装は「牛乳などの紙パック」が4割強、「ガラスびん」「ダンボール」が各30%台、「アルミ缶・スチール缶」が2割強。
-
- 調査時期:
- 2022年07月
- 設問項目:
-
日常のストレス度合い/ストレスを感じる状況/ストレスによる身体症状/ストレスの対処方法/ストレス耐性/ストレス発散・解消度合/新型コロナウィルス感染拡大前と比べ、ストレスに感じることが増えたもの/有効なストレス解消法(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■ストレスを感じている人は全体の6割強、女性の方が比率が高い。ストレス耐性があると思う人は全体の6割弱、女性10・20代での比率が低い。ストレスの発散・解消ができている人は4割強、高年代層で高い。
■ストレスを感じる状況は「仕事内容・労働環境など」が約36%、「金銭面」「職場の人間関係」「将来への不安」「病気やケガ、健康・体力面」が各2割強。コロナ禍前よりストレスに感じることが増えたものは「仕事内容・労働環境など」が2割弱、「将来への不安」「金銭面」「病気やケガ、健康・体力面」が各1割強。
■ストレスを感じた時の身体症状は「いらいらしやすくなる」が4割弱、「気力がなくなる、元気がなくなる」「眠れない・眠りが浅い」「胃痛、胃もたれ」「便秘、下痢、腹痛、おなかが張る」が各2割前後。
■ストレスへの対処法は「寝る」「好きなものを食べる」が各2割強、「音楽を聴く」「飲み物を飲む」「お酒を飲む」「映画やDVD、テレビ番組、動画共有サイトなどを見る」などが各2割弱。女性では「好きなものを食べる」などの比率が高い。
-
- 調査時期:
- 2022年07月
- 設問項目:
-
市販の医薬品購入頻度/直近1年間に購入した市販の医薬品/直近1年間での市販の医薬品購入場所/市販の医薬品購入場所の選択ポイント/医薬品購入時に不便に感じた点/市販の医薬品購入場面/市販の医薬品を購入したい場所/病気・ケガや体調不良時の対処法/市販の医薬品購入時の不満点・困ること(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■市販の医薬品月1回以上購入者は3割弱で、2018年調査よりやや増加。市販薬購入者の購入場面は「病院で治療が必要なほどの症状ではない」が7割弱、「急な症状」「応急処置」「症状にあった市販薬がある」が各20%台。
■市販の医薬品直近1年間購入場所は「ドラッグストア」が市販薬購入者の8割強、「通信販売(インターネット)」「薬局・薬店」が各1割強。今後の購入意向は「ドラッグストア」が全体の7割強、「スーパー」「薬局・薬店」「通信販売(インターネット)」「コンビニエンスストア」が各2割前後。
■市販薬購入者の購入場所選択ポイントは「欲しいときにすぐ購入できる」が5割強、「安い価格で購入できる」「ポイントが貯まる」「アクセスがよい」が各30%台。
■市販の医薬品購入者のうち、「薬剤師が不在のために医薬品が購入できなかった」「カウンターの中に置かれるために、商品を比較しづらかった」を経験した人は各1割強。
-
- 調査時期:
- 2022年07月
- 設問項目:
-
生命保険会社の認知/主加入生命保険/加入生命保険商品の種類/生命保険申込み方法/1か月あたりの生命保険料/生命保険加入・見直し時に、候補として検討した生命保険会社/生命保険に関する情報入手経路/加入したい生命保険会社/生命保険の加入・見直し意向/主加入生命保険の加入理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■生命保険申込み方法は「知り合いや紹介を受けた営業職員、保険外交員」が加入者の3割強、「自宅や勤務先に訪問してくる営業職員、保険外交員」が2割強。アクサダイレクト生命主加入者、チューリッヒ生命主加入者、ライフネット生命主加入者、楽天生命主加入者などでは「インターネットで申込み手続き」が1位。
■生命保険加入時に候補として検討した生命保険会社がある人は、生命保険加入者の4割弱。
■生保関連の情報入手経路は「テレビ番組、CM」が3割強、「営業職員、保険外交員」「家族や友人、知人」「保険商品のパンフレット、説明資料」「保険を取り扱っている企業のホームページ」「新聞記事、広告」などが各10%台。
■生命保険の加入・見直し意向は、「現在加入の生命保険を継続」が3割、「現在加入の生命保険に追加して加入」が約4%。「生命保険には当面加入しない」は3割強。
-
- 調査時期:
- 2022年07月
- 設問項目:
-
利用している飲用水/家庭用ウォーターサーバーの利用実態/ウォーターサーバーを利用し始めたきっかけ/ウォーターサーバー非利用理由/ウォーターサーバーの利用中止理由/主利用家庭用ウォーターサーバーのタイプ/主利用家庭用ウォーターサーバー/主利用ウォーターサーバーの満足度/ウォーターサーバー利用意向/主利用ウォーターサーバーの選定理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■家庭用ウォーターサーバー利用経験者は全体の1割強、現在利用者は約5%。現在利用者のうち「ワンウェイ方式のボトル・パック」利用者が5割強で、「リターナブル方式のボトル」の3割弱よりも多い。「水道直結型」は現在利用者の約6%。
■利用のきっかけは、利用経験者では「無料お試し期間」が3割強、「店頭、街頭などでのキャンペーンやデモ」が2割強。現在利用者では「店頭、街頭などでのキャンペーンやデモ」「おいしい水が飲みたいと思った」が上位2位。
■非利用理由、利用中止理由とも「維持費がかかる」「設置スペースをとられる」が上位2位。水道水やミネラルウォーターなどで十分/満足の他、「経済的余裕がない」「ボトル交換や手入れ等が面倒」なども上位にあがっている。
■家庭用ウォーターサーバー利用意向者は全体の約8%。現在利用者では8割強、認知・利用未経験者では約4%。非利用意向者の比率は全体の約75%。
-
- 調査時期:
- 2022年07月
- 設問項目:
-
意識して摂取している栄養素・成分/たんぱく質摂取の意識度合い/たんぱく質摂取量についての意識/たんぱく質摂取のために意識的に摂取している食品/たんぱく質摂取のために直近1年間に購入した商品/たんぱく質を意識的に摂取するきっかけ・理由/たんぱく質の摂取による効果の度合い/たんぱく質の摂取について意識的に行っていること/行っていない理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■たんぱく質の摂取を意識している層・意識していない層はいずれも4割強。男性10~50代では意識していない層が多い。たんぱく質を摂取している方だと思う人は約36%で60~70代で高く、摂取している方ではないと思う人は2割強。
■たんぱく質のために意識的に摂取している食品は「卵」「鶏肉」「ヨーグルト、飲むヨーグルト」「納豆」「豆腐」「豚肉」が各30%台、「牛乳」「チーズ」「魚介類」が各3割弱。たんぱく質摂取のための直近1年間購入商品は「サラダチキン」が1割強、「プロテインの粉末・錠剤」が約8%、「バランス栄養食品やプロテイン:棒状」が約7%。
■たんぱく質を意識的に摂取している人の、きっかけや理由は「健康維持」が7割強、「筋力維持」が5割弱、「免疫力・抵抗力向上」が3割強、「加齢に伴う衰えが気になる」「体力低下が気になる」が各20%台。
■たんぱく質の摂取を意識している層のうち、効果を感じる人は3割強。男性30~40代では効果を感じる人の比率が高い。女性30代では効果を感じない人の比率が他の層より高い。
-
- 調査時期:
- 2022年07月
- 設問項目:
-
揚げ物の嗜好度/好きな揚げ物/直近1年間での揚げ物を食べる頻度/揚げ物を食べる場面/直近1年間での揚げ物の調理法・準備方法/直近1年間での市販の調理済み揚げ物購入場所/直近1年間での自宅での揚げ物の調理頻度/自宅で調理する揚げ物の種類/揚げ物について気を付けていること・こだわり(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■好きな揚げ物の上位は「トンカツ」「鶏の唐揚げ・竜田揚げ」「エビフライ」「てんぷら」などで各60%台。「トンカツ」は男性50~70代、「エビフライ」は女性60~70代で1位。
■直近1年間に揚げ物を食べる頻度は「週2~3回」「週1回」がボリュームゾーンで、週1回以上は7割弱。揚げ物を食べる人のうち直近1年間では「市販の惣菜・調理済みのもの」「手作り」を食べる人が各6割弱、「市販の弁当のおかず」が4割弱、「ファストフード」「飲食店」が各3割強。
■市販の調理済み揚げ物購入者のうち、直近1年間に「スーパー」で購入した人は9割強、「惣菜店、肉屋、からあげ屋など専門店・小売店」は4割弱、「コンビニエンスストア」は3割弱。
■自宅で揚げ物をする人は全体の7割弱。週1回以上する人は3割強。自宅で調理する人のうち「鶏の唐揚げ・竜田揚げ」を作る人が6割弱、「てんぷら」「トンカツ」がそれぞれ約45%、「エビフライ」「コロッケ」が各3割強。
-
- 調査時期:
- 2022年07月
- 設問項目:
-
夏にアイスクリーム類を食べる頻度/冬にアイスクリーム類を食べる頻度/アイスクリーム類・氷菓の食べ方等の、季節による違い/アイスクリーム類を食べるシーン/アイスクリーム類の購入場所/アイスクリーム類を食べる際の重視点/直近1年間に食べたアイスクリーム類の銘柄/最も好きなアイスクリーム類の銘柄/市販のアイスクリームで好きなもの(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■夏にアイスクリーム類を週1回以上食べる人は6割弱。冬に週1回以上は2割強。アイスクリーム類を「主に暑い季節に食べる」は4割強、「季節を問わず、一年を通して食べる」は3割弱。
■アイスクリームを食べるシーンは「間食・おやつ」が利用者の4割強、「暑いとき」「くつろいでいるとき」が各20%台、「お風呂あがり」「甘いものが欲しいとき」などが各2割弱。夏に食べる頻度が高い層では「お風呂あがり」がやや高い傾向。
■アイスクリーム類を食べる人の重視点は「味」8割強、「価格」約56%、「食感」が3割強、「容器の形状」「甘すぎない」などが各2割強。購入場所は「スーパー」が8割強、「コンビニエンスストア:市販のアイス」が約46%。「ドラッグストア」が過去調査と比べ増加傾向。
■市販のアイスクリーム利用者が最も好きな銘柄は「ハーゲンダッツ」が2割強。男性10・20代では「ガリガリ君」が1位。
-
- 調査時期:
- 2022年07月
- 設問項目:
-
直近1年以内に食べたバランス栄養食品のタイプ/直近1年以内に食べたバランス栄養食品/直近1年以内に最もよく食べたバランス栄養食品/バランス栄養食品の利用頻度/バランス栄養食品の利用目的/バランス栄養食品選定時の決め手/バランス栄養食品に含まれる栄養素・成分の選定/バランス栄養食品の利用意向/バランス栄養食品の利用意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■バランス栄養食品(プロテインバー含む)直近1年以内利用者は4割弱で、女性での比率が高い。そのうち週1回以上利用者は2割強。「数ヶ月に1回程度」がボリュームゾーン。
■直近1年間バランス栄養食品の利用者の目的は「空腹感の解消」「お菓子のかわり」が各3割強、「朝食のかわり」「昼食のかわり」などが各2割前後。週5回以上利用者では「朝食のかわり」が最も多い。
■バランス栄養食品選定時の決め手は「味」が7割強、「価格」が45%、「栄養成分」が3割強、「形状 ・食べやすさ」「カロリー」「食感」が各20%台。直近1年間バランス栄養食品利用者がどのような栄養素・成分のものを選ぶかについては、「たんぱく質」が約36%、「カルシウム」「食物繊維」が各20%台、「鉄」「アミノ酸」が各2割弱。
■バランス栄養食品利用意向者・非利用意向者とも、全体の4割弱。女性や若年層での比率が高く年代差が大きい。バランス栄養食品直近1年以内利用者では8割弱の利用意向、利用経験・中止者の2割弱、未経験者の約4%。
-
- 調査時期:
- 2022年07月
- 設問項目:
-
おにぎりを食べる頻度/好きなおにぎりの種類/おにぎりと一緒に飲む物/手作りおにぎりと市販のおにぎりのどちらが多いか/おにぎりのつくり方/おにぎりの購入場所/おにぎり購入時の重視点/おにぎりを買う場面/おにぎりについてのこだわり(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■おにぎりを食べる頻度は「月に1回未満」が3割強、「月に2~3回」が2割強。週1~2回以上食べる人は3割弱。過去調査と比べ、おにぎりを食べる人や頻度が減っている傾向がうかがえる。
■好きなおにぎりの具は「鮭」が約66%で1位、「昆布」「ツナマヨネーズ」「辛子明太子」「梅」「たらこ」などが各4割前後。北海道など東日本では「たらこ」「いくら」など、九州では「高菜」などの比率が高い。
■市販のおにぎりを食べる人の購入場所は「コンビニエンスストア」が8割強。過去調査と比べ「スーパー」が増加傾向。購入場面は「昼食に食べる用」が購入者の約65%、「外出先で食べる」が3割弱、「食事を短時間で済ませたい」「屋外で食べる」「小腹がすいた」が各2割弱。
■おにぎりを食べる人のうち「自宅で作ったものを食べることが多い」は約35%、「市販のおにぎりを食べることが多い」は5割強。おにぎりを食べる人のうち、自分で作る人は7割強。
-
- 調査時期:
- 2022年07月
- 設問項目:
-
コーヒーの飲用頻度/飲んでいるコーヒーのタイプ/最もよく飲むコーヒーのタイプ/好きなコーヒーの飲み方/コーヒーを飲む場所/コーヒーを飲む場面/コーヒーに期待する効果/コーヒーの楽しみ方(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■コーヒーを毎日飲む人は全体の7割強、「1日に2~3回」が4割弱。コーヒー飲用者のうち「インスタントコーヒー」が5割強、「レギュラーコーヒー」が4割強。「ペットボトル入りコーヒー」は3割強で過去調査と比べ増加傾向。「レギュラーコーヒー」「缶コーヒー」などは過去調査より減少傾向。
■好きなコーヒーの飲み方は「ホット/ブラック」が飲用者の5割強。カフェ・オレ、カフェ・ラッテは、女性や若年層での比率が高い傾向。ブラックは、ホットは男性や高年代層、アイスは男性や若年層での比率が高い傾向。
■コーヒー飲用者のうち「自宅」で飲む人は9割強、「職場」が3割強、「車の中」「コーヒーチェーン店」「喫茶店 ・カフェ」などが各2割前後。
■コーヒーを飲む場面は「朝食時」「おやつの時」が各40%台。「休憩中・休み時間」「仕事・勉強・家事をしながら」「リラックスしたいとき」が各3割前後。コーヒー飲用者が期待する効果は「気分転換」「リラックス効果」が各5割強、「眠気を覚ます」が3割強、「集中力を高める」が2割弱。
-
- 調査時期:
- 2022年07月
- 設問項目:
-
豆乳の嗜好度/直近1年間での豆乳の摂取方法/豆乳摂取理由/豆乳に期待する効果/豆乳購入時の重視点/豆乳飲用頻度/豆乳飲用場面/豆乳飲用意向/豆乳・豆乳飲料の不満(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■豆乳が好きな人は全体の4割弱、女性若年層で高い。直近1年間豆乳・豆乳飲料飲用者は全体の5割弱。「市販の豆乳をそのまま飲む」が3割強。直近1年間飲用者のうち、週1~2回以上飲用者は4割強。飲用場面は「朝食時」が4割弱、「おやつの時」が約25%。
■直近1年間摂取者の豆乳摂取理由は「健康に良い」が5割強、「栄養価が高い」が4割強、「おいしい」「大豆イソフラボン摂取」「牛乳の代わり」が各30%台。期待する効果は「コレステロールの低減」「高血圧や高脂血症、動脈硬化などの予防」が各3割弱、「便秘を防ぐ・便通をよくする」「カルシウムの摂取」「美肌」などが各2割弱。
■豆乳購入時の重視点は「味」が直近1年間摂取者の6割弱、「価格」「飲みやすさ」が4割前後、「成分、添加物」「調製、無調整」「原材料」が各20%台。
■豆乳飲用意向者は全体の4割強、男性4割弱、女性5割強。豆乳・豆乳飲料飲用者では8割弱、非飲用者では1割強。非飲用者では非飲用意向が6割弱を占める。
-
- 調査時期:
- 2022年06月
- 設問項目:
-
今年のゴールデンウィークの休日数/今年のゴールデンウィークの連休日数/今年のゴールデンウィークに出かけた行楽・レジャー・帰省など/今年のゴールデンウィークに出かけた行楽・レジャーの予定をたてた時期/ゴールデンウィークの行楽・レジャーに使ったお金/今年のゴールデンウィークの自宅での過ごし方/ゴールデンウィークの休みの外出・在宅の割合/今年のゴールデンウィークの満足度/今年のゴールデンウィークの満足したこと・不満だったこと(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■今年のゴールデンウィーク休日数は「5日」「10日」がそれぞれ約10%、「12日以上」が15%。「1日もなかった」は1割強。2日以上休みがあった人のうち12日以上連休した人が2割弱、3日が25%。
■ゴールデンウィークに出かけた人は全体の5割弱で2020年調査(2割弱)より増加。「ショッピング」「グルメスポット、外食」にでかけた人が各1割強、「ドライブ」が9%、「公園」「帰省」が各7%。ゴールデンウィークの支出は2020年調査より増加、2019年調査より減少傾向。
■ゴールデンウィークの自宅での過ごし方は「テレビ」が6割強、「インターネットの閲覧・検索、SNS・アプリの利用など」が5割強、「録画していたテレビ番組」「部屋の片付け・掃除」などが各3~4割。これらは2020年より減少し2019年調査とほぼ同程度。ゴールデンウィークに休みがあった人のうち、家で過ごすことが多かった人は約76%。
■今年のゴールデンウィークの満足層は約46%、不満層は約16%。2020年調査では満足層の比率が大きく減少したが、今回調査では回復し2019年調査を上回っている。出かけた人の方が満足層の比率が高い。
-
- 調査時期:
- 2022年06月
- 設問項目:
-
美容に対する関心度/美容のために意識していること/美容のために食生活で意識していること/美容のために使っているアイテム/美容にかける費用(1ヶ月あたり)/直近1年間に利用したことがある美容関連サービス/新型ウイルス感染拡大により美容面で気になるようになったこと/新型コロナウイルス感染拡大前後での、美容の積極度の変化/新型ウイルス感染拡大により美容に関して行うようになったこと/行わなくなったこと(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■美容関心層は全体の4割弱、男性2割弱、女性6割強。美容のために意識しているのは「ウォーキングなど軽い運動」「食生活」「水分補給」「スキンケア・肌の手入れ(顔)」などが各3割弱。食生活を意識する人のうち「栄養バランス」「野菜を多くとる」を意識する人が各7割前後、「食べ過ぎない」が5割強。
■美容のために使うアイテムは「歯ブラシ、歯磨き粉、歯間ブラシなど」が5割強、「洗顔料」「スキンケア用品」が各4割強、「ヘアケア商品」「ハンドクリーム」「リップクリーム」「化粧品・メイク用品」が各3割前後。男性若年層では「洗顔料」「スキンケア用品」などの比率が高い。女性30代以上では「スキンケア用品」が各7割強~8割強。
■美容関連サービスの直近1年間利用経験は「美容室・ヘアサロン」が女性で約76%、「理容院」は男性高年代層での比率が高い傾向。1ヵ月あたりの美容関連費用は2021年調査と比べ、「0円」は減少、1~1000円未満の比率が増加傾向。
■美容に関して、コロナ禍以前より積極的に行う層は10%で若年層での比率が高い傾向。積極に行わない層は15%。コロナ禍以前より美容面で気になることは「顔のしわ、たるみ、筋肉のゆるみ」「体重」「顔のくすみ、しみ、そばかす、毛穴」「肌の乾燥」「体型、スタイル」「顔の肌荒れ・肌のトラブル」など。女性や若年層では「顔の肌荒れ・肌のトラブル」、女性高年代層では「顔のしわ、たるみ、筋肉のゆるみ」などの比率が高い。
-
- 調査時期:
- 2022年06月
- 設問項目:
-
お通じの頻度/お通じで困っている度合/お通じに関して困っていること/便秘の時の対処法/下痢の時の対処法/お通じの状態が悪くなる原因/お通じを自然な状態に保つために気をつけていること/お通じに効果があると感じている商品(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■お通じの頻度は「1日に1回」が全体の5割強、女性の方が頻度が低い傾向。お通じで困っていることがある人は全体の4割強。「便秘気味」が2割強、「おならが出やすい・臭い」「下痢しやすい」「コロコロ便が多い」「環境が変わると下痢や便秘になりやすい」などが各10%台。
■便秘時の対処法は「水分をとる」が3割弱、「お腹の調子を整える効果がある食品・飲料を摂取」「市販薬」が各10%台、「マッサージや体操など」「消化の良いものを食べる」などが各1割弱。下痢時の対処法は「市販薬」が3割弱、「お腹や体を温める」「温かいものを飲食」「水分をとる」「消化の良いものを飲食」が各1割強。
■お通じの状態が悪くなる原因だと思う上位は「食べ過ぎ、飲みすぎ」が3割弱、「もともとの体質」「ストレス」「運動不足」が各2割強。
■お通じを自然に保つために気をつけていることは「規則正しい生活」が4割弱、「適度な運動をする」「水分を適度にとる」「睡眠を十分とる」「野菜、果物を適度に摂る」などが各3割前後。
-
- 調査時期:
- 2022年06月
- 設問項目:
-
契約している電力会社/契約している電力会社の満足度/電力会社変更状況/電力会社を変更しない理由/電力会社の契約意向/契約しているガス会社/契約しているガス会社の満足度/ガス会社変更状況/ガス会社の契約意向/電力会社契約意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■「新電力会社」利用者は3割弱で、過去調査と比べ増加傾向。関東では4割弱、近畿では3割強。満足層は5割強で、大手電力会社利用者では5割強、新電力会社利用者では6割弱。
■電力自由化後、契約電力会社変更者は3割弱。契約会社での料金プラン変更者は約8%。電力会社を変更していな人(全体の6割弱)の理由は「現在利用している会社に特に不満がない」が4割強、「現在の契約会社の方が安心」「変更してもメリットが感じられない」が各25%。
■新規参入の電気小売事業者契約意向者は約16%、大手電力会社契約意向者は全体の4割強。現在大手電力会社と契約している人では、新規参入事業者との契約意向が約4%、大手電力会社との契約意向者が6割弱、「どちらともいえない」が4割弱。
■ガス自由化後のガス会社変更者は、ガス使用者の1割強、契約会社での料金プラン変更者は約5%。今後の意向は、従来の都市ガス会社契約意向者が4割弱。新規参入都市ガス契約意向者は全体の約7%で、新規参入都市ガス利用者では約66%、従来の都市ガス利用者では約4%。
-
- 調査時期:
- 2022年06月
- 設問項目:
-
インテリアへのこだわり/インテリアの重視点/自宅のインテリアの満足度/家具・インテリア選定時の参考情報/家具・インテリア雑貨の購入場所/直近1年間にインターネットショップで購入した家具・インテリア/直近1年間に家具・インテリアをインターネットショップで購入した場面/おうち時間を快適に過ごすためのインテリアの工夫(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■インテリアへのこだわりがある人は3割弱、女性の方が比率が高い。自宅のインテリア満足度は4割弱。
■家具・インテリア選定時の参考情報は「店頭のディスプレイ」が36%、「家具・インテリア専門店などの公式サイト・アプリ」「テレビ番組・CM」「商品カタログ・パンフレット」「オンラインショップ、ネット通販のサイト」などが各10%台。女性10~30代では「ブログ、写真共有SNS」の比率が高い。
■インテリアの重視点は、インテリアへのこだわりがある層では「部屋全体のテイストに統一感」「くつろぎ・癒しの空間となり、居心地がよい」「見た目がすっきりしている」などが上位。こだわりがない層では「使いやすく、機能的」が最も多い。
■家具・インテリア雑貨の購入場所は「家具店」が7割弱、「ホームセンター」が4割弱、「インターネットショップ」「インテリアショップ・用品店」「大型生活雑貨店」が各20%台。インターネットでの購入者3割弱のうち、直近1年間に「寝具」「収納用品」購入者は各2割弱。購入場面は「たまたま欲しいものを見つけた」「配送してもらいたい」「価格を比較して安いものを選びたい」が各20%台。
-
- 調査時期:
- 2022年06月
- 設問項目:
-
知っている食のスタイル/多様な食のスタイルへの関心度/直近1年間での食のスタイルの実施/直近1年間に最も実施した食のスタイル/直近1年間に最も実施した食のスタイルの実施度合い/多様な食のスタイルの実施意向/多様な食のスタイルに期待する効果/フリーフロム食品の直近1年間購入状況/多様な食のスタイル実施意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■多様な食のスタイルについて今回提示選択肢で内容を知っているものは「ベジタリアン」が8割強、「ヴィーガン」「グルテンフリー」「糖質制限、ローカーボ」が各5割前後。「フレキシタリアン」は約5%。多様な食のスタイルの関心層は2割弱。
■直近1年間に実施したもの(ゆるやかな実施も含む)は「糖質制限、ローカーボ」が約9%。「無添加主義・オーガニック主義」は約4%。
■直近1年間に最も多く実施した食のスタイルの実施度合いは、ベジタリアン実施者は「完全実施」が3割弱、グルテンフリー実施者では「試しにやってみた」が3割強、無添加主義・オーガニック主義実施者では「ゆるやかに実施」が7割強で、いずれも他の層より高い。
■多様な食のスタイルの実施意向は「糖質制限、ローカーボ」が15%、「無添加主義・オーガニック主義」が約10%、「ローフード」「フレキシタリアン」がそれぞれ約6%。期待する効果は「健康維持」が6割強、「体調不良の改善、体の悩み改善」「免疫力向上」「腸内環境改善」が各4割前後、「ダイエット」「胃腸の調子を整える」が各3割強。糖質制限・ローカーボ実施意向者では「ダイエット」の比率が高い。
-
- 調査時期:
- 2022年06月
- 設問項目:
-
間食の頻度/間食をする時間帯/間食をする場面/間食でよく食べるもの/間食でよく飲むもの/間食で飲食するものを購入する時の重視点/間食をとる理由/新型コロナウイルス感染拡大以前と比べた、間食を食べる頻度の変化/新型コロナウイルス感染拡大以降の、間食に関する変化の内容(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■間食をする人は全体の7割強、男性の6割強、女性の8割強。間食をする人のうち「昼食から夕方の間」が7割弱、「夕食後」が3割強。1日1回以上食べる人は約35%。新型コロナウイルス感染拡大以前と比べ、間食を食べる頻度が増えた人は約26%。
■間食をする人のうち「くつろぎながら」「おやつの時間」に間食をする人が各4割強、「仕事・勉強・家事の合間」が3割強、「テレビやDVD・BDなどを見ながら」が約25%。間食をとる理由は「お菓子など、甘いものが好き」が5割弱、「なんとなく口さびしい」「おなかがすく」が各4割前後、「気分転換」「リラックスしたい」が各3割弱。
■間食を食べる人のうち「チョコレート」を食べる人が5割強、「スナック菓子」「せんべい・あられなどの米菓」「クッキー、ビスケット」が各5割弱、「アイスクリーム類」「ケーキ類、シュークリーム、ドーナツ、マドレーヌ等」などが各4割弱。よく飲むものは「コーヒー、コーヒー飲料」「お茶、お茶系飲料」が各6~7割、「紅茶、紅茶飲料」が3割弱。
■間食を食べる人の、購入時の重視点は「価格」が4割弱、「すぐ飲食できる、手間がかからない」「食べきりサイズ」「分けて食べられる容器・包装」などが各20%台。
-
- 調査時期:
- 2022年06月
- 設問項目:
-
果物の嗜好度/好きな果物/果物の摂取方法/果物摂取理由/果物摂取頻度/生鮮果物摂取場面/生鮮果物購入時の重視点/好きな果物の理由、こだわりなど(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■果物が好きな人は全体の9割弱。好きな果物上位は「いちご」「もも」「梨」「みかん」「りんご」「ぶどう、マスカット」などが各6~7割。ほぼ毎日食べる人は、果物摂取者の3割強、週1回以上は8割弱。「ほぼ毎日・1日1回」「週2~3回」がボリュームゾーン。
■果物の食べ方は「生鮮果物をそのまま」が全体の9割強、「生鮮果物を何かにのせる・まぜる」が3割弱。摂取場面は「間食、おやつ」が摂取者の約46%、「朝食のメニューとして」「夕食後」が各4割弱。果物摂取頻度が高い層では「朝食のメニューとして」などの比率が高い傾向。
■果物摂取理由は「おいしい」が9割弱、「好き」が約56%、「健康によい」「ビタミン」が各4割前後、「手軽」「甘い」がそれぞれ約25%。ほぼ毎日食べる層では「好き」「健康によい」「習慣」などの比率が高い。
■果物購入時の重視点は「価格」が6割強、「鮮度」が4割強、「季節感・旬のもの」「産地」「国内産・外国産」などが各30%台。
-
- 調査時期:
- 2022年06月
- 設問項目:
-
自宅でのお酒飲用頻度/自宅での飲酒時おつまみを食べるかどうか/自宅での飲酒時によく食べるおつまみ/自宅でおつまみを食べながら飲むお酒の種類/自宅で飲酒時のおつまみ準備方法/自宅での飲酒時に食べる市販のおつまみ選定時の重視点/自宅での飲酒時に食べる市販のおつまみ購入場所/自宅での飲酒時に食べるおつまみで気に入っているもの・食べるシチュエーション(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■自宅でお酒を飲む人は7割弱、男性の方が比率が高い。「ほぼ毎日」は2割強、週1回以上が半数弱。自宅での飲酒者のうち、おつまみを食べる人は9割弱。「必ず食べる」は7割弱で、過去調査と比べて増加傾向。高年代層での比率が高い。
■自宅でおつまみを食べる人のうち「食事のおかずをおつまみとして食べる」は7割強、「市販のスナック、菓子、乾きものなど」は5割弱、「出来合いのおかず・惣菜」は3割強、「おかずを作る・用意する」は2割強。自宅でおつまみを食べる人では「チーズ」「刺身、たたき」「スナック菓子」「揚げ物」「枝豆」「ナッツ類」などが各40%台。
■自宅でおつまみを食べる人のうち「ビール」を飲む人が約65%、「発泡酒、新ジャンルビール」「チューハイ、サワー」が各4割強、「ワイン」が4割弱、「日本酒」「焼酎・泡盛」が各3割前後。女性20~40代では「チューハイ、サワー」が1位。
■自宅での飲酒時のおつまみ購入時の重視点は「味」約75%、「価格」4割強、「すぐ食べられる」3割弱。購入場所は「スーパー」が購入者の9割強、「コンビニエンスストア」約35%、「ドラッグストア」2割強。
-
- 調査時期:
- 2022年06月
- 設問項目:
-
海苔の嗜好度/食べる海苔のタイプ/海苔の食べ方/海苔を食べる場面/海苔を食べる頻度/海苔の保存方法/海苔購入時の重視点/海苔に期待する効果・効能/海苔の好きな食べ方やこだわり(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■海苔が好きな人は9割弱。「好き」の比率は女性や高年代層で高い傾向。食べる頻度は「週に2~3回」「週に1回程度」がボリュームゾーン。保存方法は「購入した容器・袋のまま常温」が食べる人の5割強、「購入した容器・袋のまま冷蔵庫」「チャック付きの袋やタッパーなどに入れかえ常温」が各2割強。
■食べる海苔のタイプは「焼き海苔」「味付け海苔」が各70%台、「青のり」「韓国海苔」が各4割弱。「韓国海苔」は女性若年層での比率が高い。東日本では「焼き海苔」、西日本では「味付け海苔」が1位。
■海苔を「ご飯と一緒に食べる」が海苔を食べる人の8割強、「おにぎりに巻く」が7割強、「のり巻き、軍艦巻き」「完成した料理にかける・のせる」「そのまま海苔だけ食べる」が各4割前後。海苔を食べる人のうち「朝食」に食べる人が5割弱、「昼食」が4割、「夕食」が6割弱。東北では「朝食」の比率が他の地域より高い。
■海苔を食べる人の、購入時の重視点は「味」「海苔の種類」「価格」が各5~6割、「内容量」「海苔のサイズ」が各20%台。海苔に期待する効果・効能は「生活習慣病予防」「頭皮・髪質を保持」「老化防止」などが、海苔を食べる人の各10%台。
-
- 調査時期:
- 2022年06月
- 設問項目:
-
慢性的な疲労度/ドリンク剤・滋養強壮剤の飲用銘柄/ドリンク剤・滋養強壮剤の飲用頻度/ドリンク剤・滋養強壮剤の直近1年以内最頻飲用銘柄/ドリンク剤・滋養強壮剤選定時の重視点/ドリンク剤・滋養強壮剤の飲用シーン/ドリンク剤・滋養強壮剤の飲用意向/ドリンク剤・滋養強壮剤の不満点(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■慢性的な疲労感を感じている人は全体の6割弱、女性の方がやや高い。ドリンク剤・滋養強壮剤飲用者は全体の4割弱。週1回以上飲用者は全体の1割強、ドリンク剤飲用者の3割弱。男性の方が飲用者の比率が高い。
■ドリンク剤・滋養強壮剤飲用者の、選定時の重視点は「効能・効果」「価格」が5割弱、「味」「飲みやすい」が各4割弱、「成分、添加物」が約26%。リポビタン主飲用者では「味」が1位。
■飲用シーンは「疲れがたまっている」が飲用者の7割弱、「風邪気味・発熱など体調が悪い」「栄養補給をしたい」「気合を入れたい」などが各20%台。
■今後のドリンク剤・滋養強壮剤飲用意向は全体の3割強、男性30・40代でやや高い。月1回以上飲用者では各8~9割、非飲用者では約6%。
-
- 調査時期:
- 2022年06月
- 設問項目:
-
焼酎飲用頻度/焼酎を飲む場所/直近1年間に飲んだ焼酎の種類/最も好きな焼酎の飲み方/焼酎を選ぶ際の重視点/焼酎を飲みたいシーン/焼酎をあまり飲まない理由/焼酎飲用意向/焼酎のイメージ(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■焼酎飲用者は46%で過去調査より減少傾向。週1~2日以上飲用者は全体の2割弱、男性高年代層での比率が高い傾向。家で飲む人は焼酎飲用者の7割強で、2019年調査より増加。アルコール飲用者のうち、焼酎飲用意向率は5割弱、週1~2日以上飲用者では9割強、非飲用者では約4%
■最も好きな焼酎の飲み方は「水割り」「ロック」「お湯割り」「柑橘類味+炭酸水割り」が、飲用者の各2割前後。焼酎を飲みたいシーンは「平日」「休日の前日」「休日の夜」「普段の食事のとき」などが各3割前後。
■焼酎を選ぶ際の重視点は「味・おいしさ」が飲用者の7割弱、「飲みやすさ」4割強、「価格」3割強、「主原料」「香り」「アルコール度数」が各20%台。
■焼酎非飲用者・月1日以下飲用者があまり飲まない理由は、「味が好きではない」が3割弱、「焼酎を飲む機会がない」「アルコール度数が高い」「匂いが好きではない」などが各10%台。
-
- 調査時期:
- 2022年05月
- 設問項目:
-
デジタルギフトサービスの認知/直近1年間でのデジタルギフトを贈った・もらった経験/直近1年間デジタルギフト贈答時の利用サービス/直近1年間に贈ったデジタルギフトの内容/直近1年間にもらったデジタルギフトの内容/デジタルギフトの利用意向(贈る側)/デジタルギフトを利用したい場面/デジタルギフトの利用意向(贈る側)の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■デジタルギフトサービスを知っている人は全体の5割弱。直近1年間にデジタルギフトを贈った人は1割強、もらった人は約25%。いずれも女性若年層での比率が高い傾向。
■直近1年間にデジタルギフトを贈った人(全体の1割強)のうち、「LINEギフト」が6割強、「eメールタイプのポイント・ギフトコード」が2割強、「giftee」が1割強。「飲食店、コーヒーショップ、テイクアウトサービスなどで使えるチケット・引換券」を贈った人が5割弱、「コンビニエンスストアの商品と交換」「eメールタイプのポイント・ギフトコード」が各20%台、「食品、菓子・デザート類、飲料、お酒など」が2割弱。
■直近1年間にデジタルギフトをもらった人(全体の約25%)のうち、「eメールタイプのポイント・ギフトコード」をもらった人が5割弱、「飲食店、コーヒーショップ、テイクアウトサービスなどで使えるチケット・引換券」「コンビニエンスストアの商品と交換」が各3割前後。
■デジタルギフトを贈る側としての利用意向は2割強、非利用意向は3割強。デジタルギフトを直近1年間に贈った人では約76%の利用意向、もらった人では約46%、直近1年間未利用者では1割強。利用意向者が贈りたい場面は「お返しや、ちょっとしたお礼」「誕生日や記念日」が各50%台、「お祝い事」が3割強、「気軽に贈りたい」「直接会って渡せない」「季節行事」が各2割強。
-
- 調査時期:
- 2022年05月
- 設問項目:
-
新聞購読状況/直近半年間での折込チラシ閲覧頻度/内容をよく読む折込チラシのジャンル/折込チラシがきっかけで商品・サービスを購入・利用したジャンル/折込チラシを見たときの行動/電子チラシの利用経験/ここ2~3年でのチラシを見る頻度の変化/折込チラシの代わりとしている情報収集方法(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■新聞購読者5割強のうち、折込チラシを見る人は9割弱、「ほぼ毎日見る」は6割強、「たまに見る程度」が2割強。内容をよく読む折込チラシは「スーパー」がチラシを見る人の9割弱、「ホームセンター」「ドラッグストア・薬局」が各50%台。
■折込チラシがきっかけで商品・サービスを購入・利用したジャンルは「スーパー」がチラシ閲覧者の8割強、「ホームセンター」「ドラッグストア・薬局」が各4割強。
■折込チラシがきっかけとなってしたことは「折込チラシのお店に行く」がチラシ閲読者の7割強、「折込チラシについているクーポンや割引券を利用」「キャンペーン期間に、商品・サービスを購入・利用」「商品・サービスについて他の媒体で調べる」が各20%台。
■ここ2~3年でのチラシを見る頻度が増えた人は約8%、減った人は1割強。頻度が減った人の比率は、女性50~60代でやや高い。電子チラシ利用経験は5割強。
-
- 調査時期:
- 2022年05月
- 設問項目:
-
自転車利用頻度/居住地域の自転車保険義務化の状況/自転車保険加入状況/加入自転車保険のタイプ/自転車保険加入のきっかけ/加入自転車保険の種類/自転車保険加入経路/自転車保険加入時の重視点/自転車保険への要望(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■自転車利用率は5割弱。関東や近畿、四国での利用率が高い。週1回以上利用者は全体の3割弱、自転車利用者の6割強。居住地域の自転車保険が「義務または努力義務」が4割弱。「わからない」は5割強、自転車週1回以上利用者の3~4割。
■自転車保険加入状況は、自転車利用者の6割強、近畿での加入率がやや高い。加入者のうち契約者本人対象が3割強、家族型が6割強。「自動車保険・火災保険などの特約」「自転車保険※特約以外」が各3割強。加入経路は「自転車販売店」が加入者の4割強、「インターネット」が3割弱、「保険代理店の窓口」が1割強。
■自転車保険加入のきっかけは「保険加入が義務化された」が加入者の4割弱、「自動車保険や火災保険などの加入・見直し」が2割強、「自転車購入・買い替え」「自転車に関する事故を見聞きした・あった」が各10%台。TSマーク付帯保険加入者では「自転車を購入した・買い替えた」「販売員や店員の勧め」の比率が高い。
■自転車保険加入時の重視点は、「保険料が手頃」「補償内容の充実度」が各5割前後、「商品のわかりやすさ」が3割強、「補償金額」「事故時の対応力」「自転車事故時の自分のケガ・後遺症などの補償有無・内容」が各2割強。
-
- 調査時期:
- 2022年05月
- 設問項目:
-
直近1年間コインランドリー利用頻度/コインランドリー利用場面/コインランドリー利用時間帯/コインランドリー利用時の重視点/コインランドリー利用意向/コインランドリーで気になること/利用したいと思うコインランドリーの特徴/コインランドリー利用意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■直近1年間コインランドリー利用者は全体の2割弱、利用経験者は6割弱。利用頻度は「年1~2回」がボリュームゾーン。利用者に占める月1回以上利用者は2割強。男性や若年層での比率が高い傾向。利用時間帯は「平日・午前中」「休日・午前中」がボリュームゾーン。
■利用場面は「毛布やシーツ、カーテンなど大物を洗う」が、直近1年間利用者の6割弱、「乾燥機を使いたい」が3割強、「自宅では洗いにくいもの」「洗濯物の量が多い」「クリーニングに出すより安く済ませたい」が各1割強。利用時の重視点は「アクセスの良さ」が直近1年間利用者の7割強、「料金」が4割強、「駐車場の充実度」「毛布や布団など大物の洗濯物に対応」などが各30%台。
■コインランドリー利用意向者は4割弱、非利用意向者は3割強。女性10~40代でやや高い。直近1年間利用者では各8~9割の利用意向、以前利用したことがある人では4割弱、未経験者では1割強。
■コインランドリーについて気になることは、「衛生面で不安」が5割弱、「他の人が使った後のウイルスや汚れ」「料金が高い」「洗濯機や乾燥機の手入れ」が各3割前後。利用したいと思うコインランドリーの特徴は「清潔感」が全体の5割強、「毛布や布団など大物の洗濯物に対応」「料金が割安」「防犯対策が充実」「洗濯機・乾燥機が高性能」などが各30%台。
-
- 調査時期:
- 2022年05月
- 設問項目:
-
利用している文房具/文房具へのこだわり/自分用に購入する文房具/文房具購入時の重視点/文房具購入場所/文房具の購入タイミング/こだわりがある文房具/お気に入りの文房具とお勧めポイント(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■文房具にこだわりがある人は全体の2割強。女性10~30代での比率が高い傾向。
■自分用に購入する文房具は「ボールペン」が6割強、「シャープペンシル」「セロハンテープ」「消しゴム」「のり」などが各3割前後。こだわりがある文房具は「ボールペン」が文房具購入者の約35%、「シャープペンシル」「手帳」が各1割強、「万年筆」「ノート」が各5~6%。
■文房具を「100円ショップ」で買う人が文具購入者の5割強、「雑貨店」が3割強、「ホームセンター」「スーパー」「文房具専門大型店」が各20%台。購入時の重視点は「価格」7割弱、「サイズ」「機能性に優れている、実用的」が各40%台、「デザイン」が各3割強。文房具にこだわりがある層では「デザイン」が最も多い。
■文房具を新しく購入したり買い替えるのは「使い終わった・使いきった」「使えなくなった」が購入者の各7割前後、「用途にあわせて必要」「気に入った商品を見つけた」「使いにくい」などが各2割前後。
-
- 調査時期:
- 2022年05月
- 設問項目:
-
コンビニの冷蔵コーナーのスイーツのうち購入するもの/コンビニの冷蔵コーナーのスイーツを買う頻度/コンビニスイーツ購入場面/コンビニスイーツ選定時の重視点/コンビニでのスイーツの購入金額(1回当り)/直近1年間に冷蔵コーナーのスイーツを購入したコンビニエンスストア/コンビニスイーツが最も好きなコンビニエンスストア/コンビニでスイーツを買う理由/気に入っているコンビニスイーツ(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■コンビニスイーツ購入者は全体の6割弱、男性5割弱、女性7割弱。コンビニスイーツ購入者のうち月1回以上購入者は6割強。1回あたり購入金額は「250円~300円未満」がボリュームゾーンで、2014年以降価格帯が上昇傾向。購入種類は「シュークリーム、エクレア」が約36%、「ロールケーキ」「プリン、パンナコッタ」などが各3割弱。
■コンビニスイーツ購入場面は「甘いものが食べたい」が購入者の7割弱、「食後のデザート」「店頭でおいしそうな商品を見かけた」が各3割弱、「立ち寄ったついで」「小腹が空いた」などが各2割強。
■コンビニでスイーツ購入理由は「いつでも買える」が購入者の5割弱、「おいしい・おいしそう」が4割弱、「立地がよい・行きやすい」「価格が手頃」などが各3割弱。購入者の重視点は「味」「価格」に続き、「容量、サイズ」「食感」「色合い・見た目」などが各20%台。
■スイーツが最も好きなコンビニエンスストアは、「セブン‐イレブン」がコンビニスイーツ購入者の4割弱、「ローソン」が3割強。