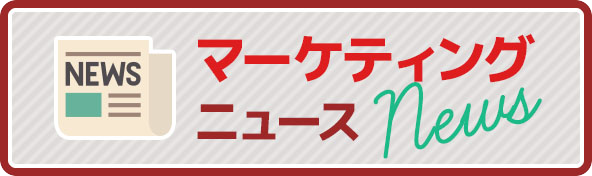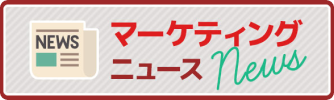- 検索
-
- テーマ別実施時期一覧
- カテゴリー別一覧
-
-
アルコール飲料・嗜好品145
-
非アルコール飲料209
-
その他19
-
-
住宅・住宅設備218
-
-
家電126
-
パソコン・カメラ・AV機器113
-
その他10
-
-
家庭用品・トイレタリー91
-
自動車・関連用品76
-
-
インターネット・情報通信327
-
携帯電話・スマートフォン180
-
メディア・広告66
-
その他7
-
-
ファッション68
-
交通・レジャー・娯楽161
-
季節行事・イベント241
-
時事・ニュース・トレンド51
-
企業ブランドイメージ246
-
広告・CM51
-
WEBサイトの利用91
-
顧客満足度100
- 実施時期別一覧
-
- 調査時期:
- 2019年11月
- 設問項目:
-
マスク着用の積極度/マスクを使う季節/マスク着用場面/使用するマスクのタイプ/最もよく購入する市販のマスクの枚数(何枚入り)/マスク選定時の重視点/マスクに期待する効能・効果/マスクの使い方・こだわり(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■マスク着用者は全体の8割強。積極的着用層、非積極的着用層はいずれも3割強。女性の方が積極的着用者の比率が高い。マスク着用者のうち「冬」に使う人が6割弱、「春」が3割弱、「特に季節は決まっていない」「一年を通して使う」が各10%台。
■着用場面は「風邪をひいている、咳が出るなどの症状がある」「風邪やインフルエンザなど感染しやすい症状の人が周囲にいる・流行っている」が、マスク着用者の各6~7割、「病気の予防」「人ごみやほこりっぽい、空気が悪い所」が各5割弱、「花粉症対策・予防」が4割弱。
■市販のマスクのうち「大容量/箱入り」を最もよく買う人が5割弱。マスク選定時の重視点は「使い捨てタイプ」が着用者の8割強、「価格」が4割強、「大きさ」「フィット感」が各3割強。「大きさ」は女性での比率が高い。
■マスクに期待する効能・効果は「細菌やウイルス、花粉、ハウスダストなどのカット率が高い」が着用者の6割強、「息苦しくない」「耳が痛くならない」が各4割強、「フィットする」「メガネがくもりにくい、メガネくもりをカット」が各3割前後。
-
- 調査時期:
- 2019年11月
- 設問項目:
-
薄型テレビ所有タイプ/薄型テレビ購入時期/薄型テレビ購入のきっかけ/主利用薄型テレビのメーカー/薄型テレビ画面で見るもの/薄型テレビ購入時に重視すると思う点/薄型テレビ購入予定時期/新4K衛星放送対応テレビ購入意向/主利用薄型テレビ選定理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■液晶テレビ所有者は9割弱、「プラズマテレビ」が8%。購入のきっかけは「故障した」が購入者の3割強、「地上放送のデジタル化」「テレビが古くなった」が各3割弱。過去調査と比べ「故障した」が増加、「地上放送のデジタル化」「価格が安くなった」「エコポイント」などが減少傾向。
■薄型テレビ購入時の重視点は「価格」「画面サイズ」が各6~7割、「メーカー・ブランド」「画質のよさ」などが各4~5割。過去調査と比べ「BSデジタル放送・スカパー対応」「デジタルハイビジョン対応」などが減少傾向。
■薄型テレビ画面でテレビ番組以外で見るものは、「DVDやBD」が薄型テレビ所有者の6割弱、「YouTubeなど動画共有サービス」「ゲーム機と接続しゲーム画面」が各1割強。
■今後の薄型テレビ購入予定者は全体の4割強、薄型テレビ所有者の各4~5割。新4K衛星放送対応テレビ購入意向者は2割強、非購入意向者は3割強。有機ELテレビ所有者や、プラズマテレビ所有者での比率が高い。
-
- 調査時期:
- 2019年11月
- 設問項目:
-
料理が好きかどうか/料理をする頻度/「何も参考にせずに作れる」と思う料理/「できる」と思う調理の技法・方法/夕食作りにかける時間/レシピの参考度合い/料理についての困りごと・不満/「料理」だと思うもの/料理を学んだ・身につけた環境(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■料理が好きな人は全体の4割弱。自分で料理をする人は男性7割強、女性30代以上で9割以上。料理を「ほぼ毎日」する人は全体の4割弱、女性40代以上の6~8割。「ほとんんどの場合レシピを見ない」は料理をする人の4割強、女性高年代層で高い。
■何も参考にせずに作れる料理は「目玉焼き」「おにぎり」が各70%台、「卵焼き」「味噌汁」「カレー」「野菜炒め」「チャーハン」「いり卵」が各60%台。できると思う調理技法の中で順位が低いのは、「魚を三枚におろす」「桂むき」各3割、「板ずり」「いかの皮をむく」「わたをとる」「隠し包丁を入れる」各4割。
■料理だと思うものの上位は「餃子等の皮は市販で具は手作り」「カレー等に市販のルーを使う」「だしの素、だしつゆを使う」「下ごしらえ済みの魚を調理」「から揚げ粉を使う」など、下位は「カップめんにお湯を注ぐ」「レトルト食品や冷凍食品を温める」「インスタントみそ汁・スープを作る」「炊いたご飯にレトルトの具材をかける」「インスタント袋めんを調理」など。
■料理についての困りごと・不満は「レパートリーが少ない」「メニューがなかなか決まらない」「後片付けが面倒」「栄養バランスのよいメニューを考えるのが難しい」などが各3~4割。女性若年層では「手際が悪い、時間がかかる」「料理の基本に自信がない」「レパートリーが少ない」などの比率が高い。
-
- 調査時期:
- 2019年11月
- 設問項目:
-
大豆食品に対する関心度/大豆食品として知らなかった商品/健康のために意識して飲食している大豆食品/食事における大豆食品の摂取度合い/大豆食品の魅力点/大豆食品購入時に気になること/大豆食品で気に入っているもの(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■大豆食品の関心層は全体の7割強。女性や高年代層での比率が高い傾向。
■大豆食品の魅力は、「値段が手頃」「手軽に食べられる」が各60%台、「たんぱく質が豊富(高たんぱく)」が4割弱、「安心して食べられる」「低カロリー」などが各2割強。
■普段の食事で大豆食品を意識して取り入れている人は6割強、女性や高年代層での比率が高い。健康のために意識して飲食している大豆食品トップ2は「納豆」「とうふ」で各6割前後。過去調査と比べ「味噌」などが増加傾向。
■大豆食品購入時に気になることは「味」「原産国」「価格」が各40%台、「遺伝子組み換え」「消費期限、製造年月日」「添加物の有無」などが各2~3割で上位。過去調査と比べ「遺伝子組み換えかどうか」「原産国」などが減少傾向。
-
- 調査時期:
- 2019年11月
- 設問項目:
-
自宅でパスタ料理を食べる頻度/自宅で食べる際の好きなパスタの種類・ソース/パスタソースの準備方法/市販のパスタソース利用頻度/市販のパスタソース利用場面/パスタソース購入時の重視点/市販のパスタソース選定時の銘柄指定/自宅でパスタを食べる際の、市販のパスタソース利用意向/市販のパスタソース不満点/非利用理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■自宅でパスタ料理を食べる人は全体の9割弱、週1回以上食べる人は2割弱。市販のパスタソース利用者は、自宅でパスタを食べる人の約75%。「レトルトパウチ入りのパスタソース・ペースト状:温める」利用者は5割強、「市販の缶詰」は2割強。
■自宅で食べるパスタで、好きな種類やソースは「ミートソース、ボロネーゼ」が6割強、「トマトソース」「ナポリタン」が各5割前後、「たらこ・明太子」「カルボナーラ」が各4割強、「ペペロンチーノ」「和風(たらこ・明太子以外)」などが各3割前後。
■市販のパスタソース利用場面は「自宅でパスタを食べる時はだいたい利用する」が、市販のソース利用者の5割強。「食事を簡単に済ませたい」「すぐに食べたい・すぐに準備する必要がある」「自分では作れないパスタソースを食べたい」などが、各2割強~3割強。
■市販のパスタソース利用者の重視点は「味」8割強、「価格」6割強、「容量、サイズ」「メーカー」「原材料」「賞味期限・消費期限」「手順が簡単」「成分、添加物」などが各2~3割。市販のパスタソース利用意向者は自宅でパスタを食べる人の7割強、現在利用者の9割弱、非利用者の3割弱。
-
- 調査時期:
- 2019年11月
- 設問項目:
-
市販のコーヒー飲料の飲用タイプ/チルドコーヒーの飲用頻度/チルドコーヒーを飲む場面/直近1年間に飲んだチルドコーヒーの銘柄/直近1年間に最もよく飲んだチルドコーヒーの銘柄/チルドコーヒー購入時の重視点/チルドコーヒー飲用理由/チルドコーヒー飲用意向/チルドコーヒーを飲むシーン(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■チルドコーヒーの飲用者は全体の5割強、女性30~50代での比率が高い。飲用場面は「おやつの時」「ちょっと一息つきたい時」「気分転換したい時」「仕事・勉強・家事の合間」などが飲用者の各20%台。
■チルドコーヒー飲用理由は「おいしい」が飲用者の5割弱、「価格が手頃」「好きな味のタイプがある」「ストローがついていて飲みやすい」「味が本格的」などが各2~3割。マウントレーニア主飲用者では「好きな味のタイプがある」の比率が高い。
■チルドコーヒー購入時の重視点は「価格の手ごろさ」「ミルクとコーヒーのバランス」「コーヒーの味の強さ」などが上位。スターバックス主飲用者では「コーヒーの味の強さ」が重視点の1位。
■チルドコーヒー飲用意向者は全体の4割強、飲用頻度が2~3か月に1本以上の層では8割強~9割強、非飲用者では約6%。
-
- 調査時期:
- 2019年10月
- 設問項目:
-
敬老の日のお祝いの有無/敬老の日に行ったこと/お祝いする立場だが何もしていない理由/今年の敬老の日に贈ったプレゼント/今年の敬老の日に関する費用総額/敬老の日の対象年齢/あなたにとって敬老の日とは/敬老の日のお祝いの内容(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■敬老の日にお祝いをした人は全体の2割弱。「お祝いをする立場だが特に何もしていない」が全体の4割強。
■プレゼントを渡した・贈った人は、全体の1割弱。プレゼントはお菓子や食品、花・植物、衣料品などが上位。
■お祝いする立場だが敬老の日に特に何もしなかった理由は「日頃から接しているので特別にお祝いしない」「季節行事のお祝い事はしない」「『敬老の日』以外の日に祝っている」などが各2割前後。
■敬老の日とは、「普段と同じ・特別な意識なし」「祖父母の長寿を祝う日」が各3割前後、「親孝行をする日」「(祖父母に限らず)高齢者を敬い、長寿を祝う日」がなどが各2割弱。
-
- 調査時期:
- 2019年10月
- 設問項目:
-
携帯電話・スマートフォン利用状況/主利用携帯電話会社・通信会社/利用携帯電話・スマートフォンの機種のメーカー/携帯電話・スマートフォンの買い替え経験/携帯電話・スマートフォン買い替え時のメーカー変更状況/携帯電話・スマートフォンの購入意向/スマートフォン購入時の重視点/スマートフォン購入時の、メーカー変更意向/主利用携帯電話・スマートフォンの端末の不満点(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■スマートフォン主利用者(約75%)のうち、スマートフォンからの買い替えは7割弱、携帯電話からの買い替えは3割弱。過去調査と比べ、スマートフォンの買い替えの比率が増加傾向。スマートフォンと携帯電話の併用者は約6%。
■「1台前と同じメーカーの機種」は、スマートフォンの買い替え者で6割強、過去調査と比べ増加傾向。携帯電話からスマートフォンへの買い替え者では「1台前とは違うメーカーの機種」が7割強。アップル主利用者やソニーモバイルコミュニケーションズ主利用者では「1台前と同じメーカーの機種」の比率が高い。
■スマートフォン購入意向は、スマートフォン主利用者の9割強、携帯電話主利用者の3割弱。携帯電話主利用者の携帯電話購入意向は4割弱。同じメーカー購入意向率は、スマートフォン購入意向者の5割弱、アップル主利用者では8割強と高い。
■スマートフォン購入意向者の重視点は「バッテリーの持ち時間」「機器本体の価格」「重さ、本体の大きさ」「画面の大きさ」「デザイン・色・形などの外観」「操作のわかりやすさ」などが各4~5割。
-
- 調査時期:
- 2019年10月
- 設問項目:
-
電子マネー・現金で支払う度合い/店頭での電子マネー支払い方法/直近1年間に利用した電子マネー/電子マネーの利用場所/電子マネーのチャージ方法/店頭での電子マネー利用頻度/直近1年間で店頭で最もよく使った電子マネー/非接触IC型電子マネーの利用意向/非接触IC型電子マネーの不満点/非利用理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■直近1年間非接触型電子マネー利用者は全体の8割弱。そのうち、週1回以上利用者は5割強。「コンビニエンスストア」「交通機関」での利用が、直近1年間利用者の各60%台、「スーパー」が5割弱、「自動販売機」「ドラッグストア」「駅の売店」が各20%台。
■店頭で支払う際「電子マネーのカード本体を端末にかざして支払う」は全体の5割強。スマートフォンで「店頭の端末にかざして支払う」は2割弱、「画面にバーコードを表示しスキャン」「店頭で表示されたQRコードを読み取る」などは各1割で、2017年調査より増加。
■電子マネー利用意向は全体の7割弱。電子マネー直近1年間利用者では8割強の利用意向、非利用者では2割弱。
-
- 調査時期:
- 2019年10月
- 設問項目:
-
婚姻・就業状況/家計の管理者/1ヶ月あたりの可処分所得/1ヶ月あたりの自由に使えるお金の金額/自由に使えるお金の使用目的/理想のお金の使い道/自由に使えるお金の金額の満足度/自由に使えるお金の理想金額/自由に使えるお金を使う際に気をつけていること、ルール(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■1ヶ月あたりの自由に使えるお金の金額が3万円未満の層は全体の6割弱。自由に使える金額(月額)は「1~2万円未満」「2~3万円未満」、理想の金額は「4~5万円未満」がボリュームゾーン。
■自由に使えるお金の使用目的は「外食」が5割弱、「旅行、レジャー」「衣類・衣類小物、アクセサリー」「書籍、雑誌、新聞代」が各30%台、「食費」「友人知人とのコミュニケーション」「交通費」「美容、化粧品」などが各3割弱。貯蓄は1割強。上位3位は男性「外食」「旅行、レジャー」「書籍、雑誌、新聞代」、女性「衣類・衣類小物、アクセサリー」「美容、化粧品」「外食」。
■理想のお金の使い道は「旅行、レジャー」が、自由に使えるお金がある人の4割弱。「貯蓄」は2割弱。
■自由に使えるお金の金額に満足している人は3割強、不満な人は約35%。満足している人の比率は60・70代で高く、男性30代で低い。
-
- 調査時期:
- 2019年10月
- 設問項目:
-
コンビニATMの利用頻度/利用しているコンビニATM/直近1年間の最頻利用コンビニATM/最頻利用コンビニATMの利用理由/最頻利用コンビニATMの利用場面/コンビニATMで1回あたりにおろす金額/コンビニATM利用意向/コンビニATM利用意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■コンビニATM利用者は7割弱、月1回以上利用者は3割強。利用しているコンビニATMは「セブン‐イレブン」が1位、「ファミリーマート」「ローソン」が2~3位。四国では「ローソン」が1位。
■直近1年間コンビニATM利用者の、最頻利用コンビニATM利用理由は「自宅・勤務先・学校などの近くにある」「口座を持っている銀行が利用できる」「手数料が安い・無料」が上位3位。
■コンビニATMの利用場面は「すぐに現金を引き出したい」「銀行ATMが近くにない」「コンビニATMが近くにある」が、直近1年間利用者の3割弱。
■コンビニATM利用意向者は全体の5割弱。2~3か月に1回以上利用者では各8~9割、年1回未満利用者では3割弱、利用未経験者では約4%。
-
- 調査時期:
- 2019年10月
- 設問項目:
-
直近3年間での問い合わせ窓口の利用手段/直近3年間にチャットサポート・チャットボットで問い合わせた企業/直近3年間にチャットサポート・チャットボットで問い合わせた内容/直近3年間にチャットサポート・チャットボットで問い合わせた理由/問合せ窓口利用時の重視点/問合せ窓口への問い合わせ方法の意向/チャットサポートやチャットボットでの問い合わせ意向/チャットサポートやチャットボットでの問い合わせ意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■直近3年間での問い合わせ窓口利用者は全体の5割強。手段は「電話」が4割強、「問い合わせフォーム」「メール」が各2割強。今後の意向は「電話」が7割弱、「メール」「問い合わせフォーム」が各40%台、「チャットサポートが2割弱。
■問い合わせ窓口利用時の重視点は「電話のつながりやすさ」が全体の6割強、「通話料・通信料がかからない」「説明のわかりやすさ」「たらい回しにされない、待たされない」「土日祝日や夜間に問い合わせ可能」などが各4割弱。
■直近3年間にチャットサポートなどでの問い合わせ経験者は全体の1割強、直近3年間問い合わせ窓口利用者の2割強。理由は「時間や場所に関わらず、いつでも相談できる」が利用者の6割弱、「気軽に問い合わせができる」「待たされない」「Webサイトなどから誘導された」が各4割前後。
■チャットサポートやチャットボットでの問い合わせ意向者は3割弱、非利用意向者は約35%。利用意向者の比率は、直近3年間チャットサポート等利用者では7割弱、非利用者では2~3割。
-
- 調査時期:
- 2019年10月
- 設問項目:
-
水筒利用頻度/利用している水筒のタイプ/主利用水筒のタイプ/水筒に入れているもの/水筒利用理由/水筒利用場面/水筒購入時の重視点/水筒利用意向/水筒の不満点・非利用理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■水筒利用者は全体の5割強、女性での比率が高い。週1日以上利用者は全体の4割弱、水筒利用者の7割強。利用意向は全体の6割弱、水筒利用者の8~9割、非利用者の約15%。
■「直飲みタイプ:ワンタッチ式」「直飲みタイプ:マグタイプ」が水筒利用者の各40%台、「コップつき」が2割弱、「プラスチックボトル」が1割強。水筒に入れるものは「日本茶」「麦茶」が各4割強、「コーヒー」「ミネラルウォーター」「水道水」が各2割前後。
■水筒利用理由は「節約」が利用者の5割強、「まめに水分補給」「いつも冷たい・温かいものを飲みたい」「長時間外出するときの水分補給」が利用者の各3~4割。利用場面は「職場や学校」が利用者の5割弱、「旅行、ドライブ」「長時間外出」が各3割前後。
■自分や家族が使う水筒購入時の重視点は「容量」「価格」「軽さ」「大きさ」などが上位。
-
- 調査時期:
- 2019年10月
- 設問項目:
-
デジタルカメラの所有台数/所有しているデジタルカメラのタイプ/所有しているデジタル一眼レフのタイプ/最もよく利用するデジタルカメラのブランド/デジタルカメラでの直近1年間の撮影頻度/デジタルカメラで撮影した写真の利用方法/デジタルカメラ利用意向/デジタルカメラ購入時の重視点/デジタルカメラの使い分け、非利用理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■デジタルカメラ所有率は全体の7割強、2010年以降減少傾向。デジタルカメラ所有者のうち、コンパクトタイプ所有者が9割強。一眼レフ所有者は2割強で、過去調査と比べ増加傾向。利用者のうち、直近1年間に月1回以上撮影者は3割強。
■デジタルカメラで撮影した写真の保存・利用方法は「パソコン内のハードディスクに保存」「撮ったまま」が利用者の各5割前後、「自宅のプリンターで印刷」が3割弱。「撮ったまま」が過去調査より増加傾向、「自宅のプリンターで印刷」は減少傾向。
■デジタルカメラ利用意向は全体の5割弱、非利用意向は2割強。デジタルカメラ1台所有者では5割強の利用意向、一眼レフ所有者では7~8割、非所有者では1割強。所有者で直近1年間に撮影していない層では2割強の利用意向。
■デジタルカメラ利用意向者の重視点は「画素数・画質」「軽い」「使いやすさ」が各50%台、「価格の安さ、手ごろさ」「持ちやすさ」が各4割前後。
-
- 調査時期:
- 2019年10月
- 設問項目:
-
住宅設備購入・リフォーム経験/住宅設備メーカー認知/商品・サービスを購入したことのある住宅設備メーカー/「信頼性・安心感がある」住宅設備メーカー/「品質・技術が優れている」住宅設備メーカー/「独自性がある」住宅設備メーカー/「革新的・先進的である」住宅設備メーカー/「親近感がある」住宅設備メーカー/住宅設備メーカーに期待すること(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■住宅設備メーカー認知率上位5位は「TOTO」「LIXIL」「パナソニック」「リンナイ」「クリナップ」で各7~9割。2013年調査より「LIXIL」が増加傾向。
■『信頼性・安心感がある』『品質・技術が優れている』『親近感がある』住宅設備メーカーは「TOTO」が各5~6割で1位、「パナソニック」「LIXIL」「YKK AP」「リンナイ」などが続く。2013年と比べ、いずれの項目でも、「LIXIL」の比率が増加。
■『独自性がある』『革新的・先進的である』住宅設備メーカーは「いずれもない」が各4~5割。「TOTO」が各3割で1位、「LIXIL」「パナソニック」「タカラスタンダード」などが続く。信頼性・品質・親近感などのイメージ項目と比べ「LIXIL」「タカラスタンダード」の順位が上位となっている。
-
- 調査時期:
- 2019年10月
- 設問項目:
-
冷凍食品利用頻度/冷凍食品利用場面/冷凍食品利用理由/冷凍食品購入頻度/購入する冷凍食品の種類/冷凍食品購入時の重視点/よく購入する冷凍食品メーカー/気に入っている冷凍食品・気に入っている理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■冷凍食品利用者は全体の8割強。週1回以上利用者が5割弱。利用場面は「夕食」が利用者の5割強、「昼食」4割強、「お弁当」「食事を簡単に済ませたい」「すぐ食べたい」「料理を作るのが面倒」「おかずの品数を増やしたい」が各20%台。
■冷凍食品利用理由は「すぐにできあがる」「保存がきく」「手順が簡単」「調理や後片付けの手間が省ける」が利用者の各4割強~5割、「少量必要なときに便利」が3割強。
■冷凍食品1回以上購入者は3割弱。購入する冷凍食品は「麺類」「米飯類」が購入者の各5割前後、「中華系の軽食」「あげもの類」などが各3~4割。過去調査と比べ「米飯類」が増加傾向、「お弁当用」などが減少傾向。素材系では「野菜などの農産物」「水産素材」が購入者の各3割弱。
■冷凍食品購入時の重視点は「味」「価格」が購入者の各6~7割、「容量、サイズ」「生産国・地域」が各3~4割、「安全性」「原材料」「メーカー」などが各2割強。
-
- 調査時期:
- 2019年10月
- 設問項目:
-
魚介類の料理の嗜好度/魚介類の料理を食べる頻度/よく食べる魚介類の加工品/好きな魚介類/魚介類購入時の重視点/魚介類の料理で好きなもの/魚介類のイメージ/魚介類の摂取についての意識/魚介類に関する不満点(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■魚介類の料理が好きな人は全体の8割弱。好きな料理は「刺身」「寿司」が、魚介類を食べる人の各8割強、「塩焼き」が6割強、「天ぷら」「フライ、唐揚げ」「干物」「照り焼き」が各5割前後。週2~3回以上食べる人が6割強。魚介類を食べるように意識している人は全体の6割強、高年代層で高い傾向。
■食べるのが好きな魚介類は「サケ」が7割弱、「サバ」が6割強、「サンマ」「エビ」「アジ」「マグロ」「イカ」が各50%台。よく食べる魚介類の加工品は「缶詰」「練り製品/かまぼこ類」「干物」「かつお節、削り節」などが各5~6割。過去調査より「干物」が減少傾向。
■魚介類購入時の重視点上位は「価格」「鮮度」が魚介類を食べる人の各5~6割、「種類」「国産・外国産」が各4割弱、「品質」「季節感・旬のもの」「産地」「食べやすさ」「安全性」などが各3割前後。
■魚介類のイメージは「健康によい」「おいしい」が各7割弱、「ヘルシー」「季節感がある」「栄養価が高い」などのよいイメージが各3~4割。悪いイメージでは「調理が面倒」「価格が高い」などが各2割強。
-
- 調査時期:
- 2019年10月
- 設問項目:
-
アルミパック入りゼリー飲料の飲用頻度/直近1年以内に飲用したアルミパック入りゼリー飲料銘柄/直近1年以内に最もよく飲用したアルミパック入りゼリー飲料/アルミパック入りゼリー飲料飲用理由/アルミパック入りゼリー飲料飲用場面/アルミパック入りゼリー飲料購入時の重視点/アルミパック入りゼリー飲料の飲用意向/アルミパック入りゼリー飲料の不満点・非飲用理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■アルミパック入りゼリー飲料飲用者は全体の3割強、週1回以上飲用者は5%。今後の飲用意向は全体の3割弱、月1回以上飲用者の9割、非飲用者の約5%。
■アルミパック入りゼリー飲料飲用理由は「エネルギー補給」「味が好き」「摂りたい栄養成分が入っている」が飲用者の各3割前後、「価格が手頃」「すばやく飲める」「空腹を満たすため」「食欲がない時や体調が悪い時でも飲みやすい」などが各2割強。
■飲用場面は「おやつ」「小腹がすいた」「体調が悪い」「食欲がない」「朝食時」などが飲用者の各2割前後。即効元気ゼリー主飲用者では「疲れたとき」、inゼリー主飲用者では「体調が悪いとき」が1位。
■アルミパック入りゼリー飲料購入時の重視点は「味」が飲用者の6割強、「価格」が約45%、「フレーバー」「効能」が各30%台、「成分、添加物」「カロリー」などが各2割。過去調査と比べ「カロリー」などが減少傾向。
-
- 調査時期:
- 2019年09月
- 設問項目:
-
1年前と比べた、生活全体の支出額の変化/1年前と比べた、生活全体の収入額の変化/1年前と比べた、購買意欲の変化/1年前と比べてお金をかけていること/今年お金をかけるのを我慢している分野/消費行動スタイル/消費に関する考え方・行動/今後1年間の購買意欲の変化/消費税10%に伴う家計支出の引き締め度合い/今後1年間の購買意欲変化の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■1年前と比べ生活全体の支出額は、増えた人が3割弱、減った人が2割弱、「変わらない」が6割弱。収入額は、増えた人が1割強。収入が減った人は約25%で、過去調査と比べ減少傾向。
■1年前と比べ購買意欲が低い人は3割弱、購買意欲が変わらない人は6割強。今後1年間の購買意欲が変わらない人が6割弱、高くなると思う人は約7%。購買意欲が低くなると思う人は3割強で、2017年より増加傾向。
■1年前よりお金をかけていることがある人は7割弱。「食品・飲料」「旅行、レジャー」「外食、グルメ」などが各2割前後。今年お金をかけるのを我慢している人の比率は過去調査より減少傾向。「旅行、レジャー」「外食、グルメ」「衣料品、アクセサリー」などが各2~3割。
■消費税10%に伴い、家計支出を引き締めると思う人が5割強、「どちらともいえない」が4割弱。
-
- 調査時期:
- 2019年09月
- 設問項目:
-
遊園地・テーマパークの直近5年以内利用頻度/直近5年以内に利用した遊園地・テーマパーク/直近で利用した遊園地・テーマパーク/直近の遊園地・テーマパーク利用時にかかった費用(1人あたり)/直近で利用した遊園地・テーマパークに一緒に行った人/遊園地・テーマパークに行くにあたり調べること/遊園地・テーマパーク選定時の重視点/今後行きたい遊園地・テーマパーク/好きな遊園地・テーマパークとその理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■遊園地・テーマパークの直近5年以内利用者は全体の4割弱。女性や若年層での比率が高い。「年に1回以下」利用者は全体の3割弱でボリュオームゾーン。
■直近5年以内に行った遊園地・テーマパークは全体では、東京ディズニーランド/シー、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンがトップ3。近畿、中国、四国では「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」、九州では「ハウステンボス」が1位。今後行きたい遊園地・テーマパークのトップ3も、東京ディズニーランド/シー、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン。
■遊園地・テーマパークに行くにあたり調べることは「現地までの行き方、交通手段等」「チケット代」「アトラクションの種類や稼働状況」が直近5年以内利用者の各5~6割、「割引・クーポン券など」「イベント・ショーなどのスケジュール」「園内の地図、経路」が各30%台。
■遊園地・テーマパーク選定時の重視点は「アクセス・立地」「アトラクションの種類の豊富さ」「料金が手頃」が直近5年以内利用者の各4割前後。
-
- 調査時期:
- 2019年09月
- 設問項目:
-
ペット所有状況/飼っているペットの種類/行っているペットの世話/ペットを飼う上で気になること/ペットの世話にかかる費用/ペット用品購入場所/定期的に購入しているペット用品/あなたにとってペットとは(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■ペット飼育者は3割弱、過去調査と比べ減少傾向。そのうち「犬」を飼っている人が4割強、「猫」が4割弱、「魚類」が2割弱。
■行っているペットの世話は「食事や餌、水などを与える」がペット飼育者の約85%、「掃除をする」が7割弱、「一緒に遊ぶ」「居住環境を整える」「からだなどの手入れ」「動物病院に連れていく」などが各5~6割。ペット飼育者が気になることは、「健康状態、病気」が4割強、「排泄物の始末」「におい」「飼育環境」などが各3割弱。
■ペット用品購入者が、定期的に購入しているペット用品は、犬や猫の飼育者では「犬猫用ドライフード」が各9割。犬飼育者では「トイレ用シーツ」「おやつ用フード」、猫飼育者では「トイレ砂」「ウェットフード」などの比率が高い。
■ペット用品購入場所は「ホームセンター」がペット飼育者の5割強、「ペットショップ、ペット用品専門店」「オンラインショッピング」「スーパー」「ドラッグストア」などが各2~3割。
-
- 調査時期:
- 2019年09月
- 設問項目:
-
健康に気をつけている度合/健康のために摂取を心がけている成分/摂取している成分に期待する効果/摂取している成分を摂取するきっかけ/成分の摂取方法/成分を摂取している飲食物/健康のために摂取したい成分/栄養成分に関することで気になっていること(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■健康のために摂取を心がけている成分がある人は全体の6割弱、女性7割弱。摂取成分の上位5項目は「ビタミンC」「乳酸菌」「カルシウム」「たんぱく質」「ビタミンB」。今後摂取したい成分の上位5項目は「ビタミンC」「カルシウム」「乳酸菌」「DHA」「鉄」。女性では「カルシウム」「鉄」「コラーゲン」などの比率が高い。
■成分を摂取するきっかけは「テレビ番組・CM」「家族や友人・知人のすすめ」「新聞記事・広告」「健康や栄養などに関するWebサイト」「メーカーや店舗のホームページ」などが上位。
■摂取成分に期待する効果は「健康維持」が栄養成分摂取者の6割弱、「免疫力・抵抗力向上」「体調不良の改善、病気の改善・悪化防止」「疲労回復」などが各3~4割。
■成分の摂取方法は「食べ物、飲み物」「サプリメント」が各6割前後。摂取している飲食物は「乳製品」「野菜、きのこ類」が各6割弱、「大豆加工品」「魚介類、水産加工品、海藻類」が各5割前後、「卵」「精肉類、食肉加工品」「果物類」などが各4割弱。
-
- 調査時期:
- 2019年09月
- 設問項目:
-
スマートフォン所有状況・主利用機種/スマートフォンで利用している機能・サービス/利用スマートフォンの満足度/スマートフォン利用意向/スマートフォン選定時の重視点/スマートフォン購入時の携帯電話会社・通信事業者の変更意向/スマートフォン購入時の携帯電話会社・通信事業者の変更意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■スマートフォン所有率は全体の8割弱で、過去調査より増加傾向。若年層で高く、10~40代8割強~9割。iPhone主利用者は2割強。iPhone主利用者では利用スマホに「満足」と回答した人の比率が他の層より高い傾向。
■スマートフォンで利用している機能・サービスは「通話」が所有者の9割弱、「カメラ」が8割弱、「時計、アラーム」「スマートフォン用のWebサイト閲覧」「電卓」「Webメール、パソコンメール、フリーメールなど」「電話帳、アドレス帳」「Wi‐Fi」などが各6~7割。過去調査と比べ「Bluetooth機能」「オンラインショッピング」「スマホ決済」などが増加傾向。
■スマートフォンの利用意向は全体の7割強、過去調査より増加傾向。スマートフォン所有者では9割弱、非所有者では2割強。意向者の選定時の重視点は「本体価格」「バッテリー」が各5~6割「通信料金」「画面サイズ・大きさ」などが各40%台。
■次回購入時に「同じ携帯電話会社・通信事業者にしたい」は、スマホ利用意向者の6割弱、NTTドコモ主利用者、au主利用者で高い。「携帯電話会社・通信事業者にはこだわらない」は2割弱、大手キャリア以外利用者で高い。
-
- 調査時期:
- 2019年09月
- 設問項目:
-
利用している音源・音楽コンテンツ/定額制音楽配信サービスの利用頻度/直近1年間に利用した定額制音楽配信サービス/直近1年間の最頻利用定額制音楽配信サービス/定額制音楽配信サービス選定時の重視点/定額制音楽配信サービスの平均利用月額/定額制音楽配信サービスを利用する機器/定額制音楽配信サービス利用意向/定額制音楽配信サービス利用意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■直近1年間の定額制音楽配信利用者は全体の2割弱、過去調査と比べ増加傾向。そのうち、週1回以上利用者は6割弱、若年層での利用頻度が高い傾向。「Amazon Prime Music」利用者が3割強。
■直近1年間の定額制音楽配信利用者の重視点は「月額料金」が5割弱、「無料版・無料お試しの充実度」「好きなアーティストの楽曲の充実度」「楽曲の曲数」が各3割前後。
■定額制音楽配信サービスの利用意向者は全体の1割強、非利用意向者は6割強。利用意向率は、週4~5回以上利用者では各9割前後、週1回利用者は6割弱、利用未経験者は約4%。
-
- 調査時期:
- 2019年09月
- 設問項目:
-
中食の利用頻度/直近1年間にテイクアウト・持ち帰りをした店舗/直近1年間にテイクアウト・持ち帰りをした頻度/食べ物のテイクアウト時の目的・用途/食べ物のテイクアウトをする理由/食べ物のテイクアウトをする際の重視点/中食の今後の利用頻度の増減/食べ物をテイクアウトする際の不満点(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■直近1年間テイクアウト利用者は、全体の7割強。「ファストフード」が4割強、「牛丼、餃子、寿司などのチェーン店」「イートインスペース」が各2~3割。
■直近1年間テイクアウト利用頻度は「月に2~3回」「月に1回程度」「2~3か月に1回程度」が直近1年間テイクアウト利用者の各2割でボリュームゾーン。週1回以上は2割弱。直近1年間での食べ物のテイクアウト利用者の目的・用途は「休日・昼食」が4割強、「平日・昼食」が3割強、平日や休日の夕食が各3割弱。
■食べ物のテイクアウト理由は「リラックスして食べたい」「時間がない、早く済ませたい」「すぐには食べない、後で食べる」「家での食事・おやつの一品」などが、直近1年間での食べ物テイクアウト利用者の各20%台。
■中食を利用する人は5割強。中食の今後の利用頻度が今後増えると思う人計は全体の2割強、減ると思うは約7%、「変わらない」が7割強。
-
- 調査時期:
- 2019年09月
- 設問項目:
-
ファストフード店の利用頻度/直近1年以内に利用したファストフード店/直近1年以内の最頻利用ファストフード店/ファストフード店利用時の重視点/ファストフード店の利用場面/最も好きなファストフード店/ファストフードの嗜好度/最も好きなファストフード店の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■ファストフード店月1回以上利用者は全体の約45%。ファストフード利用者が最も好きなファストフード店は「マクドナルド」が3割強、「モスバーガー」が2割。「マクドナルド」は2015年よりやや増加傾向。
■ファストフード店の重視点は「食べ物がおいしい」「値段が手頃」が各4~5割、「気軽に立ち寄れる」「アクセスがよい」「割引きサービス」などが各20%台。モスバーガー主利用者、フレッシュネスバーガー主利用者では「食べ物がおいしい」「原材料の品質が信頼できる」「食材の安全性」などの比率が高い。
■利用場面は「昼食」がファストフード利用者の6割強、「小腹がすいた」「手ごろな価格で飲食したい」「短時間で済ませたい」「クーポンやキャンペーン」などが各2割前後。ケンタッキーフライドチキン主利用者などでは「夕食」、サブウェイ主利用者、フレッシュネスバーガー主利用者、モスバーガー主利用者などでは「昼食」の比率が高い。
■ファストフードが好きな層は全体の6割弱、好きではない層は約15%。女性や若年層で好きな人が多い傾向。
-
- 調査時期:
- 2019年09月
- 設問項目:
-
所有している電子レンジのタイプ/所有電子レンジのメーカー/所有している電子レンジの機能/電子レンジの機能のうち、使っている機能/電子レンジ機能の利用場面/調理をする際の電子レンジ利用頻度/電子レンジで調理をする理由/電子レンジ購入時の重視点/電子レンジのメーカー選定理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■「オーブン・トースター機能付き」所有者は5割弱。「スチームオーブンレンジ」は2割強。購入時の重視点は「価格」7割弱、「操作のしやすさ」「メーカー・ブランド」「本体の大きさ」などが各4~5割。
■電子レンジについている機能は「飲み物を温める」「生解凍・半解凍」「ちょうどよい温度に自動で温める」が各5~6割。使っている機能は「ちょうどよい温度に自動で温める」「飲み物を温める」が各4割弱、「生解凍・半解凍」「温度を指定して温める」が各20%台
■電子レンジを使う場面は「家庭で作った料理やご飯の温めなおし」「市販のお弁当等の温めなおし」「解凍」「レトルト食品、電子レンジ用食品などの調理・温め」などが、電子レンジ所有者の各5割強~6割。
■調理時の電子レンジ使用者は所有者の約45%。電子レンジでの食材調理理由は「短時間で調理ができる」が、調理での電子レンジ利用者の8割弱、「キッチンコンロと並行作業ができ効率的」「下ごしらえに便利」「手順が簡単」が各4割弱。
-
- 調査時期:
- 2019年09月
- 設問項目:
-
ドレッシング利用頻度/利用するドレッシングのタイプ/利用している市販のドレッシングの数/よく使うドレッシングの種類/主に使っているドレッシングのメーカー/市販のドレッシング購入時の重視点/市販のドレッシングの用途/野菜やサラダなどにかけて食べるのが好きなもの/ドレッシングのこだわりやおすすめ(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■ドレッシング利用者は9割弱。「週に2~3回」がボリュームゾーン。週1回以上利用者は7割弱、毎日利用者は2割弱。「市販のドレッシング・液体タイプを購入」は利用者の9割強、「手作り」は2割弱。
■市販のドレッシング所有数は「1種類」が利用者の約25%、「2種類」が3割強。よく利用する種類は「ごま(乳化タイプ)」が利用者の5割強、「醤油ベース」「青じそ」が各3~4割。市販のドレッシングを野菜やサラダ以外にも使う人は、ドレッシング使用者の2割弱。
■ドレッシング購入時の重視点は「味」「値段」の他、「味の種類」「量」などが上位。2014年調査より「カロリー」「ノンオイル」などが減少傾向。
■野菜や温野菜、サラダなどの好きな食べ方は「市販のドレッシング」が約75%、「マヨネーズ」が4割強、「塩、しょうゆ、などの調味料」が3割弱。
-
- 調査時期:
- 2019年09月
- 設問項目:
-
しょうゆの嗜好度/自宅でのしょうゆの利用頻度/利用するしょうゆのタイプ/しょうゆの種類の使い分け/利用しているしょうゆのメーカー/しょうゆ開封後の保存方法/しょうゆ購入時の重視点/利用しているしょうゆの形状・容器/しょうゆのこだわり・きをつけていること(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■自宅でのしょうゆの利用頻度は「ほとんど毎日」が4割弱、「週4~5回」「週2~3回」が各2割強。東北や北陸では他地域より利用頻度が高い傾向。ペットボトルの1リットル以上がしょうゆ使用者の4割強、1リットル未満が3割強。「ボトル型」は4割弱で、2016年調査より増加。
■しょうゆ使用者のうち「こいくちしょうゆ」が6割強、「うすくち(淡口)しょうゆ」「減塩しょうゆ」「だし入りしょうゆ」「丸大豆しょうゆ」「さしみ醤油」などが各2割前後。「用途によって種類を使い分ける」はしょうゆ使用者の4割弱で、西日本での比率が高い傾向。
■しょうゆ開封後の保存方法は「冷蔵庫へ入れる」が50%、「冷暗所に保存」「常温で保存」が各3割前後。東北や北陸では「常温で保存」が最も多い。
■しょうゆ使用者の重視点は「味」「価格」がしょうゆ使用者の各5割前後、「しょうゆの種類」「塩分控えめ、減塩」「容量、サイズ」「大豆の種類」などが各2~3割。
-
- 調査時期:
- 2019年09月
- 設問項目:
-
スポーツ・機能性飲料の飲用頻度/直近1年以内に飲んだスポーツ・機能性飲料/直近1年以内に最もよく飲んだスポーツ・機能性飲料/スポーツ・機能性飲料を飲む場面/スポーツ・機能性飲料購入時の重視点/スポーツ・機能性飲料に期待する効果/スポーツ・機能性飲料飲用意向/スポーツ・機能性飲料の不満点(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■スポーツ・機能性飲料飲用者は全体の7割強。週1回以上飲用者は2割弱。
■スポーツ・機能性飲料を飲む場面は「汗をかいた」「のどが渇いた」「脱水症状を防ぎたい」「スポーツをしている時」「スポーツの後」などが各2割強~3割強。アミノバリュー主飲用者、ヴァーム・ヴァームウォーター主飲用者などでは、スポーツ中や前後の比率が高い傾向。
■購入時の重視点は「味」が飲用者の6割弱、「価格」4割強、「機能・効果」「飲み慣れている」「成分」などが各20%台。期待する効果は「水分補給」が飲用者の約75%、「熱中症対策・予防」が6割弱、「運動時や前後に適切な栄養素やエネルギーの補給」「体調を整える」「運動後の疲労回復」などが各2割前後。
■スポーツ・機能性飲料飲用意向は6割弱、男性や若年層で高い傾向。月に数回以上飲用者では9割以上、現在非飲用者では約4%。