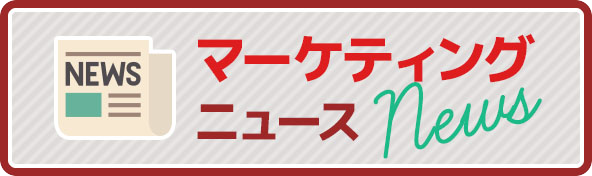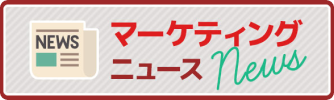- 検索
-
- テーマ別実施時期一覧
- カテゴリー別一覧
-
-
アルコール飲料・嗜好品145
-
非アルコール飲料209
-
その他19
-
-
住宅・住宅設備218
-
-
家電126
-
パソコン・カメラ・AV機器113
-
その他10
-
-
家庭用品・トイレタリー91
-
自動車・関連用品76
-
-
インターネット・情報通信327
-
携帯電話・スマートフォン180
-
メディア・広告66
-
その他7
-
-
ファッション68
-
交通・レジャー・娯楽161
-
季節行事・イベント241
-
時事・ニュース・トレンド51
-
企業ブランドイメージ246
-
広告・CM51
-
WEBサイトの利用91
-
顧客満足度100
- 実施時期別一覧
-
- 調査時期:
- 2020年04月
- 設問項目:
-
食品ロスに対する関心度/食品・食材などが食べられるのに捨てた場面・理由/食品ロス関連の言葉の認知/食品ロスに関して意識して行っていること/ワケあり商品の購入:値引きされていれば購入するか/ワケあり商品の購入:値引きされていなくても購入するか/直近1年間のフードシェアリングサービスの利用/フードシェアリングサービス利用意向/食品ロスに関して、企業などに実施してほしいこと(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■食品ロス関心層は7割弱。女性高年代層での比率が高く、男性30・40代で低い。「フードバンク」認知率3割強。食品・食材を食べられるのに捨てた場面は、「賞味期限が切れていた」が4割強、「鮮度の低下」が3割強。
■値引きされていなくても購入するものは、「品質に問題はないがワケありの商品」が4割、「消費期限間近の商品」が3割弱。
■食品ロスに関して意識して行っていることは「必要なもの以外は買わない・買いすぎない」が6割弱、「必要な分量だけ買う」が4割強、「食事を残さない」「食材・食品を無駄なく使う」が各30%台。
■フードシェアリングサービス利用意向は4割強、非利用意向は2割強。利用意向者の比率は、男性3割強、女性5割強。フードシェアリングサービス利用者の利用意向率は8割強、非利用者では4割弱。
-
- 調査時期:
- 2020年04月
- 設問項目:
-
自動車所有状況/レンタカー利用頻度/国内のレンタカーを直近で利用した時期/直近5年以内の国内でのレンタカー利用場面/直近5年以内の最頻利用レンタカー会社/レンタカー会社選定時の重視点/レンタカー利用意向/レンタカーの不満点(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■国内レンタカー利用経験は全体の6割弱、自動車所有者の6割強、非所有者の4割強。数年に1回の利用者が2割弱、それ以下が3割弱。利用経験者のうち直近1年以内利用者は3割弱、5年以内利用者は5割強。
■直近5年以内国内レンタカー利用場面は、「国内旅行での旅行先での利用」が利用者の6割強、「遊び、レジャー」が2割弱、「国内旅行での出発地からの利用」が各1割弱。
■直近5年以内国内レンタカー利用者の会社選定時の重視点は「営業所へのアクセスの良さ」「料金が割安」が各5~6割、「使い慣れている」が約25%。
■レンタカー利用意向、非利用意向は、いずれも全体の3割強。利用意向率は、週1回以上・月2~3回程度利用者で各6割弱、月1回・年数回・数年に1回程度利用者で各7~9割、数年に1回未満利用者で3割弱、非利用者では約6%。
-
- 調査時期:
- 2020年04月
- 設問項目:
-
同居者の有無/自宅でひとりで食事をする場面/自宅でひとりで食事をする際の準備方法/自宅でひとりで食事をする頻度/自宅で、個々人で食事を食べる状況の有無/同居者がそれぞれ違うメニューを食べる状況/同居者がそれぞれ違うメニューを食べる理由/同居者がそれぞれ違うメニューを食べる頻度/自宅で、個々人で食事を食べる場面(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■自宅でひとりで食事をする場面は「平日の昼食」が同居者がいる人の4割弱、「平日の朝食」が3割弱。「特に決まっていない」「自宅ではひとりで食事をすることはない」は各2割。週に4~5回以上の比率は5割弱、女性の方が頻度が高い傾向。
■自宅でひとりで食事をすることがある人の、食事の準備方法は、「インスタント食品、チルド食品、冷凍食品など」「食事の前に調理したもの」「スーパーやコンビニ、弁当店・パン屋などで購入したできあいのもの(弁当、パンなど)」「食事の残り物」などが各4~5割。
■同居者がそれぞれ違うメニューを食べる状況がある人は、同居者がいる人の5割強。「平日の朝食」が1割強。「ほとんど毎日」が2割弱、週1回以上の人が7割弱。
■同居者がそれぞれ違うメニューを食べることがある人の理由は「食べる時間帯が違う」が5割強、「それぞれ好みが違う」が4割弱、「好きなものを用意することで、楽しく食べたい」「各自が自分で食事を用意する」が各1割強。
-
- 調査時期:
- 2020年04月
- 設問項目:
-
塩味の嗜好度/塩・塩分のイメージ/自宅で使う塩の種類/塩・塩分の摂取量・頻度に気をつける度合/塩・塩分の摂取について気をつけていること/塩・塩分摂取量に関する意識/購入・利用している減塩商品/塩味・塩を用いた商品でおすすめのもの(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■塩味のものが好きな人は全体の7割強。現在購入・利用している減塩商品がある人は全体の5割強。「しょうゆ」「みそ」の減塩商品購入者が全体の各3~4割、「しお(減塩しお)」「漬物、梅干しなど」「だしつゆ・めんつゆ」などが1割強。
■塩・塩分のイメージは「高血圧になりやすい」が7割強、「健康に良くない」が4割弱などマイナスイメージが上位。「熱中症対策によい」「食品保存に適している」が各3割前後。
■塩・塩分の摂取量・頻度に気を付けている人は全体の6割弱。自分自身の塩・塩分の摂取量について、「ちょうどよいと思う」は全体の4割強、多い方だと思う人は5割弱、少ない方だと思う人は1割。
■塩・塩分の摂取について気をつけていることは「塩分の多い食品・料理は摂りすぎない」が5割弱、「薄味のものを食べる」「調味料をなるべくかけない・かけすぎない」「だしなどでうまみ成分を生かし減塩」「減塩をうたった商品を選ぶ」が各2~3割。
-
- 調査時期:
- 2020年04月
- 設問項目:
-
ミネラルウォーター飲用頻度/直近1年間に飲んだ市販のフレーバーウォーター/直近1年間の最頻飲用フレーバーウォーター/直近1年間のフレーバーウォーター飲用頻度/市販のフレーバーウォーター飲用場面/市販のフレーバーウォーター購入時の重視点/市販のフレーバーウォーターの好きな風味・味/市販のフレーバーウォーター飲用意向/市販のフレーバーウォーター不満点(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■フレーバーウォーター飲用経験者は5割強。直近1年間飲用者は4割弱で、若年層での比率が高い。飲用者のうち、週1回以上飲用者は3割弱。飲用場面は「のどが渇いた時」が4割強、「仕事・勉強・家事の合間」「お風呂上がり」「レジャー・遊びの時」が各2割前後。
■フレーバーウォーターの風味・味で好きなものは「レモン」が、直近1年間飲用者の5割弱、「オレンジ」「桃、白桃」「みかん」が各3~4割、「ヨーグルト」「グレープフルーツ」が各2割強。
■直近1年間飲用者の、購入時の重視点は「味」7割強、「価格」4割弱、「容量、サイズ」「成分、添加物」」「カロリー」「飲みなれている」「香り」などが各10%台。
■市販のフレーバーウォーターの飲用意向者は3割弱、若年層で高い傾向。フレーバーウォーター直近1年間飲用者では7割弱、飲用未経験者では約2%、ミネラルウォーター直近1年間飲用者では4~5割、非飲用者では約9%。
-
- 調査時期:
- 2020年04月
- 設問項目:
-
普段よく飲む飲み物/ペットボトルのお茶系飲料飲用頻度/直近1年間に飲んだペットボトルのお茶系飲料の銘柄/直近1年間に最もよく飲んだ、ペットボトルのお茶系飲料(紅茶以外)の銘柄/ペットボトルの緑茶・日本茶・中国茶・ブレンド茶・健康茶飲料の飲用頻度/ペットボトルの緑茶・日本茶・中国茶・ブレンド茶・健康茶購入時の重視点/ペットボトルの緑茶・日本茶・中国茶・ブレンド茶・健康茶飲用場面/ペットボトルの緑茶・日本茶・中国茶・ブレンド茶・健康茶の飲用パターン(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■ペットボトルのお茶系飲料(紅茶以外)飲用者は全体の8割強。週1回以上飲用者は4割強、男性の方がやや比率が高い。
■ペットボトルのお茶系飲料(紅茶以外)の重視点は「飲みやすさ」「価格」が飲用者の各5割弱、「旨みがありそう」「味の濃さ」「容量」が各3割前後。綾鷹主飲用者、伊右衛門主飲用者などでは「旨みがありそう」、からだすこやか茶W主飲用者、サントリー黒烏龍茶、ヘルシア緑茶主飲用者などでは「健康によさそう」の比率が高い。
■ペットボトルのお茶系飲料(紅茶以外)飲用場面は「のどが渇いたとき」「昼食」が飲用者の各4割前後、「仕事・勉強・家事の合間」「くつろいでいるとき」が各20%台。男性30代では「朝食」「昼食」「夕食」などの食事に関する項目の比率が高い傾向。
-
- 調査時期:
- 2020年03月
- 設問項目:
-
サステナビリティの認知/サステナビリティへの関心度/サステナビリティに関連する事柄の認知/SDGsの中で重要だと思うもの/エシカル消費の観点で行っていること/サステナビリティを重視する企業・ブランドであることの意識度合い/サステナビリティを重視する企業・ブランドの商品・サービスの利用意向/環境・社会・経済の面で持続可能な社会の実現のために行っていること(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■サステナビリティについて「どのようなものか、内容を知っている」「聞いたことがあるが、どのようなものか知らない」が各20%台。「どのようなものか、内容を知っている」は、男性高年代層で高い。関心層は4割弱。内容を知っている人の比率は、「ロハス」「フェアトレード」「SDGs」が各2割強。
■SDGsの中で重要だと思うものは「すべての人に健康と福祉を」「安全な水とトイレを世界中に」「気候変動に具体的な対策を」「貧困をなくそう」「飢餓をゼロに」などが各30%台。
■エシカル消費の観点で実施していることは「食品ロスを減らす」「エコバックを使う、レジ袋は使わない」が各4割、「長持ちする商品を買う」「地産地消」「省エネや節電・節水などを心がけた生活をする」が各20%台。
■サステナビリティを重視する企業・ブランドであることを意識して購入・利用する層は3割弱、意識しない層は4割弱。サステナビリティを重視する企業・ブランドの利用意向がある層は5割弱、女性高年代層での比率が高い。
-
- 調査時期:
- 2020年03月
- 設問項目:
-
ひなまつりのお祝い/ひなまつりのお祝いの対象者の有無/今年のひなまつりに関連した行動・予定/今年のひなまつりのプレゼントの内容/ひなまつりにちなんで飲食したもの/ひなまつりにあたって使った費用総額/ひなまつりに何か行う(予定の)理由/ひなまつりのお祝いの過ごし方(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■今年のひなまつりに「お祝いをした・する予定」は全体の2割弱、お祝いの対象者がいる人(3割弱)のうち5割強。ひなまつりに何かする理由は「お祝いの対象となる人がいる」「年中行事の一つ」などが実施者の各3割強。「年中行事の一つ」などは女性、「季節感を感じたい」などは女性高年代層での比率が高い傾向。
■ひなまつりに関連し何らかのことをした人・予定の人は全体の3割強、お祝いの対象者がいる人の7割強。「おひなさまを飾る」が2割弱、ひなまつりにちなんだ「お菓子を購入する」「メニューを食べる」が各1割強。
■ひなまつりのお祝いのプレゼントは「ケーキ、洋菓子」「和菓子」などのお菓子が各3割前後、「ひな人形」「おもちゃ、ぬいぐるみなど」「衣料品、衣料小物、靴など」「食品」などが各10%台。
■ひなまつりに関連することを行った人のうち、「ちらし寿司」を食べた人は5割弱、「はまぐりのお吸い物」が2割弱。お菓子類では「ひなあられ」「和菓子」が各2割強。
-
- 調査時期:
- 2020年03月
- 設問項目:
-
今年のバレンタインデーの経験/バレンタインデーのプレゼントなどの内容/バレンタインデーにかけた費用/プレゼントなどを贈った相手/プレゼントなどを贈った人数/チョコレートを贈った人数/あなたにとってバレンタインデーとは/バレンタインデーに関連して行ったこと/バレンタインデーに関連して行ったこと・過ごし方の内容(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■2020年のバレンタインデーにプレゼントなどをしたりもらったりした人は全体の4割強(女性10~40代の各50%台)。2013年調査以降微減傾向。「市販のチョコレートを贈った」は女性回答者全体の4割強。「市販のチョコレートをもらった」は男性回答者全体の3割強、女性回答者全体の約9%。
■バレンタインデーにかけた費用は「500円~1000円未満」「1000円~2000円未満」がボリュームゾーン。プレゼントを贈る相手は、女性10・20代では「恋人」「配偶者」「父親」「職場関係の人」が各3割。
■プレゼント以外で、バレンタインデーに関連して行ったことは「自分用としてチョコやお菓子・スイーツ等を購入」が全体の約9%、女性10~30代の2割強。「バレンタインデー限定のお菓子・スイーツを購入」「バレンタインデーにちなんだお菓子・スイーツを食べた」が全体の各3~4%。
■バレンタインデーは「興味がない」「家族とのコミュニケーションを図る機会」「季節行事の一つ」とらえる人が各2割前後。女性10・20代では「同性の友人・知人とのコミュニケーション」「日頃の感謝の気持ちを伝える機会」「季節行事の一つ」が上位3位。
-
- 調査時期:
- 2020年03月
- 設問項目:
-
インターネット閲覧・利用時の接続機器/直近1年間に表示されたインターネット広告の種類/直近1年間に内容を読んだインターネット広告/直近1年間にインターネット広告が表示された際に行ったこと/直近1年間に内容を読んだインターネット広告の内容/直近1年間に内容を読んだインターネット広告の種類/インターネット広告についての考え方/インターネット広告で不快に感じるもの/インターネット広告で不快に感じるもの(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■直近1年間に表示されたインターネット広告は、「バナー広告」が8割強、「動画広告」が6割弱、「コンテンツや記事間の広告」「動画サイトの、スキップできる動画広告」が各4~5割。
■直近1年間に広告表示された人のうち、内容を読む人は4割弱。
■直近1年間にインターネット広告が表示された人のうち、「広告を閉じた」「広告を間違えてクリックした」「広告をクリックした(意図的に)」が3~4割。
■インターネット広告について「気になるものや興味がある・面白いものなら読む」「関係ない広告が表示されるとイライラする」「スクロールなどの操作を妨げられわずらわしい」が各30%台。不快に感じるのは「興味がない内容の広告」「別画面やポップアップで自動的に表示」「画面の上や下に常に表示される」などが各3割強。
-
- 調査時期:
- 2020年03月
- 設問項目:
-
スマートフォン・携帯電話など端末利用状況/格安スマホ・格安SIMカード利用状況/格安スマホ購入場所/主に利用している格安スマホ・SIMサービス/格安スマホ非利用理由/格安スマホ利用意向/格安スマホ・格安SIMカードのサービス選定時の重視点/格安スマホについての不安・不満(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■格安スマホ・SIMカード利用者は全体の約25%、過去調査より増加傾向。端末+SIMカードのセット販売は1割強(利用者の5割強)、格安SIM購入+所有スマホ、格安SIM購入+新規スマホは各5%(利用者の2割弱)。格安スマホ・SIMカード利用者うち「オンラインショップ」での購入者が5割弱、「通信会社の店舗」が3割弱、「家電量販店」が2割弱。
■格安スマホ非利用者(全体の7割強)の、非利用理由は「現在利用しているもので満足」が5割弱、「格安スマホを詳しく知らない」「通信の安定性や速度に不安」「契約手続きをするのが面倒」などが各2割弱。
■格安スマホ・SIMカードの利用意向者・非利用意向者は全体の各3割強。格安スマホ・SIMカード現在利用者では9割、非利用者では2割弱、スマートフォンのみ利用者では4割弱。
■格安スマホ・SIMカード利用意向者の重視点は「月額利用料金」「通信の安定性」「通信速度の速さ」「データ通信容量」などが上位。端末+格安SIMカードのセット利用者では、「機器や端末の価格」の比率が高い。
-
- 調査時期:
- 2020年03月
- 設問項目:
-
商品・サービス購入・利用時に重視する情報源/商品・サービスの購入・利用時のネット上の口コミ情報の参考度/ネット上の口コミ情報を参考にして購入・利用する商品・サービス/ネット上の口コミ情報を参考にする時によく見るサイト・アプリ/ネット上の口コミ情報が信頼できると感じる場面/ネット上の口コミ情報の、購買行動や情報発信行動への影響/商品・サービスの口コミ情報の書き込みをする目的・理由/ネット上の口コミ情報を重視して購入・利用する場面(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■商品・サービス購入時にネット上の口コミ情報を参考にする人は全体の6割弱。口コミ情報の書き込みをする人は約35%。
■口コミ情報を参考にする人のうち「価格.com」を見る人が5割弱、「Amazonのカスタマーレビュー」「その他オンラインショッピングサイト・アプリのレビュー」「食べログ」「ぐるなび」などが各3~4割。「Twitter」などは若年層での比率が高い。口コミ情報を参考に購入するのは、家電製品や宿泊・旅行、パソコン、飲食店などが3~4割。
■インターネットの口コミ情報が信頼できると感じるのは、「口コミ件数が多い」「おすすめや良い点だけでなく良くない点についても書かれている」「内容が納得できる」「同じ評判の口コミをいろいろな人が書いている」が、口コミ情報利用者の各3割前後。
■買うかどうか迷っていたが口コミ情報をみて「買うことを決めた」「買うことをやめた」、「口コミ情報での評判がよい方を買った」などが各3割強で、商品購入決定への口コミ情報の影響がうかがえる。
-
- 調査時期:
- 2020年03月
- 設問項目:
-
直近1年間のクーポン利用状況/直近1年間に利用したクーポンのタイプ/直近1年間にクーポンを利用した店舗・サービス/直近1年間に利用したクーポン入手経路/利用するクーポンの特徴/クーポンの利用に関する考え方/クーポンの利用度合/クーポンの不満点(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■直近1年間のクーポン利用者は全体の7割強、過去調査と比べ増加傾向。「スマートフォンのクーポン画面を見せる・かざす」は利用者の7割弱で、2017年調査と比べ増加。クーポンを積極的に利用する人は全体の6割強で、2017年調査より増加。
■直近1年間のクーポン利用者のうち、「ファストフード」のクーポン利用が5割弱。2017年と比べ「ドラッグストア」「コンビニエンスストア」の比率が大きく増加。入手先は「レシートに印刷」「商品購入・サービス利用時にもらった」「新聞の折り込みチラシ」が30%台。2017年調査と比べ「LINE」「店舗や企業の公式アプリ」などが増加。
■利用するクーポンの特徴は「わずかでも割引されている」「割引率が高い」「よく利用する店や商品・サービス」が、利用者の各4~5割。
■「同じものなら、なるべくクーポンが使える店や商品を利用・購入」「利用・購入前にクーポンがあるかどうかを調べる」「クーポンを利用する目的で店に行くことがある」は各2~3割。
-
- 調査時期:
- 2020年03月
- 設問項目:
-
百貨店利用頻度/商品・サービスを利用したことがある百貨店/信頼性・安心感があると思う百貨店/品質が優れていると思う百貨店/独自性があると思う百貨店/接客がよいと思う百貨店/親近感があると思う百貨店/今後利用したい百貨店/百貨店に期待するイメージ(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■『信頼性・安心感がある』『品質が優れている』『接客が良い』と思う百貨店は、地域差はあるものの、全体では「高島屋」「三越」「伊勢丹」が上位。地域別では「大丸」は北海道、「阪急百貨店」は近畿での比率が高い傾向。
■『独自性がある』と思う百貨店は、「伊勢丹」が全体の2割弱、「高島屋」が1割強。「伊勢丹」が過去調査と比べ減少傾向。「いずれもない」が5割弱と高い。
■親近感があると思う百貨店は「高島屋」「大丸」「そごう」などが各10%台で、他のイメージ項目と比べ比率が低い。「いずれもない」は4割弱。
■今後利用したい百貨店(1つ)は、全体では「高島屋」が2割弱、「伊勢丹」「三越」「大丸」が各8~9%。「いずれもない」は3割強、男性10~40代での比率が高い。
-
- 調査時期:
- 2020年03月
- 設問項目:
-
所有パソコンのタイプ/主利用デスクトップ・ノートパソコンのタイプ/主利用デスクトップ・ノートパソコンのメーカー/デスクトップ・ノートパソコン利用頻度/主利用デスクトップ・ノートパソコンとつなげている機器/パソコン購入・買い替え予定時期/購入したいパソコンのタイプ/デスクトップ・ノートパソコン購入時の重視点/デスクトップ・ノートパソコンとモバイル端末の使い分け(自由回答設問)
- 結果概要:
-
所有パソコンのタイプは「A4サイズノートパソコン」が全体の6割弱。「デスクトップパソコン」は4割弱で過去調査より減少傾向。
デスクトップまたはノートパソコン利用者のうち「毎日」使う人は7割強、過去調査と比べ減少傾向。男性や高年代層で、利用頻度が高い傾向。
主利用パソコンとつなげている機器は「マウス」「プリンター」が利用者の各5割強、「USBメモリ」「キーボード」が各3割弱。過去調査と比べ「プリンター」「デジタルカメラ」などが減少傾向。
パソコン購入の具体的な予定がある人は全体の約9%。購入意向者は全体の5割弱。購入意向者が最も購入したいタイプは「A4サイズノートパソコン」が4割強、「デスクトップパソコン」が3割強。
■所有パソコンのタイプは「A4サイズノートパソコン」が全体の6割弱。「デスクトップパソコン」は4割弱で過去調査より減少傾向。
■デスクトップまたはノートパソコン利用者のうち「毎日」使う人は7割強、過去調査と比べ減少傾向。男性や高年代層で、利用頻度が高い傾向。
■主利用パソコンとつなげている機器は「マウス」「プリンター」が利用者の各5割強、「USBメモリ」「キーボード」が各3割弱。過去調査と比べ「プリンター」「デジタルカメラ」などが減少傾向。
■パソコン購入の具体的な予定がある人は全体の約9%。購入意向者は全体の5割弱。購入意向者が最も購入したいタイプは「A4サイズノートパソコン」が4割強、「デスクトップパソコン」が3割強。
-
- 調査時期:
- 2020年03月
- 設問項目:
-
直近1年間に食べたシリアル食品/直近1年間に最もよく食べたシリアル食品/直近1年間にシリアル食品を食べた頻度/シリアル食品を食べる場面/シリアル食品を食べる理由/シリアル食品購入場所/市販のシリアル食品購入時の重視点/シリアル食品の利用意向/シリアル食品利用意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■直近1年間にシリアル食品を食べた人は4割強。女性での比率が高い。「グラノーラ」が3割弱、「コーンフレーク」が2割弱。シリアル食品利用意向は全体の4割強。女性や若年層での比率が高い。直近1年間利用者の利用意向は7~9割弱、非利用者では1割強。
■シリアル食品を食べる頻度は「月に1回以下」が直近1年間利用者の約35%、週1回以上食べる人は4割強。主利用シリアル食品別にみると、オートミール主利用者、グラノーラ主利用者、ミューズリー主利用者では頻度が高い傾向。
■シリアル食品を食べる場面は「朝食代わり」「朝食のメニューの1つ」「おやつ、間食」が、直近1年間シリアル食品利用者の各3~4割。食べる理由は「おいしい」が5割弱、「栄養バランスがよい」「食物繊維やビタミン、ミネラルなどが多い」「手軽」が各30%台。
■市販のシリアル食品購入時の重視点は、「味」「価格」が各5~7割、「原材料」「穀物・果物等の種類」「栄養成分」「容量、サイズ」「食感」が各20%台。
-
- 調査時期:
- 2020年03月
- 設問項目:
-
野菜の嗜好度/野菜摂取量に関する意識/野菜を使った料理を食べる頻度/野菜の摂取方法/野菜を食べる理由/好きな野菜/嫌いな野菜/野菜摂取時に気を付けていること(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■野菜が好きな人は全体の8割、自分自身で、野菜を食べている方だと思う人は6割強。野菜を使った料理を「ほぼ毎日・1日3回以上」食べる人は全体の2割弱、「ほぼ毎日・1日1~2回」が5割で、毎日食べる人は7割弱。
■野菜を「生野菜、サラダ」で食べる人は全体の約85%。「炒め物」が7割弱、「汁物」「ゆでた野菜」「煮込み料理」「煮物」「鍋料理」などが各5~6割。
■野菜を食べる理由は「おいしい」「食物繊維が豊富」が、野菜を食べる人の各50%台、「健康のため」「栄養素が豊富」「体調を整える」「ビタミン、ミネラルなどを摂取する」が各40%台など。
■好きな野菜の上位10位は「キャベツ」「タマネギ」「トマト」「ジャガイモ」「ダイコン」「ナス」「キュウリ」「アスパラガス」「ネギ」「レタス」。野菜が嫌いな層での好きな野菜上位は「ジャガイモ」「サツマイモ」「トウモロコシ」「カボチャ」など。嫌いな野菜がある人は全体の5割強、「ゴーヤー」「セロリ」が各2割強、「シュンギク」「パセリ」「オクラ」が各7~9%。
-
- 調査時期:
- 2020年03月
- 設問項目:
-
カップめんを食べる頻度/普段食べるカップめんのタイプ/最もよく食べるカップめんのタイプ/最もよく食べるカップめん選定時の重視点/カップめんを食べる場面/好きなカップラーメンの銘柄/好きなカップ焼きそばの銘柄/好きなカップうどん・そばの銘柄/カップめんについての不満(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■カップめんを食べる人は全体の9割弱。週1回以上食べる人は2割強、男性3割強。
■普段食べるカップめんのタイプは「カップラーメン」が、カップめんを食べる人の9割強、「カップ焼そば」「カップうどん」が各50%台。
■最もよく食べるタイプのカップめんの重視点は「味」8割強、「価格」6割強、「スープ、つゆ」が3割強、「麺」「食べ慣れている」「商品ブランド」「容量」「メーカー」が各2割前後。カップ焼そば主利用者では「味」「価格」に続き「食べ慣れている」「容量」「商品ブランド」などが多い。
■カップめんを食べる場面は「昼食時」が、利用者の約75%、「すぐに食べたい時」「軽く済ませたい時」「小腹が空いた時」などが各2割前後。「夕食時」は若年層での比率が高い傾向。
-
- 調査時期:
- 2020年02月
- 設問項目:
-
英語力の必要性/英語を使う頻度/自主的な英語の学習状況/英語学習をしている理由/英語学習方法/英語学習にかけるお金(1ヶ月あたり)/英語学習意向/英語学習方法の意向/英語を学習したい/したくない理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■英語力の必要性を感じる人は全体の6割。普段英語を使う機会がある人は2割弱。自主的に「現在英語を学習している」は全体の約7%、若年層で高い傾向。「現在は学習していない」は約35%。
■英語学習者・経験者の学習理由は「海外旅行」「英語で会話をしたい」が各3割強、「仕事で必要」「趣味・教養の一つとして」が各20%台、「自己啓発、習い事」「海外のドラマや映画、音楽、洋書などを視聴・閲覧」「海外に興味」などが各2割弱。
■英語学習者の、英語学習方法は「参考書、教科書」が3割強、「英語学習アプリやWebサイト、ソフトウェア」「英語で映画やテレビ番組・海外ドラマなどを視聴」「ラジオの英語講座」などが各2割強。
■英語学習意向がある人・ない人は各3割強。学習意向がある人の比率は、女性や若年層で高い。学習したい方法は「英語で、映画やテレビ番組・海外ドラマなどを視聴」「オンライン英会話、オンラインでの通信学習」「英会話スクール」が学習意向者の各2割強、「英語学習アプリやWebサイト、ソフトウェア」「個人レッスン・マンツーマン」などが各2割弱。
-
- 調査時期:
- 2020年02月
- 設問項目:
-
恵方巻きの認知/恵方巻きを食べた経験/今年の恵方巻きの実施状況/恵方巻きの購入場所/恵方巻き購入時の着目点/節分にちなんでしたこと、行う予定のこと/節分にかける費用/恵方巻購入意向/今後食べてみたいと思う「恵方巻き」(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■恵方巻きを食べた経験がある人は認知者(約96%)の8割弱。今年食べる予定・食べた人は認知者の5割弱、経験者の6割強。近畿では7割弱、中国、四国では各6割弱、北海道、東北、関東では4割前後。
■恵方巻きを食べる予定・食べた人の購入場所は「スーパー」が7割弱、「コンビニエンスストア」「寿司専門店」が各1割強。手作りは2割弱。恵方巻き購入時のポイントは「価格」「具材」「味」が、購入者・予定者の各6~7割。
■市販の恵方巻き購入意向者は4割弱、女性や若年層で高い傾向。恵方巻きを食べたことがある層では5割弱、今年食べた・食べる予定の層では7割強。食べたことがない層では3%。
■節分にちなんでしたこと(予定)がある人は全体の6割弱、過去調査と比べ減少傾向。女性や60・70代、近畿での比率が高い傾向。「豆まきをする」「豆を年の数食べる」を実施する・実施予定の人が各2~3割。
-
- 調査時期:
- 2020年02月
- 設問項目:
-
関心があるスポーツ/スポーツの楽しみ方/スポーツ観戦の関心度/直近1年間に観戦したスポーツ/直近1年間に最も多く観戦したスポーツ/直近1年間に最も多く観戦したスポーツの観戦方法/直近1年間に最も多く観戦したスポーツの観戦理由/直近1年間に最も多く観戦したスポーツの観戦スタイル(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■スポーツの楽しみ方は「テレビやラジオの試合中継を視聴」が5割弱、「テレビや新聞、ネットなどで試合結果をチェック」が3割弱、「試合会場へ行って観戦」が2割弱。
■スポーツ観戦関心層は全体の5割弱。男性や高年代層で高い。直近1年間のスポーツ試合観戦者は7割強、「野球」が4割弱、「ラグビー」「サッカー」「マラソン、駅伝」が各3割前後、「テニス」「大相撲」「フィギュアスケート」が各2割強。
■直近1年間最多観戦スポーツの観戦方法は「テレビやラジオの試合中継」が観戦者の8割強。野球、サッカー、バスケットボールでは「試合会場へ行って観戦」が各4割前後、バスケットボールやプロレスなどでは「インターネットの試合中継など」が各3割前後。
■直近1年間最多観戦スポーツの観戦理由は、ラグビーは「周囲で話題」「大きな大会」、大相撲は「観戦するのが習慣」「そのスポーツが好き」が上位。バスケットボール、バドミントン、バレーボール、卓球、陸上競技などでは「自分や家族などがやっていた」、フィギュアスケートは「有名な選手・チームが出ている」などの比率が高い。
-
- 調査時期:
- 2020年02月
- 設問項目:
-
花粉症の発症状況/花粉症であることを自覚した時期/花粉症で悩まされる症状/花粉症の予防・対処法として利用するもの/花粉症対策としてマスクを購入する際の重視点/花粉症の予防・対処をし始める時期/花粉症の症状が出る季節/花粉症の症状を軽減するために気をつけていること・予防として行っていること(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■現在花粉症の人は3割強、経験者を含めると約46%。関東、中部では、他の地域より花粉症の人の比率が高い。「鼻水が出る」「目がかゆくなる」「くしゃみが出る」「鼻がつまる」などで悩まされる人が多い。
■花粉症の予防・対処開始時期は全体では「3月」が6割、「4月」が5割。重度の花粉症の人では「2月」「3月」の比率が高い。花粉症の人が症状が出る季節は「春」が9割弱、「秋」が2割弱。
■花粉症の人の予防・対策は「マスク」が6割弱、女性では7割弱。その他「医師の処方薬、注射」「市販の目薬」「市販の飲み薬」など、薬に関することが各3~4割。
■花粉症対策でのマスク購入時の重視点は、「価格」「使い捨て」がマスク利用者の各6~7割、「内容量(枚数)」「フィット感」が各40%台、「大きさ」「長時間装着しても耳が痛くならない」が各30%台。
-
- 調査時期:
- 2020年02月
- 設問項目:
-
主利用携帯電話会社/CMの印象がよいと思う携帯電話会社/先進的だと思う携帯電話会社/信頼できると思う携帯電話会社/機能が充実していると思う携帯電話会社/デザインがよいと思う携帯電話会社/電波・回線がつながりやすいと思う携帯電話会社/今後利用したいと思う携帯電話会社/今後利用したいと思う携帯電話会社の選定理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■『最もCMの印象がよい』と思うのは「au」が4割弱、2016年以降他の2社よりも比率が高い。「SoftBank」「NTTドコモ」が各2割弱。
■『最も信頼できる』『最も機能が充実している』と思う携帯電話会社は「NTTドコモ」が4~5割、「au」2割弱、「SoftBank」1割前後。「その他」は20%台で、過去調査よりも増加。『最も電波・回線がつながりやすい』は「NTTドコモ」が6割弱を占め、他社との差が大きい。
■『最も先進的だ』と思うのは「NTTドコモ」「SoftBank」が各20%台、「au」が2割弱。「その他」が3割弱で、過去調査よりも増加傾向。『最もデザインがよい』と思う携帯電話会社は「NTTドコモ」「au」が各20%台、「SoftBank」が2割弱。
■今後利用したい携帯電話会社は「NTTドコモ」が3割強、「au」が2割弱、「SoftBank」が1割強。過去調査と比べ「その他」が増加傾向。継続利用意向は、NTTドコモ主利用者8割強、au主利用者で7割強、SoftBank主利用者、Y!mobile主利用者、その他主利用者で各6割前後割。
-
- 調査時期:
- 2020年02月
- 設問項目:
-
証券会社との取引経験/直近3年以内に取引した証券会社/直近での主利用証券会社/主利用証券会社の満足度/直近3年以内に証券会社で取引・購入した金融商品/取引する証券会社選定時の重視点/今後取引したい証券会社/直近での主利用証券会社と取引している理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■証券会社との取引経験は全体の4割強。「1ヶ月以内に取引したことがある」は2割弱。取引経験者は男性や高年代層で高い。直近3年以内の取引経験者が証券会社で取引・購入した商品は「国内株式」が8割弱、「株式投資信託」が3割強。
■直近3年以内の取引経験、今後の取引意向(未経験者含む)のいずれも、「SBI証券」「楽天証券」「野村證券」が上位3位。前回と比べ「楽天証券」の比率が増加。主利用証券会社の継続利用意向は、GMOクリック証券、SBI証券主利用者などで高い。
■取引する証券会社選定時の重視点は、全体では「会社の信頼度、経営の安定性」「手数料が安い」が上位2位。「セキュリティーが信頼できる」「知名度が高い」などが続く。SBI証券主利用者、松井証券主利用者などでは「手数料が安い」が各8~9割と高い。
-
- 調査時期:
- 2020年02月
- 設問項目:
-
知っている損害保険会社/損害保険加入状況/加入している損害保険会社/信頼性・安心感がある損害保険会社/商品開発力・企画力がある損害保険会社/独自性がある損害保険会社/提供しているサービスの品質が高い損害保険会社/契約したい損害保険会社/損害保険会社に期待すること(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■損保会社の認知率は「ソニー損保」「東京海上日動火災保険」「JA共済」「県民共済」「アクサダイレクト」が各6~7割。「ソニー損保」は、加入の順位よりも契約したい損保(1つ)での順位の方が上位。
■『信頼性や安心感がある』のは、「東京海上日動火災保険」が3割強、「県民共済」「三井住友海上火災保険」「ソニー損保」「損害保険ジャパン日本興亜」「こくみん共済coop」「JA共済」などが各2割前後。
■『商品開発力や企画力』の上位は「ソニー損保」「東京海上日動火災保険」が各10%台、「アクサダイレクト」「損害保険ジャパン日本興亜」「イーデザイン損保」などが各8~9%。『独自性がある』は「ソニー損保」が約16%、「アクサダイレクト」「県民共済」などが各7%。「いずれもない」がそれぞれ5割前後。
■『提供しているサービスの品質が高い』と思う損保会社は「東京海上日動火災保険」「ソニー損保」が各10%台、「損害保険ジャパン日本興亜」「三井住友海上火災保険」「県民共済」などが各7~9%。「いずれもない」が5割弱。
-
- 調査時期:
- 2020年02月
- 設問項目:
-
スマートフォン・携帯電話利用状況/直近1年間での支払い方法/直近1年間に利用したスマホ決済アプリ・サービス/直近1年間の最頻利用スマホ決済アプリ・サービス/直近1年間にスマホ決済で支払った頻度/直近1年間にスマホ決済アプリ・サービスで支払った割合/スマホ決済アプリ・サービス利用時の行動/スマホ決済アプリ・サービスでの支払い意向/スマホ決済アプリ・サービス利用時の重視点/スマホ決済利用意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■直近1年間にスマホ決済アプリで支払った人は全体の4割強(スマホ主利用者の6割弱)。2019年調査から大きく増加。男性若年層での比率が高い傾向。スマートフォン主利用者のうち、「PayPay」利用者が4割弱、「楽天ペイ」が2割弱。「Apple Pay」はiPhone主利用者の1割強。
■直近1年間のスマホ決済アプリでの週1回以上支払い者は6割弱。2019年より増加。直近1年間の支払い回数のうちスマホ決済で支払った割合が4割以下の層が、半数強。
■直近1年間スマホ決済での支払者のうち「ポイント還元率や特典・サービスがお得なスマホ決済を利用」「キャンペーンがあるときに使うことが多い」「スマホ決済が利用できる店ではほぼスマホ決済で支払い」が各3~4割。メルペイ主利用者、LINEPay主利用者、ファミペイ主利用者などでは「キャンペーンがあるときに使うことが多い」などの比率が高い傾向。
■スマホ決済アプリ利用意向・非利用意向はいずれも4割弱。2019年より利用意向が増加。利用意向は、スマートフォン主利用者の5割弱、直近1年間スマホ決済利用者の7割強、非利用者の1割弱。スマホ決済支払意向者のサービス重視点は「ポイント還元率の高さ」「利用できる店舗・サービスの多さ」「支払いのスムーズさ・手順の簡単さ」などが上位。
-
- 調査時期:
- 2020年02月
- 設問項目:
-
所有掃除機のタイプ/ロボット掃除機利用のきっかけ・理由/主利用ロボット掃除機のメーカー/ロボット掃除機の利用パターン/主利用ロボット掃除機のタイプ/ロボット掃除機利用頻度/ロボット掃除機利用意向/ロボット掃除機選定時の重視点/ロボット掃除機利用意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■ロボット掃除機所有者は約9%。利用理由は「掃除が楽になりそう」が所有者の3割強、「テレビや新聞・雑誌で見た」「店頭で商品を見かけた」「効率よく掃除をしたい」などが各2割強。
■ロボット掃除機の利用の仕方は「従来型の掃除機をメイン、ロボット掃除機をサブ」が所有者の3割強、「ロボット掃除機をメイン、従来型の掃除機をサブ」「留守中にロボット掃除機を使う」が各2割強。利用頻度は、週2~3回以上が利用者の5割強。
■利用意向は全体の3割強、所有者の約75%、ロボット掃除機以外所有者の3割弱。
■利用意向者の重視点は、「本体価格」が6割強、「メーカー・ブランド」「吸引力」「手入れ・メンテナンスのしやすさ」が各5割前後、「ランニングコスト」「ゴミの捨てやすさ」が各4割前後。
-
- 調査時期:
- 2020年02月
- 設問項目:
-
パンを食べる頻度/パンに塗るもの/パンと一緒に飲むもの/好きな惣菜パン・菓子パン/パンを食べる場面/朝食で食べるパンの種類/直近1年間にパンを購入した場所/朝食で食べるパンのこだわり・おすすめの食べ方など(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■1日1回以上パンを食べる人は全体の3割強、高年代層での比率が高い。直近1年間に菓子パン・惣菜パンを買った場所は「スーパー」が全体の8割強、「パン屋・ベーカリーショップ」「コンビニエンスストア」が各5割前後。
■好きな惣菜パン・菓子パンは「サンドイッチ」がパンを食べる人の6割強、「カレーパン」が4割強、「ウインナーパン、ウインナーロール」「アップルパイ」「クリームパン」「あんパン」などが各3割強。
■パンを食べる人のうち「ジャム」「バター」「マーガリン」「チーズ」を塗る人が各4割前後。パンと一緒に飲むものは「コーヒー、コーヒー飲料」が7割強、「牛乳」「紅茶、紅茶飲料」などが各3割前後。
■パンを食べる人のうち「朝食」に食べる人が8割弱、「昼食」が5割強、「おやつ・間食」が3割強。朝食にパンを食べる人のうち「食パン」を食べる人が9割弱、「ロールパン、バターロール」が4割弱、「クロワッサン」「フランスパン、バゲット」が各2割前後。
-
- 調査時期:
- 2020年02月
- 設問項目:
-
スナック菓子食用頻度/スナック菓子選定時の重視点/スナック菓子の好きな味/スナック菓子を食べる場面/おつまみとしてよく食べるスナック菓子/おつまみとしてスナック菓子を食べる時に飲むお酒/スナック菓子の不満点(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■スナック菓子を週1回以上食べる人は全体の5割。食べる場面は「おやつ」が食べる人の7割弱、「お酒のおつまみ」「自宅にいるとき」「ちょっとおなかがすいたとき」などが各3割前後。
■スナック菓子を食べる人の、選定時の重視点は「価格」「塩味・チーズ味などの味の種類」「食感」が各4~5割、「食べやすい形・大きさ」「メーカー」が各2割前後。
■スナック菓子を食べる人が好きな味の上位は「うす塩」「塩」が各4~5割、「コンソメ」「チーズ」「のり塩」「ガーリック」などが各3割前後。
■スナック菓子をつまみで食べる人のうち、「ビール、発泡酒、新ジャンルビールなど」を一緒に飲む人が8割強。「チューハイ・サワー」は4割弱で2017年調査より増加。女性20・30代での比率が高い。
-
- 調査時期:
- 2020年02月
- 設問項目:
-
カップスープを食べる頻度/カップスープを食べるシーン/カップスープと一緒に食べるもの/カップスープ選定時の重視点/好きなカップスープの味/カップスープ購入時の銘柄選定/カップスープ利用意向/カップスープを食べる状況・気分など(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■カップスープを食べる人は全体の約55%。今後の利用意向は5割弱、女性や若年層で高い傾向。月1回以上利用者では9割前後、非利用者では約8%。
■カップスープを食べるシーンは「昼食のメニューの1つとして」が利用者の4割強、「温かいものが食べたい」「小腹が空いた」「朝食のメニューの1つとして」「昼食代わり」などが各2割前後。カップスープと一緒に食べるものは「パン類」「おにぎり」「ごはん(お米)」が各3~4割。「パン類」は女性での比率が高く男女差が大きい。
■カップスープ選定時の重視点は「味」「価格」に続き、「具だくさんである」「野菜が多い」が各3~4割。過去調査と比べ「具だくさんである」は2015年以降増加傾向。
■好きなカップスープの味は「コーンスープ(洋風)」「たまごスープ」「わかめスープ」「ポタージュ」が、食べる人の各4割前後。「コーンスープ(洋風)」「チャウダー、クラムチャウダー」「ポタージュ」などのクリーム系は女性での比率が高い。男性では「たまごスープ」「わかめスープ」などが上位。