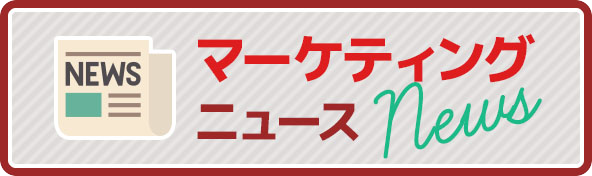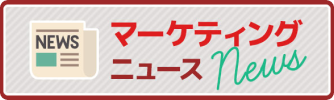- 検索
-
- テーマ別実施時期一覧
- カテゴリー別一覧
-
-
アルコール飲料・嗜好品145
-
非アルコール飲料209
-
その他19
-
-
住宅・住宅設備218
-
-
家電126
-
パソコン・カメラ・AV機器113
-
その他10
-
-
家庭用品・トイレタリー91
-
自動車・関連用品76
-
-
インターネット・情報通信327
-
携帯電話・スマートフォン180
-
メディア・広告66
-
その他7
-
-
ファッション68
-
交通・レジャー・娯楽161
-
季節行事・イベント241
-
時事・ニュース・トレンド51
-
企業ブランドイメージ246
-
広告・CM51
-
WEBサイトの利用91
-
顧客満足度100
- 実施時期別一覧
-
- 調査時期:
- 2020年09月
- 設問項目:
-
テイクアウト・持ち帰りの直近1年間利用状況/食べ物のテイクアウトをする場面/食べ物のテイクアウトをする理由/食べ物のテイクアウトをする際の重視点/テイクアウト実施に関する認知経路/今年3月以降のテイクアウト利用頻度/今年3月以降のテイクアウト利用頻度の変化/今後のテイクアウト・持ち帰りの頻度の変化/食べ物のテイクアウト時の不満/非利用理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■直近1年間のテイクアウト・持ち帰り利用者は7割弱。「ファストフード」が5割弱、「牛丼、餃子、寿司などのチェーン店」が約35%。直近1年間テイクアウト利用者のうち「休日・昼食」利用者が5割弱、「休日・夕食」「平日・昼食」が各4割弱、「平日・夕食」が3割強。
■テイクアウト理由は「食事の準備や片付けが面倒・時間がない」が直近1年間利用者の4割弱、「家でリラックスして食べたい」「食事を早く済ませたい」「出来立てを持ち帰って食べたい」などが各3割弱。
■直近1年間利用者の、テイクアウト実施の情報認知経路は「店頭でお知らせなどを見た」が約45%、「折り込みちらし、ポストのちらし」「店舗のホームページやアプリ」が各2割強。重視点は「味が好み」が6割強、「店への近さ、アクセスの良さ」「待たずに持ち帰れる」が各3割弱。
■今年3月以降テイクアウト利用頻度が増えた人は直近1年間利用者の約45%、「変わらない」は5割弱。今後のテイクアウト・持ち帰りの頻度が「変わらないと思う」は全体の7割弱、増えると思う人は2割強。
-
- 調査時期:
- 2020年09月
- 設問項目:
-
主利用自動車のタイプ/自動車走行時の映像・音声記録状況/ドライブレコーダーのタイプ/ドライブレコーダーのブランド・メーカー/ドライブレコーダーをつけたきっかけ・理由/ドライブレコーダーをつけたことで役に立った・効果があったこと/ドライブレコーダー利用意向/ドライブレコーダー購入時の重視点/ドライブレコーダー利用意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■自動車世帯所有者7割強のうち、ドライブレコーダー利用者は4割強、2017年より増加。利用者のうち「ドライブレコーダー単体」利用者が8割弱、カーナビオプション品の「連動型」「一体型」が約8~9%。
■ドライブレコーダーをつけたきっかけ・理由は「自動車事故やトラブルのニュースや記事」「事故やトラブル時の証明・記録」が、利用者の各5~6割。「自動車事故やトラブルのニュースや記事」「あおり運転・走行妨害対策」などは、2017年より増加。
■ドライブレコーダー利用意向者は、自動車所有者の8割弱、2017年調査より増加。ドライブレコーダー利用者では9割強、非利用者では7割弱。
■ドライブレコーダー利用意向者の重視点は「価格が手頃」が6割強、「操作が簡単」が5割強、「取付けやすさ」「カメラの画素数」「撮影できる範囲の広さ」が各30%台。
-
- 調査時期:
- 2020年09月
- 設問項目:
-
使用しているキッチンコンロのタイプ/ガスコンロのイメージ/IHクッキングヒーターのイメージ/使用しているキッチンコンロのメーカー/キッチンコンロの掃除頻度/今後購入したいキッチンコンロのタイプ/キッチンコンロ購入時の重視点/今後購入したいキッチンコンロのタイプの理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■ガスコンロ使用者は7割強(ビルトイン4割強、据え置き3割強)、IHクッキングヒーター使用者は全体の2割強(ビルトイン2割弱、据え置き約4%)。キッチンコンロ使用者の掃除頻度は週5回以上が3割弱、週1回以上が6割弱。
■ガスコンロのイメージ上位は「火力が強い」「掃除・手入れがしにくい」「危険性が高い」「操作しやすい」など。IHクッキングヒーターのイメージ上位は、「火事などになりにくい」「掃除・手入れが簡単」「価格が高い」「空気の汚れが少ない」「高齢者や子供でも使いやすい」「火力が弱い」など。
■キッチンコンロ利用者の、購入時の重視点は「価格」の他、「手入れのしやすさ」「口数」「メーカー・ブランド」「操作のしやすさ」「安全性」などが上位。
■今後購入したいタイプが「IHクッキングヒーター」は、IH使用者の各8割前後、ガスコンロ使用者の10%台。購入したいタイプが「ガスコンロ」の人はガスコンロ使用者の6割弱、IH使用者の約6~9%。
-
- 調査時期:
- 2020年09月
- 設問項目:
-
食品・飲料購入時に気にする栄養素・成分/食生活で糖質を気にする度合/糖質の摂取に関する意識・行動/糖質を意識して飲食する理由/直近1年間に購入した低糖質商品/糖質制限実施状況/低糖質商品の購入意向/低糖質商品の購入意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■普段の食生活で糖質を気にしている人は全体の4割強。食生活において「糖質制限している」「糖質制限していたことがあるが今は行っていない」は各1割強。
■糖質の摂取に関して意識していることは、「糖質の多い食品・飲料を控える」が3割強、「低糖質であることが表示されている商品を摂取」が2割弱。直近1年間の低糖質の商品購入者は全体の6割強。「ヨーグルト」「パン類」「ビール類」などが各10%台。
■糖質を意識して飲食する人の理由は「生活習慣病、メタボの予防」が6割弱、「体型・体重が気になる」が4割強、「ダイエット」「健康によさそう」「血糖値の改善」「糖尿病などの病気の改善」が各20%台。
■低糖質の商品の購入意向者は全体の4割弱、非購入意向者は2割強。糖質制限実施者の、低糖質商品購入意向は8割弱、糖質制限未経験者では3割弱。
-
- 調査時期:
- 2020年09月
- 設問項目:
-
麺つゆ・だしつゆの利用頻度/市販の麺つゆ・だしつゆの利用タイプ/麺つゆ・だしつゆの利用方法/市販の麺つゆ・だしつゆの調理での利用頻度/購入する麺つゆ・だしつゆのサイズ/市販の麺つゆ・だしつゆ選定時の重視点/市販の麺つゆ・だしつゆ利用理由/市販の麺つゆ・だしつゆ使用時の工夫、おすすめ(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■家庭での市販の麺つゆ・だしつゆ利用者は全体の9割弱。週1回以上利用者は約55%。市販の麺つゆ・だしつゆ利用者のうち「濃縮つゆ」利用者は8割。「ストレートつゆ・しょうゆベース」は3割強で、近畿などでの比率が高い。
■市販の麺つゆ・だしつゆ利用者のうち、そうめん、そば、うどんの「つゆ・汁として、そのまま使う」が各6~7割、「調味料として料理に入れる」「天つゆ」が各4~5割。調理に使う人は、利用者の6割弱。
■市販の麺つゆ・だしつゆ利用理由は、「だしをとる手間がかからない」が利用者の6割弱、「調味してあり失敗がない」「いろいろな料理に使える」が、利用者の各5割前後。
■麺つゆ・だしつゆ選定時の重視点は「味(おいしさ)」が利用者の8割弱、「値段」6割弱、「容量、サイズ」「濃縮タイプ」が各3~4割、「使い慣れている」「メーカー」などが各2割強。
-
- 調査時期:
- 2020年09月
- 設問項目:
-
肉類の料理の嗜好度/肉類の料理を食べる頻度/よく食べる肉の種類/よく食べる肉の部位/肉類購入時の重視点/好きな肉料理/肉類・魚類のどちらを食べることが多いか/肉類のイメージ/肉料理を食べたり作ったりするときの不満(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■肉類の料理を食べる頻度は「週4~5回」「週2~3回」がボリュームゾーン。魚介類より肉類の方を食べることが多い人は全体の6割。よく食べる肉の種類は、近畿では「牛肉」が多く地域差がみられる。
■肉類購入時の重視点は「価格」6割強、「国産かどうか」5割弱。「賞味期限・消費期限」「種類、部位」「鮮度」などが各4割前後。
■肉のイメージは「おいしい」が全体の7割強、「スタミナがつく」5割強、「栄養価が高い」4割弱、「カロリーが高い」「食べやすい」「健康によい」「調理がしやすい」などが各20%台。「スタミナがつく」「調理がしやすい」などは、女性での比率が高い。
■好きな肉料理の上位は「焼肉」7割強、「カレー」「しょうが焼き」「トンカツ」「餃子」「からあげ、フライドチキン」が各60%台。「牛丼」「トンカツ」「メンチカツ」「ハムカツ」「もつ煮込み」などは、男性で高い傾向。
-
- 調査時期:
- 2020年08月
- 設問項目:
-
今年の夏の節電意識/節電対策として今年夏に家で行っていること/今年の夏の節水意識/熱中症対策のために飲食しているもの/今年の夏の熱中症対策実施状況/夏バテの度合/暑さ対策のために利用しているアイテム/暑さを乗り切るために心がけていること・実践していること(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■今年の夏、節電を意識している人は5割強。節水を意識している人は5割弱。節電・節水とも、高年代層での比率が高い傾向。
■今年夏に家で実施した節電対策は「エアコンの使用時間・設定温度などを工夫」が4割強、「節水を心がける」「照明をなるべく使わない、こまめに消す」「エアコンをなるべく使わない」「日差しを遮る工夫」が各2割強~3割。
■今夏の熱中症対策実施者は5割弱で、2018年以降減少。熱中症対策のために飲食しているものは「水、ミネラルウォーター」が約55%、「日本茶、麦茶、ウーロン茶など」が約45%、「スポーツドリンク」などが2割強。
■今年の夏、夏バテの人(軽い夏バテを含む)は3割弱。2019年と比べて減少。暑さ対策のための利用アイテムは「帽子」が4割強、「扇子、うちわ」「日傘」が各3割弱、「汗拭きシート」「夏用マスク、冷感マスク」「機能性下着」が各15~16%。
-
- 調査時期:
- 2020年08月
- 設問項目:
-
朝の肌のお手入れに使う時間/行っているスキンケア/使用しているスキンケア・化粧品/スキンケア・化粧品選定時の重視点/スキンケア・化粧品購入時の参考情報源/スキンケア・化粧品購入場所/スキンケア・化粧品の1ヶ月あたり平均購入金額/スキンケア・化粧の際のこだわり・気をつけていること(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■朝の肌のお手入れをしている人は全体の約55%。男性3割弱、女性9割。朝の肌のお手入れにかかる時間が5分以下の人はお手入れをする人の7割弱。
■スキンケア実施者は全体の6割弱。「保湿ケア」がケア実施者の4割、「UVケア」「美白ケア」「ハンドケア」が各1割強~2割。使用スキンケア用品は「洗顔料」が全体の6割弱、「化粧水、ローション」「メイク落とし」「ファンデーション」が各3~4割。男性30代では男性の他の年代よりスキンケア・化粧品の使用率が高い。
■選定時の重視点は「肌との相性」が使用者の6割弱、「使用感・使いごこち」「効能・効果」「価格の適正さ」などが各4~5割。女性40~70代では「インターネット通販」が各5割前後と比率が高い。
■購入時の参考情報源は「テレビ番組・CM」「店頭のPOP」が使用者の各20%台。女性若年層では「ブログ、Twitter、インスタグラム、動画共有サイトなど」などの比率がやや高い。
-
- 調査時期:
- 2020年08月
- 設問項目:
-
リモコンで操作している家電製品/スマートフォンなどで遠隔操作している家電製品/スマートリモコン利用状況/利用しているスマートリモコンの種類/スマートリモコン利用意向/スマートリモコンで操作したい家電/スマートリモコンで利用したい機能/スマートリモコン利用意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■スマートフォンなどで遠隔操作している家電製品は、「テレビ」4%、「エアコン」「ブルーレイ・DVDレコーダー、プレーヤー」が各2%。
■スマートリモコン現在利用者は2%、知っているが利用していない人は6割弱、非認知者は4割強。
■スマートリモコン利用意向者は全体の2割弱、「どちらともいえない」が4割弱。利用意向者の比率は、現在利用者では8割弱、知っているが利用していない層では2割強、非認知者では1割強。
■スマートリモコンで操作したい家電は「エアコン」「テレビ」が利用意向者の各60%台、「照明」が6割弱、「ブルーレイ・DVDレコーダー、プレーヤー」が4割強。利用したい機能は「外出中に家電をスマートフォンから遠隔操作」が約65%、「自宅に近づくとエアコンの電源を自動でオン」「タイマー機能で時間や曜日を設定し自動化」が各4割弱。
-
- 調査時期:
- 2020年08月
- 設問項目:
-
動画共有サイトの閲覧・投稿状況/直近1年間に利用したことがある動画共有サイト/動画共有サイト利用頻度/今年3月以降の動画共有サイトの利用頻度の変化/動画共有サイトへのアクセス端末/動画共有サイトでよく閲覧するもの/動画共有サイト利用理由/動画共有サイト利用意向/動画共有サイトの楽しみ方(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■動画共有サイト閲覧者は7割強、投稿者は約3%。週1回以上利用者は、動画共有サイト利用者の7割強で2018年調査より増加。利用意向は全体の7割強、利用者では8割強~9割強、非利用者では1割弱。
■動画共有サイトへのアクセス方法は「スマートフォン」「ノートパソコン」が、利用者の各5割前後、「デスクトップパソコン」が3割弱、「タブレット端末」が2割弱。
■動画共有サイトでの閲覧コンテンツは「音楽関連、ミュージックビデオ」「YouTuberの動画」が各30%台、「○○のやり方・手順など紹介」「著名人・芸能人などの動画」が各20%台。
■動画共有サイト利用理由は、「自分が見たい時に好きなように見られる」が利用者の5割強、「繰り返し見られる」「見たいもの・見たい部分だけ見られる」が各30%台。
-
- 調査時期:
- 2020年08月
- 設問項目:
-
飲食店情報を調べる際の情報媒体利用頻度/飲食店情報を調べる際の情報源/飲食店情報を調べる際に利用するサイト・アプリ/飲食店情報を調べる際最もよく利用するサイト・アプリ/飲食店情報サイト・アプリ選定時の重視点/飲食店情報サイト・アプリの利用目的/飲食店情報サイト・アプリの利用情報・機能/飲食店関連情報入手先/飲食店情報を調べる際最もよく利用するサイト・アプリの利用理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■飲食店情報を調べる人の情報源は「パソコンのインターネットサイト」が7割弱、「スマートフォンのインターネットサイト」が4割強、「紙媒体情報」「スマートフォンのアプリ」が各20%台。スマートフォンのサイト・アプリは過去調査より増加傾向、若年層での比率が高い。
■飲食店情報サイト・アプリ選定時の重視点は「登録店舗数の多さ」「検索方法のわかりやすさ」などが情報サイト利用者の各4割弱。「割引クーポンなどの特典の多さ」などは過去調査より減少傾向。Retty主利用者では「口コミの信頼性」「ページ・情報の見やすさ」が上位2位。
■飲食店情報サイト・アプリのコンテンツでは「お店の場所」「価格帯」「営業時間・定休日」「料理のジャンル」「メニュー・品書き」などの利用が多い。ホットペッパーグルメ主利用者では「クーポン」「飲み放題の有無」などの比率が、他の層より高い。
■サイト・アプリ利用目的は「食べたいメニューのある店を探す」「条件にあう店を探す」が各40%台、「出かけたことのない地域にある店を探す」「行く前に調べたい」「場所を知りたい」が各30%台。ホットペッパーグルメ主利用者は「クーポンを利用できる店を探す」、食べログ主利用者は「お店の評価を知りたい」などの比率が高い。
-
- 調査時期:
- 2020年08月
- 設問項目:
-
自動車保険の加入状況/自動車保険に加入している保険会社/自動車保険について、最も多く保険料を支払っている保険会社/加入自動車保険会社の満足度/自動車保険(任意保険)の加入経路/自動車保険加入時に参考にした情報源/自動車保険選定時の重視点/自動車保険契約先の見直し意向/今後自動車保険に加入(更新)したい保険会社/加入自動車保険への加入理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■自動車保険(任意保険)加入率は全体の7割強。契約先見直し意向は加入者の3割強。主加入保険会社の「満足」「やや満足」の合計比率は、日新火災海上保険主加入者、三井ダイレクト損保主加入者、SBI損保主加入者、AIG損保主加入者などで高い。
■自動車保険の加入経路は「パソコンからインターネット経由」が加入者の3割強、「保険代理店」「自動車を購入した店」が各2割弱。加入時の参考情報源は「保険商品を扱ったホームページや比較サイト」「家族・友人などのクチコミ」「テレビ番組・CM」「保険を取り扱う企業のホームページなど」「営業職員、保険外交員」「自動車購入店」などが加入者の各10%台。
■保険選定時の重視点は「保険料の安さ」「補償内容の充実度」が、加入者の各5割前後、「事故時の対応力・サービス」「商品内容のわかりやすさ」が各3割強。
■今後加入したい保険会社は「ソニー損保」「東京海上日動火災保険」「損保ジャパン」「SBI損保」などが、上位、「わからない」は5割強。主加入自動車保険の継続加入意向はAIG損保主加入者、イーデザイン損保主加入者、ソニー損保主加入者などでの比率が高い。
-
- 調査時期:
- 2020年08月
- 設問項目:
-
株式売買の経験/インターネットでの株式売買の経験/インターネット取引経験がある証券会社/現在主にインターネット取引をしている証券会社/主にインターネット取引をしている証券会社の満足度/ネット取引による直近1年間の投資資金の増減 /ネットでの株式売買の意向 /ネットでの証券取引時の重視点/主にインターネット取引をしている証券会社の利用理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■インターネットでの株式売買現在実施者は全体の2割強、株式売買現在実施者の9割弱。インターネットでの株式売買経験者は全体の3割強。
■インターネット取引経験がある証券会社は「SBI証券」「楽天証券」「野村證券」「マネックス証券」などが上位。「満足」の比率が高いのは、SBI証券主利用者、マネックス証券主利用者、楽天証券主利用者など。
■直近1年間のネット取引による投資資金が減少した人の比率は、ネットでの株式売買経験者の4割弱、現在取引者の4割弱。2019年調査と比べ、投資資金が減少した人の比率が増えた。
■ネットでの株式売買意向は3割弱。現在ネットでの株式売買者の意向は9割、過去経験者では3割強、未経験者では約8%。株式売買意向者の重視点は「取引手数料が安い」がトップで「手続が簡単」「セキュリティ」「取引ツールが使いやすい」などが続く。
-
- 調査時期:
- 2020年08月
- 設問項目:
-
ハンドソープ・石鹸での手洗い回数/自宅での手洗い時のハンドソープ・せっけん使用状況/ハンドソープで手を洗う場面/自宅で利用しているハンドソープのタイプ/直近1年間に利用したハンドソープの銘柄/直近1年間に最もよく使ったハンドソープ/ハンドソープ選定時の重視点/手洗いやハンドソープ使用方法で気を付けるようになったこと/主利用ハンドソープの銘柄利用理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■ハンドソープ・石けんでの手洗い回数は「2~3回」「4~5回」がボリュームゾーン。1~5回が6割弱、10回以上が2割弱。自宅での手洗い時「ハンドソープのみ」使用者は6割弱、石けんと併用者は3割弱。2011年調査と比べ「ハンドソープのみ」使用者が大幅増。ハンドソープ使用者のうち泡タイプ使用者が8割弱。
■ハンドソープで手を洗う場面は「外から帰った後」が利用者の9割、「ゴミや汚物などを処理した後」が6割強、「トイレの後」「掃除の後」「汚れが気になる」が各5割前後。
■ハンドソープ利用者の重視点は「価格」が5割強、「液体タイプ・泡タイプ・ジェルタイプ」「メーカーやブランド」が各4割弱、「詰め替え用がある」「殺菌力、殺菌成分」が各3割前後。
■新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、ハンドソープ使用方法で気を付けていることは「細かいところまで丁寧に洗う」が5割弱、「ハンドソープで手を洗う回数を増やす」「ハンドソープで手を洗う時間を長くする」が各3~4割。
-
- 調査時期:
- 2020年08月
- 設問項目:
-
所有している扇風機のタイプ/扇風機所有台数/主利用扇風機のメーカー/主利用扇風機で使っている機能/主利用扇風機購入時期/扇風機購入時の重視点/購入したい扇風機のタイプ/扇風機についての不満(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■所有扇風機のタイプは「扇風機(据え置き型)」が全体の8割強。「サーキュレーター」が2割で、過去調査より増加傾向。1~3台所有者が全体の7割弱。
■所有扇風機の機能のうち「左右の首ふり機能」使用者は扇風機所有者の8割強。「オフタイマー」「リズム」「リモコン」「強風」「超微風」などが各20%台。
■扇風機購入時の重視点は「価格」が6割強、「運転音の静かさ」「本体の大きさ」「性能・パワー」などが各3割弱。バルミューダ主利用者では「運転音の静かさ」、プラスマイナスゼロ主利用者では「本体のデザイン・色」が1位。
■今後の購入意向は「扇風機(据え置き型)」が4割強。「羽なし扇風機」は2割強で、現在所有率(約6%)に比べて比率が高い。
-
- 調査時期:
- 2020年08月
- 設問項目:
-
住まいの間取り/家にある備え付けの収納/備え付けの収納に対する満足度/自宅の収納に関する不満/今より充実したい収納場所/収納場所がなくて困っている・不満な物/自宅が片付いている度合い/収納に関する工夫・こだわり(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■備え付けの収納は「押入れ」「洗面台の収納」「キッチンの収納」「玄関の収納」などが各7~8割。あったらよい・充実したいのは「ウォークイン・クローゼット」が2割強、「クローゼット」「キッチンの収納」「風呂場・脱衣場の収納」「玄関の収納」「トイレの収納」などが各10%台。
■備え付け収納がある人のうち、収納に満足している人は4割強、不満な人は3割強。
■収納の不満点は「収納スペースが少ない」が4割弱、「風通しが悪い」「収納スペースの幅や奥行きがない」「湿気がある」などが各2割弱。
■収納場所で困っている・不満な物は「衣服」が4割強、「寝具類」「食品のストック」「かばん類」「靴」「衣類小物」などが各2~3割。
-
- 調査時期:
- 2020年08月
- 設問項目:
-
中華料理の嗜好度/好きな中華料理のメニュー/中華を食べるシーン/自宅で中華料理を食べる頻度/自宅で食べる中華料理のメニュー/自宅での中華料理準備方法/自宅で食べる中華料理の重視点/中華料理のイメージ/中華料理の魅力(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■好きな中華料理や自宅で作るメニューのトップ3は「餃子」「麻婆豆腐」「チャーハン」。
■自宅で中華料理を食べる頻度は「月に2~3回くらい」がボリュームゾーン。週1回以上食べる人は4割弱。自宅で中華料理を食べる人のうち「自分や家族の手作り」が6割強、「冷凍食品、レトルト食品」「料理の素やあわせ調味料などを利用」が各4割強~5割。過去調査と比べ、「冷凍食品、レトルト食品」「お惣菜、弁当」などが増加傾向。
■自宅で中華料理を食べる際の重視点は「価格」「野菜をたくさん食べる」「味がしっかりついている」「栄養バランス」などが各2割強~3割。
■中華料理のイメージは「庶民的」が5割弱、「こってりした」「味が濃い」「スタミナがつく」「大勢で楽しむ」などが各3~4割。「低カロリー」「見栄えがしない」「革新的」「味が薄い」などは比率が少ない。
-
- 調査時期:
- 2020年08月
- 設問項目:
-
市販の果汁入り飲料の飲用頻度/直近1年間に飲んだ果汁入り飲料/直近1年間の最頻飲用果汁入り飲料/果汁入り飲料飲用場面/果汁入り飲料選定時の重視点/果汁入り飲料に期待すること/果汁入り飲料でよく飲むサイズ/市販の果汁入り飲料飲用意向/果汁入り飲料の不満点(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■果汁入り飲料飲用者は全体の7割弱、過去調査に比べ減少傾向。週1回以上飲用者は2割弱。飲用意向率は6割弱、月数回以上飲用者で各9割割前後、非飲用者で9%。
■果汁入り飲料の飲用場面は「おやつの時」「のどが渇いたとき」が飲用者の各3割前後、「くつろいでいるとき」「リフレッシュしたいとき」「朝食時」「お風呂あがり」「甘いものがほしいとき」が各2割前後。
■果汁入り飲料選択時の重視点は「味の好み・おいしさ」が飲用者の7割強、「価格」「入っている果実の種類」が各4割弱、「果汁の濃度」などが3割弱。
■果汁入り飲料飲用者の、果汁入り飲料への期待の上位3位は「健康によい」「果汁100%」「ビタミンなどの栄養素が摂取できる」などが各30%台。トロピカーナ主飲用者、Dole主飲用者では「果汁100%」、なっちゃん主飲用者、Qoo主飲用者では「すっきりしている」が1位。
-
- 調査時期:
- 2020年07月
- 設問項目:
-
2020年3月時点での就業形態/3~7月の在宅勤務状況/在宅勤務時の生産性向上・低下状況/7月現在の在宅勤務の頻度/新型コロナウイルス感染拡大の、働き方・仕事への影響/新型コロナウイルス感染拡大の、働き方・仕事に関する意識への影響/新型コロナウイルス感染拡大により、働き方・仕事に関する意識で変化したこと/勤め先の、新型コロナウイルス感染拡大防止の対応の満足度/勤め先の、新型コロナウイルス感染拡大防止の対応の満足度の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■3~6月頃在宅勤務実施経験者は、3月時点の有職者の3割強。3~6月から開始し「現在もしている」が1割強、正社員では2割弱。在宅勤務時の方が仕事の生産性が向上した人は、3月以降在宅勤務経験者の約15%。低下した人は4割弱。
■新型コロナウイルス感染拡大により働き方・仕事への影響があった人は、3月時点の有職者の6割弱。「在宅勤務、テレワークなど」が2割強、「仕事量の減少、キャンセルや延期」「時差出勤、フレックスタイム」「勤務日数が減った」が各10%台。
■新型コロナウイルス感染拡大による、働く意識の変化は「在宅勤務・テレワークや、オンラインでできる働き方・仕事をしたい」「副業・ダブルワークをしたい」「柔軟な働き方・新しいワークスタイルを取り入れている企業で働きたい」「家庭での時間を重視する働き方・仕事をしたい」が、3月時点有職者の各1割前後。仕事に対する考え方に変化があった人は、派遣社員や在宅勤務経験者などで高い傾向。
■3月時点で雇用型で勤務する有職者のうち、勤め先の新型コロナウイルス感染防止の対応について、満足層は3割弱、不満層は2割弱。
-
- 調査時期:
- 2020年07月
- 設問項目:
-
レジ袋有料化の認知/レジ袋有料化以前の、袋・入れ物などの利用/レジ袋有料化以降の、食料品・飲料購入時の袋・入れ物/レジ袋有料化以降の、衣料品購入時の袋・入れ物/有料のレジ袋購入・利用時の理由/持参した入れ物利用時の理由/レジ袋利用頻度の変化/レジ袋利用頻度の変化の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■レジ袋有料化以前に「無料のレジ袋」利用者は7割弱。「持参したエコバッグやカバン、リュックなど」は6割強で、女性40~70代での比率が高い。
■レジ袋有料化後に、利用が多くなると思う入れ物(予定)は、食料品・飲料購入時はエコバッグが8割弱、「持参したビニール袋・レジ袋」が4割弱。衣料品購入時はエコバッグが6割強、「店が提供する無料の入れ物」「持参したビニール袋・レジ袋」が各20%台。「有料のレジ袋」は1割強、男性や若年層での比率が高い傾向。
■有料のレジ袋購入・利用理由は「エコバッグや袋を持っていないときに必要」が6割弱、「持参した袋では足りない」が3割弱。持参した入れ物利用理由は「レジ袋が有料だから」が7割弱で、女性での比率が高い。
■レジ袋有料化以前の1年間と比べ、有料化後にレジ袋を利用する頻度が減ると思う人は6割強。「変わらない」は2割強で、男性10~30代でやや高い。
-
- 調査時期:
- 2020年07月
- 設問項目:
-
今年の夏の過ごし方の予定/今夏に出かける予定/夏休みの予定日数/夏休みの予定日数の増減/新型コロナウイルスの影響による今夏の予定変更状況/今夏の予定変更の理由/今年の夏の過ごし方の変化有無/今年の夏の過ごし方の具体的な内容(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■今年の夏の過ごし方の予定は「主に自宅で過ごす」が4割弱。帰省以外で外出の予定がある人は3割強で、そのうち「温泉」「ショッピング」「自然名所観光」に行く予定が各3~4割。
■就労者または学生の夏休みの予定日数は、「4~5日」「6日以上」が2割強。予定日数が例年と比べて「あまり変わらない」は6割弱、「少ない」は1割強。
■新型コロナウイルスの影響により今夏の予定を「変更したものがある」は約25%、「予定は決めていなかった」が7割弱。変更理由は「人が密集する場所やイベント、日程を避ける」「しばらくは外出を控えたい」が、変更した人の各5割前後、「あまり遠出をしないようにする」が4割弱、「行こうと思っていたイベントや施設が中止・延期・休止などになった」が3割弱。
■今年の夏は例年と「過ごし方が変わると思う」「あまり変わらないと思う」はそれぞれ4割強。「過ごし方が変わると思う」は、女性10~30代での比率が高い傾向。
-
- 調査時期:
- 2020年07月
- 設問項目:
-
父の日での立場/父の日にしたこと/今年の父の日のためにかけた費用総額/今年の父の日のプレゼントや行ったことの準備をした日/父の日に贈ったプレゼント/父の日のプレゼント購入場所/父の日にほしいプレゼントやしてほしいこと/あなたにとって父の日とは/今年の父の日のプレゼント選定時のこだわりや重視ポイント(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■父の日に関して何かした人は、全体の3割強(何かしてあげる立場の人のうち6割弱)。父の日に「プレゼントを購入して贈った」は全体の2割弱、「一緒に家で食事をした」が約6%。
■父の日に贈ったプレゼントは「酒」「食品(お菓子以外)」が、プレゼントを贈った人の各2割強、「衣料品」「お菓子」が各2割弱。購入場所は「インターネットショップ」が4割強。2019年から増加しており外出自粛要請の影響がうかがえる。
■父の日にほしいプレゼントやしてほしいことは「酒」「一緒に外食をする」「感謝の気持ち」「衣料品」などが、何かしてもらう立場の人の各10%台。
■父の日とは「父をいたわる・苦労をねぎらう日」が4割弱、「親孝行・恩返しをする日」「感謝の気持ちを伝える日」「喜んでもらう日」などが各10%台。「必要ない」は全体の2割弱。
-
- 調査時期:
- 2020年07月
- 設問項目:
-
ムダ毛が気になる度合/ムダ毛処理の頻度/ムダ毛処理を行っている部位/ムダ毛処理の方法/直近5年以内の、脱毛サロン等での脱毛・ムダ毛処理経験/脱毛・ムダ毛処理での利用店舗選定時の参考情報/ムダ毛処理方法の意向/ムダ毛処理・脱毛に関して困ること・悩み(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■ムダ毛が気になる人は全体の4割弱、2017年調査より増加。ムダ毛処理実施者は全体の5割弱。週1回以上実施者が全体の2割強、ムダ毛処理実施者の5割弱。女性や若年層での比率が高い。
■ムダ毛処理実施部位は、「ワキ」「顔」がムダ毛処理実施者の50%台、「脚」が4割強、「鼻毛」「腕」が各3割強。2017年調査と比べ「顔」などが増加。男性30~50代では「鼻毛」「ヒゲ」「顔」、女性若年層では「ワキ」「腕」「脚」が上位3位。
■脱毛サロン等での脱毛・ムダ毛処理直近5年以内実施者は約5%、経験者は1割強。女性10・20代では「脱毛サロン、エステサロン」が4割弱、「医療機関での医療脱毛」が1割強で、他の層より高い。
■現在のムダ毛処理方法は「カミソリ」が実施者の6割強、「毛抜き」が4割弱。今後のムダ毛処理方法の意向は「カミソリ」が2割強、「毛抜き」「ムダ毛用電気シェーバー」が各1割強。「ムダ毛用電気シェーバー」「脱毛器」「脱毛サロンやエステ、医療機関などでの脱毛処置」などは、女性若年層での比率が高い傾向。
-
- 調査時期:
- 2020年07月
- 設問項目:
-
体型意識/ダイエット経験/ダイエットの理由/リバウンドの経験/ダイエット方法/ダイエットをやめた理由/ダイエットに関する情報源/直近のダイエット方法に決めた理由・過程(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■現在ダイエットをしている人は全体の2割強、過去にしたことがある人(3割強)をあわせた経験者は6割弱。ダイエットに関する情報源は「テレビ番組」が全体の4割強。女性や若年層では「SNS」「動画共有サイト」などが高い。
■ダイエットをする理由は「体型・スタイルを良くする」「健康状態を改善」が経験者の各5~6割、「体型・スタイルの変化を感じた」「生活習慣病を予防」が各3割強。男性高年代層では「健康状態を改善」「生活習慣病を予防」「健康診断の結果が気になった」などの比率が高い。
■現在行っているダイエット方法は「食事制限」「食べ方に気を付ける」が各5割前後、「間食・おやつの制限」「ウォーキング、散歩など」が各4割弱。「筋力トレーニング」「普段の生活の中で、意識して体を動かす」などは各3割弱で、2017年調査よりやや増加。
■現在ダイエットを行っていない理由は「面倒くさくなった」が、行っていない人の3割弱、「ストレスがたまる」「ダイエットが成功した」が各2割弱。
-
- 調査時期:
- 2020年07月
- 設問項目:
-
紙の書籍の1年あたりの購入冊数/直近1年間に電子書籍・コミック・雑誌を読む頻度/電子書籍・コミック・雑誌で読むジャンル/直近1年間に読んだ電子書籍・コミック・雑誌の冊数/電子書籍・コミック・雑誌を読む端末/電子書籍・コミック・雑誌の利用パターン/直近1年間に利用した電子書籍ストア・アプリ/電子書籍・コミック・雑誌の利用したいパターン/電子書籍・コミック・雑誌の有料・無料利用意向理由/利用したくない理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■直近1年間に電子書籍・コミック・雑誌を読んだ人は全体の3割強、若年層で高い。直近1年間利用者のうち、週1回以上読む人は2割弱、月に1冊以上読む人が6割強。
■直近1年間に電子書籍・コミック・雑誌利用者のうち「マンガ・コミック」を読む人は6割弱、「小説」「趣味・生活関連の実用書」「雑誌」が各20%台。利用端末は「スマートフォン」が直近1年間利用者の6割弱、「タブレット端末」が3割弱、「ノートパソコン」「デスクトップパソコン」が各2割前後。
■直近1年間の、電子書籍・コミック・雑誌利用者のうち「有料:1冊ずつ購入」「有料:定額制読み放題」が各30%台。「無料の範囲で利用」が6割弱、「無料で一部分だけを読む」が4割弱で、女性若年層での比率が高い傾向。
■電子書籍・コミック・雑誌利用意向者は、全体の6割弱。直近1年間利用者の9割強、利用未経験者の3割強。「無料の範囲で利用」が3割弱、「有料:1冊ずつ購入」「無料で一部分だけを読む」が各1割強。
-
- 調査時期:
- 2020年07月
- 設問項目:
-
生命保険会社の認知/主加入生命保険/加入生命保険商品の種類/生命保険申込み方法/1か月あたりの生命保険料/生命保険加入・見直し時に、候補として検討した生命保険会社/生命保険に関する情報入手経路/加入したい生命保険会社/生命保険の加入・見直し意向/生命保険の加入に関する不満・不安(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■生命保険申込み方法は「知り合いや紹介を受けた営業職員、保険外交員」が加入者の3割強、「自宅や勤務先に訪問してくる営業職員、保険外交員」「勤務先」が各1~2割強。アクサダイレクト生命主加入者、チューリッヒ生命主加入者、ライフネット生命主加入者、楽天生命主加入者では「インターネットで申込み手続き」が1位。
■生命保険加入時に候補として検討した生命保険会社がある人は、生命保険加入者の4割強。
■生保関連の情報入手経路は「テレビ番組、CM」が3割、「営業職員、保険外交員から」「家族や友人、知人を通じて」「保険商品のパンフレット、説明資料」「保険を取り扱っている企業のホームページ」などが各10%台。
■生命保険の加入・見直し意向は、「現在加入の生命保険を継続」が3割強、「現在加入の生命保険に追加して加入」が約4%です。「生命保険には当面加入しない」は3割強。
-
- 調査時期:
- 2020年07月
- 設問項目:
-
エアコン所有台数/エアコンの直近導入時期/主利用エアコンのメーカー/冷暖房以外の使用機能/エアコン購入時に重視する点/エアコンの購入・買い替え・買い増し予定時期/どのような機能がついたエアコンを購入したいか/エアコンの不満点/非利用理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■エアコン所有率は9割強。3台以上所有者は5割弱、持ち家一戸建て居住者では7割弱。
■エアコン購入時の重視点は「価格」が7割弱、「ランニングコストの安さ」「性能・パワー」「メーカー・ブランド」「省エネ」などが各4~5割。
■冷暖房以外で使っている機能は「除湿」が所有者の6割弱、「タイマー」が3割強、「空気清浄」が1割強。
■基本機能以外であったらよい機能は「自動掃除機能」が5割弱、「内部乾燥」「除菌」「空気清浄」「除湿」などが各30%台。2017調査と比べ、「内部乾燥」「換気」などが増加。
-
- 調査時期:
- 2020年07月
- 設問項目:
-
利用している飲用水/家庭用ウォーターサーバーの利用実態/ウォーターサーバーを利用し始めたきっかけ/ウォーターサーバー非利用理由/ウォーターサーバーの利用中止理由/主利用家庭用ウォーターサーバーのタイプ/主利用家庭用ウォーターサーバー/主利用ウォーターサーバーの満足度/ウォーターサーバー利用意向/主利用ウォーターサーバーの選定理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■家庭用ウォーターサーバー利用経験者は全体の1割強、現在利用は約4%。現在利用者のうち「ワンウェイ方式のボトル・パック」利用者が約45%、「リターナブル方式のボトル」が約35%、「水道直結型」が約8%。
■利用のきっかけは、利用経験者では「無料お試し期間」が3割強、「店頭、街頭などでのキャンペーンやデモ」が2割強。現在利用者では「店頭、街頭などでのキャンペーンやデモ」「おいしい水が飲みたい」「無料お試し期間」「家族や友人・知人のすすめ」などが上位。
■非利用理由、利用中止理由とも「維持費がかかる」「設置スペースをとられる」が上位2位。水道水やミネラルウォーターなどで十分/満足の他、「経済的余裕がない」「ボトル交換や手入れ等が面倒」なども上位にあがっている。
■家庭用ウォーターサーバー利用意向者は全体の約8%。現在利用者では8割強、利用未経験者では約4%。非利用意向者の比率は全体の約75%。
-
- 調査時期:
- 2020年07月
- 設問項目:
-
夏にアイスクリーム類を食べる頻度/冬にアイスクリーム類を食べる頻度/アイスクリーム類・氷菓の食べ方等の、季節による違い/アイスクリーム類を食べるシーン/アイスクリーム類の購入場所/アイスクリーム類を食べる際の重視点/直近1年間に食べたアイスクリーム類の銘柄/最も好きなアイスクリーム類の銘柄/市販のアイスクリームで好きなもの(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■夏にアイスクリーム類を週1回以上食べる人は6割弱。冬に週1回以上は2割強。アイスクリーム類を「主に暑い季節に食べる」は3割強、「季節を問わず、一年を通して食べる」は3割弱。
■アイスクリームを食べるシーンは「間食・おやつ」が利用者の5割強、「暑いとき」「くつろいでいるとき」「甘いものが欲しいとき」「お風呂あがり」などが各20%台。夏に食べる頻度が高い層では「夕食前後」「お風呂あがり」などが、やや高い傾向。
■アイスクリーム類を食べる人の重視点は「味」8割強、「価格」5割強、「食感」が3割弱、「食べ慣れている」「甘すぎない」「容器の形状」「食べやすさ」などが各2割強。購入場所は「スーパー」が8割強、「コンビニエンスストア:市販のアイス」が5割弱、「ドラッグストア」が2割弱。
■最も好きな市販のアイスクリームは「ハーゲンダッツ」が、市販のアイスクリーム利用者の2割強。2位は男性では「チョコモナカジャンボ」、女性では「明治エッセル スーパーカップ」。
-
- 調査時期:
- 2020年07月
- 設問項目:
-
コーヒーの飲用頻度/飲んでいるコーヒーのタイプ/最もよく飲むコーヒーのタイプ/好きなコーヒーの飲み方/コーヒーを飲む場所/コーヒーを飲む場面/コーヒーへのこだわり/コーヒーの楽しみ方(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■コーヒーを毎日飲む人は全体の7割強、「1日に2~3回」が4割弱。コーヒー飲用者のうち「インスタントコーヒー」「レギュラーコーヒー」が各5割前後、「缶コーヒー」「ペットボトル入りコーヒー」が各3割弱。2017年調査と比べ、「ペットボトル入りコーヒー」が増加。
■好きなコーヒーの飲み方は「ホット/ブラック」が飲用者の5割。男性30~50代では、ホット・アイスのブラックが上位。カフェ・オレ、カフェ・ラッテは、女性や若年層での比率が高い傾向。
■コーヒー飲用者のうち「自宅」で飲む人は9割、「職場」が4割弱、「コーヒーチェーン店」「車の中」「喫茶店 ・カフェ」などが各2割前後。コンビニコーヒー主飲用者や缶コーヒー主飲用者などでは「車の中」の比率が高い。
■コーヒーを飲む場面は「朝食時」「おやつの時」が各40%台。「リラックスしたいとき」「休憩中・休み時間」「仕事・勉強・家事をしながら」「昼食時」「食後」「気分転換するとき」などが続く。