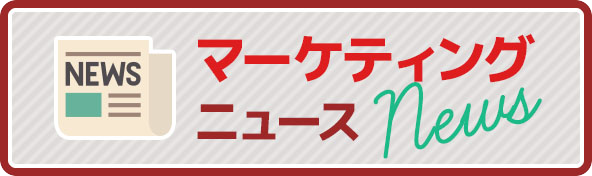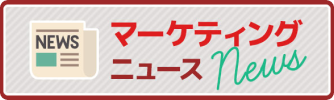- 検索
-
- テーマ別実施時期一覧
- カテゴリー別一覧
-
-
アルコール飲料・嗜好品145
-
非アルコール飲料209
-
その他19
-
-
住宅・住宅設備218
-
-
家電126
-
パソコン・カメラ・AV機器113
-
その他10
-
-
家庭用品・トイレタリー91
-
自動車・関連用品76
-
-
インターネット・情報通信327
-
携帯電話・スマートフォン180
-
メディア・広告66
-
その他7
-
-
ファッション68
-
交通・レジャー・娯楽161
-
季節行事・イベント241
-
時事・ニュース・トレンド51
-
企業ブランドイメージ246
-
広告・CM51
-
WEBサイトの利用91
-
顧客満足度100
- 実施時期別一覧
-
- 調査時期:
- 2020年11月
- 設問項目:
-
店・施設をひとりで利用することの抵抗感/普段ひとりで利用する場所/飲食店・レジャー施設をひとりで利用する理由/飲食店・レジャー施設をひとりで利用する頻度の変化/ひとりで利用したい・してみたい場所/ひとりで利用したくない場所/ひとりで利用したくない理由/ひとりで利用するのが気に入っている施設・場所と理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■飲食店・レジャー施設をひとりで利用することに抵抗感がある人は全体の6割弱、女性高年代での比率が高い。ひとりで利用する頻度が1年前より減った人は3割強、「変わらない」が6割弱。
■普段ひとりで利用する場所は「チェーンのカフェ・喫茶店等」「ファストフード店」などが上位。男性30代以上では「牛丼チェーン店」「ラーメン店」、女性は「チェーンのカフェ・喫茶店等」「ファストフード店」「映画館」などが上位。ひとりで利用する理由は「自分のペースで自由に利用したい」「ひとりの方が気が楽」などが上位。女性10・20代では「カラオケ」「コンサート・ライブ・観劇」などの比率が高い。
■ひとりで利用したい場所は、飲食系ではチェーン店やチェーン以外の「カフェ・喫茶店等」や、「ファストフード店」「ラーメン店」などが各3割弱~4割弱。飲食系以外では「映画館」「国内旅行」「美術館・博物館など」が各20%台。
■ひとりで利用したくない場所は、飲食系では「焼肉店」「居酒屋」「バイキング形式のレストラン」「フレンチ専門店」などが各3割弱。飲食系以外では「遊園地・テーマパーク」が約45%、「ボウリング」「海外旅行」が各30%台。ひとりで利用したくない理由は「他の人と利用した方が楽しい」「ひとりだと利用しづらい雰囲気」などが上位。
-
- 調査時期:
- 2020年11月
- 設問項目:
-
ハロウィンの認知/ハロウィンから連想すること/ハロウィンにあたって購入したもの/ハロウィンで購入した商品の購入場所/ハロウィンにあたって実施したこと/ハロウィンの行事を一緒にした人/ハロウィンで使った費用総額/あなたにとってハロウィンとは/今年のハロウィンで印象に残っていること(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■ハロウィン認知率は全体の98.3%。連想することは「かぼちゃ」「仮装」「お化け」「お菓子」「魔女」「ランタン」などが上位。「仮装」は2017年調査以降増加傾向。
■ハロウィンに関することの実施率は認知者の約17%。「ハロウィンにちなんだお菓子等を食べた」「自分の子どもにお菓子等をあげた」が実施者の約21%、「部屋などを装飾」「友人・知人の子どもにお菓子等をあげた」などが約15%。一緒にした人は、女性10・20代では「女性の友人・知人」、30・40代では「自分の子ども」などの比率が高い。
■ハロウィンのために何か購入したものがある人は認知者の約16%。「お菓子・スイーツ等」が実施者の6割弱、「仮装用の衣装や小物」「かぼちゃ」などが各2割強。購入場所は「スーパー」が購入者の約55%、「100円均一ショップ」が3割弱。
■ハロウィンのとらえ方は、「興味がない」が全体の4割、「海外の行事」「子どものイベント」「季節行事の一つ」が各10%台。ハロウィンに関することの実施者では「子どものイベント」「季節行事の一つ」などが上位。
-
- 調査時期:
- 2020年11月
- 設問項目:
-
SNSの認知・登録状況/利用しているSNSサイト/SNS利用頻度/最頻利用SNS/SNS利用場面/SNSを利用する機器/SNSの利用内容/今後利用したいSNS/閲覧しているSNS/あなたにとってSNSとは(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■SNS登録者は7割弱で、過去調査より増加傾向。回答者全体に占める利用者は「LINE」5割強、「Twitter」「Facebook」各30%台、「Instagram」2割強。過去調査と比べ「LINE」「Twitter」「Instagram」などが増加傾向。今後利用したいSNSでもLINEが1位で4割強、「Twitter」「Facebook」「Instagram」が各2割前後。
■SNS登録者のうち、1日2回以上利用者は5割弱。7割強が毎日アクセスしている。「スマートフォン」でアクセスする人はSNS利用者の8割強。
■SNS利用場面は「自宅でくつろいでいるとき」が利用者の5割強、「暇なとき」「すきま時間」が各30%台。「自宅でくつろいでいるとき」「家事の合間」などは、女性での比率が高い。
■SNS利用内容は「他人の投稿を読む」が利用者の6割弱、「メッセージやDM、チャット等」「他人の投稿にコメントやいいね!をする」が各30%台。過去調査と比べ「ニュースの閲覧」が増加傾向。SNSに投稿せず閲覧だけしている人は認知者の約55%。「Twitter」「Facebook」が各2割強。
-
- 調査時期:
- 2020年11月
- 設問項目:
-
金融商品投資への興味/現在投資している金融商品/金融商品の購入先/投資の判断材料の情報/金融商品に対する態度・意識/金融資産の総額/金融商品を投資する金融機関選定時の重視点/今後最も投資してみたい金融商品/今後最も投資してみたい金融商品の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■金融商品投資の興味あり層は全体の4割強で、男性での比率が高い。女性では興味なし層の方が多い。
■金融商品への現在投資率は全体の5割弱。「株(日本企業)」が3割強、「株式投資信託」が約16%、「保険」「外貨預金」が各1割。商品購入先は「証券会社」「ネット専業証券会社」が上位。最も投資したい商品は「株(日本企業)」が2割。
■投資金融機関選定時の重視点は「会社が信頼できる」「手数料が安い」「経営が安定している」がトップ3。投資の判断材料の情報は「新聞記事」「インターネットの投資情報ページ」が投資者の各30%台。
■金融商品に対してローリスク・ローリターン傾向の人は全体の7割弱。ハイリスク・ハイリターン型の人では、ネット専業証券会社の比率が高い、金融機関選定時に手数料の安さや取引スピードを重視する、などの傾向がみられる。
-
- 調査時期:
- 2020年11月
- 設問項目:
-
直近1年間での支払い方法(店頭)/直近1年間で最も多い支払い方法(店頭)/直近1年間に現金で支払った割合/キャッシュレス決済利用頻度の増減/キャッシュレス決済利用に関する行動/キャッシュレス決済で支払う理由/オンラインショッピングでの支払い方法/キャッシュレス決済で支払う際に困ること・不満(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■直近1年間の店頭での支払い方法は「現金」が9割。「クレジットカード」8割弱、「電子マネーのカード」5割強、「スマホ決済」4割弱、「デビットカード」6%で、これらのキャッシュレス決済利用者は9割弱。最も多い支払い方法は「クレジットカード」「現金」が各4割弱。
■直近1年間キャッシュレス決済利用者のうち、1年前より頻度が増えた人は6割弱、「変わらない」が4割弱。
■直近1年間にキャッシュレス決済をした人の理由は「ポイントやマイルなどがたまる」が7割弱、「少額の支払い時に便利」「支払いに時間がかからない」「高額の支払いに便利」が各4割前後。2017年調査と比べ「少額の支払い時に便利」「支払いに時間がかからない」「購入履歴が確認できる」などが増加。
■直近1年間キャッシュレス決済利用者のうち「ポイントをためるためキャッシュレス決済で支払うことが多い」は約65%、「自分が利用するキャッシュレス決済が使えない場合現金で支払う」は5割強。
-
- 調査時期:
- 2020年11月
- 設問項目:
-
直近1年間での宅配便の受け取り頻度/直近1年間での、宅配便の受け取り方法/直近1年間に配達された宅配便の再配達の比率/宅配ボックスの有無/直近1年間に、宅配便が再配達にならないように行ったこと/オープン型宅配ロッカー・ボックス直近1年間利用経験/オープン型宅配ロッカー・ボックス利用意向/オープン型宅配ロッカー・ボックス利用意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■直近1年間の宅配便受け取り者のうち「自宅で直接受け取る」が約95%。「置き配指定した場所」が2割弱、「宅配ボックス」が1割強。自宅に宅配ボックスがある層は2割弱。
■直近1年間に宅配便が配達された回数のうち、再配達の割合は「1~2割くらい」が4割。「ほぼ毎回、直接受け取る」は3割弱で、2018年調査より増加(再配達の比率が減少)。
■宅配便が再配達にならないように行うことは「日時指定便」が7強弱、「配達予定日時の通知メールを設定」が3割強、「都合が悪くなったら日時・場所を変更」が2割強。
■オープン型宅配ロッカー・ボックス直近1年間利用経験は「PUDOステーション」が約2%。利用意向者の比率は2割弱、若年層での比率が高く年代差が大きい。利用経験者の利用意向は8割強、未経験者では2割弱。
-
- 調査時期:
- 2020年11月
- 設問項目:
-
大手スーパーの認知/総合スーパー利用頻度/普段利用する総合スーパー/最頻利用総合スーパー/最頻利用総合スーパーの満足度/総合スーパー利用時の重視点/総合スーパー利用場面/総合スーパーの不満点(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■総合スーパー週1回以上利用者は全体の3割強。
■普段行く総合スーパーはいずれの地域も「イオン」が1位。北陸・中部では「アピタ・ピアゴ」、関東では「イトーヨーカドー」「西友」、近畿では「ダイエー」などの比率が高い。
■総合スーパー利用時の重視点は「立地・便利な場所」「価格が手頃」が利用者の各5割弱、「食品の品揃え」「駐車場が充実」「いろいろな商品カテゴリがそろっている」は各4割前後。「価格が手頃」は西友主利用者での比率が高い。
■総合スーパーを利用することが多い場面は「食料品を買う」が利用者の7割強、「下着や衣料小物、靴などを買う」「衣料品を買う」などが各30%台。
-
- 調査時期:
- 2020年11月
- 設問項目:
-
世帯所有の自動車のタイプ/主利用自動車のタイプ(ガソリン車以外)/主利用電気自動車・ハイブリッド自動車等の車種/主利用電気自動車・ハイブリッド自動車等のメーカー/電気自動車・ハイブリッド自動車等の購入検討意向/購入したい電気自動車・ハイブリッド自動車等の種類/電気自動車・ハイブリッド自動車等の購入時の重視点/購入したい電気自動車・ハイブリッド自動車等の種類の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■世帯所有自動車のタイプは「ガソリン車」が6割強、「ハイブリッド車」が約16%、「電気自動車」が約1%。
■今後の車購入時にガソリン車以外検討者は全体の6割。検討する種類は、「ハイブリッド車」が約36%、「電気自動車」が約17%、「プラグインハイブリッド車」が約15%。ガソリン車所有者のうち、ガソリン車以外検討者は7割弱。
■今後、ガソリン車以外購入意向者は6割強。最も購入したいものは「ハイブリッド車」が3割弱、「電気自動車」が約9%、「プラグインハイブリッド車」が約6%。主利用自動車の継続利用意向者率は、電気自動車主利用者、ハイブリッド車主利用者、プラグインハイブリッド車主利用者のいずれも50%台。
■電気自動車・ハイブリッド車購入意向者の重視点は「燃費のよさ」「ランニングコスト」「価格が手頃」が各5~6割、「安全性」「充電後の走行可能距離」「走行性能」などが各30%台。
-
- 調査時期:
- 2020年11月
- 設問項目:
-
自宅の除菌・消毒について気にする度合い/直近1年間に自宅で除菌・消毒をする場所/自宅の除菌対策実施理由・きっかけ/自宅の除菌対策実施時期/直近1年間に行った自宅の除菌・消毒方法/市販の除菌剤選定時の重視点/手指用の除菌・消毒剤利用場面/市販の除菌・消毒剤の不満点(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■自宅の室内の除菌・消毒を気にする人5割弱。直近1年間に除菌・消毒をする場所は「トイレ」約56%、「まな板、スポンジ、ふきんなど」5割弱、「キッチンのシンク、排水溝」4割弱。「おもちゃ、ぬいぐるみなど」「収納」「インテリア」「壁、床」などは1割未満にとどまる。
■直近1年間除菌実施者の、除菌対策実施理由は「家族や自分の健康」「新型コロナウイルス予防・対策」が各5割前後、「食中毒やノロウイルス対策」「カビ対策」「インフルエンザなど予防・対策」が各30%台。
■直近1年間自宅の除菌実施者の除菌方法は、「除菌スプレー」が7割強、「食器用洗剤」が4割強、「シートタイプ除菌剤」「塩素系漂白剤」「洗濯」が各30%台。市販の除菌剤重視点は「価格」が5割弱、「スプレー、ジェル、シートなどのタイプ」「メーカー、ブランド」「原材料、成分」が各30%台。
■ここ半年間での手指用の除菌・消毒剤利用場面は「店などに入る前」が6割弱、「帰宅後や、手洗いをした後」「店などに除菌剤が備え付けてあるとき」が各5割前後、「店などから出るとき」が4割強。男性10~30代ではここ半年間非利用者が2割弱で他の層よりやや高い。
-
- 調査時期:
- 2020年11月
- 設問項目:
-
食事を作る頻度/食事のメニュー検討の参考情報/食事のメニュー検討時に利用するWebサイト・アプリなど/食事のメニュー検討時のWebサイト・アプリ・SNSの利用頻度/夕食を作る頻度/夕食のメニューを決めるタイミング/夕食のメニューを決めるときの重視点/食事のメニューの決め方(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■食事を作る人の、メニュー検討時の参考情報は「レシピサイトやアプリ、レシピ動画」が5割弱で、過去調査より増加傾向。「テレビ番組」が3割強、「家族の意見」「料理レシピを書いた本」などが各2割前後。
■直近1年間レシピサイトやアプリなど利用者の利用頻度は「月に1日以下」がボリュームゾーン。週1日以上利用者は4割強で、過去調査より減少傾向。
■夕食を作る人が、作るメニューを決めるタイミングは「前もって家にある材料から」が3割強、「買い物に行って商品を見ながら」「買い物に行く前に」が各2割強、「作る直前に決める」が1割強。
■夕食を作る人がメニュー決定時の重視点は「自分や家族の好みにあう」が6割強、「栄養のバランス」「家にある食材をムダにしない」が各40%台、「手間がかからない」「短時間で作れる」「費用がかからない」「主菜、副菜、汁物など複数のメニューを用意する」が各3~4割。
-
- 調査時期:
- 2020年11月
- 設問項目:
-
ガムを食べる頻度/直近1年以内に食べたガムの銘柄/直近1年以内に最もよく食べたガムの銘柄/ガムを食べる場面/ガムの購入場所/ガム購入時の重視点/ガム利用意向/直近1年以内最頻利用ガムを食べる理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■ガムを食べる人は全体の5割強、過去調査と比べ減少傾向。週1回以上食べる人はガムを食べる人の4割強。購入場所は「スーパー」6割強、「コンビニエンスストア」が4割弱。過去調査と比べ「ドラッグストア」が増加傾向。
■ガムを食べる場面は「車を運転する」「食事の後」「気分転換したいとき」「口寂しいとき」「口の中をさっぱりさせたいとき」などが各2~3割。ブラックブラックガム主利用者では「車を運転する」「眠いとき、目を覚ましたい」などの比率が高い。
■ガム購入者の重視点は「味」が7割、「すっきり感」5割弱、「価格」4割弱、「キシリトール入りかどうか」「香り」などが各2割強。クロレッツ主利用者などでは「味が長持ちする」等の比率が高い。
■ガム利用意向者4割、非利用意向者は4割弱。利用意向者の比率は、月1回以上利用者では8~9割、非利用者では約4%。ガムを食べない人のうち、今後もガムを食べたくないという人は7割を占める。
-
- 調査時期:
- 2020年11月
- 設問項目:
-
豆乳の嗜好度/豆乳の摂取方法/豆乳摂取理由/豆乳に期待する効果/豆乳購入時の重視点/豆乳飲用頻度/豆乳飲用場面/豆乳飲用意向/豆乳・豆乳飲料の飲用意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■豆乳が好きな人は全体の4割弱、女性若年層で高い。直近1年間豆乳・豆乳飲料飲用者は全体の5割弱。「市販の豆乳をそのまま飲む」が3割強。直近1年間飲用者のうち、週1回以上飲用者は4割。飲用場面は「朝食時」が4割弱、「おやつの時」が3割弱。
■直近1年間摂取者の豆乳摂取理由は「健康に良い」が5割強、「栄養価が高い」「大豆イソフラボン摂取」「おいしい」が各4割前後、「牛乳の代わり」「低カロリー」が各3割前後。期待する効果は「高血圧や高脂血症などの予防」は男性や高年代層での比率が高い傾向。
■豆乳購入時の重視点は「味」が直近1年間摂取者の6割弱、「価格」「飲みやすさ」が4割前後、「成分、添加物」「調製、無調整」「原材料」が各20%台。
■豆乳飲用意向者は全体の4割強、女性10・20代では6割強。豆乳・豆乳飲料飲用者では8割、非飲用者では1割。非飲用者では非飲用意向が6割弱を占める。
-
- 調査時期:
- 2020年10月
- 設問項目:
-
直近5年間にキャンプに行った回数/直近5年間に購入したアウトドア・キャンプ用品/アウトドア・キャンプ用品メーカーの認知/信頼できるアウトドア・キャンプ用品メーカー/最も好きなアウトドア・キャンプ用品メーカー/直近5年間に商品を購入したアウトドア・キャンプ用品メーカー/直近5年間の商品購入アウトドア・キャンプ用品メーカーで最も満足しているメーカー/所有アウトドア・キャンプ用品で、もっと良いものが欲しいもの/最も好きなアウトドア・キャンプ用品メーカーの気に入っている点・お勧め(自由回答設問)/直近5年間購入アウトドア・キャンプ用品であまり満足していないもの・不満な点(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■直近5年間アウトドア・キャンプ用品購入者は全体の2割弱、直近5年以内キャンプ経験者のうち8割弱。
■直近5年以内キャンプ経験者が購入したものは「ライト、ランタン」「燃料、ライター、火吹き棒」「寝袋、シュラフ、マット」「手袋、軍手、グローブ」「バーナー、コンロ」「テント関連用品」などの比率が高い。
■アウトドア・キャンプ用品メーカー認知は「Coleman」が5割強、「mont‐bell」が4割強、「Columbia」「THE NORTH FACE」「LOGOS」「Patagonia」「L.L.Bean」が各3割前後。キャンプ用品メーカー認知者が信頼できる/最も好きなメーカーのいずれも「Coleman」「mont‐bell」が上位。
■もっと良いものが欲しいと思う所有アウトドア・キャンプ用品は、直近5年以内キャンプ経験者では「テント、テント関連用品」「寝袋、シュラフ、マット」「バーナー、コンロ、焚火台」などが、各2~3割。
-
- 調査時期:
- 2020年10月
- 設問項目:
-
行っている運動の程度/運動をする頻度/1日あたりの合計運動時間の平均/行っている運動の種類/運動をする理由/スマートフォンと連携したスポーツグッズの利用状況/やってみたいと思う運動/今年3月以降の運動頻度・時間の変化/運動時に気をつけている・心がけていること(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■運動をしている人は4割強。激しい運動をする層は約2%、中程度が1割強、軽度が3割弱。運動をする人の頻度は週3~4日以上が6割。2016年調査と比べ、1日あたり合計運動時間が短い傾向。
■行っている運動の種類は「ウォーキング・運動としての散歩」が運動をする人の6割弱。「筋トレ・ストレッチ」が4割弱で過去調査より増加傾向。やってみたい運動は「ウォーキング・運動としての散歩」が3割弱、「筋トレ・ストレッチ」が2割弱。「登山、ハイキング」などは、現在よりも今後の意向の方が上位となっている。
■運動をする理由は「健康のため」が運動をする人の8割強、「体力保持のため」「体力をつけるため」「リラックス・気分転換のため」「筋力をつけるため」が各3~4割。
■運動をしている人のうち「スマートフォン内蔵の歩数計」利用者2割強で2016年調査より増加。今年の3月以前と比べて運動頻度・時間が増えた人は1割、減った人は3割弱。
-
- 調査時期:
- 2020年10月
- 設問項目:
-
主利用携帯電話・スマートフォンの種類/スマートフォンでゲームをする頻度/スマートフォンでゲームをする時間(1日あたり合計)/スマートフォンでゲームをする場面/スマートフォンで遊ぶゲームのジャンル/スマートフォンで遊ぶゲームのタイプ/直近1年間の、スマートフォンの有料ゲームの利用および課金の状況/課金ゲームでの1ヶ月あたりの支払金額/スマートフォンでのゲーム利用意向/スマートフォンのゲームをするときのルール・こだわり(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■スマートフォン利用者のうち、直近1年間のスマホゲーム実施者は4割強。「ほとんど毎日」は、直近1年間実施者の約65%。ほとんど毎日ゲームをする層では、1日30分以上実施者が5割弱。
■スマートフォンでゲームをする場面は「自宅でくつろいでいるとき」が実施者の約76%、「暇なとき」「待ち時間」「ちょっとした隙間時間」などが各3~4割。
■直近1年間のスマートフォンでのゲーム利用者のうち「ダウンロードしたアプリ」利用は7割強、「Webアプリ」が2割。直近1年間に「無料のゲームをダウンロード」は約65%、「ゲームアプリ内課金」は1割強、「有料のゲームを購入」は約4%。
■スマートフォンでのゲーム利用意向は3割弱、10・20代では約56%と高い。週2~3回以上実施者では7~8割の利用意向、週1回未満実施者では4割強、非実施者では約1%。
-
- 調査時期:
- 2020年10月
- 設問項目:
-
食事のデリバリーサービス利用頻度/利用しているデリバリーサービスの種類/食事のデリバリーサービス利用場面/食事のデリバリーサービスの店・メニュー選定時の情報源/食事のデリバリーサービスへの注文方法/直近1年間に注文したデリバリーサービス/食事のデリバリーをする店舗選定時の重視点/今年3月以降のデリバリー利用頻度の変化/食事のデリバリーを利用したい場面/利用したくない理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■食事のデリバリーサービス利用者は全体の5割弱。月1回以上利用者は利用者の2割弱で、2018年調査よりやや増加。3月以降に利用頻度が増えた層は全体の約9%。直近1年間デリバリーサービス利用者のうち「休日・夕食」が5割強、「休日・昼食」「平日・夕食」が各3割前後。
■注文方法は「店舗に電話」「店舗のWebサイト・アプリなど」が利用者の各40%台、「デリバリーのWebサイト・アプリ」が3割弱。2018年調査と比べ「店舗のWebサイト・アプリなど」が増加、「店舗に電話」が減少。デリバリーサービスサイトからの注文者のうち「Uber Eats」利用者が2018年調査と比べ増加。
■デリバリーの店・メニュー選定時の情報源は「ポストに投函されるチラシ、ダイレクトメール」がデリバリー直近1年間利用者の4割弱、「店舗のWebサイト・アプリ」「デリバリーサービスのWebサイト・アプリ」が各20%台。
■食事のデリバリー店舗選定時の重視点は「価格が手頃」「手元にチラシがある」が各4割前後、「味が好み」「メニューが豊富」が各3割前後。
-
- 調査時期:
- 2020年10月
- 設問項目:
-
ネットスーパー利用経験/ネットスーパー利用理由/ネットスーパー利用時の重視点/直近1年間のネットスーパー利用頻度/直近1年間の利用ネットスーパー/直近1年間の最頻利用ネットスーパー/ネットスーパーのWebサイトを見る時間帯・場所/ネットスーパー利用意向/ネットスーパー利用意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■ネットスーパー利用経験は2割強、現在利用は1割強。現在利用者のうち、週1回以上利用者は2割弱、月1回上利用者は6割強。ネットスーパーのWebサイトを見るのは「自宅で:夜(19~22時台)」が、現在利用者の4割。
■ネットスーパー利用経験者の利用理由は「重いもの・かさばるものを届けてくれる」が5割強、「買い物時間を節約」「外出したくないときに便利」「深夜・早朝など時間を気にせずに注文できる」などが各2~3割。
■ネットスーパー利用時の重視点は、「品揃えの充実度」が5割、「送料の安さ」「品質の良さ」「商品の価格」が利用経験者の各4割、「配送の確実さ」「配送時間の正確さ」が各20%台。
■ネットスーパー利用意向者は全体の2割強、現在利用者の8~9割、利用中止者の3割、利用未経験者の1割。女性10~30代での利用意向が高い傾向。
-
- 調査時期:
- 2020年10月
- 設問項目:
-
コンビニエンスストア利用頻度/コンビニエンスストア利用時間帯/直近1年間利用コンビニエンスストア/直近1年間最頻利用コンビニエンスストア/コンビニエンスストアの店員に期待する接客態度/コンビニエンスストアの店員の接客態度で不満・不快に感じた経験/コンビニエンスストアの店員の接客態度で不満・不快に感じたことでの影響/最も接客態度がよいと思うコンビニエンスストア/直近1年間最頻利用コンビニエンスストアの不満(自由回答設問)/コンビニエンスストアの店員の接客態度で不満・不快に感じた内容(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■直近1年間のコンビニエンスストア週1回以上利用者は5割強。利用時間帯は「平日・午前中」が約26%、平日「午後」「夕方」が各2割強。男性10~50代では「平日・夜」が最も比率が高い。
■期待する接客態度は、「手際がよい」が直近1年間利用者の5割。「対応が丁寧」「笑顔で対応」などが続く。「身だしなみ、清潔感」「サービスや手続きの処理がスムーズ」「柔軟な対応、臨機応変」などは女性での比率が高い。
■直近1年間コンビニエンスストア利用者で、店員の接客態度で不満に感じた経験がある人は3割弱。影響は、「店舗の印象が悪くなった」「店舗を利用する頻度が減った」「店舗を利用しなくなった」が2~3割。
■直近1年間コンビニエンスストア利用者が、最も接客態度が良いと思うコンビニエンスストアは、「セブン‐イレブン」が約25%、「ローソン」「ファミリーマート」が各1割強。北海道では「セイコーマート」、四国では「ローソン」が1位。
-
- 調査時期:
- 2020年10月
- 設問項目:
-
所有ドライヤーのタイプ/ドライヤーの使用頻度/主利用ドライヤーのメーカー/ドライヤーの購入時期/ドライヤー選定時の参考情報源/ドライヤーに期待する効果/ドライヤー購入時の重視点/主利用ドライヤーの選択理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■ヘアドライヤー所有率は全体の8割強、「カールドライヤー」は2割弱。ドライヤー利用者は全体の7割弱、男性5割強、女性9割弱。ドライヤー利用者のうち「ほぼ毎日」は約56%。若年層での利用頻度が高い傾向。
■ドライヤーに期待する効果は「短時間で乾く」が利用者の7割強、「髪にやさしい」「髪のダメージを防ぐ」「頭皮にやさしい」が各30%台。
■ドライヤー選定時の参考情報源は「店頭の情報」が利用者の3割強、「商品パッケージの説明」「オンラインショップの商品情報、口コミレビュー」「店員の説明」が各10%台。
■ドライヤー購入時の重視点は「価格」が全体の約56%、「メーカー・ブランド」「重さ」「ナノイオン・マイナスイオン」「大きさ」などが各2~3割。ダイソン主利用者では「メーカー・ブランド」「パワー、大風量」などの比率が高い。
-
- 調査時期:
- 2020年10月
- 設問項目:
-
ご飯の準備方法/炊飯器でご飯を炊く頻度/所有している炊飯器のタイプ/炊飯器に搭載されている機能・メニュー/炊飯器で利用する機能・メニュー/所有炊飯器のメーカー/炊飯器購入時の重視点/所有炊飯器のメーカー選定理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■炊飯器所有者は9割強。ご飯を炊く頻度は「ほとんど毎日・1日1回」が約36%。毎日炊く人は5割で、過去調査と比べ減少傾向。
■所有炊飯器のタイプは「IH圧力炊飯器」「IH炊飯器(圧力式以外)」が、炊飯器所有者の各3割。
■炊飯器の搭載機能は「白米コース」が所有者の約86%、「タイマー」「保温機能」「早炊き」が各5割強。利用機能は「白米コース」が8割弱、「タイマー」「早炊き」が各20%台、「保温機能」「炊き込みコース」が各10%台。
■炊飯器購入時の重視点は「価格」が6割、「炊飯容量」「メーカー・ブランド」が各5割弱。パナソニック主利用者では「メーカー・ブランド」の比率が高い。
-
- 調査時期:
- 2020年10月
- 設問項目:
-
品質表示や商品の説明書きを気にする度合/食品購入時の品質表示・説明書きで注意してみるところ/機能性表示食品の認知/栄養機能食品の認知/特定保健用食品の認知/利用したいと思う機能性表示食品/機能性表示食品の購入意向/機能性表示食品を購入したい/したくない理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■食品購入時に品質表示を気にする人は全体の6割。品質表示で注意して見るのは「期限表示」7割強、「原産国、生産地」6割強、「価格」5割強、「原材料」「製造年月日」が各4割。
■機能性表示食品について「詳しく知っている」は1割強、「聞いたことがある程度」は8割弱、あわせて9割弱の認知率。過去調査と比べ増加傾向。栄養機能食品の認知率は7割弱、トクホの認知率は約96%
■利用したい機能性表示食品の効果は「免疫力・抵抗力向上」「疲労回復」「中性脂肪や内臓脂肪対策」「コレステロール抑制」などが各3割前後。
■機能性表示食品の購入意向は3割強、非購入意向2割強。機能性表示食品について詳しく知っている人の購入意向は6割弱、非認知者では15%。
-
- 調査時期:
- 2020年10月
- 設問項目:
-
市販のビスケット・クッキーを食べる頻度/市販のビスケット・クッキーを食べる場面/直近1年間でよく食べた市販のビスケット・クッキー/最も好きなビスケット・クッキー別/好きなビスケット・クッキーのタイプ/よく購入するビスケット・クッキーの包装形態/ビスケット・クッキー購入時の重視点/市販のビスケット・クッキーの好きな銘柄、食べ方、こだわりなど(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■市販のビスケット・クッキーを食べる人は全体の8割弱、週1回以上食べる人は2割強。直近1年間に食べた銘柄は「アルフォート」「カントリーマアム」が、食べる人の各30%台。
■市販のビスケット・クッキーを食べる場面は「おやつ、お茶うけ」が食べる人の7割強、「ちょっとおなかがすいた」が約45%、「甘いものが欲しい」「ちょっと一息つきたい」が各3割前後。
■好きなタイプは「バタークッキー」が約45%、「チョコレート・ココア生地」「プレーン」「チョコチップ入り」が各30%台。「1~2枚ずつ個包装」が約46%、「2~3パックに分けて包装されている」が3割弱。
■購入者の重視点は「価格」が6割弱、「プレーン、チョコなど、生地の味」が約46%、「食感」「食べ慣れている」「レーズン、ナッツ、ゴマ、チョコチップなどのトッピングの有無・種類」「内容量」「包装形態」などが各20%台。
-
- 調査時期:
- 2020年10月
- 設問項目:
-
味噌汁を飲む頻度/市販の即席味噌汁を飲む頻度/即席味噌汁を飲む場面/よく飲む即席味噌汁のタイプ/即席味噌汁の好きな具/よく買う即席味噌汁のメーカー/即席味噌汁を選ぶ際の重視点/気に入っている即席みそ汁と、気に入っている点(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■市販の即席みそ汁を飲む人は約76%。週1回以上飲む人は3割弱。「個包装/生味噌」が即席みそ汁飲用者の8割弱。「個包装/フリーズドライ」は3割弱で、過去調査と比べ増加傾向。
■即席みそ汁の好きな具は「豆腐」「ねぎ」「わかめ」が各6割前後、「油揚げ」「しじみ」「なめこ」「あさり」などが各3~4割。
■即席みそ汁を飲む場面は「家での夕食」「みそ汁を作るのが面倒なとき、作る時間がないとき」が各3~4割。東北では「家での朝食」がやや高い。
■即席みそ汁選定時の重視点は「具材の種類」「味噌の味・種類」「価格」が購入者の各50%台。
-
- 調査時期:
- 2020年10月
- 設問項目:
-
よく飲むアルコール飲料/ビール飲用頻度/直近1年以内のビールの飲用銘柄/直近1年以内のビールの最頻飲用銘柄/ビール飲用場面/ビールを家や外で飲む比率/ビール購入時の重視点/ビール飲用意向/ビールを飲むタイミング・場面(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■ビール飲用者は全体の5割強、過去調査と比べ減少傾向。そのうち週1回以上飲用者は6割弱。よく飲むアルコール飲料は、女性20~40代では「ビール」よりも「サワー、チューハイ」の方が多い。
■ビール飲用場面は「食事中」が飲用者の6割強、「食事の前」「最初の一杯」「仕事や飲み会などのつきあい」「家族と一緒に」などが各20%台。ビールを飲む人のうち、ここ半年くらいに自宅で飲むことが多い人は8割弱。
■ビール購入時の重視点は「味」が飲用者の7割強、「のどごし」が約46%、「価格」が各3割。
■ビールの飲用意向者はお酒飲用者の7割強、男性や高年代層で高い。ビール月1回以上飲用者では9割超、非飲用者では2割強。
-
- 調査時期:
- 2020年09月
- 設問項目:
-
今年贈ったお中元の件数/贈ったお中元の内容/お中元を贈った相手/お中元の購入場所/お中元の平均単価/お中元の品物選定時の情報源/お中元を贈る理由/今年もらったお中元の件数/今年のお中元選定時の重視点・こだわり(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■今年お中元を贈った人・もらった人は各4割前後。いずれも過去調査と比べ減少傾向。高年代層や、東北、九州などでの比率が高い。
■今年のお中元に贈ったものは「お菓子類・デザートなど」「ビール類」が、贈った人の各3割前後。北海道、中国などでは「果物」の比率が高い。贈った相手は「その他親戚」が4割強、「兄弟・姉妹」「自分の親」「配偶者の親」が各2~3割。
■購入場所は「百貨店の店頭」「総合スーパーの店頭」「オンラインショッピングサイト」などが各2割弱。参考情報源は「店頭の商品」「ギフトカタログの冊子」が各2割強。
■お中元を贈る理由は「感謝の気持ちを表す」が実施者の5割弱、「普段ご無沙汰している方へのご挨拶代わり」「相手に喜んでもらいたい」などが各3割前後。
-
- 調査時期:
- 2020年09月
- 設問項目:
-
相談できる病院・医師の有無/オンライン医療相談・診察の直近1年間での利用経験/オンライン医療相談・診察の利用方法/オンライン医療相談・診察のきっかけ/オンライン医療相談・診察利用意向/オンライン医療相談・診察を利用したい方法/オンライン医療相談・診察で利用したいサービス/オンライン医療相談・診察利用意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■「オンラインで診察・薬の処方をしてもらう」は1.3%、「オンラインで診察を受ける」は0.8%、「医師・医療従事者へのオンラインでの相談」は1.7%。利用未経験者は6割強、非認知者は3割強。
■オンライン医療相談・診察のきっかけは「コロナウイルス感染予防のため病院へ行くのを控えたい」が直近1年間利用者の3割弱、「かかりつけ医がオンライン診療や相談を実施していた」「待ち時間・通院時間をかけたくない」などが各2割前後。
■オンライン医療相談・診察の利用方法は「メール、問合せフォーム」「テレビ電話、ビデオ通話」が、直近1年間利用者の各20%台。
■オンライン医療相談・診察の利用意向、非利用意向とも各3割強。利用意向率は、利用未経験者では3割強、非認知者では2割強。利用意向者のうち、オンライン診療・処方の利用意向は約75%、診察のみが4割弱。
-
- 調査時期:
- 2020年09月
- 設問項目:
-
健康の維持・増進に役立つ食品・飲料の利用状況/健康食品利用頻度/健康食品に期待する効果/健康食品利用効果の実感度合/健康食品選定時の重視点/健康食品購入場所/健康食品に関する情報入手先/健康食品利用意向/健康食品で効果を感じたもの(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■健康食品利用者は全体の5割弱、女性での比率が高い。「ほとんど毎日利用」「たまに利用」が各2~3割。購入場所は、「スーパー」「ドラッグストア」「インターネット通販」が利用者の各4~5割。
■健康食品利用者のうち、効果を実感している人は4割弱、実感していない人は2割弱。期待する効果は「健康維持」が利用者の6割強、「疲労回復」が3割強、「免疫力・抵抗力向上」「整腸効果」「体力増進」が各20%台。
■健康食品選定時の重視点は「価格」「効能・効果」が利用者の各5割前後、「安全性」「味」が4割弱、「国産かどうか」「栄養成分」「原材料」「容量、サイズ」が各20%台。情報入手先は「テレビ番組・CM」が4割強、「メーカーや店舗の公式ホームページ」が2割強。
■健康食品利用意向者は全体の4割強、非利用意向者は2割強。利用意向者の比率は、現在利用者で7~9割、利用中止者で2割弱、利用未経験者で約6%。健康食品の利用効果を実感している人では9割強の利用意向、実感していない人では5割強。
-
- 調査時期:
- 2020年09月
- 設問項目:
-
スマートフォン所有状況・主利用機種/スマートフォンで利用している機能・サービス/利用スマートフォンの満足度/スマートフォン利用意向/スマートフォン選定時の重視点/スマートフォン購入時の携帯電話会社・通信事業者の変更意向/スマートフォン購入時の携帯電話会社・通信事業者の変更意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■スマートフォン所有率は全体の8割強で、過去調査より増加傾向。若年層で高く、10・20代98%、60・70代7割強。
■スマートフォンで利用している機能・サービスは「通話」が所有者の9割弱、「カメラ」「時計、アラーム」「スマートフォン用のWebサイト閲覧」が各7~8割、「Webメール、パソコンメール、フリーメールなど」「電卓」「電話帳、アドレス帳」などが各6割前後。過去調査と比べ「スマホ決済」「オンラインショッピング」「Bluetooth機能」などが増加傾向。
■スマートフォンの利用意向は全体の8割弱、過去調査より増加傾向。スマートフォン所有者では9割弱、非所有者では約25%。意向者の選定時の重視点は「本体価格」「バッテリー」が各6割弱、「通信料金」「画面サイズ・大きさ」などが各40%台。
■次回も「同じ携帯電話会社・通信事業者にしたい」は、スマホ利用意向者の6割弱、NTTドコモ主利用者、au主利用者で高い。「携帯電話会社・通信事業者にはこだわらない」は2割弱、大手キャリア以外主利用者で高い。
-
- 調査時期:
- 2020年09月
- 設問項目:
-
利用している音源・音楽コンテンツ/定額制音楽配信サービスの利用頻度/直近1年間に利用した定額制音楽配信サービス/直近1年間の最頻利用定額制音楽配信サービス/定額制音楽配信サービス選定時の重視点/定額制音楽配信サービスの平均利用月額/定額制音楽配信サービスを利用する機器/定額制音楽配信サービス利用意向/定額制音楽配信サービス利用意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■直近1年間の定額制音楽配信利用者は全体の2割、2017年以降増加傾向。そのうち、週1回以上利用者は6割強。過去調査と比べ、Spotify利用者などが増加傾向。
■直近1年間の定額制音楽配信利用者の重視点は「月額料金」が5割弱、「無料版・無料お試しの充実度」「好きなアーティストの楽曲の充実度」「楽曲の曲数」が各3割前後。
■利用機器は、「スマートフォン」が直近1年間利用者の7割弱、「パソコン」が5割弱、「タブレット端末」が2割弱。Amazon Music Unlimited主利用者、Google Play Music主利用者などでは「スマートスピーカー」が各2割前後。
■定額制音楽配信サービスの利用意向者は全体の2割弱、非利用意向者は6割弱。利用意向率は2017年以降増加傾向。週4~5回以上利用者では各9割強の利用意向、週1回以下利用者は各5~6割、利用未経験者は約5%。
-
- 調査時期:
- 2020年09月
- 設問項目:
-
自転車利用頻度/居住地域の自転車保険義務化の状況/自転車保険加入状況/加入自転車保険のタイプ/自転車保険加入のきっかけ/加入自転車保険の種類/自転車保険加入経路/自転車保険加入時の重視点/自転車保険への要望(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■自転車所有率は6割弱、自転車利用率は4割強。関東や近畿では、利用率が高い。週1回以上利用者は全体の3割弱、自転車利用者の7割弱。居住地域の自転車保険が「義務または努力義務」が約35%、「わからない」が5割強。
■自転車保険加入状況は、自転車利用者の6割弱。「契約者本人のみが対象」が3割強、家族型が6割強。「自動車保険・火災保険などの特約」「自転車保険」は、加入者の各3割強。加入経路は「自転車販売店」が加入者の4割強、「インターネット」が3割弱、「保険代理店の窓口」が1割弱。
■自転車保険加入のきっかけは「保険加入が義務化された」が加入者の3割強、「自動車保険や火災保険などの加入・見直し」「自転車購入・買い替え」が各2割前後、「自転車に関する事故を見聞きした・あった」が1割強。TSマーク付帯保険加入者では「自転車を購入した・買い替えた」「販売員や店員の勧め」の比率が高い。
■自転車保険加入時の重視点は、「保険料が手頃」「補償内容の充実度」が各5割前後、「商品のわかりやすさ」が4割弱、「事故時の対応力」「補償金額」が各3割弱。