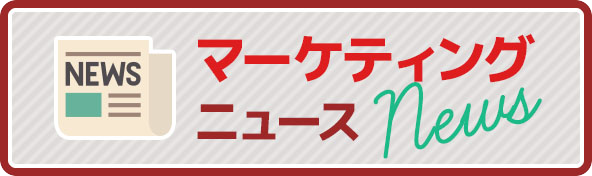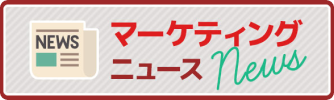- 検索
-
- テーマ別実施時期一覧
- カテゴリー別一覧
-
-
アルコール飲料・嗜好品145
-
非アルコール飲料209
-
その他19
-
-
住宅・住宅設備218
-
-
家電126
-
パソコン・カメラ・AV機器113
-
その他10
-
-
家庭用品・トイレタリー91
-
自動車・関連用品76
-
-
インターネット・情報通信327
-
携帯電話・スマートフォン180
-
メディア・広告66
-
その他7
-
-
ファッション68
-
交通・レジャー・娯楽161
-
季節行事・イベント241
-
時事・ニュース・トレンド51
-
企業ブランドイメージ246
-
広告・CM51
-
WEBサイトの利用91
-
顧客満足度100
- 実施時期別一覧
-
- 調査時期:
- 2017年07月
- 設問項目:
-
利用携帯電話・スマートフォンの種類/直近1年間に表示されたスマートフォン広告/直近1年間にスマートフォン広告が表示された際に行ったこと/スマートフォン広告の内容閲読状況/直近1年間に内容を読んだスマートフォン広告のタイプ/直近1年間に読んだスマートフォン広告の種類・内容/スマートフォン広告非表示対策/スマートフォン広告の不満・気になること(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■スマートフォンで直近1年間に表示された広告は「画面の下部に常に表示される」「ポップアップで自動的に表示される」がスマートフォン利用者の各4割、「画面の上部に常に表示される」「画面全体に表示される」「画面の上から下に降りてくる」が各3割。
■直近1年間にスマートフォン広告が表示された際の行動は「広告を閉じた」「広告の画像・動画やリンクを間違えてクリック」が、表示された人の各3~4割、「広告の画像・動画やリンクをクリック(意図的に)」が1割強。
■直近1年間にスマートフォン広告が表示された方のうち、内容を読む人は3割弱。「興味がある商品・サービス・企業等」の広告を読む人が3割強、「画面の下部に常に表示される広告」を読む人は1割。
■スマートフォン利用者のうち、広告が非表示対策実施者は2割弱。「広告をブロック・非表示するアプリを利用」「Webブラウザの設定で広告を非表示にしている」が各6%。
-
- 調査時期:
- 2017年07月
- 設問項目:
-
利用携帯電話・スマートフォンの種類/直近1年間に写真を撮った機器/直近1年間にスマートフォンで写真をとった頻度/スマートフォンで撮影する写真の被写体/スマートフォンで撮影した写真の利用方法/直近1年間のインカメラでの写真撮影頻度/インカメラで撮影する写真の被写体/スマートフォンのカメラ機能重視点/直近1年間に動画をとった機器/自撮りなど撮影時の工夫・テクニック(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■直近1年間にスマートフォンで写真を撮った人は全体の6割弱、スマートフォン主利用者の9割。直近1年間撮影者のうち、週1回以上撮影者は約45%、女性20・30代で6割強。スマートフォンでの動画撮影者は全体の3割強、スマートフォン主利用者の4~6割。
■直近1年間のスマートフォンでの撮影時の被写体は、「風景:自然」「家族、子供」「食べ物、飲み物」「風景:街並み」が各3~4割。女性20代では「食べ物、飲み物」が6割強で1位。撮影した写真は、女性20代や撮影頻度が高い層では「ブログやSNSにアップロード」が1位。
■直近1年間のスマートフォンでの写真撮影者のカメラ機能の重視点は、「手ブレ補正」「アウトカメラの画質」「逆光や、暗い所でもきれいに撮れる」「液晶画面の大きさ」が各20%台。
■直近1年間のスマートフォンでの撮影者のうち、インカメラ利用者は5割弱。女性20代では7割強。インカメラの被写体は「自分ひとりの写真」「集合写真:自分も一緒に写る」が各3~4割、「家族、子供」が2割。
-
- 調査時期:
- 2017年07月
- 設問項目:
-
生命保険会社の認知/主加入生命保険/加入生命保険商品の種類/生命保険申込み方法/1か月あたりの生命保険料/生命保険加入・見直し時に、候補として検討した生命保険会社/生命保険に関する情報入手経路/加入したい生命保険会社/生命保険の加入・見直し意向/生命保険の加入に関する不満・不安(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■生命保険会社の認知率上位は「アフラック」「かんぽ生命」「第一生命」「日本生命」「住友生命」「JA共済」など。
■生命保険申込み方法は「知り合いや紹介を受けた営業職員、保険外交員を通じて」が加入者の3割強、「自宅や勤務先に訪問してくる営業職員、保険外交員を通じて」「勤務先を通じて」が各1~2割。オリックス生命主加入者、AIG富士生命主加入者では「ファイナンシャルプランナーなどの専門家を通じて」が1位。
■生保関連の情報入手経路は「テレビ番組、CM」の他、「営業職員、保険外交員から」「保険商品のパンフレット、説明資料」などが上位。
■生保加入者は全体の8割弱。主加入生保の上位は「アフラック」「日本生命」「かんぽ生命」「県民共済」「第一生命」など。加入意向の上位は「県民共済」「アフラック」が約6~7%、「かんぽ生命」「全労済」「日本生命」「CO‐OP共済」「ソニー生命」「JA共済」が各3~4%。
-
- 調査時期:
- 2017年07月
- 設問項目:
-
メインバンク/三菱UFJフィナンシャルグループのイメージ/三井住友フィナンシャルグループのイメージ/みずほフィナンシャルグループのイメージ/りそなホールディングスのイメージ/ゆうちょ銀行のイメージ/今後メインバンクとして利用したい銀行グループ/メインバンクに対する不満点(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■三菱UFJFGのイメージは「規模が大きい」が4割弱で最も多く、「信頼できる」「伝統・歴史がある」「経営が安定している」などが続く。
■三井住友FG、みずほFGのイメージは「規模が大きい」が3割、「信頼できる」「伝統・歴史がある」が各1~2割。
■ゆうちょ銀行のイメージは「親しみやすい」が最も多く4割強。継続利用意向は8割強で、他の層より高い。今後メインバンクとして利用したい銀行グループとして、地方銀行とほぼ同率で1位にあがっている。
■りそなHDのイメージは「イメージがわかない」が5割強で、他の銀行より比率が高い。「規模が大きい」「信頼できる」「親しみやすい」などが各1割。
-
- 調査時期:
- 2017年07月
- 設問項目:
-
エアコン所有台数/エアコンの直近導入時期/主利用エアコンのメーカー/冷暖房以外の使用機能/エアコン購入時に重視する点/エアコンの購入・買い替え・買い増し予定時期/どのような機能がついたエアコンを購入したいか/主利用エアコンのメーカー選定理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■エアコン所有率は9割強。3台以上所有者は5割弱。主利用エアコンのメーカーは「パナソニック」「ダイキン」「三菱電機」「日立」などが各10%台で上位。
■エアコン購入時の重視点は「価格」「ランニングコスト(維持費用)の安さ」「性能・パワー」「メーカー・ブランド」などが上位。2011年以降、「省エネ(節電)」「環境への配慮」などが減少傾向。
■冷暖房以外で使っている機能は「除湿」が所有者の5割強、「タイマー」「フィルター自動洗浄」が各2~3割、「空気清浄」が1割強。
■購入する場合にあったらよい機能は「フィルター自動洗浄」「自動掃除機能」など、掃除機能に関するものが上位2位、「空気清浄」「除湿」「タイマー」「除菌」「内部乾燥」などが続く。
-
- 調査時期:
- 2017年07月
- 設問項目:
-
利用している飲用水/家庭用ウォーターサーバーの利用実態/ウォーターサーバーを利用し始めたきっかけ/ウォーターサーバー非利用理由/ウォーターサーバーの利用中止理由/主利用家庭用ウォーターサーバーのタイプ/主利用家庭用ウォーターサーバー/主利用ウォーターサーバーの満足度/ウォーターサーバー利用意向/主利用ウォーターサーバーの選定理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■家庭用ウォーターサーバー利用経験者は全体の1割、現在利用は約4%。主利用・利用経験銘柄のトップ2は「アクアクララ」「クリクラ」。「ワンウェイ方式のボトル・パック」が利用者の3割強、「リターナブル方式のボトル」が4割強、「水道直結型」が8%。
■利用のきっかけは「無料お試し期間があった」「店頭、街頭などでのキャンペーンやデモを見た」が利用者・経験者の各2~3割、「おいしい水が飲みたいと思った」「家族や友人・知人のすすめ」「安全な水を利用したいと思った」「営業担当者が紹介にきた」などが各10%台。
■非利用理由、利用中止理由とも「維持費がかかる」「設置スペースをとられる」が上位2位。水道水やミネラルウォーターなどで十分/満足、経済的余裕がない、の他、非利用理由では「水にこだわりがない」、利用中止理由では「ボトル交換・返却が面倒」なども上位にあがっている。
■家庭用ウォーターサーバー利用意向率は全体の約8%。現在利用者では8割の利用意向率、利用未経験者では約2~4%。
-
- 調査時期:
- 2017年07月
- 設問項目:
-
夏にアイスクリーム類を食べる頻度/冬にアイスクリーム類を食べる頻度/アイスクリーム類・氷菓の食べ方等の、季節による違い/アイスクリーム類を食べるシーン/アイスクリーム類の購入場所/アイスクリーム類を食べる際の重視点/直近1年間に食べたアイスクリーム類の銘柄/最も好きなアイスクリーム類の銘柄/寒い季節に食べるアイスのタイプ・銘柄(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■夏にアイスクリーム類を食べる人は9割強、週1回以上利用者は6割弱。冬に食べる人は7割強、週1回以上利用者は2割強。アイスクリーム類を「主に暑い季節に食べる」は3割強、「季節を問わず、一年を通して食べる」は3割弱。
■アイスクリームを食べるシーンは「間食・おやつ」が利用者の5割弱、「暑いとき」「お風呂あがり」「くつろいでいるとき」「甘いものが欲しいとき」などが各2~3割。冬に週に4~5回・週2~3回食べる層では「夕食前後」「お風呂あがり」などの比率が高い。
■アイスクリーム類を食べる際の重視点は「味」「価格」に続き、「食感」「甘すぎない」「容器の形状」「食べ慣れている」「食べやすさ」「濃厚」などが上位。過去調査と比べ「甘すぎない」「食べやすさ」などが減少傾向。
■最も好きな市販のアイスクリームは「ハーゲンダッツ」が、市販のアイスクリーム利用者の2割強。2位は男性では「ガリガリ君」、女性では「PARM」。
-
- 調査時期:
- 2017年07月
- 設問項目:
-
コーヒーの飲用頻度/飲んでいるコーヒーのタイプ/最もよく飲むコーヒーのタイプ/好きなコーヒーの飲み方/コーヒーを飲む場所/コーヒーを飲む場面/コーヒーへのこだわり/コーヒーの楽しみ方(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■コーヒーを毎日飲む人は全体の7割弱、「1日に2~3回」が4割弱。コーヒー飲用者のうち「インスタントコーヒー」「レギュラーコーヒー」が各5割で、過去調査より減少傾向。「缶コーヒー」3割強、「コンビニコーヒー」「カフェ・飲食店などのコーヒー」「ドリップバッグコーヒー」が各20%台。
■好きなコーヒーの飲み方はホットの中では「ブラック」「カフェ・オレ、カフェ・ラッテ」「砂糖・クリーム入り」「クリームのみ」、アイスの中では「ブラック」「カフェ・オレ、カフェ・ラッテ」「砂糖・クリーム入り」が上位。男性はブラック、女性はカフェ・オレ、カフェラッテがの比率が高い。
■コーヒー飲用者のうち「自宅」で飲む人は9割弱、「職場」が4割強、「コーヒーチェーン店」「喫茶店 ・カフェ」「車の中」などが各2割。
■コーヒーを飲む場面は「朝食時」「おやつの時」が上位2位。以下「リラックスしたいとき」「休憩中・休み時間」「仕事・勉強・家事をしながら」「昼食時」「食後」「気分転換するとき」などが続く。男性20代や女性では「おやつの時」、男性30・40代は「仕事・勉強・家事をしながら」が1位。
-
- 調査時期:
- 2017年07月
- 設問項目:
-
炭酸飲料の飲用頻度/炭酸飲料の飲用シーン/炭酸飲料選定時の重視点/直近1年以内に飲んだ炭酸飲料/直近1年以内に最もよく飲んだ炭酸飲料/炭酸飲料購入場所/トクホの炭酸飲料の直近1年間飲用状況/直近1年以内に最もよく飲んだ炭酸飲料の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■炭酸飲料飲用者は全体の8割弱、週1回以上飲用者約35%。直近1年以内の飲用銘柄の上位2位は「三ツ矢サイダー」「コカ・コーラ」。「コカ・コーラ ゼロ」は過去調査より減少傾向。
■飲用シーンは「「のどが渇いたとき」「スカッとしたいとき」「お風呂あがり」「休憩中・休み時間」「おやつのとき」「気分転換したいとき」などが各2割強~3割で上位。
■炭酸飲料飲用者の選定時の重視点は「味、飲み口」「価格」が各4~5割、「商品ブランド」「メーカー名」「飲み慣れている」などが各2~3割。購入場所は「スーパー」が飲用者の7割弱、「コンビニエンスストア」が4割弱、「自動販売機」が2割強。
■炭酸飲料飲用者のうち、直近1年間でのトクホ炭酸飲料飲用率は4割強。飲用理由は「味が好み」が炭酸飲料飲用者の2割弱、「脂肪や糖の吸収を抑えるなどの効能」「試しに飲んでみた」「同じ炭酸飲料を飲むなら体に良いものを選びたい」などが約6~8%。
-
- 調査時期:
- 2017年07月
- 設問項目:
-
最頻飲用ビール類/新ジャンルビールの飲用頻度/直近1年間に自宅で飲んだ新ジャンルビール/直近1年間に自宅で最もよく飲んだ新ジャンルビール/新ジャンルビール購入時の重視点/今後飲みたい新ジャンルビールの銘柄/新ジャンルビール飲用意向/新ジャンルビール飲用意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■新ジャンルビール飲用者は全体の約45%。男性や高年代層での比率が高い。発泡酒主飲用者の8割弱、ビール主飲用者の6割弱。
■直近1年間の飲用経験、今後の飲用意向とも「金麦」「キリン のどごし<生>」「クリアアサヒ」が上位3位。
■新ジャンルビール購入時の重視点は「味」「価格」に続き、「飲みやすさ」「のどごし」「ビールに近い」が上位。
■アルコール飲用者のうち新ジャンルビール飲用意向者は約45%。非飲用意向者は全体の3割強、女性20・30代で各4割強。
-
- 調査時期:
- 2017年06月
- 設問項目:
-
母の日での立場/母の日の実施状況/母の日に贈ったプレゼントの内容/母の日のプレゼント購入場所/プレゼント以外で母の日にしたこと/母の日にかけた費用総額/プレゼントを購入した時期/母の日にほしいプレゼントやしてほしいこと/プレゼントや何かをしたことの理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■母の日にプレゼントや何かをした人は5割弱、してもらった人は2割強。母の日に何かをしてあげる立場の人で 『プレゼントや何かをした』は6~7割。母の日にかけた費用総額は「3,000円~5,000円未満」がボリュームゾーン。
■今年の母の日にプレゼントしたものは「「お菓子」「カーネーション以外の花・鉢植え・観葉植物」「食品・飲料」「カーネーション」「衣料品、衣類小物」などが各2割。購入場所は「インターネットショップ」が購入者の3割弱、「総合スーパー」「専門店・小売店」が各2割、「デパート」が1割。
■プレゼントを贈る以外にしたことは「一緒に家で食事をした」「会いに行った」「一緒に外食をした」など。
■母の日に何かをしてもらう立場の人が、母の日にしてほしいもの・ことのトップは「感謝の気持ち」が3割弱、「外食」「お菓子」が各2割弱、「カーネーション以外の花・鉢植え・観葉植物」「衣料品、衣類小物」「カーネーション」「一緒に家で食事」「お手伝いや家事」「一緒に外出・遊びに出かける」などが各1割強。
-
- 調査時期:
- 2017年06月
- 設問項目:
-
健康についての関心度/健康に関する情報入手先/健康に関する情報発信手段/健康に関する情報源として信頼できるもの/健康に関する情報源として信頼できないもの/健康に関する情報の信頼度判断基準/健康に関する情報に惑わされた・失敗経験(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■健康に関する情報入手先は「テレビ番組・CM」が7割弱、「新聞」「家族や友人、知人」「病院、薬局・ドラッグストア」「健康に関する情報サイトやブログ」「一般雑誌」などが各2~3割。健康に関して「家族や友人・知人と話題にする」が2割、「ブログやホームページに投稿・コメントする」「Facebook、Twitter、ブログ、インスタグラムなどに投稿する」が各3~4%。
■健康に関する情報源として信頼できるものは「テレビ番組・CM」が3割強、「病院、薬局・ドラッグストア」「新聞」「病院や医者、薬局のホームページやブログ」「健康に関する専門誌」「家族や友人、知人」などが各1~2割。
■健康に関する情報源として信頼できないものは「折り込み広告、ダイレクトメール」「テレビ番組・CM」「Facebook、Twitter、ブログ、インスタグラムなど」「インターネットの広告」「フリーペーパー、広報誌、パンフレット」が各2割で上位。
■健康に関する情報の信頼度判断基準は「情報発信元が明確である」「情報発信元が信頼できる」「良い点だけでなく悪い点にも言及している」などが上位。
-
- 調査時期:
- 2017年06月
- 設問項目:
-
利用したことがあるスポーツクラブ/主利用スポーツクラブ/スポーツクラブ利用頻度/スポーツクラブ利用時の参考情報/民間スポーツクラブ非利用理由/民間スポーツクラブの利用意向/民間スポーツクラブ選定時の重視点/主利用スポーツクラブの利用理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■スポーツクラブ利用・登録経験は全体の3割弱。経験者のうち、現在利用者は4割強、退会者は5割強。現在利用者のうち週1回以上利用者は8割弱、週2~3回以上利用者は6割弱。
■スポーツクラブ利用時の参考情報は「実際の施設を見て」「家族や友人の意見」「折込チラシ、ダイレクトメール」などが上位。
■民間スポーツクラブの利用意向者は全体の2割弱。スポーツクラブ(公共施設含む)現在利用者の7割弱、利用中止・退会者の3割弱、未経験者の1割弱。利用意向者の選定時重視点は「入会費・月会費が手頃」「アクセスのよさ」が各7割強、「設備が充実」「施設が清潔」「一人で利用しやすい」「混んでいない」が各3~4割。
■スポーツクラブ利用経験者のうち、民間のスポーツクラブ非利用者の理由は「会費が高い」「通う時間がない」「通うのが面倒」「月に通える回数が限られ割高」などが上位。
-
- 調査時期:
- 2017年06月
- 設問項目:
-
メールマガジン受信数(パソコン版)/読んでいるメールマガジンの本数(パソコン版)/読んでいるメールマガジンのジャンル(パソコン版)/メールマガジン(パソコン版)に登録したきっかけ・送られてきたきっかけ/メールマガジン受信数(携帯・スマホ版)/読んでいるメールマガジンの本数(携帯・スマホ版)/読んでいるメールマガジンのジャンル(携帯・スマホ版)/ここ1年間に受信したメールマガジンに関する行動/内容を読むメールマガジンのタイプ(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■パソコン版のメールマガジン受信者は全体の8割、過去調査と比べ減少傾向。内容を読むジャンルは「懸賞・プレゼント・キャンペーン」「会員登録している会社やサービスなどからのお知らせ」が受信者の各5~6割、「ニュース・情報」「ショッピング」「旅行・アウトドア・レジャー」などが各2~3割。
■パソコン版のメールマガジン登録のきっかけは、「会員登録や商品購入の際、登録が必須だった」が受信者の5割、「プレゼント・キャンペーンなどの応募の際登録が必須だった」「ネット上の記事やブログ、企業サイトなどで見つけた」が各4割。
■携帯電話・スマートフォン版のメールマガジン受信者は全体の5割弱。内容を読むのは「会員登録している会社やサービスなどからのお知らせ」「懸賞・プレゼント・キャンペーン」が、受信者の各40%台。
■ここ1年間に受信したメールマガジンで「URLをクリックしてWebサイトをみた」は全体の6割弱、「メールマガジンを読んだことがきっかけで、商品・サービスを購入・利用した」は3割弱。
-
- 調査時期:
- 2017年06月
- 設問項目:
-
株式の売買経験/証券会社の認知/現在取引している証券会社/主に取引している証券会社/最も信頼感や安心感があると思う証券会社/最も手数料が安いと思う証券会社/最も先進性があると思う証券会社/最も顧客対応がよいと思う証券会社/今後取引をしてみたい・継続したい証券会社/主に取引している証券会社のイメージ(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■現在取引者の主取引先、利用意向ともに、「SBI証券」「野村證券」「楽天証券」などが上位。
■最も『信頼性や安心感がある』『顧客対応がよい』のは、1位「野村證券」、2位・3位は「SBI証券」「大和証券」。顧客対応がよい会社は「いずれもない」が7割強。
■最も『手数料が安い』は、1位「SBI証券」、2位は「楽天証券」で、以下「カブドットコム証券」「松井証券」「GMOクリック証券」などが続く。「いずれもない」が7割弱。
■最も『先進性がある』のは1位「SBI証券」、「楽天証券」「野村證券」「カブドットコム証券」「GMOクリック証券」などが続く。「いずれもない」が7割弱。
-
- 調査時期:
- 2017年06月
- 設問項目:
-
コンビニ弁当利用頻度/よく食べるコンビニ弁当のタイプ/コンビニ弁当選定基準/コンビニ弁当と一緒に買う飲み物/コンビニ弁当と一緒に買う食べ物/コンビニ弁当利用場面/コンビニ弁当の購入価格/弁当が最もおいしいと思うコンビニ/コンビニ弁当の不満点(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■コンビニ弁当利用率は5割弱。コンビニ弁当が一番おいしいと思うコンビニは「セブンイレブン」が、コンビニ弁当利用者の6割弱で、過去調査と比べ増加傾向。
■コンビニ弁当利用者がよく食べるものは「ごはん+おかず:おかずとごはんが別」が5割、「麺類」「丼もの」が各3~4割。選定基準は「見た目がおいしそう・きれい」「価格」が利用者の各4割、「味」「様々な種類のおかずが入っている」「野菜の量や種類が多い」が各2~3割。
■コンビニ弁当と一緒に飲み物を買う人はコンビニ利用者の8割弱。緑茶や日本茶系飲料などのお茶系飲料が上位。一緒に買う食べ物は「サラダ」「味噌汁」「チルドデザート、アイスなど」「お菓子・スナック類」「スープ類」などが各10%台。
■コンビニ弁当を食べる場面は「食事を簡単に済ませたい」「食事や弁当を作るのが面倒」「食事や弁当を作る時間がない」「早く済ませたい」「一人で食事をする」が、利用者の各2~3割。「昼食」は4割強、「夕食」は約15%。
-
- 調査時期:
- 2017年06月
- 設問項目:
-
髪の長さ/使用しているヘアスタイリングのタイプ/ヘアスタイリング剤使用頻度/使用しているヘアスタイリング剤の銘柄/ヘアスタイリング剤選定時に気にすること/ヘアスタイリング剤選定時の参考情報源/ヘアスタイリング剤購入場所/ヘアスタイリング剤の不満・要望(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■ヘアスタイリング剤使用者は全体の4割強。利用タイプは「スプレー」「ワックス」「フォーム・ムース」「ミスト」など。「ワックス」は男性20・30代で高い。
■ヘアスタイリング剤選定時に気にすることは「まとまり感」「つけ心地」「髪質に合うこと」「価格」「香り」などが各3割強~4割。「つけ心地」「香り」は女性での比率が高い。
■ヘアスタイリング剤購入場所は「ドラッグストア」が、利用者の7割弱、「スーパー」が2割強、「インターネットショップ」「ホームセンター」「ディスカウントストア」が1割弱。
■ヘアスタイリング剤選定時の参考情報源は「店頭のPOPやリーフレット」「商品パッケージの説明」「テレビCM」が、使用者の20%台。
-
- 調査時期:
- 2017年06月
- 設問項目:
-
嫌だと気になる匂い/自分の汗の臭いが気になる度合い/直近1年間に利用したデオドラント剤のタイプ/デオドラント剤の主利用タイプ/直近1年間に利用したデオドラント剤の銘柄/デオドラント剤利用部位/デオドラント剤の利用場面/デオドラント剤選定時の重視点/デオドラント剤の使い方(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■自分の汗の臭いが気になる人は全体の6割弱。女性や若年層で高い傾向。
■デオドラント剤直近1年間利用者は全体の6割弱、女性の方が高い。「スプレー」タイプが4割弱、「シート、ペーパー」「ロールオン」が各10%台。「シート、ペーパー」は若年層での比率が高い傾向。
■デオドラント剤の利用場面は「主に暑い季節に」「汗やにおいの予防」が直近1年間利用者の各5割、「出かける前」「汗が気になった時」「においが気になった時」「季節を問わず一年を通して」が各3割。「脇の下」に使う人は利用者の9割弱、「首」が4割、「デコルテ」「背中」が各2割。
■デオドラント剤選定時の重視点は「タイプ」「価格」が上位2位。「香りがよい」「容量、サイズ」「使いやすい」「消臭効果」「メーカー、商品ブランド」などが続く。
-
- 調査時期:
- 2017年06月
- 設問項目:
-
自宅の洗濯機のタイプ/主利用洗濯機のメーカー/主利用洗濯機メーカーの満足度/洗濯機の容量/洗濯機の使用頻度/洗濯をする時間帯/洗濯機購入・買い替え予定時期/洗濯機購入時に重視する機能・製品特長/主利用洗濯機メーカーの選定理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■自宅の洗濯機のタイプは「ドラム式洗濯乾燥機」が2割弱、「縦型洗濯乾燥機」が3割弱、「全自動洗濯機」が5割強。洗濯機の容量は「7kg台」「8kg台」がボリュームゾーン。
■洗濯機所有者の使用頻度は「ほぼ毎日」が4割。女性30代以上では5~6割、男性30代以上では3割。
■洗濯機使用者の洗濯をする時間帯は「8時台~11時台(午前中)」が半数弱。「朝4時台~7時台(早朝)」「19時台~22時台(夜)」が各20%台。
■洗濯機購入・買い替え予定者(4割強)が、洗濯機購入時に重視する点は「省エネ」「洗浄力」「大きさ・容量」「運転音の静かさ」が各5~6割。過去調査と比べ「省エネ」が減少傾向。
-
- 調査時期:
- 2017年06月
- 設問項目:
-
電力自由化の認知/ガス自由化の認知/契約している電力会社/電力会社変更状況/電力会社変更予定がない理由/電力会社の契約意向/契約しているガス会社/ガス会社変更状況/ガス会社の契約意向/ガス会社契約意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■電力自由化について「内容まで詳しく知っている」は全体の3割強、「聞いたことがある程度」は6割強。ガス自由化について「内容まで詳しく知っている」は全体の2割強、「聞いたことがある程度」は7割弱。
■電力自由化後、会社変更者は1割弱。契約会社での料金プラン変更者は約4%。会社や料金プラン変更予定者は約4%。電力会社の変更予定がない人は7割強。理由は「現在利用している会社に特に不満がない」「変更してもメリットが感じられない」が上位2位。
■電力会社契約意向は、大手電力会社契約意向者が全体の4割弱、新規参入の電気小売事業者契約意向者は1割強。
■ガス会社変更者は約1%。契約会社での料金プラン変更者は約2%。ガス会社変更予定者は約3%、変更予定がない人は9割弱。ガス会社契約意向は、従来の都市ガス会社契約意向者が全体の4割弱、新規参入都市ガス契約意向者が約4%、LPガスが1割。
-
- 調査時期:
- 2017年06月
- 設問項目:
-
間食の頻度/間食をする時間帯/間食をする場面/間食でよく食べるもの/間食でよく飲むもの/間食で飲食するものを購入する時の重視点/間食をとる理由/間食の分量・頻度の多さ/間食時に気をつけていること(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■間食をする人は全体の7割強、男性の6割強、女性の8割強。間食をする人のうち、「昼食から夕方の間」が7割弱、「夕食後」が3割強。1日1回以上食べる人は3割強、女性30代以上では5割。自分の間食の分量・頻度が多い方だと思う人は、間食をする人の5割弱。
■間食をする場面は「くつろぎながら」「おやつの時間」「仕事・勉強・家事の合間」「テレビやDVDなどを見ながら」が、間食をする人の各3~4割。間食をとる理由は「お菓子など、甘いものが好き」「なんとなく口さびしい」「おなかがすく」が各4~5割、「リラックスしたい」「気分転換」が各3割。
■間食でよく食べるものは「チョコレート」「スナック菓子」が各5割、「せんべい・あられなどの米菓」「クッキー、ビスケット」「アイスクリーム類」が各4割。よく飲むものは「コーヒー、コーヒー飲料」「お茶、お茶系飲料」が各6~7割、「紅茶、紅茶飲料」が3割。
■間食選定時の重視点は「価格」が4割弱、「食べきりサイズ」「おなかがいっぱいになりすぎない」「分けて食べられる容器・包装」「カロリーが低い」「甘い」「満腹感・腹持ちのよさ」などが各2~4割で上位。
-
- 調査時期:
- 2017年06月
- 設問項目:
-
自宅でのお酒飲用頻度/自宅でお酒を飲むときおつまみを食べるかどうか/自宅での飲酒時によく食べるおつまみ/自宅でおつまみを食べながら飲むお酒の種類/自宅で飲酒時のおつまみ準備方法/自宅での飲酒時に食べる市販のおつまみ選定時の重視点/自宅での飲酒時に食べる市販のおつまみ購入場所/自宅での飲酒時に食べるおつまみで気に入っているもの・食べるシチュエーション(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■自宅でお酒を飲む人は男性の8割弱、女性の6割強。「ほぼ毎日」が2割弱、週1回以上が半数弱。自宅での飲酒者のうち、おつまみを食べる人は約85%。「必ず食べる」が5割。
■自宅でおつまみを食べながら飲むお酒は「ビール」6割強、「発泡酒、新ジャンルビール」4割強、「チューハイ、サワー」「ワイン」「焼酎」「日本酒」などが各3割。女性20・30代では「チューハイ、サワー」が1位。
■自宅でおつまみを食べる人のうち、「食事のおかずをおつまみとして食べる」は7割弱、「市販のスナック、菓子、乾きものなどを買う」は5割強。おつまみで「チーズ」を食べる人は5割弱、「スナック菓子」「ナッツ類」「刺身、たたき」「揚げ物」「枝豆」などが各4割。
■自宅での飲酒時に食べる市販のおつまみ選定時の重視点は「味」「価格」に続き、「すぐ食べられる」「食感」「季節のもの・旬のもの」「原材料」などが各2~3割で上位。購入場所は「スーパー」9割強、「コンビニエンスストア」3割強。
-
- 調査時期:
- 2017年06月
- 設問項目:
-
魚肉加工品の嗜好度/直近1年以内に食べた魚肉加工品/魚肉加工品を食べる頻度/魚肉加工品を食べる場面/魚肉加工品購入時重視点/魚肉加工品の魅力/魚肉加工品の不満/好きな魚肉加工品とおすすめの食べ方(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■魚肉加工品が好きな人は全体の7割。週1回以上食べる人は4割強。いずれも、50代以上での比率が高い。
■直近1年以内に食べた魚肉加工品は「ちくわ」「かまぼこ」が、食べた人の各8割、「さつまあげ、つけあげ」「かにかま」「魚肉ソーセージ」「はんぺん」などが各5~6割。地域差がみられる。
■魚肉加工品購入時の重視点は「味」「価格」の他、「原材料」「賞味期限・消費期限」「生産国」「量・サイズ、販売単位」などがが上位。
■魚肉加工品の魅力は「そのまま食べられる」「味が良い・好き」「良質なたんぱく質がとれる」「価格が安い」「調理が簡単」などが上位。不満は「食品添加物が気になる」「塩分がきつい」などが各10%台で上位。
-
- 調査時期:
- 2017年06月
- 設問項目:
-
ミネラルウォーター飲用頻度/直近1年間に飲んだ市販のフレーバーウォーター/直近1年間の最頻飲用フレーバーウォーター/直近1年間のフレーバーウォーター飲用頻度/市販のフレーバーウォーター飲用場面/市販のフレーバーウォーター購入時の重視点/市販のフレーバーウォーターの好きな風味・味/市販のフレーバーウォーター飲用意向/市販のフレーバーウォーター飲用意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■フレーバーウォーター飲用経験者は5割強、直近1年間飲用者は4割強。若年層での比率が高い。飲用者のうち、週1回以上飲用者は3割。飲用場面は「のどが渇いた時」が最も多く、「仕事・勉強・家事の合間」「レジャー・遊びの時」「お風呂上がり」などが続く。
■フレーバーウォーターの風味・味で好きなものは「レモン」「オレンジ」「みかん」「桃、白桃」が、直近1年間飲用者の各3~4割、「ヨーグルト」「グレープフルーツ」「リンゴ」が各2割。
■直近1年間飲用者の、購入時の重視点は「味」「価格」の他、「容量、サイズ」「香り」「メーカー」「カロリー」「成分、添加物」などが上位。
■市販のフレーバーウォーターの飲用意向者は3割強、若年層で高い。フレーバーウォーター直近1年間飲用者では7割強、飲用未経験者では約3%、ミネラルウォーター直近1年間飲用者では4~6割、非飲用者では約9%。
-
- 調査時期:
- 2017年06月
- 設問項目:
-
缶チューハイ飲用頻度/直近1年間に飲んだ缶チューハイ/直近1年間の最頻飲用缶チューハイ/缶チューハイ飲用シーン/缶チューハイに期待すること/缶チューハイ以外に飲むお酒/缶チューハイ飲用意向/缶チューハイの不満点(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■缶チューハイ飲用者は全体の5割弱。アルコール飲用者に占める缶チューハイ飲用率は6割強で、女性や若年層の比率が高い。週1~2日以上飲用者は全体の2割弱。
■缶チューハイ飲用シーンは「食事中」が飲用者の5割、「自宅でくつろいでいるとき」「入浴後」「食事のあと」「寝る前」などが各2割。
■缶チューハイに期待することは「好みのフレーバーである」「スッキリしている」「果汁感を楽しめる」「価格が安い」「甘さ控えめ」「飲みやすい」「炭酸を楽しめる」などが各3~4割。
■缶チューハイ飲用意向は全体の4割強。月2~3日以上飲用者で9割強、非飲用者では約3~5%。
-
- 調査時期:
- 2017年06月
- 設問項目:
-
自宅でのビール類飲用頻度/直近1年間に自宅で飲んだプレミアムビール/直近1年間に自宅で最もよく飲んだプレミアムビール/直近1年間の、自宅でのプレミアムビールの飲用頻度/自宅でプレミアムビールを飲みたい気分/自宅で最も飲みたいプレミアムビール/自宅・外食でのプレミアムビール飲用/直近1年間最頻飲用プレミアムビールの飲用理由・意向(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■直近1年間の自宅でのプレミアムビール飲用者は全体の4割、そのうち週1日以上飲用者が3割、月1日未満が4割弱。
■アルコール飲用者のうち、プレミアムビールを「自宅で飲むことの方が多い」は5割弱、「外食で飲むことの方が多い」は1割強。男性や高年代層で、自宅での飲用者の比率が高い傾向。
■自宅でプレミアムビールを飲みたいのは「ゆったりとした気分で飲みたい時」「贅沢な気分を味わいたい時」が上位2位。「ビールの味を味わいたい時」「頑張った自分へのご褒美をしたい時」などが続く。
■アルコール飲用者が自宅で最も飲みたいプレミアムビールは、「ザ・プレミアム・モルツ」「ヱビスビール」が各2割。アルコール飲用者の、プレミアムビール飲用意向は7割、直近1年間プレミアムビール飲用者の9割強、非飲用者の3割弱。
-
- 調査時期:
- 2017年05月
- 設問項目:
-
イースターの認知/イースターについて知っていること/イースターにあたってしたこと/イースターにあたってしたことのきっかけ・理由/イースターに関して使った費用総額/イースターにあたって購入したもの/イースターに関するものを購入した場所/イースターにあたって何かしたこと・購入したものなど(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■イースター認知率は8割強、「どんな行事か知っている」は2割強。認知者のうち「キリスト教でイエス・キリストが復活したことを記念する日」「イースターエッグ」を知っている人が各5~6割。「イースターエッグ」などは女性での認知率が高く、男女差が大きい。
■イースター認知者のうち、イースターにあたって何かした人は1割強。「イースターエッグを作る」「イースターにちなんだ料理・お菓子等を飲食する」が各3~4%、「イースターにちなんだ料理・お菓子等を購入する」が約2%。
■イースターにあたって何かしたきっかけ・理由は「店頭等でイースター関連商品が目についた」「たまたまイベントやフェアなどをやっていた」「自分または家族がキリスト教徒だから」「季節行事の一つとして」「海外で暮らしたことがある」などが各10%台。
■イースターにあたって何かした人のうち「卵」「チョコレートエッグ」「イースター限定の味やパッケージのお菓子・デザート」が各1割強~2割。購入場所は「スーパー」が購入者の5割強。
-
- 調査時期:
- 2017年05月
- 設問項目:
-
目の健康についての関心度/目についての症状・気になること/目の症状・気になることの原因/目の健康のために行っていること/定期的な眼科検診の受診有無/メガネ・コンタクトレンズの使用状況/使用しているメガネ・コンタクトレンズのタイプ/メガネ・コンタクトレンズ利用理由/目の健康に関することで気になること(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■目の健康の関心層は全体の8割弱。症状・気になることは「目が疲れやすい」「視力低下」が各4~5割、「目がかすむ」「小さな文字が読みにくい」「目の疲れからくると思われる肩こり・頭痛」「かゆみ」などが各2~3割。
■目の症状・気になることがある人のうち、「近視・遠視・乱視や老眼など」「加齢」が原因だと思う人の比率は高年代層で高く、「スマートフォンやゲーム機などを長時間使う」「視力がよくない」は若年層で高い。
■目の健康のために行っていることは「目薬を使う」が4割、「睡眠をとる」「眼科検診をする」が各2割。
■「メガネやサングラスを使用」は全体の8割弱、「コンタクトレンズを使用」は2割。利用理由は「近視」が7割、「老眼」「乱視」が各30%台。
-
- 調査時期:
- 2017年05月
- 設問項目:
-
インスタグラムの認知・利用/直近1年間のインスタグラムへのアクセス頻度/インスタグラムのフォロー数/インスタグラム利用目的/インスタグラム利用理由/インスタグラムに関する行動/インスタグラム利用意向/インスタグラム利用意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■インスタグラム利用者は全体の1割強、投稿・閲覧両方利用、閲覧中心利用が、それぞれ約5~6%。「知っているが、登録したことはない」「名前を聞いたことがある程度」は各3割強。利用者のうち1日1回以上アクセス者は5割弱。
■インスタグラム利用目的は、「有名人・著名人などの投稿閲覧」「友人や家族などの投稿閲覧」が利用者の各4~5割、「興味がある分野の情報収集」「友人や家族などとのコミュニケーション」が各20%台。利用理由は「有名人が利用」「友人や家族が利用」が利用者の各3割強、「写真がメインなのでコメントをあまり書かなくてよい」「友人・知人など仲間同士で交流できる」が各2割。
■インスタグラム利用者のうち、直近1年間に「いいねをする」は6割強、「ハッシュタグでの検索」「投稿された商品・サービスについて調べる」が各2~3割。
■インスタグラム利用意向者は1割強、非利用意向者は6割強。インスタグラム投稿・閲覧両方利用者では9割弱、閲覧中心利用者では7割弱、非登録者では1割弱。
-
- 調査時期:
- 2017年05月
- 設問項目:
-
ブログの閲覧頻度/ブログを閲覧する機器・場所/閲覧するブログのジャンル/ブログで紹介された商品・サービスの直近1年以内の購入・利用経験/ブログ開設状況/ブログの更新頻度/開設しているブログのサービス名/ブログの閲覧・開設意向/ブログ利用理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■ブログ閲覧者は全体の5割。毎日閲覧者は2割弱。閲覧ジャンルは「芸能人・著名人などの日記」「友人・知人の日記」が、ブログ閲覧者の各3~4割。
■ブログ閲覧者のうち、ブログで紹介された商品・サービス直近1年以内購入・利用者は約15%、購入・利用経験者は3割弱。
■ブログ開設者は約8%で過去調査と比べ減少傾向。開設者のうち、1日1回以上更新者は2割。「開設したことはあるが現在はやっていない」は全体の2割弱、女性20代で4割弱。
■今後「閲覧を中心に利用したい」は全体の3割弱、月2~3回以上閲覧者では5割強~6割、非閲覧者では約6%。ブログ開設意向は全体の1割で、現在ブログ開設者では8割弱、開設経験者では2割弱、未経験者では約2%。「ブログは利用したいと思わない」は5割強。