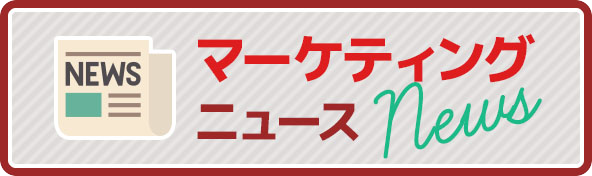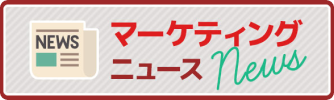- 検索
-
- テーマ別実施時期一覧
- カテゴリー別一覧
-
-
アルコール飲料・嗜好品147
-
非アルコール飲料210
-
その他19
-
-
住宅・住宅設備219
-
-
家電126
-
パソコン・カメラ・AV機器113
-
その他10
-
-
家庭用品・トイレタリー91
-
自動車・関連用品76
-
-
インターネット・情報通信328
-
携帯電話・スマートフォン180
-
メディア・広告66
-
その他7
-
-
ファッション69
-
交通・レジャー・娯楽161
-
季節行事・イベント241
-
時事・ニュース・トレンド51
-
企業ブランドイメージ250
-
広告・CM51
-
WEBサイトの利用91
-
顧客満足度100
- 実施時期別一覧
-
- 調査時期:
- 2013年09月
- 設問項目:
-
通話頻度/通話で利用する機器/モバイル機器・パソコンでの通話時に最もよく利用する機器/モバイル機器・パソコンでの通話時に利用するツール・回線/モバイル機器・パソコンでの通話時のヘッドフォン・イヤホンの利用状況/モバイル機器・パソコンで通話する場面/モバイル機器・パソコンでの通話時の、ヘッドセット・イヤホンの利用意向/モバイル機器・パソコンでの通話時の、ヘッドセット・イヤホンの利用意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■通話頻度は「1日1~2回」「2~3日に1回程度」が各2割、「月に数回程度」が2割弱。
■通話する人の利用機器は「携帯電話」「固定電話」が各6割弱、「スマートフォン」が4割弱。「スマートフォン」は若年層ほど多く、10・20代では6~7割にのぼる。「携帯電話」は高年代層ほど多い
■モバイル機器・パソコンで通話する人では「本体を耳にあてて話す」が8割強。ヘットフォン・イヤホンやマイクなどを使う人は1割強で、「車やバイクの運転中」「手がふさがっている」「ほとんどいつも」「長い時間電話をする」などの場面で利用
■モバイル機器・パソコンでの通話時の、ヘッドセット・イヤホンの利用意向は2割弱、利用したくない人が4割強。主にスマートフォンで通話する人の3割弱、携帯電話で通話する人の2割弱
-
- 調査時期:
- 2013年09月
- 設問項目:
-
所有スマートフォンの機種/スマートフォンの新規購入・機種変更/スマートフォンで利用している機能・サービス/携帯しているスマートフォン用の充電器/利用スマートフォンの満足度/スマートフォン利用意向/スマートフォン選定時の重視点/利用スマートフォン利用にあたって気をつけていること(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■スマートフォン所有率は42.1%で2013年2月調査時より約7ポイント増。10代では8割強、20代は7割弱、50代以上は3割弱。「以前持っていた携帯電話と同じ携帯電話会社のスマートフォンに機種変更した」はスマートフォン所有者の6割強で、NTTドコモのスマートフォン所有者で多い。「前の携帯電話を解約し、違う携帯電話会社のスマートフォンに買い替えた」は15.2%でiPhone所有者で多い
■スマートフォンで利用している機能・サービスは「通話」「携帯電話のメールアドレスでのメールの送受信」「カメラ」の他、Webサイト閲覧、時計・アラーム、地図、GPS機能などが上位
■ スマートフォンの利用意向は全体の半数弱。10・20代では各7~8割であるが、50代以上では4割弱にとどまる。スマートフォン所有者では8割強、非所有者では2割弱。iPhone所有者では満足度や今後の利用意向が高い
■スマートフォン利用意向者の重視点を聞いたところ、「バッテリーの持ち時間」「本体価格」が上位2位。過去調査に比べ「本体価格」「通信料金」「携帯電話と同じような機能」などが減少傾向
-
- 調査時期:
- 2013年09月
- 設問項目:
-
現在利用しているソーシャルメディア/現在よく投稿しているソーシャルメディア/現在よく利用しているブログ、ミニブログ、SNSのサービス/ブログ、ミニブログ、SNSの利用目的/ブログ、ミニブログ、SNSの利用頻度/ブログ、ミニブログ、SNSを利用する機器/ブログ、ミニブログ、SNSの利用中止経験/今後利用したいサービス/最頻利用サービスの不満点・改善要望(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■現在よく利用しているサービスは「YouTube」が最も多く、「価格.com」「Facebook」「ブログ」「Yahoo!知恵袋」「クックパッド」「Twitter」が続く。「Facebook」は過去調査より増加傾向。何らかのサービスへの投稿者は4割弱で、「Facebook」「Twitter」「ブログ」「mixi」が各1~2割
■ブログ、ミニブログ、SNSは毎日利用者が半数強。利用目的は「日記・記録の代わり」「自分の考え・意見を発信する」に次いで、「ひまつぶし」「リアルな友人や知人とのコミュニケーション」「最新・リアルタイムの情報収集」「生活関連や趣味など、興味がある分野の情報収集」など、さまざま。Facebook、mixi利用者では友人とのコミュニケーション、Twitter利用者は情報収集・発信を目的とする人が多い
■ブログ、ミニブログ、SNSの利用機器は「ノートパソコン」「デスクトップパソコン」「スマートフォン」が利用者の各4~5割。過去調査に比べ「スマートフォン」が増加、「携帯電話」が減少
■今後利用したいサービスは「YouTube」「価格.com」に続き、「クックパッド」「Yahoo!知恵袋」「Facebook」「ブログ」などが上位。過去調査に比べ「Facebook」は増加傾向、「mixi」などは減少傾向
-
- 調査時期:
- 2013年09月
- 設問項目:
-
メインバンクの金融機関/銀行利用時の重視点/メインバンクの満足度/メインバンクの満足点/メインバンクの不満点/メインバンクの満足度の1年前からの変化/メインバンクの満足度変化の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■銀行利用時の重視点は「ATMの設置台数・立地」、「手数料無料サービスの有無」「手数料の金額」「銀行支店(窓口)の数・立地」など
■メインバンクの満足点は「ATMの設置台数・立地」、「手数料無料サービスの有無」「銀行支店(窓口)の数・立地」が上位3位
■メインバンクに不満がある人は6割強。不満点は「預金金利」「手数料の金額」が上位2位
■メインバンクについて「満足」の比率をみると、ネット専業銀行、新生銀行で各2割。メインバンクの満足度が1年前より高まった人は4.1%、「変わらない」が9割弱。
-
- 調査時期:
- 2013年09月
- 設問項目:
-
ファストフード店の利用頻度/直近1年以内に利用したファストフード店/直近1年以内の最頻利用ファストフード店/ファストフード店利用時の重視点/ファストフード店の利用場面/最も好きなファストフード店/ファストフード店利用のきっかけ・理由となるクーポンの種類/ファストフード店以外に利用を検討する店舗/ファストフード利用頻度の変化/ファストフード利用が増えた/減った理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■ファストフード店利用頻度は「月に1回くらい」「年に数回以下」が各3割前後、2011年調査に比べ、利用頻度がやや低い。最も好きなファストフード店は「マクドナルド」「モスバーガー」が各3割弱でトップ2。
■ファストフード店の重視点は「値段が手頃」「食べ物がおいしい」の他「割引きサービスがある」「アクセスがよい」「気軽に立ち寄れる」「待ち時間が短い」などが多い。マクドナルド主利用者、ミスタードーナツ主利用者、ロッテリア主利用者では「値段が手頃」、他のファストフード主利用者では「食べ物がおいしい」が1位
■利用場面は「昼食」の他、「小腹がすいた時」「手ごろな価格で飲食したい時」「クーポンやキャンペーンがある時」「短時間で食事を済ませたい時」「軽く済ませたい時」などが上位。ケンタッキーフライドチキン主利用者は「昼食」に次いで「夕食」が多い
■ファストフード店以外に利用を検討する店舗は「ファミリーレストラン」「喫茶店、コーヒーショップ」が上位2位、「コンビニエンスストア」「回転すし店」「ラーメン店」「牛丼チェーン店」が続く。男性は「牛丼チェーン店」が1位。「紙のチラシのクーポン」がきっかけで店舗を利用することがある人はファストフード利用者の5割弱
-
- 調査時期:
- 2013年09月
- 設問項目:
-
直近1年間の牛丼チェーン店利用頻度/直近1年間に利用したことがある牛丼チェーン/直近1年間に最もよく利用した牛丼チェーン/最もよく利用した牛丼チェーンの利用理由/牛丼チェーン店に一緒に行く人/最もおいしいと思う牛丼チェーン店/直近1年間の牛丼チェーン非利用理由/最も利用したい牛丼チェーン/牛丼チェーン店について気になる・変えて欲しい点(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■牛丼チェーン直近1年間利用者は全体の6割強。月1回以上利用者は全体の2割強、男性3割強、女性1割強。1年以内利用経験は「すき家」「吉野家」が各6~7割で上位2位。「吉野家」は2010年調査時よりやや少ない。
■直近1年間の主利用牛丼チェーンの利用理由は「値段が手頃」に続き「近くにある、アクセスがよい」「おいしい」「待ち時間が短い」の順で多い。吉野家主利用者では「おいしい」「食べ慣れている」「牛丼が好き」、すき家主利用者では「近くにある、アクセスがよい」「メニューが豊富」、松屋主利用者では「味噌汁などがサービスで付く」などがやや多い
■牛丼チェーン店に「一人で行く」は、直近1年間利用者の5割強、男性7割強、女性2割強。一緒に行く人の中では「配偶者」「子ども」が上位で、すき家利用者で多くみられる。
■直近1年間利用者が最もおいしいと思う牛丼チェーン店は「吉野家」「すき家」が上位2位。主利用牛丼店が最もおいしいと思う人の比率は、吉野家が8割近く、すき家や松屋の4~5割を上回る。
-
- 調査時期:
- 2013年09月
- 設問項目:
-
所有している電子レンジのタイプ/所有電子レンジのメーカー/所有している電子レンジの機能/電子レンジの機能のうち、使っている機能/電子レンジ機能の利用場面/料理1回あたりに、電子レンジ機能を使う比率/電子レンジ用調理器具の所有状況/電子レンジ購入時の重視点/電子レンジの役立つ/いらない機能(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■「オーブン・トースター機能付き」所有者が半数強。「スチームオーブンレンジ」は18.5%で過去調査よりも増加傾向。購入時の重視点は「価格」の他、「操作のしやすさ」「メーカー・ブランド」「本体の大きさ」が上位
■電子レンジ所有者が使っている機能は「ちょうどよい温度に自動で温める」「飲み物を温める」「生解凍・半解凍」などが上位3位。料理1回あたりの電子レンジ機能の利用率は、30%以下が半数弱、50%以下が7割弱。
■電子レンジを使う場面は「家庭で作った料理やご飯の温めなおし」「冷凍食品や、家庭で冷凍保存した食材やご飯の解凍」「レトルト食品、電子レンジ用食品などの調理・温め」が上位。「食材を調理する」は所有者の4割、スチームオーブレンジ所有者、オーブン・トースター機能付き所有者では半数前後
■電子レンジ用調理器具所有者は電子レンジ所有者の7割弱。「シリコンスチーマー」は3割強で、女性40代以上では4~5割、スチームオーブンレンジ所有者の5割弱
-
- 調査時期:
- 2013年09月
- 設問項目:
-
弁当を食べる頻度/お弁当の準備方法/購入したお弁当を食べる時間帯/お弁当を購入する場面/自分でお弁当を作る頻度/自分でお弁当を作る理由/自分で作るお弁当に入れるおかずの準備方法/自分でお弁当を作る時の参考情報/お弁当についてのこだわり(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■お弁当を食べる人は全体の8割強。利用頻度は「週に4~5日」「月に1日未満」が各2割弱。お弁当を食べる人のうち「コンビニエンスストアで購入」したものを食べる人が半数弱で最も多く、「スーパー」「弁当店・惣菜店など専門店」などが続く。自分で作る弁当を食べる人は3割弱、購入したお弁当を食べる人は6割強
■お弁当を購入する場面は「食事の準備をする時間がない」「短時間で食事を済ませたい」「すぐに食べたい」などが上位。以下「食事の準備や後片付けが面倒」「安く済ませたい」が続く。「平日:昼食」に食べる人が購入者の6割強、休日の昼食や夕食、平日の夕食が各2~3割
■自分でお弁当を作る人は全体の4割、女性の7割弱。男性全体では2割弱で、男性20代では2割強みられる。自分で作る理由は「食費の節約」が最も多く、「家族のため、家族の要望」が続く。
■自分でお弁当を作る時の参考情報は「口コミのレシピサイト・アプリ」「料理レシピを書いた本」「テレビ番組・CM」などが上位
-
- 調査時期:
- 2013年09月
- 設問項目:
-
平日の夕食のとり方/平日の夕食のとり方で最も多いもの/平日の夕食を一緒に食べる人/平日に夕食を食べ始める時間/平日の夕食にかける時間/平日の夕食のメニューで重視していること/平日の夕食についての行動・考え方/夕食のメニューの参考にする情報/夕食のメニューの決め方(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■平日の夕食は、自宅で自分や家族が作ったものを食べる人が5~6割、「自宅で、買ってきたものを食べる」「外食をする」が各2割強。「配偶者」「子ども」「母親」「父親」の順で多い
■平日に夕食を食べ始める時間は「19時台」が4割弱、「18時台」「20時台」が各2割。夕食にかける時間は「15~30分未満」が半数近くを占め、「30分~1時間未満」が4割弱
■平日の夕食のメニューで重視していることは「栄養バランスが良い」「食べたいものを食べる」が上位2位、以下「できるだけ手作りである」「毎日の献立に変化がある」「季節感のあるメニューである」「一緒に食事を取る人みんなが同じものを食べる」などが続く
■自分で夕食を作る人が、夕食のメニューの参考にする情報は「口コミのレシピサイト・アプリ」が最も多く女性10~30代の5~6割。「テレビ番組」「料理レシピを書いた本」などが上位。過去調査に比べ「料理レシピを書いた本」などは減少傾向
-
- 調査時期:
- 2013年09月
- 設問項目:
-
半調理品の利用状況/半調理品の利用理由/半調理品購入頻度/半調理品購入時の重視点/半調理品利用意向/利用したい半調理品/半調理品を利用したくない理由/半調理品に対する要望(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■料理での半調理品利用者は全体の5割強、自分で料理をする人の7割弱。「味付け済みの魚介類」「下ごしらえ済み魚介類」「加熱前の状態に成形した肉類」「味付け済みの肉類」が各3割。購入頻度は「週2~3回」「週1回」「月2~3回」がボリュームゾーン
■半調理品利用理由は「料理の時間が短縮できる」「面倒な下ごしらえをしなくていい」が各6~7割で上位2位、「手間のかかる料理が手軽にできる」が続く
■半調理品利用意向者は全体の半数弱、女性30代以上では7割弱。利用したいものは「下処理済み」が最も多く、「焼く・蒸す前の状態のもの」「下味がついている」「電子レンジで加熱すればよい状態のもの」の順で続く
■半調理品を利用したくない理由の上位は「価格が高い」「添加物が気になる」「材料の産地や加工地などがわからない」など。
-
- 調査時期:
- 2013年09月
- 設問項目:
-
しょうゆの嗜好度/自宅でのしょうゆの利用頻度/利用するしょうゆのタイプ/利用しているしょうゆのメーカー/しょうゆ開封後の保存方法/しょうゆ購入時の重視点/しょうゆ購入時の銘柄指定/しょうゆに関するこだわり、気をつけていること(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■自宅でのしょうゆの利用頻度は「ほとんど毎日」が4割強、「週4~5回」「週2~3回」が各2~3割。東北と北陸では他地域より利用頻度が高い傾向。
■しょうゆ利用者のうち、「こいくちしょうゆ」が最も多く、「うすくちしょうゆ」「丸大豆しょうゆ」「だし入りしょうゆ」「減塩しょうゆ」などが各1~2割で続く。西日本では「うすくちしょうゆ」「さしみ醤油」などが比較的多い
■しょうゆ開封後の保存方法は「冷蔵庫へ入れる」が4割弱、「冷暗所に保存」が3割弱、「常温で保存」が3割強
■しょうゆ利用者の重視点は「味」「価格」の他、「しょうゆの種類」「大豆の種類」「使い慣れている」「メーカー、商品ブランド、生産者」「原材料」「容量、サイズ」「塩分控えめ、減塩」などが上位。「だいたい同じ商品を買う」はしょうゆ購入者の6割強、「だいたい同じタイプのしょうゆを買うがメーカーや銘柄は決まっていない」は2割弱
-
- 調査時期:
- 2013年09月
- 設問項目:
-
スポーツ・機能性飲料の飲用頻度/直近1年以内に飲んだスポーツ・機能性飲料/直近1年以内に最もよく飲んだスポーツ・機能性飲料/スポーツ・機能性飲料を飲む場面/スポーツ・機能性飲料購入時の重視点/スポーツ・機能性飲料購入場所/スポーツ・機能性飲料飲用意向/あったら飲んでみたいスポーツ・機能性飲料(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■スポーツ・機能性飲料飲用者は8割強、週1回以上飲用者は3割弱。飲用者は過去調査より減少傾向。飲用意向は全体の6割強で、男性の方が高い傾向。
■スポーツ・機能性飲料を飲む場面は「汗をかいた時」「のどが渇いた時」がトップ2で、「脱水症状を防ぎたい時」「スポーツをしている時」「スポーツの後」「お風呂あがりの時」が続く。VAAM主飲用者、アミノバリュー主飲用者、アミノバイタルボディリフレッシュ主飲用者などではスポーツ時や前後に飲む人が多い。
■スポーツ・機能性飲料購入場所は「スーパー」が最も多く、「コンビニエンスストア」「ドラッグストア」「自動販売機」の順で続く。「コンビニエンスストア」「自動販売機」は男性、「スーパー」「ドラッグストア」は女性の方が多い。
■スポーツ・機能性飲料購入時の重視点は「味」「価格」の他、「機能・効果」「飲み慣れている」「カロリー」「成分」「容量、サイズ」「糖分、甘さ」などが多い
-
- 調査時期:
- 2013年09月
- 設問項目:
-
発泡酒飲用頻度/知っている発泡酒の銘柄/直近1年以内に飲んだ発泡酒/直近1年以内に最もよく飲んだ発泡酒/発泡酒購入時の重視点/発泡酒飲用意向/今後飲みたい発泡酒/今後飲みたい発泡酒の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■発泡酒飲用者は半数弱、週1回以上飲用者は2割強。過去調査と比べ減少傾向
■直近1年以内に飲んだ発泡酒は「麒麟淡麗〈生〉」がトップ、「淡麗グリーンラベル」「スタイルフリー」などが続く。女性20・30代では「淡麗グリーンラベル」が1位
■発泡酒購入時の重視点は「味」「価格」の他、「飲みやすさ」「のどごし」「ビールに近い」などが上位
■アルコール飲用者のうち、発泡酒飲用意向者は4割弱。20代では非飲用意向者が4割強で、飲用意向者より多い。
-
- 調査時期:
- 2013年08月
- 設問項目:
-
今年の夏の節電意識/節電対策として今年夏に家で行っていること/今夏、節電・暑さ対策のために購入した家電製品/勤め先で今年夏に実施している節電対策/スマートハウスの認知/家庭の消費電力見える化システム導入状況/熱中症対策のために飲食しているもの/節電・暑さ対策のために実施していることのうち効果があるもの
- 結果概要:
-
■今年の夏、節電を意識している人は6割弱で、2011年・2012年調査時より減少傾向。今夏節電・暑さ対策のために購入した家電製品がある人は3割弱で、2012年調査より減少
■今年夏に家で行っている節電対策は「エアコンの使用時間・設定温度などを工夫」「エアコンをなるべく使わない」「照明をなるべく使わない」「日差しを遮る工夫」の順で多い。2011年調査に比べ全体的に比率が低下し、「エアコンをなるべく使わない」「家電製品を使わないときは本体の主電源を切る」などは2011年調査より15ポイント以上減少
■勤め先で今年夏に実施している節電対策は「使わない部屋・時間帯は照明や空調を消す」「照明を間引きする」「エアコン・空調の設定を28度以上にする」などが、2011・2012年調査時より減少
■スマートハウス認知率は6割強。家庭の消費電力見える化システムを「導入している」は約2%、「具体的な予定はないが、導入してみたい」は4割強
-
- 調査時期:
- 2013年08月
- 設問項目:
-
英語力の必要性/自主的な英語の学習状況/英語学習をしている理由/英語学習方法/英語学習にかけるお金(1ヶ月あたり)/英語学習意向/英語学習方法の意向/英語力の必要性の理由
- 結果概要:
-
■英語力の必要性を感じる人は6割弱。自主的に「現在英語を学習している」は全体の8.3%、10代では5割、30代以上では1割以下。「以前学習していたが、現在は学習していない」は4割弱。「学習したことはない」は半数強。
■英語を学習している理由の上位は、「自己啓発、習い事として」「海外旅行に行く」「仕事で必要になった」など
■英語学習者の、英語学習方法は「参考書」の他、「英語の書籍や新聞・雑誌を読む」「テレビの英語講座」「ラジオの英語講座」「英語の映画・DVDを字幕なしで観る」などが続く。
■英語学習意向がある人は4割弱。女性や若年層で多い。学習方法の意向は「英会話スクール」が最も多く、「テレビの英語講座」「カセット・CD教材を使った通信講座」「英語学習ソフト」「個人レッスン、家庭教師」「英語の映画・DVDを字幕なしで観る」などが続く
-
- 調査時期:
- 2013年08月
- 設問項目:
-
記念日のこだわり度/あなたにとっての記念日/記念日に飲食する場所/記念日に飲むもの/記念日に特別なことをするかどうか/最も盛大に行う記念日/記念日に特別なことをする理由/記念日に関する意識・行動/最も盛大に祝う記念日にすること(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■記念日にこだわる人は全体の約3分の1。こだわる人は女性の方が多い。自分にとっての記念日は「家族の誕生日」「自分の誕生日」「自分の結婚記念日」が上位。
■記念日に飲食する場所は「家で、特別な食事を作る」が最も多く、「いつもよりちょっと高級な飲食店に行く」「普段は買わないようなものを買って、家で飲食する」「普段も利用するような飲食店に行く」などが続く。飲む物は「ワイン」「ビール」「ノンアルコール飲料」など。
■記念日にすることは「ケーキを食べる」が最も多く、「家で特別な食事をする」「外食」「プレゼント」などが続く。友人・知人の誕生日や恋人の誕生日は「プレゼント」、自分の結婚記念日は「外食」、恋人とつきあい始めた記念日は「一緒に過ごす」が最も多い
■記念日に特別なことをする理由は「相手に喜んでもらいたい」の他、「感謝・好意・ねぎらいなどの気持ちを伝えたい」「喜びを共有したい」などが上位。女性30代以下では「思い出に残る日にしたい」が他の年代より多い
-
- 調査時期:
- 2013年08月
- 設問項目:
-
世界遺産への関心度/世界遺産に対する態度/世界遺産登録先の認知/訪問したことがある世界遺産/世界遺産登録がきっかけ・理由で訪問したところ/今後訪問したい世界遺産/世界遺産に登録されて欲しいもの/世界遺産に登録して欲しいと思う場所(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■世界遺産に関心がある人は半数強。「世界遺産への登録で、観光客増加による環境悪化等が心配」「世界遺産登録は地域活性化につながると思う」が各2~3割
■世界遺産登録先の認知率は「富士山」が8割。その他「原爆ドーム」「屋久島」「厳島神社」「知床」などが各6~7割にのぼる。
■日本の世界遺産訪問経験者は全体の8割強。いずれかの世界遺産認知者の訪問経験上位は「古都京都の文化財」「古都奈良の文化財」「原爆ドーム」「日光の社寺」「法隆寺地域の仏教建造物」「厳島神社」など。世界遺産登録がきっかけ・理由で訪問したところがある人は全体の2割弱
■今後訪問したい世界遺産は「屋久島」が最も多く、「知床」「小笠原諸島」「厳島神社」などが続く。世界遺産に登録されて欲しいのは全体では「古都鎌倉の寺院・神社」「奄美・琉球」が上位。いずれも地域により傾向が異なる。
-
- 調査時期:
- 2013年08月
- 設問項目:
-
飛行機利用頻度/利用したことがある航空会社/航空会社選定時の重視点/「サービスがよい」と思う航空会社/「安全性がある」と思う航空会社/「価格が手頃・リーズナブル」と思う航空会社/今後利用したい航空会社/飛行機でよかったと思うサービス(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■これまでに飛行機を利用したことがある人は9割弱。利用経験上位2位は「全日空(ANA)」「日本航空(JAL)」。以下「ユナイテッド航空」「大韓航空」「シンガポール航空」「キャセイパシフィック航空」「スカイマーク」などが続く
■飛行機利用経験者の、航空会社選定時の重視点は「信頼性・安全性がある」がトップ、「目的地への直行便がある」「価格が手頃・リーズナブル」「運行スケジュールが利用しやすい」が続く
■『サービスがよい』『安全性がある』『今後利用したい』と思う航空会社は、「全日空(ANA)」「日本航空(JAL)」が上位2位。「日本航空(JAL)」は2010年調査時に比べ比率が増加。利用したい航空会社の3位以下は「ピーチ・アビエーション」「シンガポール航空」「スカイマーク」など
■価格が手頃・リーズナブルと思う航空会社は、「ピーチ・アビエーション」が最も多く、「スカイマーク」「ジェットスター・ジャパン」「エア・ドゥ(AIRDO)」「エア・アジア・ジャパン」「スターフライヤー」などLCC各社が上位。
-
- 調査時期:
- 2013年08月
- 設問項目:
-
高級ブランドの認知/勢いがあると感じる高級ブランド/所有している高級ブランド/所有しているブランド品のアイテム/最もお気に入りのブランド品の銘柄/高級ブランド品の購入頻度/2013年に購入した高級ブランドのアイテム/2013年に、高級ブランドを購入した場所/高級ブランドの購入理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■所有高級ブランドは「コーチ」「ルイ・ヴィトン」「バーバリー」「グッチ」が上位。過去調査に比べ「コーチ」は増加傾向、「ルイ・ヴィトン」「バーバリー」「グッチ」などは減少傾向。所有アイテムは「バッグ類」「財布」の他、「ファッション小物」「その他小物」「ジュエリー、アクセサリー」など
■ブランド品所有者の一番お気に入りのブランドは全体では「ルイ・ヴィトン」「コーチ」「バーバリー」「グッチ」などが上位。男性では「バーバリー」「ルイ・ヴィトン」「ダンヒル」「グッチ」「コーチ」などが上位
■高級ブランドで『勢いがある』と感じる上位ブランドは「コーチ」「ルイ・ヴィトン」「エルメス」「グッチ」。以下「マーク・ジェイコブス」「クロエ」「ミュウミュウ」など、認知率が低いブランドが続く
■高級ブランド品の購入者は全体の6割弱、男性は5割、女性は7割弱。2013年購入者は2割強。購入頻度は「2~3年に1回」が1割強、「それ以下」が4割弱。「ブランド直営の百貨店内のショップ」で購入した人が最も多く、「アウトレット」「海外のショップ」「ブランド直営の路面店」などが続く
-
- 調査時期:
- 2013年08月
- 設問項目:
-
自動車保険の加入状況/自動車保険に加入している保険会社/自動車保険について、最も多く保険料を支払っている保険会社/加入自動車保険会社の満足度/自動車保険加入時に参考にした情報源/自動車保険(任意保険)の加入経路/自動車保険契約先の見直し意向/今後自動車保険に加入(更新)したい保険会社/今後自動車保険に加入(更新)したい保険会社を選んだ理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■自動車保険(任意保険)加入率は7割強。契約先見直し意向は4割弱。加入自動車保険会社は「東京海上日動火災保険」がトップ、「損保ジャパン」「SBI損保」「あいおいニッセイ同和損保」などが続く
■自動車保険加入時の参考情報源は「家族・親戚・友人・知人のクチコミ」「保険商品を扱ったホームページや保険商品の比較サイト」が上位2位。
■自動車保険の加入経路は「パソコンからインターネット経由で加入」が最も多く、過去調査より増加傾向。特にSBI損保加入者、三井ダイレクト損保加入者、イーデザイン損保加入者などで高い。以下「保険代理店経由」「自動車を購入したディーラーで」「友人・親族を通じて」の順で続く
■今後の加入意向の上位は「東京海上日動火災保険」「ソニー損保」「SBI損保」「損保ジャパン」「三井ダイレクト損保」など。主加入自動車保険の継続加入意向は、ソニー損保加入者、全労済加入者、アメリカンホーム・ダイレクト加入者、AIU保険加入者などで他の層より高い
-
- 調査時期:
- 2013年08月
- 設問項目:
-
株式売買の経験/インターネットでの株式売買の経験/インターネット取引経験がある証券会社/主にインターネット取引をしている証券会社/主にインターネット取引をしている証券会社の満足度/ネット取引による直近1年間の投資資金の増減 /ネットでの株式売買の意向 /ネットでの証券取引時の重視点/主にインターネット取引をしている証券会社の利用理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■インターネットでの株式売買経験者は25.2%。「現在も売買をしている」は18.1%。現在株式売買をしている人のうち、9割近くがインターネットで株式売買をしている
■インターネット取引経験がある証券会社は「SBI証券」がトップで、「楽天証券」「マネックス証券」「松井証券」「野村證券」が続く。「満足」の比率が高いのは、松井証券主利用者、SBI証券主利用者、カブドットコム証券主利用者など
■直近1年間のネット取引による投資資金が増加したのは、ネットでの株式売買経験者の4割強で、2012年調査(1割強)と比べ大幅増
■ネットでの株式売買意向は2割強。株式売買意向者の重視点は「取引手数料が安い」がトップで「手続が簡単」「セキュリティ」が続く。ネットでの株式売買実施者では「取引ツールが使いやすい」「セキュリティ」「システムが安定」、ネットでの株式売買未経験者では「手続が簡単」が多い
-
- 調査時期:
- 2013年08月
- 設問項目:
-
飲食店情報を調べる際の情報媒体利用頻度/飲食店情報を調べる際の情報源/飲食店情報を調べる際に利用するサイト・アプリ/飲食店情報を調べる際最もよく利用するサイト・アプリ/飲食店情報サイト・アプリ選定時の重視点/飲食店情報サイト・アプリの利用目的/飲食店情報サイト・アプリで利用する情報・機能/飲食店関連情報入手先/飲食店情報を調べる際最もよく利用するサイト・アプリの利用理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■飲食店情報を調べる際の情報源は「パソコンのインターネットサイト」が最も多い。「紙媒体情報」は過去調査に比べ減少。スマートフォンのインターネットサイトやアプリは女性や若年層で多く、過去調査に比べ増加
■パソコン・携帯端末で飲食店情報を調べる際に利用するサイト・アプリの1位は「ぐるなび」で7割弱。2位「食べログ」が半数弱で過去調査に比べ増加傾向。
■飲食店情報サイト・アプリ選定時の重視点は「登録店舗数の多さ」「検索方法のわかりやすさ」「割引クーポンなどの特典の多さ」「口コミ件数の多さ」「店に関する情報の豊富さ」「ページ・情報の見やすさ」など。食べログ主利用者は口コミ件数の多さや信頼性、ホットペッパーグルメ主利用者は特典の多さを重視する人が多い
■サイト・アプリ利用シーンは「条件にあう店を探す」「食べたいメニューのある店を探す」「出かけたことのない地域にある店を探す」「店の場所を知りたい」が上位。食べログ主利用者は「出かけたことのない地域にある店を探す」「お店の評価を知りたい」、ホットペッパーグルメ主利用者は「クーポンを利用できる店を探す」などが多い
-
- 調査時期:
- 2013年08月
- 設問項目:
-
運転免許保有状況/オートバイ所有状況/所有オートバイのメーカー/オートバイ運転頻度/オートバイの利用用途/オートバイ利用時のナビゲーションシステム利用状況/オートバイ非所有理由/オートバイ所有に対する興味度/乗ってみたいバイク・好きなバイク(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■「原付免許」保有者は2割弱、「普通二輪免許」が1割弱。オートバイ免許保有者は男性30・40代で多い。オートバイ所有者は全体の8.7%、男性12.9%、女性4.7%。「原動機付き自転車」所有者は5.3%、「自動二輪車 中型」が1.8%
■オートバイの利用用途は「ショッピング」が最も多く、「気分転換」「通勤・通学(職場・学校まで)」「ツーリング」などが続く。男性は「気分転換」「ツーリング」、女性は「ショッピング」が多い
■オートバイ非所有理由は「興味がない」「オートバイを使う必要がない」「自動車の方がいい」「免許を持っていない」「危険、事故が心配」などが上位
■オートバイ所有に興味がない人が7割強。興味がある人は全体の2割弱、男性の2割強、女性の1割弱。男性30・40代や、女性若年層で比較的多い傾向。自動車を含む運転免許所有者では2割弱
-
- 調査時期:
- 2013年08月
- 設問項目:
-
部屋・部屋の中で気になるにおい/室内用消臭・芳香剤の使用状況/使用している消臭・芳香剤/最も気に入っている消臭・芳香剤/室内用消臭・芳香剤の形状/室内用消臭・芳香剤の使用場所/室内用消臭・芳香剤選定時の重視点/室内用消臭・芳香剤の不満点/あったらよいと思う消臭・芳香剤(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■室内用消臭・芳香剤使用率は6割弱。女性や50代以上の使用率が高い。使用場所は「トイレ」「玄関、くつ箱」「居間、リビング」「寝室」が上位
■使用している消臭・芳香剤は「ファブリーズ」「消臭力」が上位2位、「消臭元」「リセッシュ」などが続く。
■部屋用消臭・芳香剤選定時の重視点は「好きな香り」がトップで、「価格」を10ポイント上回る。「効果が持続する」「消臭力が強い」「香りの強さ」なども上位
■室内用消臭・芳香剤の不満点の上位2位は「消臭力の持続性」「香りの持続性」。「価格」「消臭力の弱さ」「香りが人工的・化学的」などが続く
-
- 調査時期:
- 2013年08月
- 設問項目:
-
水筒利用頻度/主利用水筒のタイプ/水筒に入れるものの準備方法/水筒に入れているもの/水筒利用理由/水筒利用場面/水筒購入時の重視点/水筒の不満点(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■水筒利用者は半数強。女性や10代で多い。「ほとんど毎日」「週に4~5日」が各1~2割。「直飲みタイプの水筒」が水筒利用者の6割弱、「ボトルタイプ、マグタイプ」「コップつき水筒」が各2割
■水筒に入れるものは「自宅で作った・用意したもの」が水筒利用者の8割強、「購入した市販の飲料を入れる」は3割弱。「麦茶」「日本茶」が上位2位で「コーヒー」「ミネラルウォーター」「スポーツドリンク」「中国茶」などが続く
■水筒利用理由は「節約のため」「まめに水分補給をしたい」「いつも冷たい・温かいものを飲みたい」が上位3位。水筒利用場面は「学校や職場で」が最も多く、「長時間外出するとき」「旅行、ドライブ」「アウトドアレジャー」が続く
■自分や家族が使う水筒購入時の重視点を全員にたずねたところ、「容量」「価格」「軽さ」「大きさ」の順で多い
-
- 調査時期:
- 2013年08月
- 設問項目:
-
床面掃除をする際に使う掃除用具/掃除機で掃除をする頻度/所有掃除機のタイプ/所有掃除機のメーカー/掃除機購入時の重視点/今後購入したい掃除機/住居形態/最も購入したいメーカーの理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■掃除機を使って掃除をする人は全体の8割強、そのうち週1回以上掃除をする人は7割強。アイロボット主利用者では他の層よりも掃除頻度が高い傾向
■「ノーマルタイプ・紙パック式」所有者は6割弱、「ノーマルタイプ・サイクロン」が4割弱、「ロボット掃除機」は4%。
■掃除機購入時の重視点は「本体価格」「吸引力」「本体の大きさ・重さ」「ゴミの捨てやすさ」などが上位。パナソニック所有者やアイロボット所有者では「メーカー・ブランド」、ダイソンやミーレは「吸引力」「空気が汚れない、ホコリが飛びにくい」などを重視
■今後購入したい掃除機は「ダイソン」がトップ、2位が「パナソニック」。ダイソン所有者、アイロボット所有者は継続購入意向が高い
-
- 調査時期:
- 2013年08月
- 設問項目:
-
料理をする頻度/調味料に対するこだわり度/自宅にある調味料の種類/よく使用する調味料/こだわりがある調味料/最も好きな調味料/料理の味付けで気をつけていること/何かと重宝する調味料(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■調味料に対するこだわりがある人は3割強、こだわりがない人は4割弱。女性、特に年代が高いほど、こだわりがある人が多い傾向。
■自宅にある調味料の種類は「塩」「しょうゆ」「こしょう」「砂糖」「味噌」「マヨネーズ」「ソース」などさまざま。「塩麹」「コチュジャン」「タバスコ、チリソース」などは各2~3割。
■よく使用する調味料上位3位は「塩」「しょうゆ」「こしょう」。「砂糖」「味噌」が6割弱、「マヨネーズ」「みりん」「めんつゆ」「だしの素、液体だし(和風)」「料理酒」などが続く。「ソース」「ケチャップ」「酢」などは、家にある調味料よりも順位を下げている
■こだわりがある調味料がある人は半数強。「しょうゆ」「塩」「味噌」が上位3位。「しょうゆ」は九州、「ぽん酢」は近畿でやや多い。最も好きな調味料は「しょうゆ」「塩」「ぽん酢」「マヨネーズ」「めんつゆ」の順で多い。
-
- 調査時期:
- 2013年08月
- 設問項目:
-
カレーを食べる頻度/カレーの準備方法/よく使うカレー・ルウ/最もよく使うカレー・ルウ/市販のカレー・ルウ購入時の重視点/カレーを自分で作る頻度/カレーを作る理由/カレーを作るときの工夫・こだわり(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■カレーを食べる頻度は「月に2~3回程度」「月に1回程度」がボリュームゾーン。「自宅で作ったカレー」が9割弱、「レトルトカレー」が5割弱、「外食」が3割弱
■自宅で作ったカレーを食べる人では、「こくまろカレー」「2段熟カレー」「バーモントカレー」を使う人が多い。
■市販のカレー・ルウ購入時の重視点は「味」「価格」の他、「辛さ」「こく」「香り」「メーカー」「容量、サイズ」などが多い。こくまろカレー主利用者、2段熟カレー主利用者、とろけるカレー主利用者などでは味よりも「価格」を重視
■カレーを自分で作る人は全体の約4分の3で、男性20代以上で4~5割、女性30代以上で9割弱。カレーを作る理由は「カレーを食べたい」「簡単に作れる」が上位2位で「作り置きできる」「みんなが好きなメニュー」「野菜をたくさんとれる」「時間がたってもおいしい」などが続く
-
- 調査時期:
- 2013年08月
- 設問項目:
-
夏に飲む飲み物の量(1日あたり)/夏によく飲む飲み物/夏の定番の飲み物/夏に飲む物に期待すること/夏における、常温での飲用状況/夏に常温で飲む飲み物/夏に常温で飲む理由/夏にホットで飲む飲み物/夏の定番の飲み物の飲み方(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■夏によく飲む飲み物の上位2位は「麦茶」「コーヒー、コーヒー飲料」。「緑茶」「ミネラルウォーター、水」「ビール類」などが続く。夏に飲む定番の飲み物は「麦茶」「ビール類」などが上位
■夏に飲む物に期待することは「冷たい」「のどの渇きをいやす」が上位2位。「スッキリしている」「脱水症状を防ぐ」「のどごしが良い」「リフレッシュ、気分転換できる」などが続く。
■夏に常温で飲むことがある人は全体の4割弱。常温で飲むことがあるものは、「ミネラルウォーター、水」「緑茶」「麦茶」などが上位
■夏にホットで飲む飲み物は「コーヒー、コーヒー飲料」が最も多く、「緑茶」「紅茶、紅茶飲料」などが続く。夏にホットで飲む物がある人は高年代層ほど多い。
-
- 調査時期:
- 2013年08月
- 設問項目:
-
市販の果汁入り飲料の飲用頻度/直近1年間に飲んだ果汁入り飲料/直近1年間の最頻飲用果汁入り飲料/果汁入り飲料飲用場面/果汁入り飲料選定時の重視点/果汁入り飲料に期待すること/果汁入り飲料でよく飲むサイズ/果汁入り飲料の不満点(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■果汁入り飲料飲用者は8割弱で過去調査に比べ減少傾向。週1回以上飲用者は3割弱。直近1年間に飲んだ銘柄の上位は「なっちゃん」「トロピカーナ」「バヤリース」
■果汁入り飲料の飲用場面は「のどが渇いたとき」「おやつの時」「くつろいでいるとき」「朝食時」「お風呂あがり」などなどが上位
■果汁入り飲料選択時の重視点は「味の好み・おいしさ」「価格」の他「入っている果実の種類」「果汁の濃度」などが多い。ウェルチ、POM ポンジュースなどの主飲用者では、価格より「果汁の濃度」を重視する人の方が多い
■果汁入り飲料飲用者の、果汁入り飲料への期待の上位は「健康によい」「果汁100%」「ビタミンなどの栄養素が摂取できる」など。10代は「ごくごく飲める」を期待。