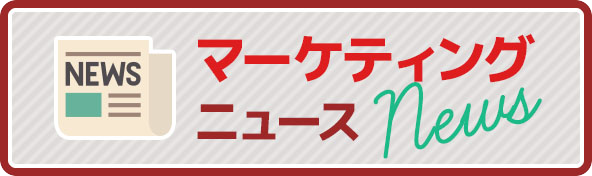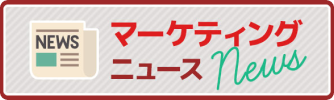- 検索
-
- テーマ別実施時期一覧
- カテゴリー別一覧
-
-
アルコール飲料・嗜好品147
-
非アルコール飲料210
-
その他19
-
-
住宅・住宅設備219
-
-
家電126
-
パソコン・カメラ・AV機器113
-
その他10
-
-
家庭用品・トイレタリー91
-
自動車・関連用品76
-
-
インターネット・情報通信328
-
携帯電話・スマートフォン180
-
メディア・広告66
-
その他7
-
-
ファッション69
-
交通・レジャー・娯楽161
-
季節行事・イベント241
-
時事・ニュース・トレンド51
-
企業ブランドイメージ250
-
広告・CM51
-
WEBサイトの利用91
-
顧客満足度100
- 実施時期別一覧
-
- 調査時期:
- 2023年07月
- 設問項目:
-
環境問題への関心度/使い捨てプラスチック製品の利用についての意識度/利用する使い捨てプラスチック製品/使い捨てプラスチック製品であった方がよいと思うもの/使い捨てプラスチック製品に関して実施していること/レジ袋有料化で不便に感じる度合い/レジ袋有料化後の、プラスチックごみ削減の意識度合いの変化/環境問題の意識・行動の直近3年間での変化/使い捨てプラスチック製品に関して意識していることや取り組み(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■使い捨てのプラスチック製品利用を意識する人は6割弱。女性や高年代層で■使い捨てのプラスチック製品利用を意識する人は6割弱。女性や高年代層で高い傾向。使い捨てプラスチック製品に関する実施内容は「エコバッグ・マイバッグを使う」「有料レジ袋は買わない」が各60%台、「詰め替え用を買う」が約45%、「プラスチックのゴミを分別、洗浄し、リサイクルできるようにする」「プラスチック製のスプーン・フォーク、ストローなどはもらわない」「水筒を使う」が各30%台。
■使い捨てのプラスチック製品や容器で普段使う・もらうものは「ペットボトル」が7割強、「食品トレイ」「プラスチック製の容器・袋の商品」が各60%台、「無料のポリ袋」が約55%。
■使い捨てのプラスチック製品のうち、あった方がよいと思うものは「ペットボトル」が5割強、「無料のポリ袋」が4割強、「食品トレイ」「無料レジ袋」が各3割強。レジ袋有料化で不便に感じる・感じない人は、いずれも4割強。
■2020年7月のレジ袋有料化以降のプラスチックごみ削減意識は「以前から意識しており、より意識するようになった」が3割弱、「以前はあまり意識していなかったが、意識するようになった」は約35%、「以前からあまり意識しておらず、あまり変化はない」は2割強。環境問題に関する意識や変化で3年前と比べて「ゴミの分別やリサイクルの意識が高まった」が3割強、「ゴミを減らす意識が高まった」が約25%。
-
- 調査時期:
- 2023年07月
- 設問項目:
-
父の日での立場/父の日にしたこと/今年の父の日のためにかけた費用総額/今年の父の日のプレゼントや行ったことの準備をした日/父の日に贈ったプレゼント/父の日のプレゼント購入場所/父の日にほしいプレゼントやしてほしいこと/あなたにとって父の日とは/今年の父の日のプレゼント選定時のこだわりや重視ポイント(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■父の日に関して何かした人は、全体の3割弱(何かしてあげる立場の人のうち6割弱)。父の日に「プレゼントを購入して贈った」は全体の約16%、「一緒に家で食事をした」が5%。
■父の日に贈ったプレゼントは「酒」「食品(お菓子以外)」が、プレゼントを贈った人の各24~25%、「衣料品」「お菓子」が2割弱。「インターネットショップ」での購入者は4割弱。「総合スーパー」での購入者は過去調査と比べ減少傾向。
■父の日にほしいプレゼントやしてほしいことは「酒」「一緒に外食をする」「衣料品」「感謝の気持ち」などが、何かしてもらう立場の人の各10%台。
■父の日とは「父をいたわる・苦労をねぎらう日」が3割強、「親孝行・恩返しをする日」「感謝の気持ちを伝える日」などが各2割前後。「必要ない」は全体の2割弱。
-
- 調査時期:
- 2023年07月
- 設問項目:
-
ムダ毛が気になる度合/ムダ毛処理の頻度/ムダ毛処理を行っている部位/ムダ毛処理の方法/直近5年以内の、脱毛サロン等での脱毛・ムダ毛処理経験/脱毛・ムダ毛処理での利用店舗選定時の参考情報/脱毛処理の意向・脱毛処理をしたい部位/脱毛処理をしたい理由/専門機関での脱毛・ムダ毛処理意向/ムダ毛処理・脱毛に関して困ること・悩み/ムダ毛に関して気になること(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■ムダ毛が気になる人は全体の3割強。ムダ毛処理実施者は全体の5割弱、女性7割強、男性性3割強。週1回以上実施者はムダ毛処理実施者の4割強で、女性や若年層での比率が高い。
■ムダ毛処理実施者の処理部位は「顔」が5割強、「ワキ」「脚」が各40%台、「鼻毛」が4割弱。2020年調査と比べ「VIO」などが増加、「ワキ」などが減少。男性30~50代では「鼻毛」「ヒゲ」「顔」、女性10~30代では「ワキ」「腕」「脚」が上位3位。現在のムダ毛処理方法は「カミソリ」が実施者の6割弱、「毛抜き」が3割強。
■脱毛サロン等での脱毛・ムダ毛処理直近5年以内実施者は約6%、経験者は15%。「脱毛サロン、エステサロン」5年以内利用経験者は全体の約4%、女性10~30代で各2割前後。店舗選定時の参考情報は「店舗の公式ホームページ」が2割強、「美容や脱毛などに関する情報サイト」「テレビ番組・CM」「口コミサイト」「家族や友人、知人」などが各2割弱。
■今後の脱毛処理意向者は全体の約36%、男性3割弱、女性5割弱。男性10~40代では「ヒゲ」「脚」が上位2位(男性30代では「脚」「VIO」が同率2位)。女性10~30代では「ワキ」が5割弱、「腕」「脚」が各4割前後。脱毛処理意向者の理由は「毛深い」「つるつるな肌になりたい」「除毛処理の場合、継続するのが面倒」「衛生的」などが各20%台。
-
- 調査時期:
- 2023年07月
- 設問項目:
-
体型意識/ダイエット経験/ダイエットの理由/リバウンドの経験/ダイエット方法/ダイエットをやめた理由/ダイエットに関する情報源/比較的うまくいったダイエット方法/直近のダイエット方法に決めた理由・過程(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■現在ダイエットをしている人は全体の2割弱、過去にしたことがある人(4割弱)をあわせた経験者は6割弱。ダイエット経験者のうち、リバウンド経験者は7割強、「1~2回ある」は4割弱。
■ダイエットをしようと思った理由は「体型・スタイルを良くする」「健康状態を改善」が経験者の各5割前後、「生活習慣病予防」「体型・スタイルの変化を感じた」が各3割弱。男性50~70代では「健康状態を改善」「生活習慣病を予防」「健康診断の結果が気になった」などの比率が高い。
■現在行っているダイエット方法は「食事制限」が5割強、「間食・おやつの制限」「ウォーキング、散歩など」が各4割強、「食べ方に気を付ける」が3割強。ダイエットに関する情報源は「テレビ番組」が全体の3割強で過去調査と比べて減少。女性10~30代では「SNS」が1位。
■現在ダイエットを行っていない人の理由は「面倒くさくなった」が3割弱、「ダイエットが成功した」「ストレスがたまる」が各2割弱。
-
- 調査時期:
- 2023年07月
- 設問項目:
-
生命保険会社の認知/主加入生命保険/加入生命保険商品の種類/生命保険申込み方法/1か月あたりの生命保険料/生命保険加入・見直し時に、候補として検討した生命保険会社/生命保険に関する情報入手経路/加入したい生命保険会社/生命保険の加入・見直し意向/主加入生命保険の加入理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■生命保険加入者は全体の8割弱。生命保険申込み方法は「知り合いや紹介を受けた営業職員、保険外交員」が加入者の3割強、「自宅や勤務先に訪問してくる営業職員、保険外交員」が2割強。アクサダイレクト生命主加入者、チューリッヒ生命主加入者、楽天生命主加入者などでは「インターネットで申込み手続き」が1位。
■生命保険加入者のうち、加入時に他社を候補として検討した人は、生命保険加入者の4割弱。アクサダイレクト生命主加入者、チューリッヒ生命主加入者などでの比率が高い。
■生保関連の情報入手経路は「テレビ番組、CM」が3割強、「家族や友人、知人」「営業職員、保険外交員」「保険商品のパンフレット、説明資料」「保険を取り扱っている企業のホームページ」などが各10%台。
■生命保険の加入・見直し意向は、「現在加入の生命保険を継続」が3割弱、「現在加入の生命保険に追加して加入」が約4%。「生命保険には当面加入しない」は3割強。加入したい生命保険会社は、「県民共済」が約9%、「アフラック」が約7%。
-
- 調査時期:
- 2023年07月
- 設問項目:
-
テイクアウト・持ち帰りの直近1年間利用状況/食べ物のテイクアウトをする場面/食べ物のテイクアウトをする理由/食べ物のテイクアウトをする際の重視点/直近1年間でのテイクアウト利用頻度/直近1年間のテイクアウト店舗の認知経路/直近1年間のテイクアウト時のモバイルオーダー利用状況/今後の食べ物テイクアウト利用頻度の変化/食べ物テイクアウト利用時の不満/非利用理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■直近1年間のテイクアウト・持ち帰り利用者は6割強で2020年調査より減少。「ファストフード」が4割強、「牛丼、餃子、寿司、うどん・そば、カレーなどのチェーン店」が3割弱。直近1年間テイクアウト利用者のうち「休日・昼食」利用者が約45%、「休日・夕食」「平日・昼食」「平日・夕食」が各30%台。
■直近1年間テイクアウト利用者の理由は「家で、リラックスして食べたい」「食事の準備や片付けが面倒・時間がない」が各30%台、「食事を早く済ませたい」「出来立てを持ち帰って食べたい」などが約26~27%。重視点は「味が好み」が6割強、「店への近さ、アクセスの良さ」「持ち運びやすさ」「待たずに持ち帰れる」「食べやすさ」が各3割前後。
■直近1年間テイクアウト利用者が、食べ物をテイクアウトした店の認知経路は「以前その店で食べたことがある」が6割強、「店の前を通った・見かけた」が3割強、「店舗のホームページやアプリ」が約15%。
■直近1年間テイクアウト利用者の利用頻度は「月に1回以下」が6割弱。若年層での利用頻度が高い傾向。直近1年間テイクアウト利用者のうち、モバイルオーダー利用者は5割強、「ファストフード」でのモバイルオーダー利用者が3割弱。
-
- 調査時期:
- 2023年07月
- 設問項目:
-
イヤホン・ヘッドホン・ヘッドセットの利用状況/最もよく利用しているイヤホン・ヘッドホンのタイプ/主利用ワイヤレスイヤホン・ヘッドホン等のメーカー/ワイヤレスイヤホン・ヘッドホン等の接続機器/ワイヤレスイヤホン・ヘッドホン等で聴く音源/ワイヤレスイヤホン・ヘッドホン等の利用理由/ワイヤレスイヤホン・ヘッドホン・ヘッドセットの利用意向/ワイヤレスイヤホン・ヘッドホン・ヘッドセット利用意向者の重視点/ワイヤレスイヤホン・ヘッドホン・ヘッドセットの利用意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■イヤホン・ヘッドホン・ヘッドセット利用者は全体の6割弱。「完全ワイヤレスイヤホン」が2割弱で2021年調査より増加、ワイヤレスイヤホン・ヘッドホン等利用者は全体の3割弱。「イヤホン・有線」は4割弱。
■ワイヤレスイヤホン・ヘッドホン等利用者の接続機器は「スマートフォン」が8割弱で完全ワイヤレスイヤホン主利用者での比率が高い。「パソコン」との接続は3割強、「タブレット端末」「携帯音楽プレーヤー」が各10%台。「音楽」を聞く人が8割弱、「動画の音」が5割弱、「ラジオ」が2割強。
■ワイヤレスイヤホン・ヘッドホン等利用者の利用理由は「動いたり何かをしながらでも、コードが邪魔にならない」が6割強、「軽量でコンパクトなので持ち運びやすい」が3割弱、「運動時など、動いても耳から外れにくい」「ハンズフリー通話をする」「音源から離れて使う」が各2割弱。
■ワイヤレスイヤホン・ヘッドホン利用意向者は全体の4割強。若年層での比率が高く年代差が大きい。ワイヤレス以外主利用者では5割強の利用意向。利用意向者の重視点は「価格」が7割強、「音質」が6割弱、「フィット感」「耳から外れにくい」が各44~46%。
-
- 調査時期:
- 2023年07月
- 設問項目:
-
エアコン所有台数/エアコンの直近導入時期/主利用エアコンのメーカー/冷暖房以外の使用機能/エアコン購入時に重視する点/エアコンの購入・買い替え・買い増し予定時期/どのような機能がついたエアコンを購入したいか/エアコンの電気代節約に関して取り組んでいる・取り組みたいこと/主利用エアコンのメーカー選定理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■エアコン所有率は9割強。3台以上所有者は5割強、持ち家一戸建て居住者では7割弱。
■エアコン購入時の重視点は「価格」が7割弱、「ランニングコストの安さ」が5割強、「性能・パワー」「省エネ」「メーカー・ブランド」などが各40%台。
■冷暖房以外で使っている機能は「除湿」が所有者の5割強、「タイマー」「自動運転」が各20%台、「送風」が1割強。基本機能以外であったらよい機能は「自動掃除機能」が約46%、「内部乾燥」が35%、「除菌」「自動運転」「タイマー」などが各3割弱。
■エアコンの電気代節約に関して7月以降に取り組んでいる・取り組みたいことは「設定温度を高くする」「扇風機やサーキュレーターと併用する」「フィルターをこまめに掃除する」が各3割前後。
-
- 調査時期:
- 2023年07月
- 設問項目:
-
普段自分で行っている家事/平日の1日あたりの家事時間/平日の家事時間帯/休日の1日あたりの家事時間/休日の家事時間帯/できればもっと手間をかけたい家事/やらなくて済むならやりたくない家事/日常の家事を負担に感じる度合い/あなたにとって家事とは(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■普段行う家事は、男性の上位は「ゴミだし・分別」「食品の買い物」「日用品の買い物」「食後の食器を洗い場に運ぶ」「風呂掃除」などが各5割強~6割強。女性の上位は「食品の買い物」「日用品の買い物」「洗濯物をしまう」「洗濯物を干す」「料理、食事の支度」などで各9割前後。女性より男性の方が上位なのは「ゴミだし・分別」「風呂掃除」「掃除機をかける」など。
■できればもっと手間をかけたい家事は、全体では「室内の整理整頓」が2割強、「風呂掃除」「料理、食事の支度」「雑巾がけ、拭き掃除」などが各13~15%。過去調査と比べ「料理、食事の支度」などは減少傾向。
■やらなくて済むならやりたくない家事は「風呂掃除」「トイレ掃除」「アイロンをかける」「窓拭き」「台所の掃除」「料理、食事の支度」「雑巾がけ、拭き掃除」「食器洗い」などの掃除に関する項目が上位。
■日常の家事を負担に感じる層は男性3割弱、女性6割弱。1日あたり家事時間は、平日・休日ともに女性は2時間程度・3時間程度。男性は30分・1時間がボリュームゾーンで、女性の方が家事時間が長いことがうかがえる。平日家事をする時間帯は、夜が約55%、早朝・夕方が各4割前後。休日は、午前中が6割弱、夕方・夜が各4~5割。
-
- 調査時期:
- 2023年07月
- 設問項目:
-
利用している飲用水/家庭用ウォーターサーバーの利用実態/ウォーターサーバーを利用し始めたきっかけ/ウォーターサーバー非利用理由/ウォーターサーバーの利用中止理由/主利用家庭用ウォーターサーバーのタイプ/主利用家庭用ウォーターサーバー/主利用ウォーターサーバーの満足度/ウォーターサーバー利用意向/主利用ウォーターサーバーの選定理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■家庭用ウォーターサーバー利用経験者は全体の1割強、現在利用者は約5%。現在利用者のうち「ワンウェイ方式のボトル・パック」利用者が5割弱、「リターナブル方式のボトル」の2割強、「水道直結型」「水道水補充型」はそれぞれ約6%。
■利用のきっかけは、利用経験者では「無料お試し期間」が3割強、「店頭、街頭などでのキャンペーンやデモ」が2割強。現在利用者では「店頭、街頭などでのキャンペーンやデモ」が1位。
■非利用理由、利用中止理由とも「維持費がかかる」「設置スペースをとられる」が上位2位。水道水やミネラルウォーターなどで十分/満足の他、「ボトル交換や手入れ等が面倒」なども上位にあがっている。
■家庭用ウォーターサーバー利用意向者は全体の約8%。現在利用者では8割強、認知・利用未経験者では約3%。非利用意向者の比率は全体の約76%。水道水補充型主利用者では他の層より利用意向者の比率が高い。
-
- 調査時期:
- 2023年07月
- 設問項目:
-
低糖質の食品・飲料購入度合い/直近1年間低糖質麺利用状況/直近1年間に食べた市販の低糖質麺の種類/直近1年間に食べた市販の低糖質麺の材料/市販の低糖質麺を食べる理由/市販の低糖質麺利用意向/市販の低糖質麺で食べたい種類/市販の低糖質麺選定時の重視点/市販の低糖質麺利用意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■直近1年間に低糖質麺を食べた人は3割強、利用経験者は4割強。「カップ麺、インスタント食品の低糖質麺」が1割強、「低糖質麺を購入し自宅で調理」が約9%、「調理済みの低糖質麺を購入」が約7%。
■直近1年間に市販の低糖質麺利用者のうち、「こんにゃく、したらき」の低糖質麺を食べた人は約45%、「豆類、大豆」が4割弱。食べた人の理由は「健康維持のため」が6割弱、「麺類が好き・食べたいが糖質が気になる」が約26%、「ふだんから糖質の取りすぎが気になる」「体型・体重が気になる」が各2割強。
■市販の低糖質麺利用意向者は3割で、女性10~30代でやや高い。直近1年間低糖質麺利用者では6割弱、低糖質麺利用未経験者では約15%の利用意向。
■市販の低糖質麺利用意向者が食べたい種類は「カップラーメン」が6割弱、「パスタ」「袋麺のラーメンやチルドのラーメンなど」「うどん」が各5割弱。重視点は「普通の麺と変わらない味」が7割弱、「価格」が4割強、「原材料・成分、製法」「一食あたりの糖質の少なさ」「カロリー」が各30%台。
-
- 調査時期:
- 2023年07月
- 設問項目:
-
直近1年間に食べたシリアル食品/直近1年間に最もよく食べたシリアル食品/直近1年間にシリアル食品を食べた頻度/シリアル食品を食べる場面/シリアル食品の食べ方/シリアル食品を食べる理由/市販のシリアル食品購入時の重視点/シリアル食品の利用意向/シリアル食品利用意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■直近1年間にシリアル食品を食べた人は4割強、女性での比率が高い。「グラノーラ」が3割弱、「コーンフレーク」が2割弱。「オートミール」は約14%で2020年調査と比べて増加。シリアル食品利用意向は全体の約46%で2020年調査より増加。直近1年間利用者の利用意向は8~9割、利用中止者では24%、利用未経験者では約5%。
■直近1年間シリアル食品利用者のうち週1回以上食べる人は5割強で、2020年調査より増加。シリアル食品の食べ方は「冷たい牛乳を入れる」が直近1年間利用者の6割弱、「ヨーグルトを入れる」「そのまま食べる」が各20%台。
■シリアル食品を食べる場面は「朝食代わり」「朝食のメニューの1つ」「おやつ、間食」が、直近1年間シリアル食品利用者の各3~4割。食べる理由は「おいしい」が5割弱、「栄養バランスがよい」「食物繊維やビタミン、ミネラルなどが多い」が各4割弱、「手軽」が3割弱。
■市販のシリアル食品購入時の重視点は、「味」「価格」が各5~6割、「原材料」「栄養成分」「穀物・果物等の種類」「容量、サイズ」が各20%台。
-
- 調査時期:
- 2023年06月
- 設問項目:
-
新型コロナウイルスワクチンの接種回数/接種したことがある新型コロナウイルスワクチンの種類/新型コロナウイルスワクチン接種意向/新型コロナウイルスワクチンを接種したい理由/今後接種したい新型コロナウイルスワクチンの特徴/新型コロナウイルスワクチンを接種したいと思わない理由/新型コロナウイルスワクチン接種に対する不安/新型コロナウイルスに対する脅威度/新型コロナウイルス感染拡大によりやりたかったができなかったこと・今後やりたいこと(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■新型コロナウイルスワクチン接種者は全体の9割弱。接種回数は「3回」が2割強、「4回以上」が約55%。新型コロナウイルスについて「季節性インフルエンザ以上」と感じる人は全体の4割強、「季節性インフルエンザと同程度」が3割弱。
■新型コロナウイルスワクチン接種意向者4割・非意向者4割弱。接種意向者は男性や高年代層で高い傾向。10~50代では非接種意向者の方が多いが60~70代では接種意向者の方が多い。
■新型コロナウイルスワクチン接種意向者の理由は「自分自身の感染を予防し重症化や後遺症などのリスクを減らしたい」が9割弱、「家族や周りの人にうつしたくない」が6割強、「仕事や家事、育児など日常生活に支障が出ないようにしたい」「社会に感染が広がるのを防ぐ」「継続してワクチン接種をしてきた」が各3割弱。
■新型コロナウイルスワクチン非接種意向者の理由は「ワクチンの副反応がつらい、体に負担」「ワクチンの安全性に不安」が約44~46%、「効果がよくわからない」「副反応で生活に支障がでる」が各3割弱。新型コロナウイルスワクチン接種に不安を感じる人は全体の5割弱、不安を感じない人は約26%。
-
- 調査時期:
- 2023年06月
- 設問項目:
-
母の日での立場/母の日の実施状況/母の日に贈ったプレゼントの内容/母の日のプレゼント購入場所/プレゼント以外で母の日にしたこと/母の日にかけた費用総額/プレゼントを購入した時期/プレゼントしてほしいもの/プレゼントや何かをしたことの理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■母の日にプレゼントや何かをした人は約36%、してもらった人は約15%。母の日に何かをしてあげる立場の人で 『プレゼントや何かをした』は約55%。母の日にかけた費用総額は「3,000円~5,000円未満」がボリュームゾーン。
■今年の母の日にプレゼントしたものは「お菓子」「食品・飲料」「カーネーション以外の花・鉢植え・観葉植物」が各2割強、「カーネーション」「「衣料品、衣類小物」が各2割弱。購入場所は「インターネットショップ」が3割強で、2020年調査よりやや減少。
■プレゼントを贈る以外にしたことは、「一緒に家で食事」「会いに行った」が各19%、「一緒に外食をした」が1割強。2020年調査と比べ「会いに行った」「一緒に外食をした」などがやや増加。
■母の日に何かをしてもらう立場の人が、母の日にしてほしいもの・ことは「感謝の気持ち」「お菓子」「外食」が各2割強、「カーネーション以外の花・鉢植え・観葉植物」「食品・飲料」「一緒に家で食事」が各13~14%。
-
- 調査時期:
- 2023年06月
- 設問項目:
-
美容に対する関心度/美容のために意識していること/美容のために食生活で意識していること/美容について意識して行う理由/美容のために使っているアイテム/美容にかける費用(1ヶ月あたり)/直近1年間に利用したことがある美容関連サービス/美容に関して気になること/美容のために気を付けていること・こだわり(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■美容関心層は全体の約36%で女性は6割弱。男性は2割弱で男性10・20代では4割と高い。美容のために意識していることは「ウォーキングなど軽い運動」「食生活」「水分補給」「スキンケア・肌の手入れ(顔)」などが各3割前後。食生活を意識する人のうち「栄養バランス」「野菜を多くとる」を意識する人が各7割前後、「食べ過ぎない」が5割強、「寝る直前に食べない」「たんぱく質を意識してとる」「三食きちんと食べる」などが各4割弱。
■美容のために使うアイテムのうち、「洗顔料」「スキンケア用品」は女性で各70%台。男性10~30代では「洗顔料」が各4割前後、「スキンケア用品」が各25~26%で男性40代以上と比べて高い。
■美容関連サービスの直近1年間利用経験は女性では「美容室・ヘアサロン」が約76%。「理容院」は約25%で男性高年代層での比率が高い傾向。
■美容に関して気になることは「顔のくすみ、しみ、そばかす、毛穴など」「顔のしわ、たるみ、筋肉のゆるみなど」が各3割強、「体重」「肌の乾燥」「体型、スタイル」が各2割強。性別や年代により上位項目が異なっている。
-
- 調査時期:
- 2023年06月
- 設問項目:
-
株式の売買経験/証券会社の認知/現在取引している証券会社/主に取引している証券会社/信頼感や安心感があると思う証券会社/手数料が安いと思う証券会社/先進性があると思う証券会社/顧客対応がよいと思う証券会社/今後最も取引をしてみたい・継続したい証券会社/主に取引している証券会社のイメージ(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■現在取引先、利用意向ともに、「SBI証券」「楽天証券」「野村證券」などが上位。証券会社認知率は「野村證券」「大和証券」「SBI証券」「楽天証券」「松井証券」「岡三証券」などが上位。
■『信頼性や安心感がある』『顧客対応がよい』のは「野村證券」「大和証券」「SBI証券」「楽天証券」などが上位。『顧客対応がよい』は「いずれもない」が7割弱と高い。
■『手数料が安い』は、「楽天証券」「SBI証券」が各2割強、「GMOクリック証券」が約8%。「いずれもない」が5割強。
■『先進性がある』のは「SBI証券」「楽天証券」が各10%台、「GMOクリック証券」が7%、「マネックス証券」「野村證券」が各5%。「いずれもない」が6割弱。
-
- 調査時期:
- 2023年06月
- 設問項目:
-
衣料品の購入頻度/直近1年間の衣料品購入場所/直近1年間の衣料品最頻購入場所/直近1年間での、1ヶ月あたりの衣料品購入金額/衣料品を購入する店舗を選ぶ際の重視点/インターネットで衣料品を購入する場面/衣料品購入時の参考情報/衣料品最頻購入場所での購入理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■衣料品の購入頻度は「3~4ヶ月に1回程度」「半年に1回程度」がボリュームゾーン。過去調査と比べ購入頻度が減少傾向。1ヶ月あたりの平均購入金額は「1000円~3000円未満」「3000円~5000円未満」がボリュームゾーン。
■衣料品購入者の直近1年間の購入場所は「衣料量販店」が約45%、「ショッピングセンター」「インターネットショップ」が各4割弱、「スーパー」が3割弱。2018年調査以降「スーパー」「百貨店・デパート」などが減少傾向。女性10~40代では「ショッピングセンター・モール」「インターネットショップ」が上位2位。
■直近1年間衣料品購入者の店舗での購入時の重視点は「品揃えが豊富」「値段が安い」が各40%台、「好みに合ったコンセプト・テイスト」「商品が探しやすい・見やすい」が各30%台。購入時の参考情報は「店頭の商品、商品情報」「店頭のディスプレイ、マネキン」などの店頭情報が各20%台、「通販サイト・オンラインショップの商品紹介・レビュー」「メーカーや店舗の公式ホームページ」などのネットの情報や「折込チラシ、ダイレクトメール」などが各2割弱。
■インターネットでの衣料品購入者の理由は「セールなどで割安で購入できる」「店頭よりも価格が安い」が各3割強、「たまたま欲しいものを見つけた」「店に行けない・行くのが面倒」「色やサイズ等がわかっているものを買う」などが各3割弱。
-
- 調査時期:
- 2023年06月
- 設問項目:
-
ポイントサービスを利用している店舗・施設・サービス/ポイントサービス利用個数/直近1年間ポイントを使ったことがあるサービス/ポイントカードアプリの利用/直近1年間の共通ポイントサービス利用状況/直近1年間の最頻利用共通ポイントサービス/ポイントカードのポイント利用度合い/ポイントサービスに関する行動/最頻利用共通ポイントサービスの利用理由/共有ポイント非利用理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■直近1年間ポイントサービス利用店舗・サービスは「スーパーマーケット」「ドラッグストア」「コンビニエンスストア」が各6~7割、「クレジットカード」「オンラインショップ」が各5割前後。過去調査と比べ「オンラインショップ」「ファストフード店」などが増加傾向、「家電量販店」などが減少傾向。
■スマートフォンのポイントカードアプリ利用者は、直近1年間ポイントサービス利用者の7割強で2019年調査以降増加傾向。「共通ポイントサービスの公式アプリ」が6割強、「店舗独自のポイントの公式アプリなど」は約35%。
■直近1年間に利用した共通ポイントサービスは「楽天ポイント」が7割強、「Tポイント」が6割強、「Pontaポイント」「dポイント」が各40%台。過去調査と比べ「楽天ポイント」「dポイント」「Pontaポイント」などが増加傾向。「Tポイント」は2021年調査より減少。
■たまるポイントを積極的に利用する人は、全体の約75%。「ポイントサービスの取り扱い店を選んで利用」が5割弱。「ポイントがたまる支払い方法を選ぶ」は4割強で、過去調査より増加傾向。
-
- 調査時期:
- 2023年06月
- 設問項目:
-
コンビニ弁当利用頻度/よく食べるコンビニ弁当のタイプ/コンビニ弁当選定基準/コンビニ弁当と一緒に買う飲み物/コンビニ弁当と一緒に買う食べ物/コンビニ弁当利用場面/コンビニ弁当の購入価格/弁当が最もおいしいと思うコンビニエンスストア/コンビニ弁当についての不満(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■コンビニ弁当利用率は全体の約45%。週1回以上利用者は1割強。コンビニ弁当が一番おいしいと思うコンビニは「セブン-イレブン」が、コンビニ弁当利用者の約54%。
■コンビニ弁当利用者がよく食べる種類は「ごはん+おかず」が5割強、「麺類」「丼もの」「おにぎりとおかずの弁当」を食べる人が各30%台。選定基準は「価格」「見た目がおいしそう・きれい」が各4割強、「味」が3割強、「様々な種類のおかずが入っている」「健康に配慮している」「野菜の量や種類が多い」「全体の量が多い」などが各2割前後。
■コンビニ弁当と一緒に飲み物を買う人はコンビニ利用者の7割強、男性の方がやや多い。緑茶や日本茶系飲料などのお茶系飲料が上位。一緒に買う食べ物は「サラダ」が2割強、「味噌汁」「チルドデザート、アイスなど」「パン類」などが各13~15%。
■コンビニ弁当を食べる場面は「食事を簡単に済ませたい」「食事や弁当を作るのが面倒」が利用者の各30%台、「食事や弁当を作る時間がない」「早く済ませたい」が各20%台。「昼食」は3割強で2021年調査より減少。
-
- 調査時期:
- 2023年06月
- 設問項目:
-
健康に気をつけている度合/健康管理のための家電製品の所有状況/直近1年間での健康管理・チェックのための家電製品利用状況/健康管理のための家電製品選定時の重視点/健康管理のための家電製品のスマートフォンとの連携状況/健康状態の定期的なチェック状況/スマートフォン・タブレット端末で利用している健康管理アプリ/健康管理や維持増進のための家電製品で、利用したいものと理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■健康管理・チェックのための家電製品の所有は「電子体温計」「体重計、体脂肪計」が各7割前後、「血圧計」が5割強、「歩数計」「体組成計」が各20%台。健康管理・チェックのための家電製品の直近1年間利用者のうち、「スマートフォンと連携して利用」は約16%。
■健康管理・チェックのための家電製品直近1年間利用者の重視点は「本体価格」が6割弱、「メーカー・ブランド」が約45%、「操作のわかりやすさ」が4割弱、「性能・パワー」が3割弱。
■健康状態を数値としてチェック・測定する方法は「健康診断や定期健診など」が全体の67%、「健康管理・チェックのための製品・家電製品」「スマートフォンのアプリなど」は各10%台。
■スマートフォン等の健康管理アプリ利用者は全体の4割。アプリの種類は「歩数管理・記録、歩数計、活動量計」が3割弱、「体重や体脂肪率などの管理・記録」が1割強、「血圧管理・記録」「食事、運動、睡眠などを総合的に管理」が各6~7%。
-
- 調査時期:
- 2023年06月
- 設問項目:
-
インテリアへのこだわり/インテリアの重視点/自宅のインテリアの満足度/家具・インテリア選定時の参考情報/家具・インテリア雑貨の購入場所/家具・インテリアをインターネットショップで購入した場面/直近1年間の模様替えの実施/おうち時間を快適に過ごすためのインテリアの工夫(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■インテリアへのこだわりがある人は3割弱、女性の方が比率が高い。自宅のインテリア満足度は4割弱。女性は男性と比べて満足している人の比率が低い。
■家具・インテリア選定時の参考情報は「店頭のディスプレイ」が4割弱、「家具・インテリア専門店などの公式サイト・アプリ」が2割弱。女性若年層では「SNS、写真共有SNS」の比率が高い。
■インテリアの重視点は「見た目がすっきりしている」「使いやすく、機能的である」が各4割強。過去調査と比べて「使いやすく、機能的である」が増加傾向。インテリアにこだわりがある層では「部屋全体のテイストに統一感」「くつろぎ・癒しの空間となり居心地がよい」「見た目がすっきりしている」などが上位。こだわりがない層では「使いやすく機能的」が最も多い。
■家具・インテリア雑貨の購入場所は「家具店」が7割弱、「ホームセンター」が4割弱、「インターネットショップ」「大型生活雑貨店」「インテリアショップ・用品店」が各20%台。インターネットで購入する場面は「配送してもらいたい」「たまたま欲しいものを見つけた」「価格を比較して安いものを選びたい」がインターネット購入者の各30%台。
-
- 調査時期:
- 2023年06月
- 設問項目:
-
魚肉加工品の嗜好度/直近1年以内に食べた魚肉加工品/魚肉加工品を食べる頻度/魚肉加工品を食べる場面/魚肉加工品購入時重視点/魚肉加工品の魅力/魚肉加工品の不満/好きな魚肉加工品とおすすめの食べ方(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■魚肉加工品が好きな人は全体の約76%。週1回以上食べる人は5割弱。いずれも、高年代層での比率が高い傾向。
■直近1年以内に食べた魚肉加工品は「ちくわ」「かまぼこ」が、食べた人の各7~8割、「かにかま」「さつまあげ、つけあげ」が各6割前後、「魚肉ソーセージ」「はんぺん」が各40%台。地域により差がみられる。「夕食」に食べる人は8割強、「昼食」「おつまみ」は各3割弱。
■魚肉加工品購入時の重視点は「味」「価格」の他、「原材料」「賞味期限・消費期限」「生産国」「量・サイズ、販売単位」などが上位。
■魚肉加工品の魅力は「そのまま食べられる」「良質なたんぱく質がとれる」「味が良い・好き」が各40%台、「調理が簡単」「低脂肪、低カロリー」「価格が安い」などが各3割弱。不満は「食品添加物が気になる」「塩分がきつい」などが各10%台。
-
- 調査時期:
- 2023年06月
- 設問項目:
-
サラダを食べる頻度/好きなサラダのタイプ/サラダの食材(野菜以外)で好きなもの/サラダを食べる理由/サラダの準備方法/自宅で作ったサラダによく使う野菜/市販のサラダ購入頻度/市販のサラダの重視点/気に入っているサラダ(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■サラダを1日1回以上食べる人は全体の4割弱。サラダを食べる人のうち「袋入りカット野菜を買ってきて調理」は3割強で過去調査より増加傾向。「市販のサラダ」は4割弱。サラダを食べる理由は「健康に良い」「おいしい」「野菜をたくさん摂取できる」が食べる人の各5割強、「食物繊維をとりたい」「野菜が好き」「食事の栄養バランス」などが各4割前後。
■好きなサラダのタイプは「ポテトサラダ」「グリーンサラダ」が食べる人の各5~6割、「トマトサラダ」「マカロニサラダ」「ツナサラダ」「大根サラダ」などが各4割前後。野菜以外で好きな具材は「ハム、生ハム」「ツナ」「卵」が各5割前後、「えび、かに、ほたて」「海藻類」「麺類」などが各30%台。
■自宅で作るサラダによく使う野菜は、「キュウリ」「トマト」「キャベツ」「レタス」がサラダを食べる人の各60%台、「ブロッコリー」「タマネギ」「葉レタス」などが各4~5割。
■市販のサラダを食べる人(全体の4割弱)のうち週1回以上購入者は5割強。サラダ購入時の重視点は「価格」が7割弱、「味」が約55%、「野菜や具材の種類が豊富」「鮮度」「分量・サイズ」が各4~5割。
-
- 調査時期:
- 2023年06月
- 設問項目:
-
缶チューハイ飲用頻度/直近1年間に飲んだ缶チューハイ/直近1年間の最頻飲用缶チューハイ/缶チューハイ飲用シーン/缶チューハイに期待すること/缶チューハイ以外に飲むお酒/缶チューハイ飲用意向/缶チューハイ飲用時に飲みたい度数/缶チューハイの飲み方(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■缶チューハイ飲用率は全体の5割弱。アルコール飲用者に占める比率は7割弱で、若年層で高い傾向。週1~2日以上飲用者は全体の2割弱、缶チューハイ飲用者の4割弱。
■缶チューハイ飲用シーンは「食事中」が飲用者の6割弱、「自宅でくつろいでいるとき」が約26%、「食事のあと」「入浴後」などが各10%台。
■缶チューハイ飲用者が期待することは「好みのフレーバー」が約46%、「スッキリ」「果汁感を楽しめる」「甘くない・甘さ控えめ」「炭酸を楽しめる」などが各30%台。「好みのフレーバー」などは女性、「アルコール度数が高め」などは男性での比率が高い。主飲用銘柄別にみると、贅沢搾り主飲用者、キリン本搾りチューハイ主飲用者などでは「果汁感を楽しめる」が1位。
■缶チューハイ飲用意向・非飲用意向者はいずれも全体の4割強。月2~3日以上飲用者では9割強、非飲用者では約3~5%。飲用意向者のうち「度数5~6%」の飲用意向が4割弱。女性や若年層では「度数1~4%」の比率が高い。「度数8%以上」は男性高年代層や高頻度層で高い傾向。
-
- 調査時期:
- 2023年05月
- 設問項目:
-
イースターの認知/イースターについて知っていること/イースターに関して実施したこと/イースターにあたってしたことのきっかけ・理由/イースターに関して使った費用総額/イースターにあたって購入したもの/イースターに関連するものの購入場所/あなたにとってイースターとは/イースターにあたって何かしたこと・購入したものなど(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■イースターの認知率は8割強、「どんな行事か知っている」は約25%。「キリスト教でイエス・キリストが復活したことを記念する日」「イースターエッグ」を知っている人は認知者の各6割弱。
■イースターにあたって何かした人は、認知者の1割強。「イースターエッグを作る」「イースターに関連する・限定のお菓子やスイーツを食べる」「イースター料理を食べる」が各2~3%。購入したものは、「卵」「チョコレートエッグ」「イースター限定の味やパッケージのお菓子・デザート」などが、実施者の各1~2割。
■イースターにあたって何かしたきっかけ・理由は「イースター関連商品が目についた」「イベントなどをやっていた」「海外で暮らしたことがある」「キリスト教徒」などが各10%台。
■自分にとってイースターとは「興味がない、自分とは関係ない」が全体の3割弱、「海外の行事」ととらえる人が1割強、「季節行事の一つ」「子どものイベント」が各4%。
-
- 調査時期:
- 2023年05月
- 設問項目:
-
直近1年間に体の調子が悪いと感じる程度/直近1年間に体の調子が悪いと感じる症状/体の調子が悪いと感じ始めた時期/体の調子の悪さへの対処の必要性/体の調子の悪さの原因と思うもの/体の調子の悪さを整えるために直近1年間に行ったこと/体の調子が悪いときの病院受診方法/体の調子が悪い時の病院受診方法の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■直近1年間になんとなく体の調子の悪さを「慢性的に感じる」「毎日ではないがよく感じる」が各1割強、「時々感じる」は2割強、「たまに感じる程度」は3割強で、これらを合わせた体の調子が悪いと感じる人は8割弱。そのうち「2年以上前から」感じている人は6割弱、対処が必要と感じる人は5割強。
■直近1年間に体の調子が悪いと感じる人の症状は「肩こり」「腰痛」が各4割強、「体がだるい、疲れがとれない」「頭痛」が各3割強、「疲れやすい」「睡眠に関すること」「目に関すること」「便秘・下痢」が各3割弱。体の調子の悪さを慢性的に感じる層では「体がだるい、疲れがとれない」「疲れやすい」が上位2位。
■直近1年間に体の調子が悪いと感じる人が、原因だと思うものは「加齢、年齢的なもの」が5割強、「運動不足」が4割強、「ストレス、精神的」「睡眠不足」が各30%台、「目の使い過ぎ」「姿勢が悪い」が各20%台。直近1年間に行ったことは「睡眠をとる、質・時間を見直す」「体を休める、休憩・休息」が各4割前後、「運動、トレーニング、体操、ストレッチなどを習慣的に行う」が3割弱。
■なんとなく体の調子が悪くなったとき「早めに医者にかかるほう」「市販薬を利用し、医者にはなるべくかからないようにするほう」はいずれも約24%。「医者も薬も、なるべく利用しないようにするほう」は3割強。
-
- 調査時期:
- 2023年05月
- 設問項目:
-
損害保険の加入状況/加入損害保険の種類/火災保険を契約している保険会社/火災保険を契約している保険会社の満足度/地震保険を契約している保険会社/地震保険を契約している保険会社の満足度/加入したい損害保険/火災保険加入/継続したい保険会社/地震保険加入/継続したい保険会社/火災保険・地震保険について不安・不満に思うこと(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■損害保険加入者は78%。「自動車保険・任意加入」「火災保険・建物への補償」への加入者は、損害保険加入者の各70%台、「火災保険・家財への補償(家財保険)」「地震保険」が各4~5割。
■全体に占める火災保険加入者は6割強。満足+やや満足の比率は、ソニー損保主加入者で7割弱、県民共済主加入者、CO‐OP共済主加入者で各6割強。全体に占める地震保険加入者は約35%。
■今後加入したい損害保険(1つ)は、「自動車保険・任意加入」が約6%、「地震保険、地震補償保険」が約5%、「火災保険・建物への補償」が4%、「自転車保険」「火災保険・家財への補償(家財保険)」が各約3%。
-
- 調査時期:
- 2023年05月
- 設問項目:
-
外貨預金の利用経験/外貨預金をしている主な金融機関/外貨預金をしている主な金融機関を選んだ理由/外貨預金の利用方法/外貨預金利用のきっかけの情報源/外貨預金の金額/外貨預金の利用意向/預金・運用する通貨として興味があるもの/外貨預金利用意向あり・なしの理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■外貨預金現在利用者は1割強、利用経験者は2割強。預金・運用する通貨で興味があるものは、「米ドル(USD)」が全体の3割強、「日本円(JPY)」が2割弱。
■外貨預金利用経験者の主利用金融機関利用理由は「口座を持っている」が3割強、「手数料が安い・お得」「金利が高い」が各20%台、「信頼できる」が2割弱。住信SBIネット銀行主利用者、ソニー銀行主利用者などでは「手数料が安い・お得」が1位。
■外貨預金利用方法は「金利がよいので、中長期間で保有し金利差益を求める」が、利用経験者の約35%、「為替レートの変動を利用し、中長期間で保有し為替差益を求める」が約25%。外貨預金利用のきっかけの情報源は「金融機関のWebサイト」が利用経験者の4割弱、「金融機関の担当者のアドバイス」が2割弱。
■外貨預金利用意向は全体の1割強、非利用意向が5割強、「わからない」が3割強。現在利用者の利用意向は7割強、未経験者では5%。
-
- 調査時期:
- 2023年05月
- 設問項目:
-
利用したことがある大手スーパー/直近1年間での最頻利用大手スーパー/大手スーパー利用時の重視点/最も品揃えが充実していると思う大手スーパー/最も品質がよいと思う大手スーパー/価格が最も魅力的だと思う大手スーパー/最も革新的・先進的であると思う大手スーパー/最も信頼できると思う大手スーパー/大手スーパーの不満点・改善点(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■利用経験は、全体では「イオン」が8割弱、「イトーヨーカドー」が5割強、「ダ■利用経験は、全体では「イオン」が8割弱、「イトーヨーカドー」が5割強、「ダイエー」「西友」が各40%台。関東では「イトーヨーカドー」「イオン」「西友」が上位3位。大手スーパー利用時の重視点は「価格が手頃」「アクセスがよい」「商品のジャンルが幅広い」などが上位。
■最も『品揃えが充実している』『品質がよい』『信頼できる』と思う大手スーパーは、全体では「イオン」が各3~5割、「イトーヨーカドー」が各10%台。関東では『最も品質がよい』『最も品揃えが充実している』は「イトーヨーカドー」がやや高い。最頻利用スーパーが『最も品揃えが充実している』と回答した人の比率はイオン主利用者が特に高い。
■『価格が最も魅力的だ』と思う大手スーパーは、全体では「イオン」が3割強、「西友」が1割強。他のイメージ項目に比べ「西友」の比率が高い。
■最も革新的・先進的だと思う大手スーパーは、全体では「イオン」が3割強、「イトーヨーカドー」が約6%、「わからない」が5割強。最頻利用スーパーが最も革新的・先進的だと回答した人は、イオン主利用者で5割弱、アピタ・ピアゴ主利用者、イトーヨーカドー主利用者では各2割強。
-
- 調査時期:
- 2023年05月
- 設問項目:
-
コンビニの冷蔵コーナーのスイーツのうち購入するもの/コンビニの冷蔵コーナーのスイーツを買う頻度/コンビニスイーツ購入場面/コンビニスイーツ選定時の重視点/コンビニでのスイーツの購入金額(1回当り)/直近1年間に冷蔵コーナーのスイーツを購入したコンビニエンスストア/コンビニスイーツが最も好きなコンビニエンスストア/コンビニでスイーツを買う理由/気に入っているコンビニスイーツ(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■コンビニスイーツ購入者は全体の約55%、男性5割弱、女性7割弱。コンビニスイーツ購入者のうち月1回以上購入者は6割弱。1回あたり購入金額は「250円~300円未満」がボリュームゾーンで、2014年以降価格帯が上昇傾向。購入種類は「シュークリーム、エクレア」「ロールケーキ」「プリン、パンナコッタ」などが各2~3割。
■コンビニスイーツ購入場面は「甘いものが食べたい」が購入者の7割弱、「食後のデザート」「店頭でおいしそうな商品を見かけた」が各3割弱、「立ち寄ったついで」が2割強。
■コンビニでスイーツ購入理由は「いつでも買える」が購入者の4割強、「おいしい・おいしそう」が4割弱、「立地がよい・行きやすい」「価格が手頃」などが各3割弱。購入者の重視点は「味」が8割弱、「価格」が5割強、「容量、サイズ」「食感」「色合い・見た目」などが各2割強。
■スイーツが最も好きなコンビニエンスストアは、「セブン‐イレブン」がコンビニスイーツ購入者の4割弱、「ローソン」が3割強、「ファミリーマート」が2割弱。