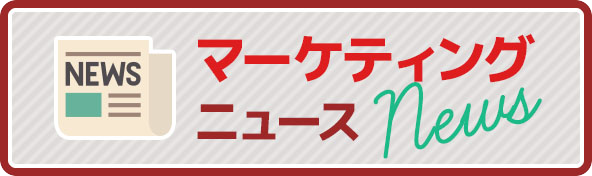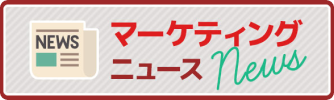- 検索
-
- テーマ別実施時期一覧
- カテゴリー別一覧
-
-
アルコール飲料・嗜好品147
-
非アルコール飲料210
-
その他19
-
-
住宅・住宅設備219
-
-
家電126
-
パソコン・カメラ・AV機器113
-
その他10
-
-
家庭用品・トイレタリー91
-
自動車・関連用品76
-
-
インターネット・情報通信328
-
携帯電話・スマートフォン180
-
メディア・広告66
-
その他7
-
-
ファッション69
-
交通・レジャー・娯楽161
-
季節行事・イベント241
-
時事・ニュース・トレンド51
-
企業ブランドイメージ250
-
広告・CM51
-
WEBサイトの利用91
-
顧客満足度100
- 実施時期別一覧
-
- 調査時期:
- 2023年02月
- 設問項目:
-
恵方巻きの認知/恵方巻きを食べた経験/今年の恵方巻きの実施状況/恵方巻きの購入場所/恵方巻き購入時の着目点/節分にちなんでしたこと、行う予定のこと/節分にかける費用/恵方巻購入意向/恵方巻購入意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■恵方巻きを食べた経験がある人は認知者の8割弱。今年食べる予定・食べた人は認知者の5割弱、経験者の6割強。近畿や中国、四国で高く、北海道や東北で低い傾向。
■恵方巻きを食べる予定・食べた人の購入場所は「スーパー」が7割弱、「コンビニエンスストア」「寿司専門店」が各1割弱。手作りは2割弱。恵方巻き購入時のポイントは「具材」「価格」「味」が、購入者・予定者の各6割強~7割強。
■市販の恵方巻き購入意向者の比率は4割弱。恵方巻きを食べたことがある層では5割弱、今年食べた・食べる予定の層では7割強。食べたことがない層では3%。
■節分にちなんでしたこと(予定)がある人は全体の6割弱。「豆まきをする」「豆を年の数食べる」の実施者・実施予定者は各2~3割。
-
- 調査時期:
- 2023年02月
- 設問項目:
-
直近1年間のゲーム頻度/eスポーツの認知/直近1年間のeスポーツに関する行動/eスポーツに対する興味度/eスポーツに関してやってみたいこと/eスポーツの普及についての賛否/eスポーツの協賛・スポンサー企業に対するイメージ変化/eスポーツの協賛・スポンサー企業に対するイメージ/eスポーツに対するイメージ(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■eスポーツについて「どのようなものか知っている」は36%、「名前を聞いたことはあるがどのようなものか知らない」は約45%で、認知率は全体の8割強。eスポーツに興味あり層は全体の約6%、興味なし層は8割強。男性若年層での比率が高い。
■eスポーツに関連して行ったことがあるのは、「テレビ・新聞・ネットなどで見聞き」が認知者の50%、「家族や友人と話題にする」「インターネット等で情報収集」が各3~4%。やってみたいことは「インターネット等で情報収集」「試合・大会をテレビ観戦」「試合・大会をネットの実況動画・配信で観戦」が全体の各2~4%。
■eスポーツが普及することについて、良いと思う人は3割弱、良いと思わない人は2割強、どちらともいえないが5割弱。
■企業がeスポーツの協賛・スポンサーをする・していることで、イメージが良くなる人は1割強で、若年層での比率が高い傾向。イメージが「変わらない」が7割強。eスポーツの協賛・スポンサー企業に対するイメージは「革新的・先進的」「柔軟性がある」「活気がある」などが各1割強。
-
- 調査時期:
- 2023年02月
- 設問項目:
-
パチンコ経験/パチスロ経験/パチンコ店利用頻度/パチンコまたはパチスロでの1回あたり使用金額/パチンコ・パチスロ店の選定基準/パチンコ・パチスロをする理由/パチンコの利用意向/直近1年間でのパチンコ・パチスロのゲーム利用状況/利用してみたいパチンコの機種・店舗・サービスなど(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■パチンコ・パチスロのいずれか実施者は全体の約7%。パチンコをしている人は約6%、経験者は5割弱。パチスロをしている人は約4%、経験者は約26%。パチンコ・パチスロのゲームの直近1年間利用者は約3%。
■パチンコ・パチスロいずれか実施者のうち、パチンコ店の週1~2回以上利用者は5割弱。店の選定基準の上位は「立地」「プレイしたい機種の台数の多さ」「稼働率」など。女性では「店への入りやすさ」「清潔感」などの比率がやや高い傾向。
■パチンコ・パチスロいずれか実施者の理由は「気分転換」が5割強、「ストレス解消」「暇つぶし」が各4割弱。
■パチンコの利用意向は全体の約8%、パチンコのみ実施者では8割強、パチンコ・パチスロ非実施者では約3%。
-
- 調査時期:
- 2023年02月
- 設問項目:
-
筋肉・筋力の程度/筋肉・筋力の直近2~3年間での増減/筋肉・筋力の維持・向上に関する直近1年間での取り組み実施状況/筋肉・筋力の維持・向上のために直近1年間に実施したこと/筋肉・筋力の維持・向上のために直近1年間に摂取した食品・飲料/筋肉・筋力の維持・向上のために直近1年間に行った運動/筋肉・筋力の維持・向上の取り組み意向/筋肉・筋力の維持・向上のための取り組みをしたい理由/筋肉・筋力の維持・向上のために行いたいこと(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■自分の筋肉・筋力がない方だと思う人は50%、ある方だと思う人は約15%、「普通」は約35%。ここ2~3年間で自分の筋肉・筋力が減ったと感じる人は6割弱で高年代層ほど高い傾向。「変わらない」が約35%。
■筋肉・筋力の維持・向上の取り組みの直近1年間実施者は4割弱。取り組み実施者のうち「筋トレ、体操、ストレッチ、運動・スポーツなど」の実施者は約76%、「日常生活の中で体を動かす」が約65%、「睡眠を十分とる、睡眠の質の向上」は3割弱。
■直近1年間での筋肉・筋力の維持・向上の取り組み実施者が、意識的に摂取したものは「牛乳、乳製品」「豆類、大豆製品」が各4割弱、「精肉類:鶏肉」「卵」が各3割前後、「精肉類:豚肉」「魚介類」「バナナ」などが各2割前後。運動や筋トレ・体操の内容は「ウォーキング」「自宅での器具を使わない筋トレ・運動・体操」が実施者の各40%台、「ジム・スポーツクラブなどでの筋トレ・トレーニング」「自宅での器具を使った筋トレ・運動・体操」が各2割弱。
■筋肉・筋力の維持・向上のための取り組み実施意向者は約66%で、女性の方が高い。女性は高年代層、男性は10・20代や60~70代がやや高い。実施意向者の理由は「健康維持・増進」が8割弱、「体力づくり、身体能力向上」が5割強、「免疫力・抵抗力向上」「生活習慣病など、病気の予防」が各4割強。
-
- 調査時期:
- 2023年02月
- 設問項目:
-
慢性的な疲れ・疲労の度合い/普段の生活で感じる身体的・精神的な疲労の程度/普段の生活で疲れ・疲労を感じる部位/普段の生活で疲れ・疲労を感じる場面/普段の生活で疲れ・疲労を感じる原因/疲れをとる・疲労回復のためにすること/疲れをとりたい・疲労回復のために飲むもの/疲れを感じたときの対処や事前対策(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■慢性的な疲労を感じている人は6割強。身体的疲労の方が多い人は3割弱、精神的疲労の方が多い人は約25%、同じくらいの人は約35%。疲労を感じる人のうち「全身」「目」「肩」が各30%台、「首」「腰」「精神的に」が各3割弱。疲労感を感じる場面は「夕方」「夜」が3割強、「朝」が約26%、「季節の変わり目」「天候不順、低気圧など」が各2割弱。
■疲れ・疲労の原因だと思うのは「加齢」「運動不足」が、疲労を感じる人の各4割前後、「睡眠不足」「目の使い過ぎ、スマホ・PC等の画面を見る時間が長い」が各3割前後。女性10・20代では「目の使い過ぎ、スマホ・PC等の画面を見る時間が長い」が1位。
■疲労感を感じる人が疲れをとるためにすることは「寝る」が6割強、「体を休める」が4割強、「入浴、半身浴など」が2割強。
■疲労を感じている人が疲れをとりたいときに飲むものは「コーヒー、コーヒー系飲料」が3割強、「栄養ドリンク」「日本茶、中国茶、健康茶、ハーブティーなど」が各2割弱。男性30代では「エナジードリンク」「炭酸飲料」が上位2位。
-
- 調査時期:
- 2023年02月
- 設問項目:
-
主利用携帯電話会社/CMの印象がよいと思う携帯電話会社/先進的だと思う携帯電話会社/信頼できると思う携帯電話会社/機能が充実していると思う携帯電話会社/電波・回線がつながりやすいと思う携帯電話会社/最もサポートの品質がよいと思う携帯電話会社/今後利用したいと思う携帯電話会社/今後利用したいと思う携帯電話会社の選定理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■『最もCMの印象がよい』と思うのは「au」が2割強、2021年調査と比べて減少。「SoftBank」「NTTドコモ」が各2割弱。
■『最も信頼できる』『最も機能が充実している』と思う携帯電話会社は「NTTドコモ」が各40%台、「au」が13~14%、「SoftBank」1割前後。「その他」は20%台。『最も電波・回線がつながりやすい』は「NTTドコモ」が約65%を占め、他社との差が大きい。
■『最も先進的だ』と思うのは「NTTドコモ」が3割強、「SoftBank」が約15%、「楽天モバイル」「au」が各1割強。2021年調査と比べ、「SoftBank」「楽天モバイル」などが減少、「その他」が増加。『最もサポートの品質がよい』と思う携帯電話会社は「NTTドコモ」が4割強、「au」が約15%、「SoftBank」が1割弱、「その他」が3割弱。
■今後利用したい携帯電話会社は「NTTドコモ」が3割強、「au」が約15%、「楽天モバイル」が約9%。継続利用意向は、NTTドコモ主利用者8割強、au主利用者7割強。SoftBank主利用者、Y!mobile主利用者、楽天モバイル主利用者では各60%台。
-
- 調査時期:
- 2023年02月
- 設問項目:
-
知っている損害保険会社/損害保険加入状況/加入している損害保険会社/信頼性・安心感がある損害保険会社/商品開発力・企画力がある損害保険会社/独自性がある損害保険会社/提供しているサービスの品質が高い損害保険会社/契約したい損害保険会社/損害保険会社に期待すること(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■損保会社の認知率は「ソニー損保」「東京海上日動火災保険」が各7割前後。「ソニー損保」は、加入の順位よりも契約したい損保(1つ)での順位の方が上位。
■『信頼性や安心感がある』のは、「東京海上日動火災保険」が3割強、「県民共済」「三井住友海上火災保険」「損害保険ジャパン」「ソニー損保」「こくみん共済coop」などが各2割前後。
■『商品開発力や企画力』の上位は「ソニー損保」「東京海上日動火災保険」が各10%台、「損害保険ジャパン」「イーデザイン損保」「アクサダイレクト」などが各8~9%。『独自性がある』は「ソニー損保」が1割強、「イーデザイン損保」「県民共済」「アクサダイレクト」などが各7~8%。「いずれもない」がそれぞれ5割強。
■『提供しているサービスの品質が高い』と思う損保会社は「東京海上日動火災保険」が2割弱、「ソニー損保」「損害保険ジャパン」「三井住友海上火災保険」が各1割強、「県民共済」が約8%。「いずれもない」が5割弱。
-
- 調査時期:
- 2023年02月
- 設問項目:
-
スマートフォン・携帯電話利用状況/直近1年間での支払い方法/直近1年間に利用したスマホ決済アプリ・サービス/直近1年間の最頻利用スマホ決済アプリ・サービス/直近1年間にスマホ決済で支払った頻度/直近1年間にスマホ決済アプリ・サービスで支払った割合/スマホ決済アプリ・サービスでの支払い意向/スマホ決済アプリ・サービス利用時の重視点/スマホ決済利用意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■直近1年間にスマホ決済アプリで支払った人は全体の6割強(スマホ主利用者の7割弱)、過去調査と比べ増加傾向。若年層での比率が高い。直近1年間スマホ決済利用者のうち、「PayPay」利用者が7割弱、「楽天ペイ」「d払い」が各3割前後。
■直近1年間のスマホ決済アプリ利用者のうち週1回以上支払い者は7割弱。直近1年間の支払い回数のうちスマホ決済の割合が6割以上の層は4割弱。支払い頻度・割合ともに、過去調査と比べ増加傾向。
■スマホ決済アプリ利用意向は全体の5割強、過去調査より増加傾向。利用意向はスマートフォン主利用者の6割弱、直近1年間スマホ決済利用者の8割弱、非利用者の約7%。
■スマホ決済支払意向者のサービス重視点は「利用できる店舗・サービスの多さ」「支払いのスムーズさ・手順の簡単さ」が各7割弱、「ポイント還元率の高さ」が55%。直近1年間スマホ決済非利用者では「設定の簡単さ」の比率が高い。
-
- 調査時期:
- 2023年02月
- 設問項目:
-
定額制サービス直近1年間利用状況/定額制サービス:使い放題サービス直近1年間利用状況/定額制サービス:レンタル・試し放題サービス直近1年間利用状況/定額制サービス:定期便サービス直近1年間利用状況/定額制サービスにかける費用総額(1ヶ月あたり)/定額制サービス利用のきっかけ・理由/定額制サービス利用意向/定額制サービス利用時の重視点/お勧めのサブスクリプションサービス/利用してみたいサービス(非利用者)(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■定額制サービス直近1年間利用者は全体の3割強、過去調査と比べ増加傾向。若年層での比率が高い。「定額料金で、条件内でサービスを使い放題」が3割弱。直近1年間利用者のきっかけ・理由は「月額料金に対してお得」「利用したい商品・サービスがある」「無料お試しやキャンペーンをやっていた」が各20%台。
■直近1年間定額制サービス利用者のうち、使い放題のサービスでは「定額制映像配信サービス」が7割弱(回答者全体の2割強)。「定額制音楽配信サービス」「定額制の電子書籍・雑誌・コミック」が各1~2割。定額制レンタル・試し放題サービスでは「家電」「自動車、中古車」が各2%。定期便サービスでは「スキンケア用品、化粧品、コスメなど」が約6%。
■定額制サービス利用意向は全体の3割弱。若年層での比率が高い。定額制サービス直近1年間利用者では7割強の利用意向、非利用者では約7%。
■定額制サービス利用意向者の重視点は「料金に見合う内容である」「月額料金」が各8割弱、「品質」「品ぞろえ」が各30%台、「解約のしやすさ、解約手順のわかりやすさ」「飽きずに利用できる」「無料お試し・体験の充実度」が各20%台。定額制サービス直近1年間非利用者では「無料お試し・体験」「解約のしやすさ、解約手順のわかりやすさ」などが高い。
-
- 調査時期:
- 2023年02月
- 設問項目:
-
コンビニエンスストア利用頻度/よく利用するコンビニエンスストア/最頻利用コンビニエンスストア/コンビニエンスストア利用時の重視点/コンビニエンスストア利用場面/コンビニエンスストアにあってよかったと思うもの/コンビニエンスストア利用時の行動/コンビニエンスストアの不満点(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■コンビニエンスストア週1回以上利用者は5割強。よく利用するコンビニエンスストアは、全体では「セブン‐イレブン」が1位、「ファミリーマート」「ローソン」が続く(地域により傾向が異なる)。利用時の行動として「何かというとコンビニを利用する」は男性若年層で高いが、「コンビニで買うものはだいたいいつも決まっている」は若年層で低い傾向。
■コンビニエンスストア利用時の重視点は「アクセスのよさ」が利用者の6割弱、「弁当・パン・惣菜類の充実度」「品揃えが豊富」が各3割強、「お菓子、デザート類、アイス等の充実度」「駐車場の充実度」「ポイントやキャンペーンなどのお得なサービス」などが各2割前後。
■利用シーンは「お弁当やおにぎり、パン、お惣菜などの食品を買う」が利用者の6割強、「お菓子、デザート類、アイスなど」が4割強、「サービスを利用」「飲料(お酒以外)」が各3割前後。
■コンビニエンスストアにあってよかったものは「お弁当やおにぎり、パンなど」が利用者の約45%、「トイレ」約36%「コンビニATM」「公共料金の支払い」「郵便ポスト、切手・はがき類」「お菓子類、チルドデザート、アイスクリームなど」「飲み物(お酒以外)」などが各20%台。
-
- 調査時期:
- 2023年02月
- 設問項目:
-
所有パソコンのタイプ/主利用デスクトップ・ノートパソコンのタイプ/主利用デスクトップ・ノートパソコンのメーカー/主利用デスクトップ・ノートパソコンで行っていること/デスクトップ・ノートパソコン利用頻度/主利用デスクトップ・ノートパソコンとつなげている機器/購入したいパソコンのタイプ/デスクトップ・ノートパソコン購入時の重視点/デスクトップ・ノートパソコンでやりたいこと/購入したくない理由(非購入意向者)(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■所有パソコンのタイプは「A4サイズノートパソコン」が全体の6割弱。「デスクトップパソコン」は3割強で過去調査より減少傾向。女性10~30代ではパソコン非所有者の比率が高い。
■デスクトップまたはノートパソコン利用者のうち「毎日」使う人は7割強、過去調査と比べ減少傾向。男性や高年代層で、利用頻度が高い傾向。主にすることは「Webサイトの閲覧、メール送受信、SNS・チャットなど」が9割弱、「ネットショッピング」が7割強、「動画の視聴」「金融取引」「印刷」が各4割強。
■主利用パソコンとつなげている機器は「マウス」「プリンター」が利用者の各6割弱、「USBメモリ」「キーボード」が各3割前後。若年層では「ヘッドホン、ヘッドセット、イヤホン」「スマートフォン」などが高い。
■最も購入したいタイプは「A4サイズノートパソコン」が全体の3割強、「デスクトップパソコン」が2割弱。大画面ノートパソコン購入意向者の重視点は「画質」「画面の大きさ、みやすさ」など、B5・モバイルサイズのノートパソコン購入意向者では「バッテリーの持ち時間」「重さ」などの比率が高い。
-
- 調査時期:
- 2023年02月
- 設問項目:
-
平日の昼食スタイル/平日の昼食で最も多いスタイル/平日の昼食を一緒に食べるのが最も多い人/平日の昼食にかける平均時間/平日の昼食の平均予算/平日の昼食によく食べる組み合わせ/平日の昼食のメニューの重視点/直近1年間の平日の昼食の頻度の変化/昼食のメニューの決め方(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■平日の昼食のスタイルは「自宅で、自分で作って食べる」が4割弱、「スーパーで購入」「コンビニエンスストアで購入」が各3割弱。平日の昼食を食べる人のうち「主食+おかず」の組み合わせが6割弱、「単品で済むもの」が3割弱。
■昼食を食べる人のうち、平日昼食を一緒に食べる人が最も多いパターンは、「自分ひとり」が6割強で、過去調査と比べ増加傾向。「家族」2割強、「職場の同僚、上司、部下」1割強で、いずれも過去調査と比べ減少傾向。
■昼食を食べる人のうち、15分未満で食べる人は半数弱。「10分~15分未満」「15分~30分未満」がボリュームゾーン。平均予算は「100円以上~300円未満」「300円以上~500円未満」がボリュームゾーン。弁当店主利用者やファストフード系外食店主利用者では「500円以上~700円未満」、ファストフード以外の外食店主利用者やテイクアウト主利用者では「700円以上~1000円未満」がボリュームゾーン。
■昼食を食べる人の、平日の昼食のメニューの重視点は「時間をかけずに食べられる」が4割強、「安く済ませられる」が3割強。ファストフード系外食店主利用者では「安く済ませられる」、ファストフード系以外の外食主利用者では「自分が好きなもの・食べたいものである」が1位。
-
- 調査時期:
- 2023年01月
- 設問項目:
-
2022年の生活満足度/昨年1年間の節約度/昨年1年間に経費を節約した項目/昨年1年間に経費を節約した理由/今年節約を心がけようと思っている項目/今年はできればお金をかけたい項目/幸福感/直近2~3ヶ月の消費意識/昨年1年間の買い控えの内容と理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■2022年の生活に満足できた人は全体の5割強、満足できなかった人は5割弱。満足できた人の比率は2022年調査より微増。自分が幸せだと思う人は全体の6割弱で、男性30・40代で低い。
■昨年経費を節約した人は6割弱。節約の理由は「物価上昇」「将来の生活に備えて」が各30%台、「収入が少ない・減った」が3割弱、「不況、景気後退」「出費がかさむことがあった・支出が多かった」などが各2割弱。2022年調査と比べ「出費がかさむことがあった・支出が多かった」などが微増傾向。
■経費を節約した項目の上位は「外食」「食料品」が各4割弱、「衣料品」「公共料金」「旅行」が各20%台。2022年調査より「食料品」「公共料金」などが増加、「外食」「旅行」などが減少。今後節約を心がけたい項目は「食料品」「公共料金」が各3割弱で2022年調査より増加。昨年よりお金をかけたいものは「旅行」が2割強、「趣味・娯楽・教養」が1割強。
■直近2~3ヶ月の消費意識は「節約はしつつ、ちょっとした贅沢も楽しむ」「必要なもの以外はなるべく買わないよう、我慢する」が4割弱。「電気代を節約する(節電)」は3割強で、2022年調査より増加。
-
- 調査時期:
- 2023年01月
- 設問項目:
-
お正月の過ごし方/お正月関連の準備や行ったもの/お正月関連の費用/クリスマスの過ごし方/クリスマス関連で購入したもの/クリスマス関連で購入したものの購入場所/クリスマス関連の費用総額/クリスマスに対する準備・工夫度合い/年末年始の過ごし方で普段と違うことや変化(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■お正月は「家で過ごす」が約85%、「初詣に行く」が3割弱。「帰省する」は約8%で2021年調査より増え、2018~2020年とほぼ同程度。
■お正月関連で行ったものは「年越しそば」「年賀状」が各40%台後半、「お雑煮」「おせち料理」が各40%台前半で、2021年調査より減少。男性若年層では「特に何もしていない」の比率が高い。
■クリスマスを楽しむ準備・工夫をする人は全体の2割弱。女性では若年層での比率が高く、年代差が大きい。クリスマスに関することの実施者は全体の6割強。「クリスマスケーキを買う」「ケーキ、スイーツなどを食べる」「クリスマスの料理・ごちそうを食べる」が各20%台。
■クリスマスに関連実施者のうち「ケーキ」購入者は5割強、「調理済みの惣菜・料理」が約26%、「シャンパン、清涼飲料などの飲み物」「クリスマスプレゼント」が各2割弱。
-
- 調査時期:
- 2023年01月
- 設問項目:
-
体力・認知機能などで気になるもの/認知機能が気になる度合い/認知機能の維持・向上のために行っていること/認知機能の維持・向上を期待して直近1年間に利用した食品・飲料/直近1年間に利用した認知機能をサポートする健康食品・機能性表示食品等/認知機能をサポートする健康食品を利用したきっかけ・理由/認知機能をサポートする健康食品・機能性表示食品等の利用意向/認知機能の維持・向上のために行いたいこと・利用・購入したいもの(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■身体や認知機能等で気になることは「体力」6割強、「記憶力」5割強、「筋力」5割弱。自分の認知機能が気になる人は約56%。50~70代で高い傾向。
■認知機能の維持・向上のために何らかのことを行っている人は50代で7割弱、60~70代では各7~8割。「睡眠を十分とる」「栄養バランスのとれた食事」「規則正しい生活」が全体の各3割前後。女性70代ではこれらに続いて「脳トレなど、記憶する・考えることを意識」「体操やストレッチ」「趣味や興味のあることに取り組む」「手先を動かす」などの比率が他の層より高くなっている。
■認知機能の維持・向上を期待して直近1年間に利用した食品・飲料は、「青魚」が2割弱、「大豆、大豆製品」「緑黄色野菜」「乳製品」「豚肉」が各1割強。女性70代で比率が高いものが多い。
■認知機能をサポートする健康食品等の直近1年間利用者は1割強、70代では約16%。今後の利用意向は全体の3割弱、直近1年間利用経験者の9割弱、利用未経験者の2割弱。直近1年間利用者の理由は「認知機能の低下が気になる」「気軽に栄養素を摂取したい」「認知機能をさらに高めたい」が各30%台。
-
- 調査時期:
- 2023年01月
- 設問項目:
-
インターネットバンキング利用経験/インターネットバンキングでの利用サービス/現在利用インターネットバンキング/最頻利用インターネットバンキング/最もよく利用しているインターネットバンキングの満足度/インターネットバンキング選定時の重視点/インターネットバンキング利用意向/インターネットバンキングを利用したい機器/最頻利用インターネットバンキングの利用理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■インターネットバンキング現在利用者は全体の7割弱で2018年調査以降微増傾向。「口座情報の照会・明細の確認」「振り込み・送金」が利用者の各8割前後。セブン銀行主利用者、PayPay銀行主利用者、楽天銀行主利用者などでは「ネットショッピングなどの決済」の比率が高い傾向。
■最頻利用インターネットバンキングについて満足している人(「満足」「やや満足」)の比率は、ソニー銀行主利用者、住信SBIネット銀行主利用者で各9割前後、セブン銀行主利用者、auじぶん銀行主利用者、SBI新生銀行主利用者で各8割強。
■インターネットバンキング選定時の重視点は「手数料が安い」が利用者・経験者の7割弱、「銀行に取引口座がある」「信頼できる」が各4割強、「24時間リアルタイムで利用が可能」が3割強。みずほ銀行主利用者、三井住友銀行主利用者、りそな銀行主利用者など実店舗を持つ銀行主利用者は「銀行に取引口座がある」が1位。
■インターネットバンキング利用意向は7割強。現在利用者の約97%、未経験者の約15%。利用意向者のうち、スマートフォンからの利用意向者は6割弱で、過去調査と比べ増加傾向。若年層での比率が高い。
-
- 調査時期:
- 2023年01月
- 設問項目:
-
オーガニック商品利用状況/直近1年間に購入したオーガニック商品:食品・飲料/直近1年間に購入したオーガニック商品:食品・飲料以外/オーガニック商品利用理由/オーガニック商品購入場所/オーガニック商品購入意向/購入したいオーガニック商品のジャンル/オーガニック商品購入意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■オーガニック商品利用者は全体の約36%。女性や高年代層での比率が高い。購入意向者は3割強で、過去調査と比べ減少傾向。現在利用者の利用意向は7~9割、非利用者では約9%。
■オーガニック商品利用者が直近1年間に購入したものは、飲料では「お茶、お茶系飲料」が4割強、「健康茶、ハーブティ」が約26%、「コーヒー飲料」「紅茶飲料」などが各2割弱。食品では「野菜・果物類」が約45%、「大豆、大豆製品」「パン類」が各2割弱。食品以外では、「肌着・下着類」「タオル類」が各2割弱。
■オーガニック商品利用理由は「健康によい」が利用者の5割弱、「環境に配慮している」が4割、「品質がよい」「安全」などが各3割弱。
■オーガニック商品購入場所は「スーパー」が6割強、「インターネットショップ」「オーガニック専門店」「ドラッグストア」「生協など、食材宅配サービス」「デパート」などが各10%台。
-
- 調査時期:
- 2023年01月
- 設問項目:
-
100円ショップ利用頻度/直近1年間に利用した100円ショップ/直近1年間での最頻利用100円ショップ/100円ショップでの直近1年間の購入商品/100円ショップ利用時の重視点/100円ショップでの購入場面/100円ショップでの1回あたり購入個数/100円ショップでの目的買いの状況/100円ショップの利用の仕方(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■100円ショップ利用頻度は「月に数回程度」「月に1回程度」がボリュームゾーン。月1回以上利用者は6割弱、女性の方が利用頻度が高い傾向。1回あたり購入個数は3個以上が7割強、4個以上が4割強。女性の方が購入個数が多い傾向。
■直近1年間100円ショップ利用者の購入商品は「キッチン用品、調理器具、キッチン消耗品」が6割弱、「文具」が4割強、「収納用品、整理小物」「掃除用品、洗剤類」が各30%台。
■直近1年間100円ショップ利用者の重視点は「品揃えの豊富さ」が7割弱、「商品の実用性」「商品の品質」が各4割弱、「アクセスの良さ」「値ごろ感」が各3割強、「便利グッズ・アイデアグッズの充実度」が2割強。
■直近1年間100円ショップ利用者の購入場面は「普段の買い物」「安く買いたい、節約のため」が利用者の各4割弱、「使い捨て、すぐ壊れてもよいもの」「急に買う必要が生じた」「雑貨・小物などちょっとしたものを買う」が各20%台。また「買う予定ではなかった商品もついでに買うことが多い」は4割強で、女性の方が多い。
-
- 調査時期:
- 2023年01月
- 設問項目:
-
普段利用するコンビニエンスストア/直近1年間のコンビニコーヒー利用頻度/直近1年間にコンビニコーヒーを購入したコンビニエンスストア/直近1年間にコンビニコーヒーを最もよく購入したコンビニエンスストア/コンビニコーヒー購入理由/コンビニコーヒー購入時の重視点/コンビニコーヒー利用意向/普段飲むコーヒー/コンビニコーヒーの不満点/利用しない理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■コンビニエンスストア利用者のうち、コンビニコーヒー直近1年以内購入者は6割弱。週1回以上購入者は全体の2割強、直近1年間購入者の4割弱。男性や若年層での利用頻度が高い傾向。
■直近1年間コンビニコーヒー購入者の理由は「価格が安い」「値段の割においしい」「缶コーヒーやペットボトル入りコーヒー等よりおいしい」が各4割前後、「できたてが飲める」「気軽に買える」「味が本格的」などが各20%台。購入時の重視点は「味」が6割強、「価格」約45%、「香り」4割弱。
■コンビニコーヒー利用意向者は全体の5割弱。コンビニコーヒー月1回以上購入者では80%台、直近1年間非購入者では3割弱、購入未経験者では約5%。
■普段飲むコーヒーは「自分や他の人が淹れたもの」が6割強、「カフェ・飲食店などのコーヒー」が3割強、「コンビニコーヒー」「缶コーヒー」「ペットボトル入りコーヒー」が各3割弱。男性30~40代では「缶コーヒー」が1位。
-
- 調査時期:
- 2023年01月
- 設問項目:
-
世帯での自動車所有状況/主利用自動車のタイプ/主利用自動車所有期間/主利用自動車購入時の決定権/主利用自動車の購入経路/自動車購入意向/購入したい自動車のタイプ/購入したい自動車(動力)/車購入時のこだわり(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■世帯での自動車所有者は全体の7割強で過去調査と比べ減少傾向。世帯での主利用車は、新車が5割強、中古車が2割弱。
■主利用車のタイプは「軽自動車」「コンパクトカー」が車の世帯所有者の各20%台、「ミニバン」「セダン」が各1割強。過去調査と比べ「セダン」が減少傾向。主利用車購入経路は「ディーラー」が、購入者の7割強。
■自動車購入意向者は全体の5割弱。新車・中古車所有者では各6割前後、車非所有者では1割弱。関東や近畿での購入意向が低い。
■自動車購入意向者が購入したいタイプは「軽自動車」が3割強、「コンパクトカー」「SUV」が各20%台。過去調査と比べ「SUV」が増加傾向、「セダン」が減少傾向。動力のタイプは「ハイブリッド車(HV)」が自動車購入意向者の約55%、「ガソリン車」が5割弱。「電気自動車(EV)」「プラグイン ハイブリッド車(PHEV)」は各20%台。
-
- 調査時期:
- 2023年01月
- 設問項目:
-
戸建て住宅の購入経験/住宅メーカーの認知/信頼性・安心感があると思う住宅メーカー/品質・技術が優れていると思う住宅メーカー/独自性があると思う住宅メーカー/革新的・先進的であると思う住宅メーカー/親近感があると思う住宅メーカー/省エネ・エコ住宅というイメージがあると思う住宅メーカー/家を建てる際に依頼したい住宅メーカー/家を建てる際に依頼したい住宅メーカーの理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■『信頼性・安心感がある』『品質・技術が優れている』と思う住宅メーカーは「積水ハウス」「住友林業」が各3割前後、「積水化学工業」「旭化成ホームズ」などが各2割前後。『親近感があると思う』は、「積水ハウス」が2割弱、「タマホーム」「住友林業」「ミサワホーム」「積水化学工業」が各1割強。
■『独自性がある』は「住友林業」「旭化成ホームズ」「スウェーデンハウス」が各1割強。『革新的・先進的』は「旭化成ホームズ」が1割強、「積水ハウス」「積水化学工業」「パナソニックホームズ」「住友林業」が各7~9%。特にないが6割強と高い。
■『省エネ・エコ住宅というイメージ』は、「パナソニックホームズ」が1割強、「積水ハウス」「旭化成ホームズ」「積水化学工業」が各9%台。「特にない」は6割強。
■家を建てる際に最も依頼したい住宅メーカーは「住友林業」が約8%、「積水ハウス」が約7%、「旭化成ホームズ」「パナソニックホームズ」が各4~5%。「特にない」が5割強。
-
- 調査時期:
- 2023年01月
- 設問項目:
-
味覚の敏感度/好きな味/苦手な味/ここ2~3年で食べるようになった味/ここ2~3年で食べなくなった味/好きな味のベース/好きな味のジャンル/最も好きな味/過去5年間での味の好み・嗜好の変化(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■味覚に対して敏感な人は全体の4割強。好きな味のベースは「しょうゆ」「かつおだし」「昆布だし」が各4~5割、「みそ」「塩こしょう」が各4割弱。
■好きな味は「甘い」が5割弱、「薄い・あっさり」「さっぱり」が各4割強、「甘辛い」「スパイシー」などが各4割弱。つい選んでしまう最も好きな味は「薄い・あっさり」「甘辛い」が各1割強、「甘い」「スパイシー」「塩辛い・しょっぱい」が各8~9%。
■ここ2~3年で食べるようになった味がある人は3割強、食べなくなった味がある人は4割弱。食べるようになった味の上位は「薄い・あっさり」「スパイシー」「すっぱい」「辛い」など。食べなくなった味は「濃い・こってり」「塩辛い・しょっぱい」「辛い」などが上位。
■好きな味のジャンルは「和風」が8割弱、「洋風」「中華風」が各50%台。女性では「洋風」「韓国風」などの比率が高い。
-
- 調査時期:
- 2023年01月
- 設問項目:
-
つけものの嗜好度/つけものを食べる頻度/好きなつけもの・漬け方/つけものを食べる場面/つけものの準備方法/市販のつけもの選定時の重視点/つけものの魅力/市販のつけもので気に入っている点・こだわり(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■つけものが好きな人は全体の7割強、高年代層で高い傾向。好きなつけものは「浅漬け」「たくあん」「キムチ」「ぬか漬け」「白菜漬け」「塩漬け」「梅干」などが上位。つけものの魅力は「手軽に食べられる」が7割弱、「発酵食品」が4割弱、「野菜を多く摂取できる」「保存がきく」が各3割弱。
■つけものを食べる頻度は「週に2~3日程度」がボリュームゾーン。週1日以上食べる人が全体の6割弱で、過去調査より減少傾向。高年代層で食べる頻度が高い傾向。
■つけものを食べる人のうち「市販のつけものを購入する」は約85%。「調味料や漬け床を調合して漬ける」「市販のつけものの素を利用して漬ける」など、自宅でつける人が各2割強。女性高年代層で高い傾向。
■市販のつけものを食べる人の重視点は「味」が8割弱、「つけものの種類」「味付け方法」「価格」「材料の種類」などが各4~5割。
-
- 調査時期:
- 2023年01月
- 設問項目:
-
ノンアルコールビール飲用頻度/直近1年以内に飲んだノンアルコールビール/直近1年以内に最もよく飲んだノンアルコールビール/ノンアルコールビール選定時の重視点/ノンアルコールビール飲用シーン/ノンアルコールビール飲用理由/ノンアルコールビール飲用意向/ノンアルコールビール飲用意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■ノンアルコールビール飲用者は全体の3割強。「月に1回未満」がボリュームゾーン。飲用者に占める週1回以上飲用者は約25%で、若年層での比率が高い傾向。
■ノンアルコールビール飲用者の重視点は、「味」が7割弱、「ビールに近い」が4割弱、「のどごし」「価格」が各26%。「ビールに近い」の比率は若年層で低い。
■ノンアルコールビール飲用者が飲む場面は「夕食時」が約46%、「車を運転」「お風呂あがり」が各10%台。2017年調査時以降、「夕食時」が増加傾向。飲用理由は「車を運転するときでも飲める」「お酒を飲む気分を味わえる」「おいしい」が各20%台、「お酒を飲む場に参加しやすい」「お酒を飲みすぎないため」が各16%。
■ノンアルコールビール飲用意向は全体の2割強、非飲用意向は6割強。飲用意向の比率は、月1回以上飲用者の8~9割、月1回未満飲用者の5割弱、非飲用者の約2%。
-
- 調査時期:
- 2022年12月
- 設問項目:
-
今年お歳暮を贈る件数/お歳暮の内容/お歳暮を贈る相手/お歳暮の購入場所/お歳暮を最も多く購入する場所/お歳暮の平均単価/お歳暮に贈った品物選定時の参考情報/お歳暮を贈る理由/お歳暮を最も多く購入した場所の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■今年お歳暮を贈る人・予定の人は全体の4割弱で過去調査と比べ減少傾向。贈る理由として「相手からも毎年もらう」「毎年贈っている相手がいる」などは高年代層での比率が高い傾向。
■今年のお歳暮を贈る人・予定の人のうち、「お菓子・デザート・アイス類」「加工肉」「ビール類」を贈る人が20%台、「魚介類、水産加工品」「果物」が各10%台。
■お歳暮の購入場所は「総合スーパーの店頭」「百貨店の店頭」「オンラインショッピングサイト」などが各2割弱。過去調査と比べ「百貨店のオンラインショップ」が増加傾向、「百貨店の店頭」は減少傾向。
■お歳暮を贈る人が参考にした情報源は「店頭の商品」「ギフトカタログの冊子」が各2割強、「家族・友人・知人の意見」「百貨店・スーパーなど店舗のネットショップ・オンラインストア」が各1割強。
-
- 調査時期:
- 2022年12月
- 設問項目:
-
知っている生命保険会社/生命保険加入状況/加入している生命保険会社/「信頼性や安心感がある」と思う生命保険会社/「商品開発力や企画力がある」と思う生命保険会社/「独自性がある」と思う生命保険会社/「革新的・先進的である」と思う生命保険会社/契約したいと思う生命保険会社/最も契約したい生命保険会社の選定理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■生命保険加入率は全体の約75%。「現在の会社との契約を継続したい」が7割強。最も契約したい生命保険会社は「県民共済」「アフラック」「日本生命」「ソニー生命」などが上位。
■『信頼性・安心感がある』生保は、「日本生命」「県民共済」が各20%台、「第一生命」「アフラック」「明治安田生命」などが各10%台後半。
■『商品開発力・企画力』があると思う生保は「アフラック」が2割弱、「日本生命」「ソニー生命」「ライフネット生命」などが各6~8%。「いずれもない」が5割強。
■『独自性がある』『革新的・先進的』と思う生保はどちらも「アフラック」「ライフネット生命」が上位2位。『独自性』は「県民共済」「ソニー生命」、『革新的・先進的』は「ソニー生命」などが続く。
-
- 調査時期:
- 2022年12月
- 設問項目:
-
医療保険加入状況/主加入医療保険会社/主加入医療保険の満足度/医療保険加入時の申し込み経路/医療保険加入・見直し意向/加入したい医療保険会社/医療保険加入時の商品選定の決め手/医療保険加入時のインターネット利用意向/主加入医療保険の加入理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■医療保険加入者は全体の7割強、医療保険単独加入が4割弱、特約が2割強。医療保険加入者の商品加入継続意向は各6割前後。未加入者の新規加入意向は1割強。
■医療保険加入経路は「知り合いや紹介を受けた営業職員、販売員を通じて」が加入者の約25%。アクサダイレクト生命主加入者、ソニー損保主加入者、チューリッヒ生命主加入者、楽天生命主加入者などでは「インターネットで申込み手続き」が1位。
■商品選定ポイントは「月々の保険料が安い」が全体の6割弱、「病気での入院給付金日額が十分」「十分な額の手術給付金がある」が各20%台、「商品内容がわかりやすい」「日帰り入院も保障」「払込期間が終身」などが各2割弱。
■医療保険加入時「情報収集から申し込みまですべてインターネットを利用したい」が3割強で2018年以降微増傾向。アクサダイレクト生命主加入者、ソニー損保主加入者、楽天生命主加入者、県民共済主加入者などでの比率が高い。「ネットで情報収集し最終的には販売員などに相談」は約25%。
-
- 調査時期:
- 2022年12月
- 設問項目:
-
家電量販店の利用頻度/家電量販店利用目的/直近1年間に利用した家電量販店/直近1年間の最頻利用家電量販店/直近1年間の最頻利用家電量販店の利用理由/直近1年間に家電量販店の店頭で購入したもの/家電量販店店頭で商品購入時の、事前の情報収集手段/家電製品購入場所/家電量販店の不満点(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■家電量販店月1回以上利用者は約16%で、過去調査と比べ利用頻度が低下傾向。利用目的は「家電製品や関連用品を購入」「実物を見る」が利用者の各6~7割、「価格を確認」が36%、「家電に関する情報収集」が2割強。
■最頻利用家電量販店の利用理由は「家から近い」が6割弱、「ポイントカードなどのお得なサービス」が3割強、「駐車場」「品揃えが豊富」「価格が安い」が各2割前後。ヨドバシカメラ主利用者では「ポイントカードなどのお得なサービス」「品揃えが豊富」が上位2位。
■直近1年間家電量販店店頭での家電購入者の事前情報収集は、「店頭の商品、商品情報」「店員の説明」が各20%台で、女性高年代層でやや高い傾向。続いて「メーカーの公式ホームページ」「折込チラシ、ダイレクトメール」「商品比較サイト、口コミサイトなど」が各2割弱。
■家電製品・関連用品購入場所は「家電量販店の店頭」が全体の7割強、「家電量販店以外のオンラインショップ」が4割強、「家電量販店のオンラインショップ・通販サイト」が3割弱。
-
- 調査時期:
- 2022年12月
- 設問項目:
-
プライベートブランド購入頻度/直近1年間に購入したプライベートブランド商品/直近1年間に最もよく購入したプライベートブランド商品/プライベートブランド商品をよく買うカテゴリ/プライベートブランド購入場面/プライベートブランドとナショナルブランドの購入割合/プライベートブランド購入意向/プライベートブランド購入意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■プライベートブランド商品購入頻度が週1回以上の人は全体の4割弱。同カテゴリ商品の場合にプライベートブランド商品を買うことが多い人、メーカーのブランド商品を買うことが多い人はいずれも3割弱。
■直近1年間プライベートブランド商品購入者がよく買うカテゴリは「インスタント食品・レトルト食品、料理の素」「お菓子、チルドデザート、アイス類」「調味料、たれ・ソース類、油など」が各3割前後、「パン類」「冷凍食品」「牛乳、乳製品」などが各2割強。
■プライベートブランド商品を購入する場面は「コストパフォーマンスが良い」「価格を抑えたい、安いものを買いたい」が直近1年間購入者の各5割前後、「その商品が気に入っている」「味や品質、機能などが優れている」が各2割強~3割強。
■プライベートブランド購入意向者は全体の7割弱。「購入したいと思う」という強い購入意向は3割弱で、2017年調査より増加。週に1回以上購入者では80%台後半の購入意向、購入未経験者では約8%。
-
- 調査時期:
- 2022年12月
- 設問項目:
-
コンビニエンスストア利用頻度/商品・サービスをよく利用するコンビニエンスストア/信頼性・安心感があると思うコンビニエンスストア/商品開発力や企画力があると思うコンビニエンスストア/独自性があると思うコンビニンスストア/革新的・先進的であると思うコンビニエンスストア/顧客サービスが充実していると思うコンビニエンスストア/最も利用したいコンビニエンスストア/利用したいコンビニエンスストアの理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■『信頼性・安心感』『商品開発力や企画力』があると思うコンビニは、全体では「セブン‐イレブン」が各6割前後で1位、「ローソン」「ファミリーマート」が続く。『信頼性・安心感』は、四国では「ローソン」が1位、北海道では「セイコーマート」が2位。
■『革新的・先進的である』『顧客サービスが充実している』と思うコンビニは、全体では「セブン‐イレブン」が各4割弱で1位、「ローソン」「ファミリーマート」が各1割強~2割強、「特にない」が各5割弱。北海道では「セイコーマート」が『顧客サービスが充実している』の1位、『革新的・先進的である』の2位。
■『独自性がある』は「セブン‐イレブン」「ローソン」が各20%台、「ファミリーマート」「ミニストップ」が各2割弱。「セイコーマート」は全体では1割強で、過去調査と比べ増加傾向。北海道では約65%で1位。
■生活圏にあった場合に最も利用したいコンビニは全体では「セブン‐イレブン」が4割強、「ローソン」が2割弱、「ファミリーマート」が1割強。北海道では「セイコーマート」が1位、四国では「ローソン」が1位。