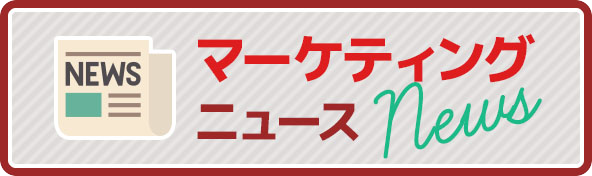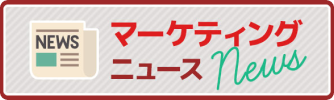- 検索
-
- テーマ別実施時期一覧
- カテゴリー別一覧
-
-
アルコール飲料・嗜好品147
-
非アルコール飲料210
-
その他19
-
-
住宅・住宅設備219
-
-
家電126
-
パソコン・カメラ・AV機器113
-
その他10
-
-
家庭用品・トイレタリー91
-
自動車・関連用品76
-
-
インターネット・情報通信328
-
携帯電話・スマートフォン180
-
メディア・広告66
-
その他7
-
-
ファッション69
-
交通・レジャー・娯楽161
-
季節行事・イベント241
-
時事・ニュース・トレンド51
-
企業ブランドイメージ250
-
広告・CM51
-
WEBサイトの利用91
-
顧客満足度100
- 実施時期別一覧
-
- 調査時期:
- 2025年06月
- 設問項目:
-
コンビニ弁当利用頻度/よく食べるコンビニ弁当のタイプ/コンビニ弁当選定基準/コンビニ弁当と一緒に買う飲み物/コンビニ弁当と一緒に買う食べ物/コンビニ弁当利用場面/コンビニ弁当の購入価格/弁当が最もおいしいと思うコンビニエンスストア/コンビニ弁当購入場面/コンビニ弁当非購入理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■コンビニ弁当利用者は全体の6割強、男性の方が比率が高い。コンビニ弁当利用者のうち週1回以上利用者は約15%、月1回以上利用者は4割強、男性や若年層での利用頻度が高い。コンビニ弁当利用者のうち、「セブン-イレブン」の弁当が一番おいしいと思う人の比率は4割弱。
■コンビニ弁当利用者がよく食べる弁当の種類は「ごはん+おかず」が5割強、「丼もの」「麺類」がそれぞれ約35%、「おにぎりとおかずの弁当」が3割弱。選定基準は「価格」「見た目がおいしそう・きれい」が各40%台、「味」が3割強、「様々な種類のおかずが入っている」「全体の量が多い」「健康に配慮」「野菜の量や種類が多い」などが各2割前後。
■コンビニ利用者のうち、コンビニ弁当と一緒に飲み物を買う人は7割強。緑茶や日本茶系飲料などのお茶系飲料が上位。一緒に買う食べ物は「サラダ」が2割弱、「スイーツ・デザート(ヨーグルト、プリン、ケーキなど)、アイスなど」が15.2%、「味噌汁」「パン類」などが各1割強。
■コンビニ弁当利用者が食べる場面は「食事を簡単に済ませたい」3割強、「食事や弁当を作るのが面倒」「食事や弁当を作る時間がない」各3割弱、「早く済ませたい」「移動中、旅行中など」「一人で食事をする」各2割前後。「昼食」は25%で2021年調査以降減少傾向。
-
- 調査時期:
- 2025年06月
- 設問項目:
-
ポイントサービスを利用している店舗・施設・サービス/ポイントサービス利用個数/直近1年間にポイントを使った店・施設/ポイントカードアプリの利用/直近1年間のポイントサービス利用状況/直近1年間の最頻利用ポイントサービス/ポイントサービスのポイント利用度合い/ポイントサービスの利用に関する行動/最頻利用ポイントサービスの利用理由/ポイントサービス非利用理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■ポイントサービス直近1年間利用店舗・サービスは「スーパーマーケット」「ドラッグストア」が各6~7割、「コンビニエンスストア」「クレジットカード」「オンラインショップ」が各5割強。過去調査と比べ「オンラインショップ」が増加傾向、「家電量販店」などが減少傾向。
■スマートフォンのポイントカードアプリ利用者は、ポイントサービス直近1年間利用者の8割弱で、2019年調査以降増加傾向。「共通ポイントサービスの公式アプリ」7割弱、「店舗独自のポイントの公式アプリ、会員アプリなど」は4割強。
■直近1年間ポイントサービス利用者のうち、ポイントを貯めたり使ったりしたポイントサービスは「楽天ポイント」8割弱、「Vポイント」5割強、「dポイント」「Pontaポイント」が各5割弱。「Vポイント」は男性の方が比率が高く、「WAON POINT」「LINEポイント」は女性の方が高い。
■ポイントサービスでたまるポイントを積極的に利用する人は、全体の7割強。「ポイントサービスの取り扱い店を選んで利用」「ポイント○倍デー、ポイント○倍対象商品などのキャンペーンがある時を狙って店や商品を利用・購入」「ポイントがたまる支払い方法を選ぶ」が各4割前後、「ポイ活をしている」が3割強。
-
- 調査時期:
- 2025年06月
- 設問項目:
-
衣料品の購入頻度/直近1年間の衣料品購入場所/直近1年間の衣料品最頻購入場所/直近1年間での、1ヶ月あたりの衣料品購入金額/衣料品を購入する店舗を選ぶ際の重視点/インターネットで衣料品を購入する場面/衣料品購入時の参考情報/衣料品最頻購入場所での購入理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■衣料品の購入頻度は「3~4ヶ月に1回程度」「半年に1回程度」がボリュームゾーン。過去調査と比べ購入頻度が減少傾向。1ヶ月あたりの平均購入金額は「1,000円~3,000円未満」「3,000円~5,000円未満」がボリュームゾーン。
■衣料品購入者の直近1年間の購入場所は「衣料量販店の単独店舗」が4割強、「インターネットショップ」「ショッピングセンター・モール」が各4割弱、「スーパー」が約26%。2018年調査以降「スーパー」「百貨店・デパート」などが減少傾向。女性10~50代では「ショッピングセンター・モール」「インターネットショップ」が上位2位。
■直近1年間衣料品購入者の店舗での購入時の重視点は「品揃えが豊富」5割弱、「値段が安い」「自分の好みに合ったコンセプト・テイスト」各4割前後、「店内に気軽に入れる」「商品が探しやすい・見やすい」「サイズ構成が幅広い」が各3割弱。購入時の参考情報は「店頭の商品、商品情報」「店頭のディスプレイ、マネキン」などの店頭情報が各20%台、「通販サイト・オンラインショップの商品紹介・レビュー」「メーカーや店舗の公式ホームページ」などのネットの情報や「折込チラシ、ダイレクトメール」などが各1割台後半。
■インターネットでの衣料品購入者の理由は「セールなどで割安で購入できる」「店頭よりも価格が安い」「たまたま欲しいものを見つけた」が各3割前後、「色やサイズ等がわかっているものを買う」「店に行けない・行くのが面倒」などがそれぞれ約25%。「衣料品は、ほぼインターネットで買う」は約25%。
-
- 調査時期:
- 2025年06月
- 設問項目:
-
株式の売買経験/証券会社の認知/現在取引している証券会社/主に取引している証券会社/信頼感や安心感があると思う証券会社/手数料が安いと思う証券会社/先進性があると思う証券会社/顧客対応がよいと思う証券会社/今後最も取引をしてみたい・継続したい証券会社/主に取引している証券会社のイメージ(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■現在取引先、利用意向ともに、「SBI証券」「楽天証券」「野村證券」などが上位。証券会社認知率は「野村證券」「大和証券」「SBI証券」が各6~7割、「楽天証券」「松井証券」「岡三証券」などが各5割前後で上位。
■『信頼性や安心感がある』『顧客対応がよい』のは「野村證券」「大和証券」「SBI証券」「楽天証券」などが上位(順不同)。『顧客対応がよい』は「いずれもない」が7割弱と高い。
■『手数料が安い』は、「SBI証券」「楽天証券」が各2割台半ば、「GMOクリック証券」「松井証券」「マネックス証券」がそれぞれ約5~6%。「いずれもない」が5割強。
■『先進性がある』のは「SBI証券」「楽天証券」が各10%台、「GMOクリック証券」「マネックス証券」が各5%台。「いずれもない」が6割弱。
-
- 調査時期:
- 2025年06月
- 設問項目:
-
美容に対する関心度/美容のために意識していること/美容のために食生活で意識していること/美容について意識して行う理由/美容のために使っているアイテム/美容にかける費用(1ヶ月あたり)/直近1年間に利用したことがある美容関連サービス/美容に関して気になること/美容のために気を付けていること・こだわり(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■美容関心層は全体の3割強、男性2割弱、女性5割強。男性10~30代では3割強。美容のために意識していることは「ウォーキングなど軽い運動」「食生活」「スキンケア・肌の手入れ(顔)」「水分補給」などが各2割台半ば~後半。食生活を意識する人のうち「栄養バランス」「野菜を多くとる」が各7割前後、「食べ過ぎない」が約45%、「たんぱく質を意識してとる」「寝る直前に食べない」「三食きちんと食べる」などが各4割前後。
■美容のために意識して行っている人の理由は「身だしなみを整える、清潔感」が5割強、「若々しく見られたい」「若さを維持したい」「よい印象を与えたい」が各20%台。「きれいに見られたい」「自分に自信をつけたい」「気分をあげるため」などは女性や、若年層での比率が高い。
■美容に関して気になることは「顔のしわ、たるみ、筋肉のゆるみなど」「顔のくすみ、しみ、そばかす、毛穴など」が各3割強、「体重」「肌の乾燥」「体型、スタイル」が各2割前後。「肌の乾燥」「顔の肌荒れ・肌のトラブル」「ヒゲや鼻毛、うぶ毛」「体のムダ毛」などは若年層、「顔のしわ、たるみ、筋肉のゆるみなど」は高年代層での比率が高い傾向。
■美容のために使うアイテムのうち「スキンケア用品」「洗顔料」は、女性では各7~8割、男性10~30代では各3割前後で上位2位の項目。美容関連サービスの直近1年間利用経験は「美容室・ヘアサロン」が女性の75%。「理容室」は男性の4割強で、男性高年代層での比率が高い傾向。
-
- 調査時期:
- 2025年06月
- 設問項目:
-
母の日での立場/母の日の実施状況/母の日に贈ったプレゼントの内容/母の日のプレゼント購入場所/プレゼント以外で母の日にしたこと/母の日にかけた費用総額/プレゼントを購入した時期/プレゼントしてほしいもの/プレゼントや何かをしたことの理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■母の日にプレゼントや何かをした人は約36%、してもらった人は約15%。母の日に何かをしてあげる立場の人で 『プレゼントや何かをした』は6割弱。母の日にかけた費用総額は「3,000円~5,000円未満」がボリュームゾーン。
■今年の母の日にプレゼントなどを贈った人のうち「お菓子」「食品・飲料」を贈った人は各2割強、「カーネーション以外の花・鉢植え・観葉植物」が各2割強、「カーネーション」」「カーネーション以外の花・鉢植え・観葉植物」が各2割弱、「衣料品、衣類小物」が各1割強。購入場所は「インターネットショップ」が3割強。
■プレゼントを贈る以外にしたことは、「一緒に家で食事」「会いに行った」がそれぞれ約17%、「一緒に外食をした」が1割強。
■母の日に何かをしてもらう立場の人が、母の日にしてほしいもの・ことは「感謝の気持ち」「お菓子」「外食」が各2割前後、「カーネーション以外の花・鉢植え・観葉植物」「食品・飲料」「カーネーション」「会いに来る」が各1割強。
-
- 調査時期:
- 2025年05月
- 設問項目:
-
キャンディを食べる頻度/キャンディを食べる場面/好きなキャンディの味/キャンディ購入時の重視点/キャンディ購入場所/どのような効能・効果があるキャンディを食べたいか/キャンディを食べない理由/物価上昇による、キャンディ購入の仕方の変化/市販のキャンディの不満点(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■キャンディを食べる人は全体の5割。週1回以上食べる人は3割強。好きなキャンディの味は「のど飴」が約56%、「フルーツ味」が5割弱、「ミルク味」「ハチミツレモン味」「ハーブキャンディ」などが各30%台。物価上昇により購入の仕方に変化があった人は2割強。
■キャンディを食べる人のうち「咳やのどの炎症をおさえたいとき」に食べる人が5割弱、「仕事・勉強・家事」「くつろぎながら」「ちょっと一息つきたいとき」「移動中」「口さびしくなったとき」などが各3割弱。食べる人の購入時重視点は「味」8割弱、「価格」「容量、サイズ」が各4割前後、「効能・効果」が3割強、「食べ慣れている」「形や大きさ、色」が各2割前後。
■購入者のうち「スーパー」で購入するが8割弱、「ドラッグストア」「コンビニエンスストア」が各30%台。「ドラッグストア」が過去調査と比べて増加傾向、「コンビニエンスストア」が減少傾向。キャンディをほとんど食べない人(全体の5割)の理由は「虫歯の原因になる」が約25%、「キャンディを必要とする場面・食べたい場面が少ない」が2割弱。
■効能・効果があるキャンディの利用意向は「のどの痛み、イガイガを抑える」が6割強、「リラックス効果」が約26%、「虫歯予防、キシリトール配合など」「口臭予防」「ビタミン、クエン酸、葉酸など栄養素配合」が各2割強。
-
- 調査時期:
- 2025年05月
- 設問項目:
-
しょうゆの嗜好度/自宅でのしょうゆの利用頻度/利用するしょうゆのタイプ/しょうゆの種類の使い分け/使用しているしょうゆのメーカー/使用しているしょうゆの形状・容器/しょうゆ購入時の重視点/しょうゆ購入時の銘柄・価格による選定状況/しょうゆのこだわり・気をつけていること(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■自宅でのしょうゆの利用頻度は「ほとんど毎日」が3割強、「週4~5回」「週2~3回」が各2割台半ば。東北での利用頻度が高い傾向。「プッシュタイプ」使用者(しょうゆ使用者のうち4割強)が過去調査と比べ増加傾向。
■しょうゆ使用者が自宅で使うタイプは「こいくちしょうゆ」が6割弱、「減塩しょうゆ」「うすくち(淡口)しょうゆ」が各2割強、「丸大豆しょうゆ」「だし入りしょうゆ」「さしみ醤油」などが各1割台半ば~後半。「用途や料理によって使い分ける」はしょうゆ使用者の4割弱で、西日本での比率が高い傾向。
■しょうゆ使用者の重視点は「味」6割弱、「価格」5割弱、「しょうゆの種類」が約35%、「容量、サイズ」が3割弱。しょうゆ使用者の自宅での使用メーカーは「キッコーマン」が6割強、「ヤマサ醤油」が2割強、「ヒガシマル醤油」が1割強。
■市販のしょうゆ購入時に「だいたい同じ商品を買う」はしょうゆ購入者の約3分の2。「メーカーや銘柄はだいたい決まっているがその中で価格が安いものを買うことが多い」が約16%。
-
- 調査時期:
- 2025年05月
- 設問項目:
-
朝食の頻度/朝食を食べない理由/朝食として飲食するもの/朝食にかける時間/朝食のメニュー決定時の重視点/朝食をしっかり食べる派/軽めに済ませる派/朝に飲食しているもので最も多いパターン/平日の朝食・休日の朝食で変わること/朝食の定番メニューや食べることが多いメニュー(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■朝食を「毎日食べている」は全体の7割強で、過去調査と比べ微減傾向。若年層での比率が低い。朝食を食べない時の理由は「時間がない」「おなかがすかない」が約13~15%。
■朝食として飲食するものは「パン類」が約65%で高年代層での比率が高い。「ご飯類」は約45%。おかず・他は「卵や卵料理のおかず」が3割強、「味噌汁」が3割弱、「野菜のおかず」が2割強、「ヨーグルト、飲むヨーグルト」は4割弱、「果物」は2割強。飲み物は「コーヒー、コーヒー系飲料」が4割強、「牛乳」が2割強。朝食をとる人のメニュー決定時の重視点は、「食べるのに時間がかからない」が4割強、「栄養バランス」「作るのに時間がかからない」が各20%台。
■朝食をとる人のうち、朝食にかける時間が10分以内の比率は4割強。朝食をとる人のうち、しっかり食べる派は4割強、軽めに済ませる派は4割弱。平日朝の飲食パターンで最も多いものは「主食+おかず」が4割強、「主食+おかず以外」「主食のみ」が各2割弱。
■朝食をとる人のうち、「平日も休日も、基本的にあまり変わらない」は約75%。「平日と休日で主なメニューを変える」が約9%、「平日は朝食をとる/休日はとらない」が約4%、「平日は簡単なものを食べることが多い/休日は準備に時間をかけたり、しっかり食べることが多い」が約3%。
-
- 調査時期:
- 2025年05月
- 設問項目:
-
洋食の嗜好度/好きな洋食のメニュー/洋食を食べるシーン/自宅で洋食を食べる頻度/自宅で食べる洋食のメニュー/自宅で食べる洋食の準備方法/自宅で食べる洋食の重視点/洋食のイメージ/洋食の魅力(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■洋食を「夕食」に食べる人は全体の8割弱、「昼食」「外食」が各5割弱。自宅で洋食を食べる人のうち「週に2~3回くらい」食べる人が4割強。女性や高年代層での比率が高い傾向。
■自宅で洋食を食べる人の準備方法は「自分や家族の手作り」が8割弱、「冷凍食品、レトルト食品」は約46%。「お惣菜、弁当」は4割弱で、過去調査と比べ増加傾向。自宅で洋食を食べる人の重視点は「価格」が4割強、「栄養バランス」「野菜をたくさん食べる」が各3割弱、「原材料」が2割強。
■好きな洋食のメニューの上位は「カレーライス」「ハンバーグ」「ステーキ」「オムライス」「エビフライ」など。自宅で洋食を食べる人が食べるメニューの上位は「カレーライス」8割弱、「ハンバーグ」5割強、「スパゲティミートソース」3割強、「スパゲティナポリタン」「トンカツ、ポークカツレツ」「ポテトコロッケ」「クリームシチュー」「オムライス」「コーンスープ、ポタージュ」各20%台。
■洋食のイメージは「庶民的」「カロリーが高い」が各3割台後半、「こってりした」「味が濃い」「華やか」が各20%台。「見栄えがしない」「味が薄い」「カロリーが低い」「あっさりした」「繊細」「革新的」「ヘルシー」などは比率が低い。
-
- 調査時期:
- 2025年05月
- 設問項目:
-
プラントベースフードの認知/直近1年間のプラントベースフード飲食状況/プラントベースフードを飲食したきっかけ・理由/プラントベースフードが植物由来であることの意識度合い/プラントベースフード飲食意向/プラントベースフードの魅力/プラントベースフードで気になること・不安なこと/プラントベースフード飲食意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■プラントベースフードの認知率は3割弱(「どのようなものか内容を知っている」約8%、「聞いたことがある程度」2割弱)。直近1年間飲食者は4割弱で女性の方が比率が高い。飲食したものは「植物性ミルク」が約16%、「大豆ミートなどの代替肉を調理したもの」が1割強。
■プラントベースフード直近1年間利用者の、利用のきっかけ・理由は「健康のため」「からだによさそう」が各3割弱、「試してみた」が2割弱、「糖質や脂質が低い」「高たんぱく低カロリー」「体調の維持・改善」が各1割強。プラントベースフード飲食意向者は約26%で、2021年調査以降減少傾向。非飲食意向者は3割強。
■プラントベースフードについて魅力的に感じる点は「健康に良い」が約35%、「食物繊維を多く摂取できる」「脂質の吸収を抑えられる」「ヘルシーで、ある程度の満足感が得られる」「高たんぱく低カロリー」「良質な植物性タンパク質を摂取できる」などが各10%台。
■プラントベースフードについて気になることは「おいしいかどうか」が約45%、「価格が高そう」が約25%、「添加物が不安」「加工の過程で、何が入っているかわからない」「本当に安全かどうか不安」などが各2割弱。
-
- 調査時期:
- 2025年05月
- 設問項目:
-
高齢家族との同居・別居状況/見守りサービス利用状況/利用したことがある見守りサービス/見守りサービス利用のきっかけ・理由/見守りサービス利用意向/利用したい見守りサービスの種類/利用したい見守りサービスの重視点/見守られる側の立場として利用してもよいサービス/見守りサービス利用意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■離れて暮らす家族などの状態を確認・サポートする見守りサービスの現在利用者は約3%、利用経験者は約5%、サービス認知者は6割弱。別居している65歳以上高齢者がいる層のうち、サービス利用者は約5%。見守りサービス利用経験者の利用のきっかけ・理由は「高齢になり、体の衰えや物忘れなどが気になるようになった」が4割強、「要介護、認知症などの診断・疑いがあった」「家族・親族などが一人暮らし・夫婦だけの生活になった」が約25~26%。
■見守りサービス利用経験者のうち「定期的に訪問して安否確認」「食事宅配サービス、新聞などの配達時に安否確認」が各2割強。別居している65歳以上高齢者がいる層では、「センサーを設置、異常時に自動通知」「担当者が定期的に訪問して安否確認」「要請があった際に、サービス事業者が駆けつける」が上位。
■見守りサービス利用意向者は全体の25%、非利用意向者は1割強。利用意向者は、現在利用者の8割弱、利用経験あり・中止者の4割強、サービス認知・利用未経験者の3割弱。利用意向者が利用したいサービスは「定期的に訪問し安否確認」「センサーを設置、異常時に通知」「要請があった際にサービス事業者が駆けつける」が各3割強、「食事宅配サービス、新聞などの配達時に安否確認」が3割弱。
■見守りサービス利用意向者の重視点は「料金」が7割強、「サービスの種類やプランの充実度」「料金体系のわかりやすさ」「緊急時対応のスムーズ・迅速さ」が各4割前後。
-
- 調査時期:
- 2025年05月
- 設問項目:
-
コンビニの冷蔵コーナーのスイーツのうち購入するもの/コンビニの冷蔵コーナーのスイーツを買う頻度/コンビニの冷蔵スイーツ購入場面/コンビニの冷蔵スイーツ選定時の重視点/コンビニでの冷蔵スイーツ購入時の1回あたりの許容額/直近1年間に冷蔵コーナーのスイーツを購入したコンビニエンスストア/コンビニの冷蔵スイーツが最も好きなコンビニエンスストア/コンビニで冷蔵スイーツを買う理由/気に入っているコンビニの冷蔵スイーツ(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■コンビニの冷蔵スイーツ購入者は全体の約54%、男性約46%、女性65%。購入種類は「シュークリーム、エクレア」が3割強、「ロールケーキ」「プリン、パンナコッタ」がそれぞれ約24%。コンビニの冷蔵スイーツ購入者のうち月1回以上購入者は約56%。1回あたり購入許容額は「250円~300円未満」がボリュームゾーン。購入許容額は2016年以降上昇傾向。
■コンビニの冷蔵スイーツ購入者が買う場面は「甘いものが食べたい」が7割弱、「食後のデザート」「店頭でおいしそうな商品を見かけた」が各3割弱、「立ち寄ったついで」「小腹が空いた」「自分へのご褒美をあげたい」「気分転換やストレス解消」が各2割前後。
■コンビニの冷蔵スイーツ購入者がコンビニで買う理由は「いつでも買える」4割強、「おいしい・おいしそう」4割弱、「立地がよい・行きやすい」3割弱、「価格が手頃」「少量でも買いやすい」各2割強。購入者の重視点は「味」8割弱、「価格」が56%、「容量、サイズ」25%、「食感」「色合い・見た目」「甘さ」「季節感」各2割前後。
■コンビニの冷蔵スイーツ購入者が、スイーツが最も好きなコンビニエンスストアは、「ローソン」約35%、「セブン‐イレブン」3割強、「ファミリーマート」2割弱。「セブン‐イレブン」は過去調査と比べて減少傾向で、2024年調査よりも順位が低下し2位。
-
- 調査時期:
- 2025年05月
- 設問項目:
-
分譲マンション購入時期/マンション購入時の重視点/マンション購入時の情報源/マンションブランドの認知/住んでみたいマンションブランド/一戸建て/マンション居住意向/一戸建て/マンション居住意向理由/住んでみたいマンションブランドの理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■マンション購入経験者・意向者の重視点は「最寄駅からの距離」「生活環境の利便性」が各60%台、「日当たり・採光」「間取り」などが各50%台。
■マンション購入経験・意向者の情報源は「住宅情報サイト」「マンション販売会社・仲介会社など不動産会社のWebサイト」が各4割弱、「展示場・モデルルーム」が3割、「ポストに投函されるチラシ、ダイレクトメール」が2割強。
■一戸建て・マンションのどちらに住みたいかをたずねると、一戸建ては約54%、マンションは2割強。「マンションに住みたい」は関東、北海道、近畿、九州で他地域よりやや高い。一戸建てに住みたい理由は「駐車場代がかからない」「庭を造ることができる」が各4割強、「管理組合などのわずらわしさがない」「プライバシーを守りやすい」が各30%台。
■マンションに住みたい理由は「セキュリティが充実」「機密性、断熱性が高い」「設備のメンテナンス・清掃などの負担が少ない」が各40%台、「設備が充実」「耐震性が高い」「近所付き合いのわずらわしさが少ない」が各30%台。
-
- 調査時期:
- 2025年05月
- 設問項目:
-
損害保険の加入状況/加入損害保険の種類/火災保険を契約している保険会社/火災保険を契約している保険会社の満足度/地震保険を契約している保険会社/地震保険を契約している保険会社の満足度/加入したい損害保険/火災保険加入/継続したい保険会社/地震保険加入/継続したい保険会社/火災保険・地震保険について不安・不満に思うこと(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■損害保険加入者は約76%。損害保険加入者のうち「自動車保険・任意加入」「火災保険・建物への補償」への加入者は各70%台、「火災保険・家財への補償(家財保険)」「地震保険」が各4~5割。全体に占める火災保険加入者は6割強、地震保険加入者は約35%。
■火災保険の契約保険会社について満足+やや満足の比率は、ソニー損保主加入者で約65%、県民共済主加入者、日新火災海上保険主加入者で各6割弱。
■今後加入したい損害保険は、「火災保険・建物への補償」が2割弱、「自動車保険・任意加入」「地震保険、地震補償保険」「火災保険・家財への補償(家財保険)」が約15~16%。
-
- 調査時期:
- 2025年05月
- 設問項目:
-
ラジオ番組受信方法/ラジオ番組受信方法で最も多いもの/ラジオ局の放送の、リアルタイム・録音での聴取状況/ラジオ局の放送を受信する機器/ラジオ局の放送を聞く頻度/ラジオ局の放送の1日あたり聴取時間/ラジオ局の放送を聞く場面/ラジオ番組受信方法の意向/ラジオを聞くときの様子・スタイル(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■ラジオ聴取者は約56%。地上波ラジオ放送を「ラジオチューナーで受信」は全体の4割弱で、過去調査と比べ減少傾向。「インターネット経由」は2割強。地上波ラジオ放送聴取者(全体の5割強)のうち、「タイムフリー・聞き逃し機能などで放送後に聞く」は約25%で、過去調査と比べて増加傾向。
■地上波ラジオ聴取者のラジオ放送受信手段は「カーステレオ、カーナビ」4割強、「スマートフォン」3割弱、「ラジカセ、CDラジオ」「パソコン」が各2割弱。「スマートフォン」は若年層での比率が高い傾向で、10~30代では1位。
■地上波ラジオ聴取者のうち週4~5回以上聞く人は4割強。ほとんど毎日聴取者は男性や高年代層で高い傾向。2021年調査と比べ、聴取頻度は低下傾向。聴取場面は「トークを聞く」5割弱、「音楽」「ニュース・天気予報」各4割強、「運転中、車の中」が3割強。「好きな・興味がある人が出演する番組を聞く」は10・20代や、インターネット経由で受信する層で比率が高い。
■ラジオ番組の受信方法の意向は「ラジオチューナーで受信」が全体の4割強で、過去調査と比べやや減少。「インターネット経由で受信」は約25%。今後「ラジオは聞きたいと思わない」は約26%で、10~30代での比率が高い。
-
- 調査時期:
- 2025年05月
- 設問項目:
-
デジタルサイネージ広告の直近1年間認知経験/デジタルサイネージ広告を直近1年間に見た店・施設/印象に残る・興味があったデジタルサイネージ広告があった店舗(直近1年間)/デジタルサイネージ広告で印象に残っている・興味があった場所(直近1年間)/印象に残る・興味があったデジタルサイネージ広告の内容(直近1年間)/デジタルサイネージ広告を見た後の意識・行動/デジタルサイネージ広告の意識度合い/デジタルサイネージ広告に関する意見/デジタルサイネージ広告で印象に残ったもの/あったらよいと思う広告の内容(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■デジタルサイネージ広告直近1年間認知率は認知率は6割強(直近1年間に「見たことがある」4割弱、「見たことがあるような気がする」2割強)。直近1年間認知者のうち「スーパー」で見た人が5割強、「コンビニエンスストア」約35%、「ショッピングモール」「ドラッグストア」「家電量販店」各2割強。
■デジタルサイネージ広告直近1年間認知者のうち、広告が印象に残った店舗は「スーパー」約19%、「コンビニエンスストア」約15%。「特にない」は5割弱。印象に残る広告があった場所は「店内」が約19%、「店の入り口付近」「商品の近くや、陳列棚近く」がそれぞれ約15%。「レジの周辺」は1割強で、コンビニエンスストアでの広告認知者で比率が高い。
■デジタルサイネージ広告直近1年間認知者が、印象に残る広告の内容は「おすすめや人気の商品・サービス等の紹介」「新しい商品・サービス等の紹介」が各2割強、「お得情報」が1割強。
■デジタルサイネージ広告直近1年間認知者の、広告認知後の意識・行動は広告で見た商品・サービス・メニューに「興味を持った」が2割弱、「見た・手に取った」「店内で探した」がそれぞれ約7%。デジタルサイネージ広告についての意見は「わざわざ見るほどの内容ではない」が3割弱、「映像や音声があるので、目に入りやすい」は約24%、「映像や音声があるので商品やサービスの内容がわかりやすい」は約16%。
-
- 調査時期:
- 2025年05月
- 設問項目:
-
犬・猫の飼育状況/犬のえさのタイプ/猫のえさのタイプ/市販の犬・猫のペットフードの直近1年間購入場所/市販の犬・猫のペットフードの直近1年間での月額費用/市販のペットフード購入時の重視点/市販の犬や猫のペットフード選定時の参考情報源/犬・猫の食事・ペットフードについての悩み・困りごとの対処方法/犬・猫のペットフードについての悩み・困りごと(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■犬・猫のいずれかを飼っている人は全体の2割弱。犬のみを飼っている人は約9%、猫のみを飼っている人は約8%。
■市販のペットフードのタイプは「ドライ」が犬飼育者の8割強、猫飼育者の約94%、「おやつ・スナック」が犬・猫の各5割前後。犬を飼っている人では「ウェット」が約25%、「半生」「市販のペットフードと、手作りのものや素材などを混ぜたもの」が各2割弱。猫を飼っている人では「ウェット」が5割弱。犬や猫の飼育者のペットフード直近1年間購入場所は「ホームセンター」4割弱、「オンラインショッピング」約35%、「スーパー」「ドラッグストア」各3割弱。
■ペットフード直近1年間購入者の重視点は「対象年齢」「原材料」が各4割強、「嗜好性」「安全性」「価格」が各4割弱、「製品特徴」「成分」が約34%。猫を飼っている人では「嗜好性(ペットの好みにあっている)」「対象年齢」「価格」が上位3位。ペットフード直近1年間購入者のうち、1ヶ月あたりの費用が3千円以上の比率は約54%で、2022年調査より増加。
■直近1年間ペットフード購入者の選定時の参考情報源は「商品パッケージの説明」が3割弱、「獣医師やブリーダーなど専門家の意見」「店頭の情報(POPなど)」が各2割弱。小型犬飼育者・大型犬飼育者では「獣医師やブリーダーなど専門家の意見」が1位。飼育に関する悩みの対処法は「獣医師、動物病院に相談」が4割弱、「家族や友人・知人に相談」「犬や猫に関する情報サイトや、口コミサイトなどで調べる」が2割弱。
-
- 調査時期:
- 2025年04月
- 設問項目:
-
スーツ所有数/スーツ着用場面/直近1年間でのスーツ着用頻度/スーツ購入場所/スーツ購入店舗の重視点/スーツの購入価格帯(1着あたり)/スーツ購入時の重視点/直近3年間でのスーツ購入頻度/直近3年間に購入したオーダースーツのタイプ/スーツ購入時の不満点(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■スーツ所有数は「2~3着」がボリュームゾーン。スーツを着る頻度が年に1回未満の比率はスーツ所有者の4割強。週1回以上は約16%。
■スーツ所有者の着用場面は「法事、お葬式等」が約55%、「仕事」「結婚式」が各4割弱、「入学式・卒業式など行事やお祝いごと」などが3割弱。「仕事」は男性30~50代で各50%台。「入学式・卒業式など行事やお祝いごと」は女性40~50代での比率が高い。
■スーツ購入者のうち、直近3年間での購入者は3割弱。「2~3年に1回程度」は1割強。スーツ所有者のうち「スーツ量販店」での購入者は約46%、男性では6割強で1位。女性の上位2位は「デパート」「大型スーパー」。実店舗でのスーツ購入者の店舗選定時の重視点は「品揃えが豊富」「サイズが豊富」が各5割弱、「価格が安い」「自分の好みに合ったコンセプト・テイスト」が各30%台。
■スーツ購入者の重視点は「サイズが合う」が8割弱、「好みの色・柄」「価格」が各6割弱、「着心地」「好みの形」が各4割強、「素材」が3割強。直近3年間スーツ購入者のうち、オーダースーツ購入者は5割弱、男性6割弱、女性3割弱。「フルオーダー」約5%、「イージーオーダー」2割弱、「パターンオーダー」3割弱。
-
- 調査時期:
- 2025年04月
- 設問項目:
-
デジタルギフトサービスの認知/直近1年間でのデジタルギフトを贈った・もらった経験/直近1年間デジタルギフト贈答時の利用サービス/直近1年間に贈ったデジタルギフトの内容/直近1年間にもらったデジタルギフトの内容/デジタルギフトの利用意向(贈る側)/デジタルギフトを利用したい場面/デジタルギフトの利用意向(贈る側)の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■デジタルギフトサービスを知っている人は全体の7割弱。直近1年間にデジタルギフトを贈った人は1割強、もらった人は4割弱。いずれも若年層での比率が高い傾向。2022年調査と比べ、直近1年間にもらった人の比率が増加。
■直近1年間にデジタルギフトを贈った人(全体の1割強)の利用サービスは、「LINEギフト」が4割強、「Amazonギフトカード」が4割弱、「giftee」が1割強。贈った内容は「飲食店、コーヒーショップ、テイクアウトサービスなどで使えるチケット・引換券」が4割弱、「Amazonギフトカード、Apple Gift Cardなどデジタルギフト券」が3割強、「コンビニの電子ギフト券、コンビニエンスストアの商品と交換できる」「食品、菓子・デザート類、飲料、お酒など」が各2割前後。
■直近1年間にデジタルギフトをもらった人(全体の4割弱)の内容は「Amazonギフトカード、Apple Gift Cardなどデジタルギフト券」が約54%、「飲食店、コーヒーショップ、テイクアウトサービスなどで使えるチケット・引換券」「ポイント、電子マネー」「コンビニの電子ギフト券、コンビニエンスストアの商品と交換できる」が各20%台。
■デジタルギフトを贈る側としての利用意向は約25%、非利用意向は3割強。デジタルギフトを直近1年間に贈った人の利用意向は8割弱、もらった人では4割強、直近1年間未利用者では1割強。利用意向者が贈りたい場面は「お返し、ちょっとしたお礼」「誕生日や記念日」が各5割台半ば、「お祝い事」が3割強、「直接会って渡せない」「気軽に贈りたい」が各2割強。
-
- 調査時期:
- 2025年04月
- 設問項目:
-
通信販売利用経験/直近1年以内での通信販売の申し込み手段/ショッピングサイト利用時の重視点/オンラインショッピングで購入する場面/パソコンのオンラインショッピングで直近1年間に購入したもの/パソコンでのオンラインショッピング直近1年間利用頻度/スマートフォン・携帯電話のオンラインショッピングで直近1年間に購入したもの/スマートフォン・携帯電話での直近1年間オンラインショッピング利用頻度/オンラインショッピングサイト利用時の不満点(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■通信販売利用経験者のうち、1年以内「インターネット(パソコン)」での通販利用者は7割強で、過去調査より減少傾向。そのうち年間10回以上利用者は5割弱。スマートフォン・携帯電話での1年以内通販利用者は5割強で、過去調査と比べ増加傾向。そのうち年間10回以上利用者は4割弱、女性の方が利用頻度が高い傾向。
■直近1年間のパソコンでのオンラインショッピング経験者の購入商品は「食料品、飲料、アルコール」が5割強、「衣料品」が4割強、「書籍・雑誌・コミック」が3割強。
■スマートフォン・携帯電話でのオンラインショッピング直近1年間経験者の購入商品は「食料品・飲料・アルコール」「衣料品」が各40%台、「衣類小物、装飾品」「生活用品「化粧品、美容用品」「書籍・雑誌・コミック」「健康食品、サプリメント、医薬品等」がそれぞれ20%台後半。パソコンでの順位と比べ「衣類小物、装飾品」「化粧品、美容用品」などの順位が上位、「家電製品、AV機器等」などの順位が下位となっている。
■オンラインショッピング直近1年間利用者のサイト重視点は「送料が安い・無料」「商品価格」「豊富な品揃え」が各6割強~7割強。店頭ではなくオンラインショッピングで購入する場面は「価格が安い」が直近1年間利用者の6割強、「ポイントで商品が買える」が4割強、「クーポンやキャンペーン」「持ち帰りしにくいもの」「配送料が割安」「手に入りにくい商品・サービスの購入・利用」などが各3割前後。
-
- 調査時期:
- 2025年04月
- 設問項目:
-
口座を所有している銀行/所有口座数/銀行口座の2個以上所有理由/銀行口座の用途に応じた使い分け状況/メインバンクとして使っている銀行/メインバンクの口座の利用目的/サブバンクとして使っている銀行/サブバンクの口座の利用目的/銀行口座の使い分け方法(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■銀行口座所有数は、5個以上が全体の3割強、男性の方が口座保有数が多い傾向。2個以上の口座所有者のうち、用途に応じて口座を「使い分けている」は85%。
■2個以上の口座所有者の理由は「ATMや店舗が近くにある銀行を使える」「引き落とし用、貯蓄用など目的別に使い分ける」「口座開設の必要があった」が各3割強、「金利・手数料など利便性に応じて使い分ける」「入金・出金を整理し効率よく資産管理」が各20%台。
■2個以上の銀行口座を使い分けている人の、メインバンク利用目的は「給与・年金などの振込」約66%、「クレジットカード引き落とし」「引き落とし(公共料金など)」各5割強、「生活費」4割強、「貯蓄」3割弱。
■2個以上の銀行口座を使い分けている人のサブバンク利用目的は「貯蓄」3割弱、「クレジットカード引き落とし」「引き落とし(公共料金など)」各2割前後。メインバンクの目的と比べ「貯蓄」「投資」などが上位。サブバンクで住信SBIネット銀行利用者では1位「投資」、2位「貯蓄」。
-
- 調査時期:
- 2025年04月
- 設問項目:
-
洗濯機・洗濯乾燥機所有状況/直近1年間コインランドリー利用頻度/コインランドリー利用場面/コインランドリー利用時間帯/コインランドリー利用時の重視点/コインランドリー利用意向/コインランドリーで気になること/利用したいと思うコインランドリーの特徴/コインランドリー利用意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■コインランドリー直近1年間利用者は全体の約24%で2022年調査より増加。直近1年間利用者に占める月1回以上利用者の比率は約25%で男性や若年層での比率が高い傾向。利用時間帯は「平日・午前中」「休日・午前中」がボリュームゾーン。
■コインランドリー直近1年間利用者の利用場面は「毛布や布団、シーツ、カーテンなど大物を洗う」が6割弱、「天気が悪い、雨が続く」が25.6%、「乾燥機を使いたい」が22.6%。利用時の重視点は「アクセスの良さ」が7割強、「料金」が約46%、「駐車場の充実度」が4割弱、「毛布や布団など大物の洗濯物に対応」「洗濯機・乾燥機の台数」「店内の清潔感」が各3割前後。
■コインランドリー利用意向者は4割強、非利用意向者は3割強。過去調査と比べ利用意向者の比率が増加傾向。直近1年間利用者の利用意向の比率は各8割強~9割強、以前利用したことがある人では4割強、未経験者では1割強。
■コインランドリーについて気になることは、「衛生面で不安」が4割台半ば、「料金が高い」「他の人が使った後のウイルスや汚れ」「洗濯機や乾燥機の手入れ」が各3割前後。利用したいと思うコインランドリーの特徴は「清潔感」が全体の5割強、「毛布や布団など大物の洗濯物に対応」「料金が割安」「防犯対策が充実」「洗濯機・乾燥機が高性能」などが各30%台。
-
- 調査時期:
- 2025年04月
- 設問項目:
-
直近1年間のプレゼント・キャンペーンへの応募頻度/直近1年間に応募したプレゼント・キャンペーンの応募条件/直近1年間に応募したプレゼント・キャンペーンの提供元/直近1年間に応募したプレゼント・キャンペーンの景品・賞品/直近1年間に応募したプレゼント・キャンペーンの応募経路/直近1年間に応募したプレゼント・キャンペーンの応募時の行動/直近1年間に応募したプレゼント・キャンペーンに関する情報入手先/プレゼント・キャンペーンに応募したいと思う条件/応募してみたいと思うプレゼント・キャンペーンの内容(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■直近1年間のプレゼント・キャンペーン応募者は全体の5割強で、女性の方がやや比率が高い。10回以上応募者が2割。応募者のうち「スマートフォンから」の応募が7割弱、女性や若年層での比率が高い。
■直近1年間応募者の応募条件は、「条件はない」「対象商品についているシールやバーコードなどを集める」「クイズやアンケート、キーワード等に答える」がそれぞれ4割強。今後応募したいと思う条件は「条件はない」が5割弱、「クイズやアンケート、キーワード等に答える」が3割弱、「対象商品についているシールやバーコードなどを集める」「QRコードやID、シリアルナンバー等がついている商品を購入」「対象商品を購入」が各2割強。
■直近1年間に応募したプレゼント・キャンペーンの提供元は「食料品」が応募者の約55%、「飲料(お酒以外)」が4割強、「お酒」が3割強。景品は「食料品」「ギフト券、図書カード、QUOカード、現金・金券、キャッシュバックなど」が各4割弱、「ポイント、ポイント●●倍など」「飲料(お酒以外)」「お酒」が各3割弱。
■直近1年間応募者の情報入手先は「商品パッケージの説明、商品についていたシール・バーコードなど」が3割強、「店頭の告知物」「商品やサービス購入時についていた・もらったもの」「SNS」「プレゼント・キャンペーン、懸賞の情報サイト」「メールマガジン」が各2割前後。「SNS」は10~30代では1位。直近1年間応募者のうち「応募のために購入する量や利用回数が増えた」が2割強。
-
- 調査時期:
- 2025年04月
- 設問項目:
-
コーヒーチェーン店の利用頻度/直近1年間に利用したコーヒーチェーン店/直近1年間に最もよく利用したコーヒーチェーン店/コーヒーチェーン店利用場面/コーヒーチェーン店利用時間帯/コーヒーチェーン店利用時の重視点/最も利用したいコーヒーチェーン店/最も利用したいコーヒーチェーン店の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■コーヒーチェーン店現在利用者は全体の約55%で、2021年調査以降増加傾向。利用頻度は「月に1回以下」がボリュームゾーン。コーヒーチェーン店利用者が最も利用したい店は「スターバックスコーヒー」が3割弱、「コメダ珈琲店」が20%、「ドトールコーヒーショップ」が約15%。
■コーヒーチェーン店直近1年間利用者の利用場面は「休憩」が4割強、「友人や仲間とのおしゃべり」が3割弱。過去調査と比べ「暇つぶし、時間つぶし」などは減少傾向。スターバックス主利用者では「ドリンクのテイクアウト」の比率が高い。
■コーヒーチェーン店直近1年間利用者の利用時間帯は、「午後(14時~16時台)」が6割強、「昼(11時~13時台)」が3割強。コメダ珈琲店主利用者では「朝(7時~10時台)」の比率が高い。
■直近1年間コーヒーチェーン店利用者の重視点は「コーヒーの味・品質」が5割強、「価格」「居心地のよさ」「店の雰囲気」「アクセスのよさ」「店内の入りやすさ」などが各30%台。「ドリンクメニューの充実度」の比率は女性や、若年層で高い傾向。
-
- 調査時期:
- 2025年04月
- 設問項目:
-
スマートホームの認知/スマートホームデバイス・関連機器の所有状況/スマートホームデバイス・関連機器を所有していない理由/スマートホームデバイス・関連機器の所有ブランド・メーカー/スマートホームデバイス・関連機器の利用状況/スマートホームデバイス・関連機器を所有しようと思ったきっかけ/スマートホームの興味度/スマートホームのイメージ/スマートホームでやってみたいこと/スマートホーム利用者:利用状況/非利用者:利用したいこと、利用したくない理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■スマートホームの「内容について知っている」約15%、「聞いたことがある程度」56%。スマートホーム関連機器所有率は「スマートスピーカー」10%、「ロボット掃除機」「スマートリモコン」各約5%、「スマート電球」「見守りカメラ、ネットワークカメラ」各約4%。スマートホーム興味層は約23%、非興味層は約56%。
■スマートホーム関連機器非所有者の非所有理由は「必要性を感じない」が5割弱、「便利だと思うが、わざわざ設定するほどではない」が3割強、「十分知らない・よくわからない」「購入費用・維持費がかかる・かかりそう」が各20%台。
■スマートホーム関連機器所有者の利用方法は「自宅でスマートフォンから遠隔操作」「外出時にスマートフォンから遠隔操作」が各20%台、「音声で操作」が2割弱。今後やってみたいことは「外出時にスマートフォンから遠隔操作」が約24%、「自宅のセキュリティ対策」が2割弱。所有者のきっかけは「家電の購入・買い替え時」が2割弱、「日常生活の効率化・時短」が約14%。
■スマートホームのイメージは「費用がかかる」が3割弱、「故障や誤動作などのトラブル時、災害時などの対応が大変」「スマートフォンに依存しすぎ」が各2割弱、「自分自身の生活の手間が省ける」「操作や設定、メンテナンスなどが難しい・わかりにくい」が各約15%。スマートホーム関連機器利用者では「家族全体の快適な暮らしが実現」「自分自身の快適な暮らしが実現」「自分自身の生活の手間が省ける、効率的に暮らせる」が上位3位。
-
- 調査時期:
- 2025年04月
- 設問項目:
-
食生活の状況/完全栄養食の認知・直近1年間利用状況/完全栄養食直近1年間飲食状況/完全栄養食を直近1年間に飲食した理由/購入時の完全栄養食の意識度合い/完全栄養食直近1年間飲食頻度/完全栄養食利用意向/完全栄養食を利用したい場面/完全栄養食についての考え方/完全栄養食利用意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■完全栄養食の認知率は7割強、利用経験者は約13%、直近1年間利用者は約9%で、いずれも過去調査より増加傾向。直近1年間に「完全メシ、冷凍完全メシDELI」飲食者は2割弱、「BASE FOOD」は1割。提示した完全栄養食の直近1年間飲食者は3割弱で、そのうち「定期的に利用していない」「試しに数回利用」が各3割強。
■完全栄養食といわれている食品・飲料(完全メシ、BASEFOODなど)の直近1年間飲食者のうち、「完全栄養食であることを意識して購入」が約26%、「何も意識せずに購入、たまたま完全栄養食だった」が約25%。直近1年間飲食者の理由は「時間がない時に手軽に利用できる」約25%、「健康維持・管理」「栄養バランス・栄養不足が気になる」「なんとなく健康によさそう」各2割弱。
■完全栄養食利用意向者は2割弱。非利用意向者は約35%で、過去調査より減少傾向、「どちらともいえない」は5割弱で、過去調査より増加。直近1年間利用者のうち利用意向者の比率は6割強、利用中止者では4割強、認知・利用未経験者では2割強、非認知者では約8%。完全栄養食利用意向者が利用したい場面は「昼食の代わり」「栄養バランス・栄養不足が気になる」「小腹がすいたときや、おやつの代わり」「健康を維持したい」「災害時・非常時の備え」「朝食の代わり」などが各20%台。
■完全栄養食については「手軽」「災害時・非常時の備え」「価格が高い」「栄養バランスについて考えなくてよいので楽」「合理的」が各20%台。完全栄養食であることを意識して購入した層では「合理的」「手軽」が上位。非利用意向者では「価格が高い」「おいしくない・なさそう」「人工的に作られており、原材料・添加物の安全性が不安」が上位3位。
-
- 調査時期:
- 2025年04月
- 設問項目:
-
海苔の嗜好度/食べる海苔のタイプ/海苔の食べ方/海苔を食べる場面/海苔を食べる頻度/海苔購入頻度/海苔購入時の重視点/海苔に期待する効果・効能/海苔の好きな食べ方やこだわり(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■海苔が好きな人は9割弱。「好き」の比率は女性や50~70代で高い傾向。海苔を食べる人のうち週1回以上食べる人は6割強で、過去調査と比べて減少傾向。
■食べる海苔のタイプは「焼き海苔」「味付け海苔」が各7割強、「韓国海苔」が4割弱。「韓国海苔」は女性での比率率が高い。東日本では「焼き海苔」、西日本では「味付け海苔」が1位。
■海苔を食べる人のうち、「ご飯と一緒に食べる」が8割強、「おにぎりに巻く」が7割強、「のり巻き、軍艦巻き」が4割弱、「そのまま海苔だけ食べる」「完成した料理にかける・のせる」「いそべ巻き」が各3割強。海苔を食べる人のうち「朝食」に食べる人は5割弱、「昼食」が4割弱、「夕食」が6割弱。東北や北陸、九州では「朝食」がやや高く、「夕食」がやや低い。
■海苔を食べる人の、購入時の重視点は「価格」「海苔の種類」「味」が各6割強、「内容量」が4割弱、「海苔のサイズ」が3割弱。海苔に期待する効果・効能は「生活習慣病予防」「頭皮・髪の健康維持」などが上位。
-
- 調査時期:
- 2025年04月
- 設問項目:
-
家庭に常備している缶詰/直近1年間に利用した缶詰の種類/直近1年間の缶詰利用頻度/缶詰の購入頻度/缶詰購入時の重視点/缶詰購入理由/非常用食品としての缶詰備蓄状況/好きな缶詰の種類や食べ方、おすすめ(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■直近1年間に食べたり利用したりしたのは「魚介類の素材缶詰」6割強、「魚介類の加工・調理缶詰」4割強、「野菜・豆類の素材缶詰」3割強、「フルーツの缶詰」約26%。常備している缶詰は野菜類では「トマト加工品」「コーン、スイートコーン、ヤングコーンなど」が各20%台、魚介類では「ツナ缶」が5割強、「さば」が3割強。
■直近1年間に缶詰を食べたり利用したりした人の利用頻度は「月に2~3回程度」がボリュームゾーン。週1回以上利用者は2割弱、月1回以上購入者は約45%で、いずれも2022年調査より減少。
■缶詰購入者の理由は「保存がきく」が約85%、「価格が手頃」が約45%、「そのまま食べられる」「味がおいしい」「一年中、手に入る」などが各3割弱。購入者の重視点は「価格」が7割強、「味」が約65%、「原材料」「容量、サイズ」が各4割弱、「賞味期限・消費期限」「生産国」が各3割前後。
■非常用食品として缶詰を備蓄している人は、全体の4割強。「備蓄しており普段の食事などでも利用(ローリングストック)」は3割強で、女性高年代層での比率が高い。
-
- 調査時期:
- 2025年04月
- 設問項目:
-
お米を食べる頻度/自宅でのお米の炊飯状況/自宅で食べるお米のタイプ/自宅で食べるお米の品種・ブランド/お米の購入場所/お米購入時の重視点/お米を食べる量の5年前と比べた変化/お米を食べる量が5年前より減った理由/お米に関するこだわり(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■お米を「毎日・1日2回」食べる人は4割弱。毎日2回以上食べる人は5割弱で、過去調査と比べて減少傾向。東北や北陸での比率が高い。「お米を研いで炊く」は8割強、「無洗米」「レトルトパックのご飯を温める」は各2割弱、「炊いてあるご飯を買う」は約5%。
■自宅でお米を食べる人のうち「白米のみ(精米済みの白米)」を食べる人は8割弱、「白米と、雑穀を混ぜる(五穀米、十六穀米など雑穀ごはん)」は約17%、「白米と、麦(もち麦、押し麦など)を混ぜる」は約14%。
■自宅でお米を食べる人の購入場所は「スーパーの店頭」が6割強、「生産者から直接購入」が1割強、「インターネットショップ」「ドラッグストア」「ネットスーパー」が各1割弱。お米購入者の重視点は「価格」が約65%、「味」「国産米かどうか」が各4割強、「産地」「容量」が3割台半ば、「ブランド」が2割強。2022年調査と比べ「価格」が増加。
■5年前と比べお米を食べる量が増えた人は約8%、減った人は3割弱、「変わらない」は6割強。5年前と比べ食べる量が減った人の理由は「お米の価格が高くなり、購入量を減らした」が4割弱、「少食になり、全体の食事量が減った」「体重管理のため、ご飯の量・全体の食事量を減らした」が各3割弱、「糖質を控える」「ご飯よりもパンや麺類を食べることが増えた」が各2割弱。