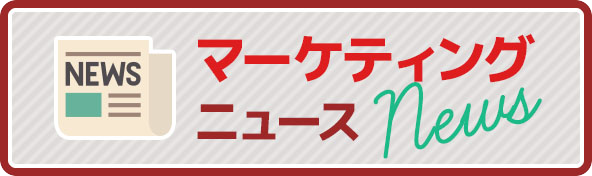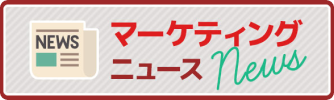- 検索
-
- テーマ別実施時期一覧
- カテゴリー別一覧
-
-
アルコール飲料・嗜好品146
-
非アルコール飲料209
-
その他19
-
-
住宅・住宅設備218
-
-
家電126
-
パソコン・カメラ・AV機器113
-
その他10
-
-
家庭用品・トイレタリー91
-
自動車・関連用品76
-
-
インターネット・情報通信327
-
携帯電話・スマートフォン180
-
メディア・広告66
-
その他7
-
-
ファッション69
-
交通・レジャー・娯楽161
-
季節行事・イベント241
-
時事・ニュース・トレンド51
-
企業ブランドイメージ249
-
広告・CM51
-
WEBサイトの利用91
-
顧客満足度100
- 実施時期別一覧
-
- 調査時期:
- 2025年10月
- 設問項目:
-
コンビニATM利用頻度/利用しているコンビニATM/直近1年間の最頻利用コンビニATM/最頻利用コンビニATMの利用理由/コンビニATMの利用場面/コンビニATMで1回あたりにおろす金額/コンビニATM利用意向/コンビニATM利用意向の理由
- 結果概要:
-
■コンビニATM利用経験者は7割弱。コンビニATM利用者に占める月1回以上の比率は約44%。男性は若年層での利用頻度が高い傾向。
■コンビニATM直近1年間利用者の、最頻利用ATM利用理由は「自宅・勤務先・学校などの近くにある」「口座を持っている銀行が利用できる」が各4割前後、「手数料が安い・無料」が2割弱。
■コンビニATM直近1年間利用者の利用場面は「コンビニATMが近くにある」「銀行ATMが近くにない」「すぐに現金を引き出したい」が各20%台。「コンビニATMで現金の引き出しは行わない」は約25%で、過去調査と比べて増加傾向。
■コンビニATM利用意向率は全体の5割弱。利用頻度が2~3か月に1回以上の層では各8~9割、年1回未満利用者では3割弱、利用未経験者では3%。
-
- 調査時期:
- 2025年10月
- 設問項目:
-
プライベートブランド商品購入頻度/直近1年間に購入したプライベートブランド商品/直近1年間に最もよく購入したプライベートブランド商品/プライベートブランド商品を直近1年間に購入した場所/プライベートブランド商品の購入割合が高かったジャンル(直近1年間)/プライベートブランド商品を選ぶ理由/プライベートブランド商品とナショナルブランド商品の購入割合/プライベートブランド商品の積極的購入意向/プライベートブランド商品で気に入っているもの/プライベートブランド商品非購入理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■プライベートブランド商品(以下『PB商品』)購入頻度は「週に1回」「月に2~3回」がボリュームゾーン。週1回以上購入者は全体の4割弱。同カテゴリ商品の場合にPB商品を買うことが多い人は3割強、メーカーのブランド商品を買うことが多い人は2割強。
■PB商品直近1年間購入者について、購入場所は「スーパー」8割弱、「コンビニエンスストア」3割弱、「ドラッグストア」2割弱。PB商品を買う割合が高かった商品ジャンルは、「加工食品」が7割強、「お菓子・デザート類」約34%、「飲料」「日用品、トイレタリー用品」各3割弱。
■PB商品直近1年間購入者のPB商品選定理由は、「価格が安い」7割強、「その商品が気に入っている」「品質がよい」が各20%台。
■PB商品の積極的購入意向あり層の比率は全体の5割強。女性の方が比率が高い。ほとんど毎日・週に4~5回と購入頻度が高い層では各8割前後、購入未経験者では約3%。
-
- 調査時期:
- 2025年10月
- 設問項目:
-
婚姻・就業状況/1ヶ月あたりの可処分所得/1ヶ月あたりの自由に使えるお金の金額/自由に使えるお金の使用目的/理想のお金の使い道/自由に使えるお金の金額の満足度/自由に使えるお金の理想金額/自由に使えるお金の1年前からの変化/自由に使えるお金を増やすためにしていること(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■1ヶ月あたりの自由に使えるお金の金額が3万円未満の層は全体の6割強。自由に使える金額(月額)のボリュームゾーンは「2~3万円未満」。理想の金額は「4~5万円未満」がボリュームゾーン。
■自由に使えるお金がある人の使用目的は「外食」約46%、「飲食※外食以外」「衣類・衣類小物、アクセサリー」各30%台、「旅行、レジャー」「美容、化粧品」「日用品」「書籍、マンガ、雑誌、新聞」などが各2割台半ば~後半。「貯蓄」は2割弱。男性上位3位は「外食」「飲食※外食以外」「旅行・レジャー」、女性上位3位は「美容、化粧品」「衣類・衣類小物、アクセサリー」「外食」。
■自由に使えるお金がある人の理想の使い道は「旅行、レジャー」4割弱。「外食」は2割強で、2019年調査以降増加傾向。
■自由に使えるお金の金額について満足層は全体の4割弱、高年代層で高く男性30~50代や女性30代で低い。不満層は3割弱、男性30~40代では不満層が満足層を上回る。1年前と比べ自由に使えるお金に余裕がなくなった人は全体の3割強、2022年調査より増加。
-
- 調査時期:
- 2025年10月
- 設問項目:
-
コンタクトレンズ・メガネの使用状況/最頻使用コンタクトレンズのタイプ/最頻使用コンタクトレンズのメーカー/コンタクトレンズ入手経路/コンタクトレンズ選定時の重視点/コンタクトレンズ着用時の不快感・目のトラブル(直近1年間)/コンタクトレンズで改善してほしい点/ICL(眼内コンタクトレンズ)の利用意向/コンタクトレンズ購入時の不満点(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■コンタクトレンズ使用者は全体の2割弱、女性や若年層での比率が高く、女性10~30代では各4~5割強。使用者のうち「ソフトコンタクトレンズ1日使い捨て」約45%、「ソフトコンタクトレンズ 2週間・1ヶ月交換」3割弱、「ハードコンタクトレンズ」2割強。
■コンタクトレンズ使用者の入手経路は「インターネット販売」「コンタクトレンズ専門店:眼科併設」が各4割弱。「インターネット販売」は過去調査と比べ増加傾向で、1日使い捨てソフトコンタクト主利用者、 2週間・1ヶ月交換ソフトコンタクト主利用者などでの比率が高い。
■コンタクトレンズ使用者の重視点は「販売価格が安い」「装着感」が各4割台前半~半ば、「メーカー、商品ブランド」が4割弱、「見え方の良さ、視力の安定性」「眼への負担の少なさ」が3割弱。コンタクトレンズ使用者が改善してほしい点は「レンズの価格が高い」が4割弱、「長時間装用による目の乾燥や疲れ、目への負担」が約26%、「装着や取り外しが面倒」「目の健康への影響」「眼科での処方や、定期的な受診が面倒」が各2割前後。
■コンタクトレンズ使用者が直近1年間に不快に感じたこと・目のトラブルなどは、「異物感がある」「目が乾燥する」が各3割前後、「目の疲れ」「目がかすむ、ぼやける」が各2割強。ICL(眼内コンタクトレンズ)の利用意向者は、コンタクトレンズ使用者の4割弱で、非利用意向者より高い。
-
- 調査時期:
- 2025年10月
- 設問項目:
-
胃腸薬の利用頻度/直近1年間に利用した胃腸薬/直近1年間に最もよく利用した胃腸薬/胃腸薬の利用場面/胃腸薬購入時の重視点/胃腸薬選定時の参考情報/胃腸薬の購入場所/胃の調子が悪い時の対処法/市販の胃腸薬についての不満・要望(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■胃腸薬利用者は全体の約4割弱で、過去調査と比べ減少傾向。利用者のうち月1回以上利用者は4割弱、男性若年層での利用頻度が高い。市販の胃腸薬直近1年間利用者の利用場面は「胃もたれ」「食べすぎ」約34~36%、「胸やけ、胃酸の逆流」「胃痛」「胃がむかむかする」「なんとなく胃の調子が悪い・すっきりしない」が各20%台。
■市販の胃腸薬直近1年間利用者の重視点は「効能・効果」6割弱、「効き目のはやさ」「価格」「飲みやすさ」などが各3割前後。参考情報源は「テレビ番組・CM」「商品パッケージの説明」「販売店の店頭の情報」「家族や友人の意見」などが各2割前後。
■市販の胃腸薬直近1年間利用者の購入場所は「ドラッグストア、薬局・薬店」が8割強、「オンラインショップ」が約9%。
■胃の調子が悪い時の対処法は「胃腸薬を飲む」が全体の3割強、「消化の良いものを食べる」3弱、「食事を控える」「体を休める」「寝る」「病院・診療所などの医療機関に行く」各2割強。
-
- 調査時期:
- 2025年10月
- 設問項目:
-
健康に気をつけている度合/健康の維持・増進のために取り組んでいる分野/健康の維持・促進のために行っていること/健康の維持・促進のために今後も続けたいこと、新たに始めたいこと/健康の維持・促進のために必要だができていないこと/健康についての参考情報源/健康維持のために改善したいこと/健康維持のために実践していること(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■健康に気をつけている人は7割強。2021年調査以降減少傾向。気をつけている人の比率は高年代層で高く、男性30~40代で低い。健康に関する情報で参考にするものは「テレビ番組・CM」が5割弱、「家族や友人、知人」「新聞」「ニュースサイト・アプリ」「健康や病気などに関する情報サイト」が各2割弱。
■健康のために取り組んでいる分野は「食生活」6割弱、「睡眠」「運動」各4割強。今後健康維持のために改善したいことは「運動不足」4割強、「睡眠の量や質」3割弱、「精神的ストレス」「太りすぎ・やせすぎ」各2割前後。「生活リズムが不規則」「食生活がよくない」「精神的ストレス」などは若年層での比率が高い。
■健康の維持・促進のための実施内容は「朝食を毎日食べる」4割弱、「日常生活でなるべく歩いたり階段を使う」「ウォーキング、ジョギング」「栄養バランスを考えた食事」「十分に睡眠をとる」などが各3割強。「ウォーキング、ジョギングをする」は男性10~60代で1位。
■健康のために必要だができていないことは「ウォーキング、ジョギング」3割弱、「甘いものを控える」「十分に睡眠をとる」「食べ過ぎない」「スポーツをする」各2割前後。「甘いものを控える」「スポーツをする」は現在行っていることよりも上位。今後続けたい・始めたいことは「ウォーキング、ジョギング」4割弱、「十分に睡眠をとる」3割台半ば、「日常生活でなるべく歩いたり階段を使う」「栄養バランスを考えた食事」「食べ過ぎない」「朝食を毎日食べる」各3割前後。
-
- 調査時期:
- 2025年09月
- 設問項目:
-
所有スマートフォンの機種/所有スマートフォンの契約事業者/スマートフォンで利用している機能・サービス/スマートフォン購入時期/利用スマートフォンの満足度/スマートフォン利用意向/スマートフォン利用意向者の重視点/スマートフォン購入時の携帯電話会社・通信事業者の変更意向/スマートフォン購入時の携帯電話会社・通信事業者の変更意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■スマートフォン所有率は全体の9割強。いずれの年代でも高い。iPhone所有者は3割強で、10・20代の比率が高く、若年層で高い傾向。「AQUOS」は約16%、「Xperia」「Google Pixel」は約8~9%。
■スマートフォン所有者の利用機能・サービスは「通話」が8割強、「カメラ」「Webサイト閲覧」が各7割前後、「Webメール、パソコンメール、フリーメールなど」「時計、アラーム」「インターネット電話、IP電話」「電卓」「チャット、トーク」が各6割前後。「スマホ決済、モバイル決済」「ビデオ通話、テレビ電話」などは2020年調査から比率が高い。
■スマートフォンの利用意向は全体の8割強、「とても利用したい」が約55%で、過去調査より増加傾向。スマートフォン所有者では9割弱の利用意向、非所有者では2割弱。スマートフォン利用意向者の端末の重視点は「本体価格」が6割強、「バッテリーの持ち時間」が5割強、「画面サイズ・大きさ」「通信料金」が各4割台前半~半ば。
■次回も「同じ携帯電話会社・通信事業者にしたい」は、スマホ利用意向者の6割強。NTTドコモ主利用者での比率が高く、キャリア以外・その他主利用者で低い。「携帯電話会社・通信事業者にはこだわらない」は約15%。
-
- 調査時期:
- 2025年09月
- 設問項目:
-
お酒の飲用頻度/好きなお酒の種類/最初の一杯で飲むアルコール飲料/お酒を一緒に飲む人/お酒を自宅・外のどちらで飲むか/どんな気分のときに家でお酒を飲むか/どんな気分のときに外でお酒を飲むか/あなたにとってお酒とは(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■酒類飲用者は全体の7割弱、過去調査と比べ減少傾向。週1日以上飲用者は酒類飲用者の7割強。男性高年代層での飲用頻度が高い。酒類飲用者が好きなお酒は「ビール」7割弱、「サワー、チューハイ」約45%。過去調査と比べ「ハイボール」が増加、「サワー、チューハイ」が2018年以降増加、「焼酎・泡盛」などが減少傾向。最初の一杯が「ビール」の人は酒類飲用者の5割強。女性20~30代では「サワー・チューハイ」が1位。
■酒類飲用者のうち、直近1年間にお酒をひとりで飲むことが多い人は6割強。一緒に飲む人は「配偶者(夫・妻)」が4割弱、「友人」が2割強。過去調査と比べ「配偶者」は減少傾向。
■酒類飲用者のうち、家で飲むことが多い人は9割弱。外で飲むことが多い人(1割強)は、2018年調査から2021年調査にかけて減少したが、その後やや増加傾向。
■酒類飲用者が家でお酒を飲むときの気分は「リラックスしたい」5割弱、「ゆったりとした時間を過ごしたい」3割強、「リフレッシュ・気分転換したい」3割弱。外でお酒を飲むときの気分は「一緒に飲む人と打ち解けたい」「リフレッシュ・気分転換したい」が約25~26%、「語り合いたい」「リラックスしたい」が各2割弱。
-
- 調査時期:
- 2025年09月
- 設問項目:
-
スポーツドリンク・機能性飲料の飲用頻度/直近1年以内に飲んだスポーツドリンク・機能性飲料/直近1年以内に最もよく飲んだスポーツドリンク・機能性飲料/スポーツドリンク・機能性飲料を飲む場面/スポーツドリンク・機能性飲料購入時の重視点/スポーツドリンク・機能性飲料に期待する効果/スポーツドリンク・機能性飲料飲用意向/スポーツドリンク・機能性飲料の不満点/飲まない理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■スポーツドリンク・機能性飲料飲用者は全体の6割強、過去調査と比べ減少傾向。週1回以上飲用者は2割弱、男性の方が飲用頻度が高い。スポーツドリンク・機能性飲料飲用者の直近1年以内飲用銘柄は「アクエリアス」「ポカリスエット」がそれぞれ約52%でトップ2。
■スポーツドリンク・機能性飲料飲用者の飲用場面は「汗をかいた時」4割弱、「脱水症状を防ぎたい時」「のどが渇いた時」各3割強、「スポーツをしている時」「スポーツの後」「体調の悪い時」などが各2割前後。OS-1主飲用者では「脱水症状を防ぎたい時」が1位。
■スポーツドリンク・機能性飲料飲用者の、購入時の重視点は「味」6割弱、「価格」約46%、「機能・効果」3割強、「成分」「飲み慣れている」「容量、サイズ」などが各2割強。飲用者が期待する効果は「水分補給」が7割強、「熱中症対策・予防」が6割弱、「体調を整える」「運動時や前後に、適切な栄養素やエネルギーの補給」が各2割強。
■スポーツドリンク・機能性飲料飲用意向は5割強、2022年調査より減少。男性10~40代での飲用意向がやや高い。週に1回以上飲用者では9割以上の飲用意向、現在非飲用者では約6%。
-
- 調査時期:
- 2025年09月
- 設問項目:
-
ドレッシング利用頻度/市販のドレッシング・手作りのドレッシングの利用度合い/利用している市販のドレッシングの数/よく使うドレッシングの種類/直近1年間に利用したドレッシングのメーカー、ブランド/市販のドレッシング購入時の重視点/市販のドレッシングの用途/野菜やサラダなどにかけて食べるもの(直近1年間)/市販のドレッシングのおすすめのもの・使い方/市販のドレッシングを利用しない理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■ドレッシング利用者は8割強。「週に2~3回」がボリュームゾーン。週1回以上利用者は約65%、毎日利用者は2割弱。ドレッシング利用者のうち、手作りより市販のドレッシングの方が多い層は9割弱。ドレッシング利用者のうち、市販のドレッシングを、野菜やサラダ以外にも使う人は2割弱。
■市販のドレッシング利用者の所有数は「1種類」3割弱、「2種類」が約35%。よく利用する種類は「ごま(乳化タイプ)」が利用者の約54%、「醤油ベース」が3割強、「青じそ」「オニオン・玉ねぎ」「フレンチ:白」「イタリアン」などが各2割前後。
■市販のドレッシング利用者の購入時重視点は「味」が8割弱、「値段」5割強、「味の種類」4割弱、「量」2割弱。2014年調査以降「ノンオイル」が減少傾向。
■生野菜や温野菜、サラダなどの好きな食べ方は「市販のドレッシング」7割強、「マヨネーズ」4割強、「塩、しょうゆ、ポン酢、オリーブオイル、ごま油などの調味料」3割弱。
-
- 調査時期:
- 2025年09月
- 設問項目:
-
直近1年間での麺類を食べる頻度/直近1年間に麺類を食べるシーン/麺類を食べる理由/自宅でよく食べる麺類/自宅で最もよく食べる麺類/直近1年間での自宅でよく食べる麺類のタイプ・準備方法/自宅で最もよく食べる麺類の商品購入時の重視点/直近1年間に外食でよく食べる麺類/好きな麺類の種類やタイプ、作り方・食べ方・タイミングなど(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■麺類を週1回以上食べる人は全体約75%。「週2~3回」「週1回」がボリュームゾーン。麺類を食べる人のうち、平日・休日の昼食に食べる人は各60%台。平日・休日の夕食は30%台で、若年層での比率が高い傾向。
■麺類を食べる人が、直近1年間に自宅で食べる麺類は「うどん」7割強、「ラーメン、中華麺」「パスタ、スパゲッティ」が各60%台、「そば」「やきそば」「そうめん」が50%台。自宅で最もよく食べる麺類の、商品購入・調理者の重視点は「味」「価格」各5割強、「麺のタイプ」4割強、「容量、サイズ」約26%、「賞味期限・消費期限」「スープやつゆ、ソースがついているかどうか」「メーカー・商品ブランド」が各2割弱。
■麺類を食べる人の理由は「麺類が好き」が6割強、「調理が簡単」「すぐに食べられる、早く準備ができる」が各4割前後、「食べやすい」が3割弱。
■麺類を食べる人に、直近1年間に外食で食べる麺類をたずねたところ、「ラーメン、中華麺」が6割弱、「うどん」「そば」「パスタ、スパゲッティ」が各3割強~4割強。西日本では「うどん」の比率が高く、四国、九州では1位。東北、北陸では「ラーメン、中華麺」の比率が高い。
-
- 調査時期:
- 2025年09月
- 設問項目:
-
料理が好きかどうか/料理をする頻度/「何も参考にせずに作れる」と思う料理/「できる」と思う調理の技法・方法/夕食作りにかける時間/レシピの参考度合い/料理についての困りごと・不満/「料理」だと思うもの/料理を学んだ・身につけた環境(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■料理が好きな人は全体の3割強、過去調査と比べて減少傾向。自分で料理をする人は男性73%、女性約96%。料理を「ほぼ毎日」する人は全体の3割強、男性1割強、女性6割強、女性60~70代では各7割強~8割弱。「ほとんどの場合レシピを見ない」は料理をする人の4割弱で、過去調査と比べて減少傾向。
■何も参考にせずに作れる料理は「目玉焼き」が約75%、「おにぎり」「卵焼き」「味噌汁」「野菜炒め」が各60%台、「カレー」「チャーハン」「いり卵」が各6割弱。できると思う調理技法の中で順位が低いのは「魚を三枚におろす」「いかの皮をむく」「桂むき」「板ずり」「わたをとる」などで各2割強~3割台半ば。
■料理だと思うものの上位は「カレー等に市販のルーを使う」「餃子等の皮は市販で具は手作り」が各7割弱、「だしの素、だしつゆを使う」「下ごしらえ済みの魚を調理」「から揚げ粉を使う」が各6割強。下位は「カップめんにお湯を注ぐ」「レトルト食品や冷凍食品を温める」「インスタントみそ汁・スープを作る」など。
■料理についての困りごと・不満は「レパートリーが少ない」が4割強、「メニューがなかなか決まらない」「後片付けが面倒」「栄養バランスのよいメニューを考えるのが難しい」などが各2割台後半。女性の方が比率が高い項目が多く「メニューが決まらない」「毎日作らなければならない」などは、特に男女差が大きい。
-
- 調査時期:
- 2025年09月
- 設問項目:
-
所有している電子レンジのタイプ/所有電子レンジのメーカー/所有している電子レンジの機能/電子レンジの機能のうち、使っている機能/電子レンジ機能の利用場面/調理をする際の電子レンジ利用頻度/電子レンジで調理をする理由/今後の電子レンジ購入時の重視点/電子レンジのメーカー選定理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■「オーブン・トースター機能付き」の電子レンジ所有者は4割強、「電子レンジ機能のみ」が3割強、「スチームオーブンレンジ」は2割強。購入時の重視点は「価格」7割弱、「操作のしやすさ」「メーカー・ブランド」40%台、「本体の大きさ」「庫内の広さ・容量」各30%台。
■電子レンジ所有者のうち「解凍」の機能付き電子レンジ所有者は約65%、「飲み物を温める」約55%、「ちょうどよい温度に自動で温める」46%、「温度を指定して温める」約36%。電子レンジ所有者の使用機能は「ちょうどよい温度に自動で温める」「飲み物を温める」「解凍」が各3割強、「温度を指定して温める」が2割強。
■電子レンジ所有者の使用場面は「家庭で作った料理やご飯の温めなおし」6割強、「市販のお弁当等の温めなおし」「レトルト食品、電子レンジ用食品などの調理・温め」「解凍」が各50%台。
■調理時に電子レンジを使う人は所有者の4割強。調理での電子レンジ利用者の調理理由は「短時間で調理ができる」8割強、「下ごしらえに便利」「キッチンコンロと並行作業ができ効率的」「手順が簡単」各4割弱。
-
- 調査時期:
- 2025年09月
- 設問項目:
-
ファストフード店の利用頻度/直近1年以内に利用したファストフード店/直近1年以内の最頻利用ファストフード店/ファストフード店の直近1年間での利用場面/ファストフード店利用時の重視点/最も好きなファストフード店/ファストフードの嗜好度/最も好きなファストフード店の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■ファストフード店月1回以上利用者は全体の4割強、若年層での利用頻度が高い傾向。ファストフード利用者が最も好きなファストフード店は「マクドナルド」3割強、「モスバーガー」2割弱、「ケンタッキーフライドチキン」約15%。
■ファストフード利用者の直近1年間利用場面は「昼食」が6割弱、「テイクアウトの利用」「夕食」「小腹がすいた時」などが各2割弱。過去調査と比べ「夕食」が増加傾向。「夕食」は若年層での比率が高い傾向。
■ファストフード利用者の重視点は「食べ物がおいしい」が5割強、「値段が手頃」が4割強、「気軽に立ち寄れる」「アクセスがよい」などが各2割強。モスバーガー主利用者、フレッシュネスバーガー主利用者では「原材料の品質が信頼できる」「食材の安全性」などの比率がやや高い。
■ファストフードが好きな人は全体の6割強で、女性の方がやや比率が高い。マクドナルド主利用者、バーガーキング主利用者などでは、ファストフードが好きな人の比率が他の層よりやや高い。
-
- 調査時期:
- 2025年09月
- 設問項目:
-
昼食の直近1年間の外食頻度/直近1年間に昼食を外食するときの1回あたりの支出額/直近1年間に昼食を外食する場面/昼食を外食するときの店舗選定時の重視点/夕食の直近1年間の外食頻度/直近1年間に夕食を外食するときの1回あたりの支出額/直近1年間に夕食を外食する場面/夕食を外食するときの店舗選定時の重視点/外食店で利用してよかった店(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■直近1年間に外食した人は昼食8割強、夕食8割弱。2023年調査とほぼ同程度で、コロナ禍前の2018年より低い。月1回以上外食者は、昼食外食者の7割強、夕食外食者の約5割強。昼食外食者の頻度は男性の方が高い。
■外食する人の、1回あたりの支出額は、昼食は「800~1,000円未満」、夕食は「2,000~3,000円未満」がボリュームゾーン。昼食・夕食とも過去調査と比べ支出額の増加がうかがえる。特に昼食では1000円以上の比率が、2021年調査以降大きく増加。
■外食する場面は、昼食を外食する人では「平日の昼」が約46%、「休日の昼」「外出のついで」が各4割弱。夕食を外食する人では「休日の夜」が約44%、「平日の夜」「外出のついで」が各3割強、「家族がそろう」「おいしいものを食べに行く」が各2割強。
■外食時の店舗選定時の重視点は「料理の味」「価格」が上位2位、次いで「店へのアクセス」「メニューの内容」などが続く。
-
- 調査時期:
- 2025年09月
- 設問項目:
-
健康に気をつけている度合/健康のために摂取を心がけている成分/健康のための摂取成分に期待する効果/健康のための成分摂取のきっかけとなった情報源/健康のための成分摂取方法/健康のための成分を摂取している飲食物/健康のために摂取したい成分/栄養成分に関することで気になっていること(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■健康のために摂取を心がけている成分がある人は全体の6割強。摂取成分の上位は「たんぱく質」26%、「カルシウム」「ビタミンC」「乳酸菌」各2割強、「ビタミンB」「鉄」「DHA」「ビタミンD」各1割強。「たんぱく質」が過去調査と比べ微増傾向。今後摂取したい成分上位5位は「カルシウム」「たんぱく質」「ビタミンC」「乳酸菌」「鉄」。
■健康のための成分摂取者が期待する効果は「健康維持」が6割強、「免疫力・抵抗力向上」が5割弱、「体調不良の改善、病気の改善・悪化防止」「疲労回復」などが各3割前後。
■健康のための成分摂取者のきっかけは「テレビ番組・CM」が4割弱、「健康や栄養などに関するWebサイト」「家族や友人・知人のすすめ」がそれぞれ約16~17%、「新聞記事・広告」「メーカーや店舗のWebサイト」などが各1割強。
■健康のための成分摂取者では「食べ物、飲み物」からの摂取が約74%、「サプリメント、プロテイン、健康食品など」が5割強。飲食物からの成分摂取者のうち「乳製品」「大豆加工品」「野菜、きのこ類」各6割前後、「魚介類、水産加工品、海藻類」5割強。
-
- 調査時期:
- 2025年09月
- 設問項目:
-
1年前と比べた、生活全体の支出額の変化/1年前と比べた、生活全体の収入額の変化/1年前と比べた、購買意欲の変化/1年前と比べてお金をかけていること/今年お金をかけるのを我慢している分野/消費行動スタイル/消費に関する考え方・行動/今後1年間の購買意欲の変化/今後1年間の購買意欲変化の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■1年前と比べ生活全体の支出額が増えた人は6割弱で、2024年調査と比べて増加。支出額が減った人は約8%。収入額が増えた人は2割弱、収入額が減った人は2割強、変わらない人は6割強で、2024年調査とほぼ同程度。
■1年前と比べ購買意欲が低い人は3割強で、高い人(1割強)より比率が高い。購買意欲が変わらない人は6割弱。今後1年間の購買意欲が高くなると思う人は約9%、低くなると思う人は約26%、変わらないと思う人は6割強。
■1年前よりお金をかけていることは「食品・飲料」が3割台半ば、「旅行、レジャー」「外食、グルメ」は各2割前後。今年お金をかけるのを我慢しているものは「旅行、レジャー」が3割強、「外食、グルメ」が2割強、「衣料品」が2割弱。
■節約に関する消費行動は「節約はしつつちょっとした贅沢も楽しむ」が4割弱、「常に節約を意識」「必要なもの以外はなるべく買わないよう我慢」が各2割前後。「収入に見合った買い物をするべきだ」が4割強、「必要な物かどうかをよく考えてから買う」が4割弱、「とにかく安く経済的であることを重視する」「話題になっているものでも、自分の趣味にあわなければ買わない」などが各3割弱。
-
- 調査時期:
- 2025年09月
- 設問項目:
-
普段の生活での時間の使い方・過ごし方/直近1年間に比較的お金をかけた分野/商品やサービス選定時の最重視点/商品・サービス選定時の検討度合い/商品・サービス選定時の他者意見の参考度合い/新しいものを取り入れる際の行動傾向/普段利用している情報メディア/興味・関心がある分野/余暇についての考え方/最近買った商品・サービスで買ってよかったもの(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■普段の生活での時間の使い方は「流れ重視」3割強、「計画重視」2割強。女性10~30代では「気分重視」が高い。新しいものを取り入れる際の行動は「新しいものは人より早く先に試してみる」が約2%、「自分で評判や情報を確かめてから、なるべく早く取り入れる」が2割強、「他の人の反応・評判を見聞きしてから」が3割弱、「多くの人が利用し、一般的に普及してから」4割弱、「世間のほとんどの人が利用し、使わざるを得ない状況になってから」が1割強。
■商品・サービス選定時に「ほとんど迷わずその場ですぐに決める」約8%、「気になるものをいくつか比べて比較的早めに」約45%、「情報を集めじっくり比較」4割弱、「かなり時間をかけて検討」が約8%。他人の意見参考度合いは「他人の意見もある程度参考」が6割弱。「他人の意見にはほとんど左右されず自分で判断」は男性や高年代層で高く、「他人の意見を重視し評判をよく確認してから」は女性や若年層での比率が高い。
■直近1年間に比較的お金をかけた分野は「家庭内の食費」「旅行、レジャー」が各3割弱、「外食」2割強、「趣味、娯楽、文化・芸術活動」「健康、医療」が各2割弱。普段利用している情報メディアは「テレビ」7割強、「ニュースサイト、ニュースアプリ」6割強、男性10・20代や女性10~30代では「SNS」が各6割弱~7割弱で1位。
■余暇についての考え方は「心身を休めるために使いたい」4割強、「自分の好きなことに熱中・集中し、リフレッシュしたい」3割強、「お金をかけずに工夫して楽しみたい」「家族や友人など身近な人との時間を楽しみたい」「普段はできないようなことをしたり感じたりすることで、気分転換したい」が各2割前後。
-
- 調査時期:
- 2025年08月
- 設問項目:
-
夏に飲む飲み物の量(1日あたり)/夏によく飲む飲み物/夏の定番の飲み物/夏に飲む物に期待すること/夏における、常温での飲用状況/夏に常温で飲む飲み物/夏に常温で飲む理由/夏の飲み物で気に入っているもの(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■夏によく飲む飲み物の上位は「コーヒー、コーヒー飲料」が6割弱、「水、ミネラルウォーター」「麦茶」が各5割強、「緑茶」が4割強、「牛乳」「ビール類」が各3割弱。夏に飲む定番の飲み物(1つ)は「麦茶」が4割強、「水、ミネラルウォーター」「緑茶」「ビール類」が各1割前後。
■夏に飲む物に期待することは「冷たい」が75%、「のどの渇きをいやす」が5割強、「脱水症状を防ぐ、熱中症対策」「スッキリしている」が各30%台、「糖分ゼロ、無糖」「のどごしが良い」「リフレッシュ、気分転換できる」が各2割強。
■夏に常温で飲むことがある人は全体の4割強。常温で飲む人のうち「水、ミネラルウォーター」が5割強で、過去調査と比べ増加傾向。「緑茶」3割強、「麦茶」約25%、「コーヒー、コーヒー飲料」「ほうじ茶」が各10%台。
■夏に常温で飲むことがある人の理由は「体を冷やさないため」「冷たいものは胃に負担がかかる」「体にやさしい」が各20%台、「冷たいものはおなかをこわしやすい」「健康のため」「夏に限らず、常温のものを飲むことが多い」が各2割弱。
-
- 調査時期:
- 2025年08月
- 設問項目:
-
カレーを食べる頻度/カレーの準備方法/直近1年間でのカレーを食べるタイミング/カレーを食べる場面/カレーを自分で作る頻度/カレーを作る時に使う市販のルウのタイプ/直近1年間に使ったカレールウ/直近1年間の最頻使用カレールウ/市販のカレールウ購入時の重視点/カレーを作る時の工夫・こだわり(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■カレーを食べる頻度は「月に2~3回程度」「月に1回程度」がボリュームゾーン。月1回以上食べる人は8割弱で過去調査と比べ減少傾向。カレーを食べる人のうち「自宅で作ったカレー」を食べる人が8割弱、「レトルトカレー」が6割弱、「外食」が3割弱。
■カレーを食べる人の、直近1年間での食べるタイミングは「平日:夕食」7割弱、「休日:夕食」4割強、「平日:昼食」「休日:昼食」が各3割前後。カレーを食べる場面は「カレーを食べたい」7割弱、「調理や後片付けを簡単に済ませたい」「辛いものが食べたい」「家族の要望」「食欲を増進させたい」「食事のメニューとして出された」などが各10%台。
■カレーを自分で作る人は全体の6割強、男性約44%、女性40~70代で各80%台。自分で作る人のうち月1回以上作る人は男性5割強、女性6割強。自分で作る人のうち「固形タイプ」を使う人が9割弱、「フレーク、パウダー、顆粒タイプ」が2割強。
■市販のカレールウ使用者の重視点は「味」7割強、「辛さ」「価格」が約43~45%、「こく」「香り」「メーカー」などが各2割前後。
-
- 調査時期:
- 2025年08月
- 設問項目:
-
レトルト食品の料理での利用頻度/直近1年間に利用したレトルト食品の種類/レトルト食品の利用場面/レトルト食品購入場所/レトルト食品購入時の重視点/レトルト食品購入理由/レトルト食品についての不満/気に入っているレトルト食品とその理由/利用しない理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■レトルト食品を利用して料理をする人は全体の9割弱。ボリュームゾーンは「月2~3回程度」。週1回以上利用者は3割弱で、男性の方が比率が高い。レトルト利用者が直近1年間に利用したものは「カレー」8割弱、「パスタソース」5割弱、「料理の素」3割弱、「惣菜」「丼もの」「ご飯:白米・玄米」「混ぜご飯の素、釜めしの素」が各2割前後。
■レトルト食品利用者の利用場面は「ふだんの食事のメニューとして」が50%で、過去調査と比べ増加傾向。「作るのが面倒」「時間がない、すぐ食べたい」は各4割前後で、女性の方が比率が高い。レトルト食品利用者の購入場所は「スーパー」が9割弱。「ドラッグストア」は2割強で2019年以降増加傾向。
■レトルト食品購入者の重視点は「味」「価格」が各7~8割、「容量、サイズ」が4割弱、「賞味期限」「メーカー」「食べなれている」などが各2割前後。購入理由は「すぐに食べられる」「簡単に食べられる」が各6割弱、「価格が安い」「調理の手間が省ける」「長持ちする・保存がきく」が各3割前後。
■レトルト食品の不満点は「価格が高い」「野菜や肉などの具材の量が少ない」が各2割前後、「添加物が多い」「味が濃すぎる」「塩分量が多い」が各10%台。
-
- 調査時期:
- 2025年08月
- 設問項目:
-
夏を感じ始める時期/夏の味覚を楽しむ度合い/夏の味覚とは/夏の味覚を味わうときの重視点/夏の味覚に合うお酒/夏に飲みたくなる飲み物/夏によく食べる味/夏の味覚を使った料理のおすすめ(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■夏を感じ始める時期は「6月上旬」「6月下旬」「7月上旬」が各2割弱。6月下旬以前の比率が7割強。夏の味覚を味わう際の重視点は「鮮度」「価格」「見た目(彩りなど)」が上位3位。
■夏の味覚といえば「スイカ」7割弱、「トウモロコシ」5割弱、「きゅうり」「枝豆」「トマト」各4割弱。「トウモロコシ」「枝豆」などは西日本での比率が低い傾向。「メロン」は北海道や東北で高く、「はも」は近畿で高い。
■夏の味覚に合うお酒は「ビール類」が約56%で過去調査より減少傾向、「チューハイ・サワー」は2割弱。夏に飲みたくなる飲み物は「麦茶」5割強、「炭酸飲料」2割強、「緑茶」「コーヒー、コーヒー系飲料」「スポーツドリンク」「水、ミネラルウォーター」「炭酸水」がそれぞれ約15~19%。
■夏によく食べる味は「さっぱり」約36%、「スパイシー」3割弱、「すっぱい」「辛い」「塩辛い・しょっぱい」「薄い・あっさり」が各2割前後。「すっぱい」「甘酸っぱい」「さっぱり」などは女性の方が比率が高い。
-
- 調査時期:
- 2025年08月
- 設問項目:
-
好きな料理のジャンル/最も好きな料理のジャンル/最も好きな料理のジャンルのイメージ/苦手な料理のジャンル/苦手な料理のジャンルの、苦手な理由/以前はあまり食べなかったが食べるようになったジャンル/外食やデリバリーで食べたい料理のジャンル/最も好きな料理のジャンルの魅力(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■好きな料理のジャンルは「和食」が8割強、「洋食」「中華料理」が各6割弱、「イタリア料理」が5割弱、「ジャンクフード」「B級グルメ」が各20%台。「イタリア料理」「韓国料理」などは女性の方が比率が高い。
■最も好きな料理のジャンルのイメージは、和食は「季節感」「庶民的」「伝統的」「ヘルシー」など、洋食は「気軽」「庶民的」など、中華料理は「庶民的」「気軽」「スタミナがつく」「濃い味」「大勢で楽しむ」「脂っこい」などが上位。
■苦手な料理のジャンル上位は「タイ料理」「ベトナム料理」「韓国料理」などで各2割前後。苦手な料理の理由は「香辛料」「味付け」「苦手な食材がある」「匂い」「刺激が強い」「クセがある」などが上位。
■外食やデリバリーで食べたい料理のジャンルは「和食」「中華料理」「イタリア料理」「洋食」が各3割前後、「ジャンクフード(ファストフードなど)」「B級グルメ」が各2割弱。
-
- 調査時期:
- 2025年08月
- 設問項目:
-
掃除機で掃除をする頻度/所有掃除機のタイプ/掃除機の台数/主利用掃除機のタイプ/主利用掃除機のメーカー/今後の掃除機購入時の重視点/今後購入したい掃除機のタイプ/住居形態/主利用掃除機のメーカー選定理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■掃除機を使って掃除をする人は全体の約85%、週1回以上掃除をする人は全体の6割強、男性5割強、女性8割弱。ロボット掃除機主利用者では他の層より掃除の頻度が高い傾向。
■「スティッククリーナー、スティック型」所有者が全体の5割強で過去調査と比べ増加傾向。「キャニスター型・紙パック式」4割弱で減少傾向、「キャニスター型・サイクロン」3割弱で2017年以降減少傾向。掃除機所有者のうち「1台」所有者が5割弱、「2台」が3割強。一戸建て2階建て以上居住者では、集合住宅と比べ所有台数が多い傾向。
■今後の掃除機購入時の重視点は「本体価格」「吸引力」が各5割強~6割強、「本体の大きさ・重さ」が4割強、「メーカー・ブランド」「ゴミの捨てやすさ」「手入れのしやすさ」が各30%台。ダイソン主利用者では「吸引力」が1位。
■今後購入したい掃除機は「スティッククリーナー、スティック型」が5割弱で過去調査と比べて増加傾向、「キャニスター型・紙パック式」「キャニスター型・サイクロン」が各2割前後。スティッククリーナー・スティック型主利用者のうち今後も同タイプを利用したい人の比率は8割強と高い。
-
- 調査時期:
- 2025年08月
- 設問項目:
-
室内の匂いが気になる度合/自宅で気になる匂い/室内用消臭・芳香剤の使用状況/直近1年間に使用した消臭・芳香剤/最も気に入っている消臭・芳香剤/室内用消臭・芳香剤の形状/室内用消臭・芳香剤の使用場所/室内用消臭・芳香剤選定時の重視点/スプレータイプの消臭・芳香剤使用頻度/室内用消臭・芳香剤スプレーの不満/非使用理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■自宅の室内のにおいが気になる人は4割強。自宅で気になる匂いは「トイレのにおい」「生ごみのにおい」が各3割強、「料理をした後のにおい」「キッチンの排水溝のにおい」が各2割強、「玄関や靴箱のにおい」「お風呂のにおい」が各2割弱。
■室内用消臭・芳香剤使用率は全体の5割弱。使用者のうち「トイレ」で使う人は6割強、「居間、リビング」5割弱、「玄関、くつ箱」4割弱、「寝室」3割弱。
■室内用消臭・芳香剤の形状は「置き型:ビーズタイプ」2割台半ば、「置き型:液体タイプ」4割弱、「スプレータイプ」5割強。スプレータイプ使用者の利用頻度は「ほとんど毎日」「週2~3回」がボリュームゾーン。
■消臭・芳香剤使用者の選定時の重視点は「好きな香り」「価格」が各5割弱、「消臭力が強い」「効果の持続性」「メーカー」「商品ブランド」「無香、微香」が各20%台。
-
- 調査時期:
- 2025年08月
- 設問項目:
-
自動車保険の加入状況/自動車保険に加入している保険会社/自動車保険について、最も多く保険料を支払っている保険会社/加入自動車保険会社の満足度/自動車保険(任意保険)の加入経路/自動車保険加入時に参考にした情報源/自動車保険選定時の重視点/自動車保険契約先の見直し意向/今後自動車保険に加入(更新)したい保険会社/主加入自動車保険への加入理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■自動車保険(任意保険)加入率は全体の7割弱。契約先見直し意向は、自動車保険世帯加入者の3割。見直し意向の比率が低いのは共栄火災海上保険主加入者、JA共済主加入者、こくみん共済coop主加入者など。
■自動車保険世帯加入者の加入経路は「パソコンからインターネット経由」が3割強で、SBI損保主加入者、SOMPOダイレクト損害保険主加入者、チューリッヒ保険主加入者などで高い。「自動車を購入した店」「保険代理店」は各2割弱。
■自動車保険世帯加入者の参考情報源は「保険商品を扱ったホームページや比較サイト」が2割弱。ソニー損保主加入者では「テレビ番組・CM」が1位。加入者の重視点は「保険料の安さ」が5割強、「補償内容の充実度」が5割弱、「商品内容のわかりやすさ」「事故時の対応力・サービス」が約34%。
■今後加入したい保険会社は「ソニー損保」「東京海上日動火災保険」「損保ジャパン」「SBI損保」などが上位。「わからない」は5割強。
-
- 調査時期:
- 2025年08月
- 設問項目:
-
株式売買の経験/インターネットでの株式売買の経験/インターネット取引経験がある証券会社/現在主にインターネット取引をしている証券会社/主にインターネット取引をしている証券会社の満足度/ネット取引による直近1年間の投資資金の増減/ネットでの株式売買の意向/ネットでの証券取引時の重視点/主にインターネット取引をしている証券会社の利用理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■インターネットでの株式売買現在実施者は全体の3割弱、株式売買現在実施者の9割強。男性約36%、女性2割弱。
■インターネット取引経験がある証券会社は「SBI証券」「楽天証券」「野村證券」「マネックス証券」などが上位。満足計(TOP2)の比率が高いのは、SBI証券主利用者、楽天証券主利用者など。
■直近1年間のネット取引による投資資金が増加した人の比率は、ネットでの株式売買経験者の5割強、現在取引者の6割強。2020年調査以降、投資資金が増加した人の比率が増加。
■ネットでの株式売買意向は3割強。現在取引者の今後の意向は9割強、過去経験者では3割強、未経験者では約7%。株式売買意向者の重視点は「取引手数料が安い」が7割強、「セキュリティが信頼できる」が4割弱、「取引ツールが使いやすい」「口座開設手続が簡単」「システムが安定」が各3割弱。
-
- 調査時期:
- 2025年08月
- 設問項目:
-
こり・痛みを感じる部分/肩こり・腰痛の経験/肩こりまたは腰痛の状況/肩や腰のこり・痛みの対処として利用するもの/肩や腰のこり・痛みへの対処として使用する市販の医薬品のタイプ/直近1年間に肩こり・腰痛の対処として利用した市販の医薬品/直近1年間に肩こり・腰痛の対処として最もよく利用した市販の医薬品/肩こり・腰痛の対処として使用する市販の医薬品選定時の重視点/肩こり・腰痛の対処としてやっていること・効果があること(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■こり・痛みを感じる部分は「肩の周辺」「腰」「首の付け根あたり」が、全体の各40%台。肩こり・腰痛を感じる人は全体の約75%、慢性的に感じる人は3割強で、女性40~50代での比率が高い。肩こりまたは腰痛を感じる人のうち、肩こりと腰痛の両方感じる人は4割弱。
■肩こり・腰痛者がよく利用するものは「市販の医薬品」が4割弱、「医師の処方薬、注射」「鍼灸、指圧、マッサージ、カイロプラクティック、整体など」「マッサージ器、マッサージチェア」「入浴剤」が各1割強。
■肩こり・腰痛の対処で市販の医薬品を利用する人は、肩こり・腰痛者の5割強。「湿布薬」が3割強、「塗り薬」が2割強。
■肩こり・腰痛の対処で市販の医薬品を利用する人の重視点は「効能・効果」が6割強、「価格」3割強、「飲みやすさ・使いやすさ」「即効性」「成分」「効果の持続力」などが各2割強。
-
- 調査時期:
- 2025年08月
- 設問項目:
-
朝の肌のお手入れに使う時間/行っているスキンケア/使用しているスキンケア・化粧品/スキンケア・化粧品選定時の重視点/スキンケア・化粧品購入時の参考情報源/スキンケア・化粧品購入場所/スキンケア・化粧品の1ヶ月あたり平均購入金額/スキンケア用品・化粧品選定時、安全性・環境への配慮で重視すること/スキンケア用品・化粧品についてこだわっていること・気を付けていること(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■朝の肌のお手入れをしている人は全体の6割弱、男性4割弱、女性9割強。そのうち、かかる時間が5分以下の人は7割弱。「保湿ケア」実施者は4割強、「UVケア」は約25%、「ハンドケア」「美白ケア」がそれぞれ約13%。
■使用スキンケア・化粧品は「洗顔料」が全体の約55%、「化粧水、ローション」が4割強。「口紅」は2020年以前と比べ比率が低い。「洗顔料」「化粧水、ローション」は女性では各8割弱~8割台半ば。男性10~40代では「洗顔料」が約43~45%、「化粧水、ローション」が約24~25%。
■スキンケア・化粧品使用者の重視点は「肌との相性」が6割弱、「使用感・使いごこち」「効能・効果」が各5割弱、「価格の適正さ」が3割強。スキンケア・化粧品使用者の購入場所は「ドラッグストア」が6割強。「インターネット通販」(約35%)は女性での比率が高い。購入者の参考情報源は「店頭のPOP」「テレビ番組・CM」「製品のパッケージ」が各2割前後。女性10~30代では「SNS、YouTubeなど」「商品比較サイト」が上位2位。
■スキンケア・化粧品使用者が安全性・環境への配慮で重視することは「詰め替え・付け替え可能な容器」が2割強、「合成香料・着色料が使われていない」「過剰包装がない、簡素なパッケージ」が約15~17%。
-
- 調査時期:
- 2025年08月
- 設問項目:
-
リカバリーウェア直近1年間利用状況/直近1年間に利用したリカバリーウェアのブランド/リカバリーウェア利用理由/リカバリーウェア利用のきっかけ/リカバリーウェア直近1年間利用場面/リカバリーウェアの効果の実感度合い/リカバリーウェア利用意向/リカバリーウェア利用意向者の重視点/リカバリーウェアの魅力/リカバリーウェア利用意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■リカバリーウェア現在利用者は約3%、直近1年間利用者は約4%、認知率は2割強。直近1年間利用者は男性10・20代で高く、認知率は女性の方が高い。リカバリーウェア直近1年間利用者の利用場面は「就寝時」が約45%、「日常的に利用」「家でくつろいでいるとき」が各2割強。期待する効果を感じた人は直近1年間利用者の5割弱、感じなかった人は2割強。
■リカバリーウェア直近1年間利用者の利用理由は「疲労回復効果が期待できる」「健康のため」各4割強、「血行促進効果が期待できる」3割弱、「筋肉のこり・ハリをやわらげる効果が期待できる」「睡眠の質の改善が期待できる」各2割強。利用のきっかけは「テレビ」が約36%、「ネットの広告」「店頭で見た、店員のすすめ」「家族や友人・知人のすすめ」「SNSやYouTubeで見た」などが約13~15%。
■リカバリーウェア利用意向者の比率は2割弱、非利用意向者は4割弱。利用意向者の比率は女性の方が高く、男性10・20代で4割強と高い。利用意向者の比率は、リカバリーウェア現在利用者では7割強、利用経験者では6割強、認知者では約45%、非認知者では1割強。
■リカバリーウェアについて魅力に感じる点は「疲労回復効果が期待できる」「健康や体調の維持・改善が期待できる」が各3割前後、「血行促進効果が期待できる」「筋肉のこり・ハリをやわらげる効果が期待できる」「睡眠の質の改善が期待できる」が各2割強。