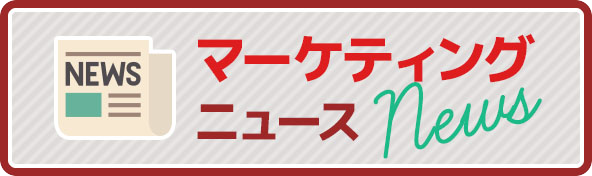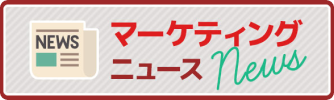- 検索
-
- テーマ別実施時期一覧
- カテゴリー別一覧
-
-
アルコール飲料・嗜好品147
-
非アルコール飲料210
-
その他19
-
-
住宅・住宅設備219
-
-
家電126
-
パソコン・カメラ・AV機器113
-
その他10
-
-
家庭用品・トイレタリー91
-
自動車・関連用品76
-
-
インターネット・情報通信328
-
携帯電話・スマートフォン180
-
メディア・広告66
-
その他7
-
-
ファッション69
-
交通・レジャー・娯楽161
-
季節行事・イベント241
-
時事・ニュース・トレンド51
-
企業ブランドイメージ250
-
広告・CM51
-
WEBサイトの利用91
-
顧客満足度100
- 実施時期別一覧
-
- 調査時期:
- 2025年01月
- 設問項目:
-
サブスクリプションサービス直近1年間利用状況/サブスクリプションサービス:使い放題の直近1年間利用状況/サブスクリプションサービス:試し放題の直近1年間利用状況/サブスクリプションサービス:定期便の直近1年間利用状況/サブスクリプションサービスにかける費用総額(1ヶ月あたり)/サブスクリプションサービス利用のきっかけ・理由/サブスクリプションサービス利用意向/サブスクリプションサービス利用時の重視点/お勧めのサブスクリプションサービス/利用したことがない理由(非利用経験者)(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■サブスクリプションサービス(サブスク)直近1年間利用者は全体の約36%。若年層での比率が高く年代差が大きい。直近1年間利用者のきっかけ・理由は「月額料金に対してお得」が4割強、「利用したい商品・サービスがある」「使い放題、何度でも利用できる」が各3割前後、「会員に登録すると会員特典としてサブスクを利用できる」「自分の好みにあったものを利用できる」が各2割弱。
■サブスク直近1年間利用者のうち、使い放題のサービス利用は「定額制動画配信サービス」が8割弱(回答者全体の3割弱)、「定額制音楽配信サービス」は2割強(全体の約7%)、「電子書籍・雑誌、電子コミック」が11%(全体の約4%)。定額制レンタル・試し放題サービスでは「家電」「家具、インテリア」「自動車、中古車」がそれぞれ約2%。定期便サービスでは「サプリメント、健康食品・健康飲料など」が約8%、「スキンケア用品、化粧品、コスメなど」が約5%。
■サブスク利用意向は全体の3割。若年層で高い傾向で、10・20代約55%、30代4割強。サブスク直近1年間利用者では7割強の利用意向、非利用者では約5%。
■サブスク利用意向者の重視点は「月額料金」「料金に見合う内容」が各8割弱、「商品やサービスの品質」「商品やサービスの品ぞろえ」が各3割強、「解約のしやすさ、解約手順のわかりやすさ」が2割強。
-
- 調査時期:
- 2025年01月
- 設問項目:
-
普段利用するコンビニエンスストア/直近1年間のコンビニコーヒー購入頻度/直近1年間にコンビニコーヒーを購入したコンビニエンスストア/直近1年間にコンビニコーヒーを最もよく購入したコンビニエンスストア/コンビニコーヒー購入理由/コンビニコーヒー購入時の重視点/コンビニコーヒー利用意向/普段飲むコーヒー/コンビニコーヒーの不満/コンビニコーヒー非飲用理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■コンビニエンスストア利用者のうち、コンビニコーヒー直近1年以内購入者は約55%。週1回以上購入者は全体の2割強、直近1年間購入者のうち4割弱で、男性や若年層での頻度が高い傾向。
■コンビニコーヒー直近1年間購入者の理由は「値段の割においしい」「缶コーヒーやペットボトル入りコーヒー等よりおいしい」「価格が安い」が各4割前後、「できたてが飲める」「気軽に買える」「味が本格的」などが各20%台。2020年調査以降、「価格が安い」が減少傾向。購入時の重視点は「味」が6割強、「価格」約45%、「香り」約35%、「容量、サイズ」が2割強。
■コンビニコーヒー利用意向者は全体の5割弱、非利用意向は3割強。コンビニコーヒー週1回以上購入者では80%台の利用意向、直近1年間非購入者では3割強、購入未経験者では約6%。
■普段飲むコーヒーは「自分や他の人がいれたもの」が6割弱、「カフェ・飲食店などのコーヒー」が3割強、「ペットボトル入りコーヒー」「コンビニコーヒー」「缶コーヒー」が各3割弱。「缶コーヒー」「ペットボトル入りコーヒー」は男性30~50代で高い。
-
- 調査時期:
- 2025年01月
- 設問項目:
-
味覚の敏感度/好きな味/苦手な味/ここ2~3年で食べるようになった味/ここ2~3年で食べなくなった味/最も好きな味/好きな味のベース/お菓子類の好きな味/過去5年間での味の好み・嗜好の変化(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■好きな味は「甘い」「薄い・あっさり」が各40%台、「さっぱり」「甘辛い」がそれぞれ約38~39%、「スパイシー」「塩辛い・しょっぱい」「クリーミィ」が各3割強。つい選んでしまう最も好きな味は「甘い」が約15%、「甘辛い」「スパイシー」「薄い・あっさり」「塩辛い・しょっぱい」が各1割前後。
■ここ2~3年で食べるようになった味がある人は全体の3割弱。上位項目は「薄い・あっさり」「スパイシー」「さっぱり」など。食べなくなった味がある人は4割弱で、「濃い・こってり」「塩辛い・しょっぱい」「辛い」などが上位。
■好きな味のベースは「しょうゆ」「かつおだし」が各40%台、「昆布だし」「塩こしょう」「みそ」が各30%台、「カレー」「塩」「チーズ」が3割弱。「チーズ」「ミルク・クリーム系」「ぽん酢」「甘酢」などは女性の方が比率が高い。
■お菓子類の好きな味・フレーバーは「チョコレート」が5割弱、「バニラ」が41.3%、「コーヒー」「ナッツ系」「抹茶」が各30%台、「はちみつ、メープルシロップ」「キャラメル」「いちご、ストロベリー」「ミルク」などが各3割弱。
-
- 調査時期:
- 2025年01月
- 設問項目:
-
カット野菜・パッケージサラダ直近1年間購入経験/直近1年間に購入したカット野菜・パッケージサラダのタイプ/カット野菜・パッケージサラダ利用方法/カット野菜・パッケージサラダ購入理由/カット野菜・パッケージサラダ直近1年間購入場所/カット野菜・パッケージサラダ直近1年間購入頻度/カット野菜・パッケージサラダ購入意向/カット野菜・パッケージサラダ購入時の重視点/カット野菜・パッケージサラダの利用場面・食べ方/購入しない理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■カット野菜・パッケージサラダ直近1年間購入者は約54%、そのうち週1回以上購入者は5割弱。直近1年間購入者のうち「キャベツ:千切り」「サラダ用ミックス」購入者が各6割強、「野菜炒め用ミックス」「刻みねぎ、青ねぎ」が各30%台、「カットレタス、ちぎりレタス」が約26%。「スーパーの店頭」での購入者は約95%、「コンビニエンスストア」が約25%。
■カット野菜直近1年間購入者の用途は「生のまま」が9割弱、「炒め物」が4割弱、「温野菜として食べる」「麺類の具」が各2割弱。購入理由は「そのまま食べられる」が8割弱、「料理の時間が短縮」が5割弱、「後片付けが楽」「下ごしらえが面倒」「分量がちょうどよい」が約35~38%。
■カット野菜の購入意向者は約55%、非購入意向者は約25%。カット野菜直近1年間購入者の購入意向の比率は9割弱、直近1年間非購入者では3割強、購入未経験者では約7%。
■カット野菜購入意向者の重視点は、「価格」「鮮度」が各7割前後、「品質」「変色していない」が各3割強、「野菜の種類の多さ」「食べきりサイズかどうか」「国産かどうか」「日持ちする」がそれぞれ約24~26%。
-
- 調査時期:
- 2025年01月
- 設問項目:
-
豆腐を食べる頻度/よく食べる豆腐のタイプ/好きな豆腐料理/豆腐を食べる場面/豆腐購入時の重視点/豆腐について魅力に感じること/普段食べる豆腐関連食品/豆腐のおすすめの食べ方・調理法/豆腐を食べない理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■豆腐を食べる頻度は「週2~3回」「週1回」がボリュームゾーン。週1回以上食べる人は7割強で過去調査よりやや減少傾向。豆腐を食べる人のうち「夕食」に食べる人が9割弱、「朝食」が2割強、「さっぱりしたものが食べたい」「昼食」が各2割弱。
■豆腐を食べる人のうち「きぬごし豆腐」を食べる人が7割強、「もめん豆腐」が6割弱。近畿では「きぬごし豆腐」がやや高い。普段食べる豆腐関連食品は「油揚げ」「厚揚げ」が回答者全体の各60%台、「がんもどき」が3割弱。
■豆腐を食べる人が好きな豆腐料理は「冷奴」が7割強、「麻婆豆腐」が6割弱、「豆腐のみそ汁」が5割強、「揚げ出し豆腐」「すき焼き」「湯豆腐」が各4割前後。
■豆腐を食べる人が魅力に感じることは「高タンパク、低カロリー」が5割強、「健康によい」が4割強、「手間をかけずに食べられる」「安い」「食べやすい」などが各3割前後。食べる人の重視点は「価格」「味」「豆腐の種類」が各4割強~5割強、「国産大豆」「容量、サイズ」「賞味期限・消費期限」が各3割弱。過去調査と比べ「国産大豆」「新鮮さ」などは減少傾向。
-
- 調査時期:
- 2025年01月
- 設問項目:
-
普段よく飲む水/ミネラルウォーター飲用頻度/直近1年間に飲用した市販のミネラルウォーター/直近1年以内の最頻飲用ミネラルウォーター/市販のミネラルウォーター飲用場面/市販のミネラルウォーター購入場所/ミネラルウォーター購入時の重視点/市販のミネラルウォーター使用場面/直近1年以内の最頻飲用ミネラルウォーター選定理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■ミネラルウォーター飲用者は全体の約65%。関東や近畿などでやや高い。飲用者に占める週1回以上飲用者は4割強。
■ミネラルウォーター飲用者が飲む場面は「のどが渇いた時」4割強、「水分補給」4割弱、「お風呂上がり」「起床時」「仕事・勉強・家事の合間」「寝る前」が各2割強。10~30代の若年層では「朝食時」「昼食時」「夕食時」など食事の時の比率が高い傾向。
■ミネラルウォーター飲用者の購入場所は「スーパー」6割弱、「コンビニエンスストア」35%、「自動販売機」が2割強。購入時の重視点は「価格」が飲用者の約55%、「商品名(ブランド)」「味」がそれぞれ約28%、「メーカー」「容量」などが各2割前後。
■市販のミネラルウォーター使用場面は「自宅で水を飲む」「外出時に持ち歩いて飲む」が全体の各4割弱。「食事のときに飲む」「災害時の備蓄用」がそれぞれ約13%。「外出時に持ち歩いて飲む」は女性の方が比率が高い。
-
- 調査時期:
- 2024年12月
- 設問項目:
-
住居形態/複数拠点生活の状況/目的・理由/別拠点へ通う頻度/別拠点への移動時間/複数拠点生活の興味度/複数拠点生活の意向/新たな生活スタイルの意向/複数拠点生活の意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■主な住まいとは別に、一定期間生活する拠点がある人の比率(複数拠点生活実施者)は、全体の約9%。目的・理由は「別居の親や祖父母などの介護や世話・見守り、サポート」「空き家になった実家などの管理」がそれぞれ約2%(別拠点がある人の各2割前後)、「単身赴任・転勤」「気分を変えたい」が各1%強(別拠点がある人の1割)。
■複数拠点生活実施者が、別拠点に通う頻度は「週1回以上」が2割強、月1回以上が5割強。別拠点への移動にかかる時間は「30分~1時間未満」「1~2時間未満」「2~3時間未満」などが各2割弱。
■複数拠点生活について興味あり層は2割強、興味なし層は約55%。意向層は2割強、非意向層は約56%。意向層の比率は、若年層でやや高く、世帯年収が高い層で高い傾向。現在複数拠点生活実施者では5割弱、非実施者では2割強の利用意向。
■新たな生活スタイルの意向をみると、「生活拠点は都市部でときどき地方部」「平日と休日、仕事とプライベートなどで複数の生活拠点を使い分ける」がそれぞれ約13~15%。
-
- 調査時期:
- 2024年12月
- 設問項目:
-
今年お歳暮を贈る件数/お歳暮の内容/お歳暮を贈る相手/お歳暮の購入場所/お歳暮を最も多く購入する場所/お歳暮の平均単価/お歳暮に贈った品物選定時の参考情報/お歳暮を贈る理由/お歳暮の品物選定時の決め手(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■今年お歳暮を贈る人・予定の人は全体の約35%で過去調査と比べ減少傾向。贈る理由として「相手からも毎年もらう」「毎年贈っている相手がいる」などは高年代層での比率が高い傾向。
■今年のお歳暮を贈る・贈った人のうち、「お菓子・デザート・アイス類」「精肉類、加工肉」「ビール類」を贈る人が各20%台、「魚介類、水産加工品」「果物」が各10%台。
■お歳を贈る・贈った人の購入場所は「百貨店の店頭」「総合スーパーの店頭」「オンラインショッピングサイト」などが各2割弱。過去調査と比べ「百貨店の店頭」は2017年から2020年にかけて減少傾向。
■お歳暮を贈る人が参考にした情報源は「店頭の商品」「ギフトカタログの冊子」が各2割前後、「百貨店・スーパーなど店舗のネットショップ・オンラインストア、アプリ」「家族・友人・知人の意見」が各1割強。
-
- 調査時期:
- 2024年12月
- 設問項目:
-
直近5年間にキャンプに行った回数/直近5年間にキャンプ実施時に利用したキャンプ場の種類/直近5年間キャンプ実施時の同行者/直近5年間にキャンプに行った理由・きっかけ/直近5年間キャンプ実施時の、キャンプ用品レンタル状況/直近5年間に購入したアウトドア・キャンプ用品/アウトドア・キャンプ用品購入場所(直近5年間)/直近5年間に商品を購入したアウトドア・キャンプ用品メーカー/今後のキャンプ実施意向/直近5年間キャンプ実施時の、キャンプ用品レンタル内容・理由/非レンタル理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■直近5年間キャンプ実施者は約9%。そのうち「キャンプ場(フリーサイト)」利用者は4割強、「オートキャンプ場」「コテージ等の場所だけ借り設営・食事準備や片付けなどは自分たち」は各3割強、「グランピング」は2割弱。キャンプ用品をレンタルした人は3割強。
■直近5年間キャンプ実施者について、同行者は「友人・知人やその家族」「家族:小学生以下の子どもを含まない」「家族:小学生以下の子どもを含む」が各3割前後。男性では「ひとりで」が2割弱。理由・きっかけは「自然の中で過ごしたい」「キャンプやアウトドアレジャーが好き」が各4割弱、「気分転換、ストレス解消」「非日常の時間・空間を楽しみたい」「家族とのコミュニケーション」が各3割前後。
■直近5年間アウトドア・キャンプ用品購入者は約16%。購入者のうち「総合オンラインショッピングサイト・ECサイト」「ホームセンターの店頭」「アウトドア・スポーツ用品、アウトドアブランドメーカー店舗の店頭」で購入した人が各3割前後。
■今後キャンプの意向あり層は2割強。若年層での比率が高い。直近5年間キャンプ実施者では8割弱の意向、直近5年間非実施者では2割強、キャンプ未経験者では約7%。
-
- 調査時期:
- 2024年12月
- 設問項目:
-
高級ブランドの認知/所有している高級ブランド/所有している高級ブランド品のアイテム/最もお気に入りの高級ブランド品の銘柄/直近3年間での高級ブランド品売却経験/高級ブランド品の購入頻度/直近3年以内の高級ブランド品購入場所/高級ブランド品選定時の重視点/高級ブランド品の所有・利用についての考え方/高級ブランド品購入理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■高級ブランド品所有者は全体の約46%、女性50~70代で各6割強。所有ブランド上位は、男性では「バーバリー」「コーチ」「ルイ・ヴィトン」など、女性では「コーチ」「ルイ・ヴィトン」「グッチ」など。高級ブランド品所有者のアイテムは「バッグ類」「財布」が各5~6割、「ファッション:小物」が約36%、「時計」が3割弱。
■高級ブランド品所有者のうち、直近3年間売却経験者の比率は2割。「ブランド買取店・買取サービス」が1割強、「リサイクルショップ、古着店」「フリマアプリ」がそれぞれ約5~6%。
■高級ブランド品の購入者は全体の約45%、男性4割弱、女性約54%。高級ブランド品購入者が直近3年以内に購入した場所は「百貨店内にあるブランド直営の店舗」が3割弱。購入経験者の重視点は「デザイン」が6割弱、「品質」が約46%、「使いやすさ」「価格」が各4割弱、「機能性」「素材」が各3割弱。
■高級ブランド品について「関心がない」は男性5割弱、女性約35%。「憧れがある」「所有することで気持ちが引き締まる、自信につながる」は各1割強で、女性若年層での比率が高い傾向。
-
- 調査時期:
- 2024年12月
- 設問項目:
-
身体の悩み/1日の平均睡眠時間/睡眠の質の度合い/睡眠の質の悩み・不満の程度/睡眠の質の生活への影響度/睡眠の質をよくするために行っていること/睡眠の質向上・改善を目的とした飲料の直近1年間利用状況/睡眠の質をよくするために利用したい商品・サービス/睡眠の質をよくするもので効果があった・おすすめのもの(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■1日の平均睡眠時間は「6時間くらい」が約36%、「7時間くらい」が3割弱。6時間以上が約76%、7時間以上が4割弱、5時間以下は約25%。50代では他の層より睡眠時間が短い傾向。
■睡眠の質について、よい方だと思う人は3割弱、よくない方だと思う人は4割強。睡眠の質がよい方だと思う人の比率は、男性10・20代や男女70代で高く、睡眠の質がよくない方だと思う人の比率は女性30・50代でやや高い。
■睡眠の質について悩みや不満を「慢性的に感じている」は2割半ば、「いつもではないが、感じることがある」が4割強。これらをあわせた悩みや不満を感じる人は約66%で、女性の方が高い。睡眠の質に悩みや不満がある人のうち、普段の生活に影響がある人は6割弱、女性30代で高い。
■睡眠の質をより良くするために行っていることは「規則正しい生活」が3割弱、「ふだんの生活の中で体を動かす」「運動・スポーツ、トレーニング」「体を温める」「ストレスをためない」「食生活を整える」などが各2割前後。直近1年間に睡眠の質向上・改善のために寝る前等に飲み物を飲んだ人は約26%。今後睡眠の質改善のために利用したいものは「睡眠の質向上・快眠を目的とした商品」が1割強。
-
- 調査時期:
- 2024年12月
- 設問項目:
-
サプリメント利用状況/サプリメントで摂取している成分・素材/サプリメントの摂取頻度/サプリメントの利用目的/サプリメントの効果/サプリメント直近1年間購入場所/サプリメント選定時の重視点/サプリメント利用意向/サプリメント利用意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■サプリメント現在利用者は全体の約36%、女性で高く、10・20代で低い。利用者のうち「1日1回」摂取する人が7割弱。利用者が直近1年間に購入した場所は「インターネット通販サイト、オンラインショッピング」が約44%、「ドラッグストア」が35%、「メーカーに直接注文」が2割強。
■サプリメント現在利用者の摂取成分・素材は「ビタミンC」が3割弱、「ビタミンB群」「DHA」が各2割強、「亜鉛」「ルテイン」「ビタミンE」などがそれぞれ約16~18%で上位。過去調査と比べ「DHA」「亜鉛」「ルテイン」などが増加傾向、「ブルーベリー」「グルコサミン」などが減少傾向。
■サプリメント現在利用者の利用目的は「健康維持」が7割強、「免疫力・抵抗力向上」「疲労回復」「目の健康の維持・改善」が各2割前後。利用者の重視点は「効果・効能」が7割弱、「成分」「価格」が各5割強、「メーカー・ブランド」が4割強、「安全性」「飲みやすさ」が各20%台。
■サプリメント利用者のうち、求める効果を実感している人は5割弱、実感していない人は約16%。サプリメント利用意向者は全体の4割弱、非利用意向者は4割。利用意向者の比率は、現在利用者の約86%、利用中止者の2割強、非利用者の約3%。
-
- 調査時期:
- 2024年12月
- 設問項目:
-
知っている生命保険会社/生命保険加入状況/加入している生命保険会社/「信頼性や安心感がある」と思う生命保険会社/「商品開発力や企画力がある」と思う生命保険会社/「独自性がある」と思う生命保険会社/「革新的・先進的である」と思う生命保険会社/契約したいと思う生命保険会社/最も契約したい生命保険会社の選定理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■生命保険加入率は全体の約75%。「現在の会社との契約を継続したい」が7割強。最も契約したい生命保険会社は「県民共済」「アフラック」「日本生命」「ソニー生命」などが上位。
■『信頼性・安心感がある』生保は、「日本生命」「県民共済」が各20%台、「第一生命」「アフラック」「明治安田生命」「住友生命」などが各10%台。
■『商品開発力・企画力』があると思う生保は「アフラック」が2割弱、「日本生命」「ソニー生命」「ライフネット生命」などが各6~9%。「いずれもない」が5割強。
■『独自性がある』『革新的・先進的』と思う生保はどちらも「アフラック」「ライフネット生命」が上位2位。『独自性』は「県民共済」「ソニー生命」、『革新的・先進的』は「ソニー生命」などが続く。『革新的・先進的』は「いずれもない」が6割強。
-
- 調査時期:
- 2024年12月
- 設問項目:
-
医療保険加入状況/主加入医療保険会社/主加入医療保険の満足度/医療保険加入時の申し込み経路/医療保険加入・見直し意向/加入したい医療保険会社/医療保険加入時の商品選定の決め手/医療保険加入時のインターネット利用意向/主加入医療保険の加入理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■医療保険加入者は全体の7割弱、医療保険単独加入が4割弱、特約が2割。医療保険加入者の商品加入継続意向は6割強。未加入者の新規加入意向は1割強。
■医療保険加入経路は「知り合いや紹介を受けた営業職員、販売員を通じて」が加入者の2割強。チューリッヒ生命主加入者では「インターネットで申込み手続き」が1位。ネオファースト生命主加入者、メディケア生命主加入者などでは「保険ショップ」の比率が高い。
■商品選定ポイントは「月々の保険料が安い」が全体の6割弱、「病気での入院給付金日額が十分」「十分な額の手術給付金がある」が各20%台、「商品内容がわかりやすい」「日帰り入院も保障」「払込期間が終身」などが各2割弱。
■医療保険加入時「情報収集から申し込みまですべてインターネットを利用したい」は全体の3割強で、県民共済主加入者、こくみん共済coop主加入者などで比率が高い。「ネットで情報収集し最終的には販売員などに相談」は約25%。
-
- 調査時期:
- 2024年12月
- 設問項目:
-
グルテンフリーの認知/グルテンが含まれることを知っていた食品・調味料/グルテンフリーの食生活実施経験/グルテンフリーの食生活実施理由/グルテンフリーの食生活で実施したこと/グルテンフリーの食生活実施意向/グルテンフリーの食生活のイメージ/市販のグルテンフリー製品直近1年間利用状況/グルテンフリーの食生活実施意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■グルテンフリーについて「どのようなものか内容を知っている」が約26%、認知率は8割強。グルテンフリー実施者は約6%で、「ほぼグルテンをとらない食生活を実施」が約1%、「グルテン摂取を減らす食生活を実施」が約5%。グルテンフリーの食生活実施経験者のうち「小麦粉の代わりに米粉で作られた食品・製品を食べる」が5割強、「主食をお米にする」が46%。
■グルテンフリーの食生活実施経験者の理由は「腸内環境改善によい」が4割弱、「血糖値の上昇を防ぐ」「小麦製品を摂取すると体調がよくないことがある」「ダイエットによい」が各20%台。女性30~50代では「腸内環境改善によい」「小麦製品を摂取すると体調がよくないことがある」「ダイエットに良い」が上位3項目。
■グルテンフリーの食生活実施意向者は1割強、非実施意向者は約56%。「実施したくない」の比率が2021年調査より増加。実施意向者は若年層で高い傾向。グルテンフリー現在実施者では8割弱の実施意向、過去経験者では4割強、未経験者では約6%。
■グルテンフリーの食生活のイメージは「好きなものが食べられない」「なんとなく健康によい」が各2割強、「グルテンフリーの食品を確認・準備するのが大変」「血糖値の上昇を防ぐ」「ダイエットによい」などが各2割弱。グルテンフリーの食生活実施経験者では「腸内環境改善によい」「血糖値の上昇を防ぐ」「ダイエットによい」が上位。
-
- 調査時期:
- 2024年12月
- 設問項目:
-
料理をする頻度/調味料に対するこだわり度/自宅にある調味料の種類/よく使用する調味料/2種類以上のタイプを常備している調味料/こだわりがある調味料/料理の味付けで気をつけていること/何かと重宝する調味料(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■調味料に対するこだわりがある人は全体の3割強、こだわりがない人は4割弱。女性高年代層では、こだわりがある人の比率が高い傾向。料理をする人が味付けで気をつけていることは「薄味にする」が4割弱、「素材の味をなるべく生かす」「おかずが2品以上あるとき、同じ味付けにならないようにする」は約25~27%。
■自宅にある調味料は「塩」「しょうゆ」「こしょう」が各90%台、「砂糖」「味噌」「マヨネーズ」が80%台後半、「ソース」「ケチャップ」「めんつゆ」「酢」が80%台前半。「塩麹」「コチュジャン」「タバスコ、チリソース」などは各2~3割と低い。
■家に調味料がある人がよく使用するのは「しょうゆ」「塩」が各70%台、「こしょう」「味噌」「砂糖」が各5割強~6割強、「マヨネーズ」「めんつゆ」「だしの素、液体だし」「みりん」などが各40%台。「めんつゆ」は東北などの東日本でやや高い傾向。
■こだわりがある調味料は、「しょうゆ」「味噌」「塩」が上位3位。家に調味料がある人のうち2種類以上を常備しているのは「しょうゆ」「塩」が各2割前後、「こしょう」「ソース」「味噌」「砂糖」「酢」「だしの素、液体だし(和風)」が約10~15%。
-
- 調査時期:
- 2024年12月
- 設問項目:
-
チョコレートを食べる頻度/好きなチョコレートのタイプ/チョコレートを食べる場面/市販のチョコレート購入時の重視点/直近1年間に食べた機能性チョコレート/機能性チョコレート利用理由/チョコレートに関する考え/市販のチョコレートの好きな銘柄・食べ方など(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■チョコレートを週1回以上食べる人は全体の5割弱で、女性での比率が高い。好きなチョコレートのタイプは「ミルクチョコレート・クリームチョコレート」約54%、「ビターチョコレート・ブラックチョコレート」「ナッツ入りチョコレート」各40%台、「板チョコレート」3割強。
■チョコレートを食べる人のうち「おやつ、間食」に食べる人が約75%、「甘いものが欲しくなった時」「ちょっと一息つきたい時」が各30%台、「疲れている時」「仕事や勉強・家事の合間」「食後」「小腹がすいた時」などが各2割前後。購入時重視点は「味」8割弱、「価格」5割強、「甘さ」「容量、サイズ」「カカオ含有率」各20%台、「食べなれている」「メーカー」「食感」各2割弱。
■チョコレートを食べる人のうち、直近1年間に機能性チョコレートを食べた人は5割強。「高カカオ」が4割、「GABA」「乳酸菌」「ストレス・緊張の緩和」が各1割前後。直近1年間機能性チョコレート利用者の利用理由は「健康によい」が約46%、「味が好き」が3割強、「甘いものを食べて健康になれる」「甘いものが食べたいがカロリーや脂質、糖質が気になる」「甘さが控えめ」が各2割弱。
■チョコレートについての考え方では「おやつの一品として買い置き」は4割強、「高カカオチョコレートは健康によい」「自分へのごほうびとして買う」「気分転換に欠かせない」が各2割前後。
-
- 調査時期:
- 2024年12月
- 設問項目:
-
代替肉の認知/直近1年間での代替肉の喫食状況/直近1年間に代替肉を食べた理由・きっかけ/直近1年間に購入した代替肉・加工品のタイプ/代替肉喫食意向/代替肉購入時に重視すると思う点/代替肉の魅力点/代替肉の不安・不満な点/代替肉喫食意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■代替肉を「どのようなものか内容を知っている」は3割強。認知率は約85%で2022年調査より減少。代替肉直近1年間喫食者は全体の2割強、喫食経験者は4割弱。「大豆ミート加工品や惣菜を自宅で食べた」が約14%、「大豆ミートを購入し料理」が約7%。代替肉・加工品直近1年間購入者は全体の2割強で、そのうち「ミンチタイプ」購入者は約46%。
■代替肉を直近1年間に食べた人の理由は「どんな味か試しに食べてみた」が4割弱、「健康のため」が約26%、「高たんぱくで低カロリー」「店で販売していた、店のメニューにあった」などが各2割弱。
■代替肉の今後の喫食意向者は2割強。非喫食意向者は4割強で2022年調査より増加。喫食意向者は、直近1年間に食べた人・購入した人では各5割、いままでに食べたことはない人では1割強。代替肉喫食意向者の重視点は「味」が約76%、「価格」「原材料」が各50%台、「添加物」が4割弱、「国産かどうか」「栄養成分」「食感」が各3割前後。
■代替肉の魅力点は「健康に良い」が全体の3割強、「食物繊維を多く摂取できる」「脂質の吸収を抑えられる」「高たんぱく低カロリー」「ヘルシーでありながら、肉を食べているような満足感が得られる」などが各2割弱。気になること・不安・不満は「味がよくない」「何が入っているかわからない」が各3割前後、「肉らしさが低い・物足りない」「価格が高い」「本当に安全かどうか不安」「食感がよくない」などが各2割前後。
-
- 調査時期:
- 2024年11月
- 設問項目:
-
普段の生活のゆとり/余暇の過ごし方のタイプ/余暇についての考え方/余暇の過ごし方などについての満足度/平日の余暇時間の過ごし方/休日の余暇時間の過ごし方/平日1日あたりの平均余暇時間/余暇時間を一緒に過ごす人/余暇の過ごし方の最も多いパターン(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■生活全般のゆとりを感じている人は4割弱で、2015年調査以降減少傾向。ゆとりを感じる人は10・20代と60~70代で高く、男性40~50代で低い。
■余暇の過ごし方のタイプはアクティブ派が2割弱、ゆったり派が約55%。「余暇は心身を休めるために使いたい」が5割弱、「自分の好きなことに熱中・集中しリフレッシュしたい」が約35%、「普段はできないようなことをしたり感じたりすることで気分転換したい」「健康維持のために使いたい」「家族や友人などとのコミュニケーションを楽しみたい」が各20%台。
■平日1日あたりの余暇時間は「~2時間」「~3時間」がボリュームゾーン。余暇の過ごし方や時間・お金などに満足している人は全体の4割強で、10・20代や60~70代で高く、男性30~50代で低い。
■余暇時間の過ごし方は、「テレビ番組を見る」「パソコンやタブレット端末を利用」「家でごろごろ」などが上位。若年層では「家でごろごろ過ごす」「寝る」「ゲーム」などが高く、「テレビ番組を見る」などが低い。高年代層では「パソコンやタブレット端末を利用する」などが高い傾向。
-
- 調査時期:
- 2024年11月
- 設問項目:
-
ハロウィンの認知/ハロウィンから連想すること/ハロウィンにあたって購入したもの/ハロウィンで購入した商品の購入場所/ハロウィンにあたって実施したこと/ハロウィンの行事を一緒にした人/ハロウィンで使った費用総額/あなたにとってハロウィンとは/今年のハロウィンで印象に残っていること(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■ハロウィン認知率は全体の約98%。連想することは「かぼちゃ」8割弱、「お化け」約55%、「お菓子」「仮装」各5割前後。
■ハロウィンに関することの実施率は認知者の約17%、女性や、10~30代での比率が高い。実施者のうち「ハロウィンにちなんだ・限定のお菓子等を食べた」「自分の子どもや孫にお菓子等をあげた」が各2割強、「部屋などを装飾」「友人・知人・親類の子ども等にお菓子等をあげた」などが約12~13%。30~40代では「自分の子ども」と一緒に実施した人の比率が高い。
■ハロウィン認知者のうち、ハロウィンのために何か購入したものがある人は約16%。そのうち「お菓子・スイーツ等」の購入者が5割強、「かぼちゃ」「仮装用の衣装や小物」などが各2割強。「スーパー」での購入者は5割強、「100円均一ショップ」が2割強。
■ハロウィンのとらえ方は、「興味がない」が全体の4割弱、「子どものイベント」「海外の行事」「季節行事の一つ」などが各10%台。ハロウィンに関することの実施者では「子どものイベント」「季節行事の一つ」「家族とのコミュニケーションを図る機会」などが上位。
-
- 調査時期:
- 2024年11月
- 設問項目:
-
直近1年間にギフトを贈った回数/直近1年間にギフトを贈った機会/直近1年間にギフトを贈った相手/ギフト選定時の重視点/直近1年間のギフト選定時の参考情報/直近1年間に贈ったギフトを届けた方法/直近1年間に贈ったギフトの購入場所/直近1年間にプチギフトを贈った経験/直近1年間にもらったプチギフトの内容・場面(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■直近1年間に何らかの贈り物をした人は約64%で、女性の方が比率が高い。贈った回数は年間「2~3回」がボリュームゾーン。直近1年間贈答者のうち「誕生日」に贈った人は約55%、「お中元・お歳暮」は4割強、「手土産・ご挨拶」「ちょっとしたお礼・お返し、プチギフト」「母の日」はそれぞれ約25~29%、「クリスマス」が2割弱。直近1年間でのプチギフト実施状況は、「ちょっとしたお礼・お返しとして」が3割強。
■直近1年間ギフト贈答者の重視点は「相手の好みにあうか」が7割弱、「もらった人が喜ぶか」「贈り物の内容が状況にふさわしいか」「価格が高すぎたり安すぎたりしないか」が各4割強~5割。
■直近1年間ギフト贈答者の参考情報は「店頭の商品」が4割弱、「相手の希望」「オンラインショップの商品情報、口コミレビュー」「家族・友人・知人の意見」などが各2割前後。「SNS、ブログ、YouTubeなど」は若年層での比率が高い。
■直近1年間ギフト贈答者の購入場所は「インターネットショップ、ネット通販」が5割弱、「デパートの店頭」「専門店・小売店」が各3割前後、「ショッピングセンター・モール」「スーパーの店頭」が各2割弱。直近1年間ギフト贈答者のうち、「直接会って渡す」が7割弱、「宅配便や郵送、振込など」が6割弱。
-
- 調査時期:
- 2024年11月
- 設問項目:
-
運動不足を感じる度合い/自宅での運動・トレーニングの直近1年間実施内容/自宅での運動・トレーニング開始時期/自宅で運動・トレーニングを行う理由・きっかけ/自宅で運動・トレーニングを行う頻度(直近1年間)/自宅での運動・トレーニング実施時間(直近1年間)/自宅での運動・トレーニングでの参考情報/自宅での運動・トレーニングの意向/運動不足解消のために直近1年間に実施したこと/実施していない理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■現在運動不足だと感じる人は約75%。自宅での運動・トレーニング直近1年間実施者は全体の5割弱。「室内や敷地内でのウォーキング、階段の上り下り、足踏みなど」が2割強、「腹筋、背筋、腕立て伏せ、スクワットなど、器具を使わない筋トレ」「体操、ストレッチ」が約15~16%。
■自宅での直近1年間運動実施者のうち、1年以内開始者が約26%、3年以内開始者が4割強。女性若年層での比率が高い傾向。実施頻度は「ほぼ毎日」は3割強で、高年代層で高い傾向。1日あたり実施時間は30分未満が7割弱、女性や高年代層での比率が高い傾向。
■自宅での直近1年間運動実施者の理由は「健康維持」が7割強、「体力の維持、体力をつける」が4割強、「筋力維持、筋力をつける」「加齢に伴う体の機能低下を防ぐ・補う」が各30%台。参考情報は「動画共有サイトの動画」「テレビやラジオの、運動や体操関連の番組」が各2割強、「本や雑誌など」が1割強。
■今後自宅での運動・トレーニング意向あり層は65%、女性や高年代層で高い。自宅での運動直近1年間実施者のうち、意向あり層の比率は9割弱、非実施者では約45%。
-
- 調査時期:
- 2024年11月
- 設問項目:
-
スキンケアに対する関心度/肌のトラブル・悩み事/肌のためにしていること/現在使用しているスキンケア用品/スキンケア用品に期待する効果/スキンケア用品購入時の重視点/スキンケア用品の1ヶ月あたり購入費用/スキンケア用品購入場所/スキンケア関連用品について困っていること・不満(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■スキンケア関心層は全体の5割強で、女性8割弱。男性3割強で男性10~30代では各5割前後。悩み事は「シミ・そばかす」が4割弱、「しわ」「乾燥」「たるみ」が各3割弱、「ハリがない」「くすみ」「毛穴が目立つ」「クマ」などが各2割弱。
■肌のためにしていることの上位3位は「スキンケア用品を使用」が4割、「紫外線対策」「規則正しい生活」「睡眠を十分とる」が各20%台。女性では、3位以下は「肌の保湿」「肌に負担のかからない化粧品を使用する」「規則正しい生活」「睡眠を十分とる」などとなっている。
■スキンケア用品使用者は全体の7割強、男性54%、女性約94%。男性10~30代では「化粧水」が各3割前後など、男性の中でのスキンケア用品使用率が高い傾向。使用者が期待する効果は「保湿効果」が4割弱、「アンチエイジング」「肌のハリ・ツヤのアップ」が各3割弱、「肌をなめらか・つるつるにする」「肌荒れ防止」「しわ改善・予防」が各2割強。
■スキンケア用品購入時の重視点は「効能・効果」「肌との相性」が各40%台、「使用感」「品質・成分」が各4割弱。購入場所は「ドラッグストア」がスキンケア用品購入者の6割強、「インターネット通販、オンラインショップ」が3割強、「スーパー」が1割強。
-
- 調査時期:
- 2024年11月
- 設問項目:
-
SNSの認知・登録状況/利用しているSNSサイト/SNS利用頻度/最頻利用SNS/SNS利用場面/SNSを利用する機器/SNSの利用内容/今後利用したいSNS/閲覧しているSNS/あなたにとってSNSとは(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■SNS現在登録者は7割強。回答者全体に占める利用者は「LINE」約64%、「X」「Instagram」約30%台。「Facebook」各3割弱。過去調査と比べ「LINE」「Instagram」などが増加傾向、「Facebook」が減少傾向。今後利用したいSNSでは「LINE」5割弱、「X」「Instagram」各2割強、「Facebook」約16%。過去調査と比べ「LINE」「Instagram」などが増加傾向。
■SNS登録者のうち、1日2回以上利用者は5割強で、8割弱が毎日アクセスしている。女性や若年層で利用頻度が高い傾向。「スマートフォン」でアクセスする人はSNS利用者の9割強。
■SNS利用場面は「自宅でくつろいでいるとき」が利用者の6割弱、「暇なとき」「すきま時間」が各4割弱。女性10~30代で他の層より比率が高い項目が多い。
■SNS利用内容は「他人の投稿を読む」が利用者の6割弱、「メッセージやチャット、DM等を個人同士・グループ内で送信・受信」が4割弱、「他人の投稿にコメントやいいね!をする」「他の人の画像や動画を見る」「ニュースの閲覧」が各20%台。SNS認知者のうち閲覧だけしているSNSの比率は「X」「Instagram」がそれぞれ約27%、「LINE」が2割強。
-
- 調査時期:
- 2024年11月
- 設問項目:
-
ファミリーレストラン直近1年間利用頻度/直近1年間に利用したファミリーレストラン/直近1年間最頻利用ファミリーレストラン/ファミリーレストラン選択時の重視点/ファミリーレストラン利用場面/ファミリーレストランに行くと決める基準・経緯/最もおいしいと思うファミリーレストラン/ファミリーレストランでの、テイクアウト・デリバリーの直近1年間での利用状況/直近1年間最頻利用ファミリーレストランの利用理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■ファミリーレストラン直近1年間利用率は約55%。月1回以上利用者はファミレス利用者の約46%で10~30代での比率が高い。ファミリーレストラン利用者が最もおいしいと思うのは「ロイヤルホスト」「サイゼリヤ」「ガスト」が各1割強。北海道では「びっくりドンキー」の比率が高い。
■直近1年間テイクアウト利用者は約7%、デリバリー利用者は約5%。ファミリーレストラン利用場面は「昼食」が直近1年間利用者の7割強、「夕食」が5割弱、「家族での利用」が3割弱。
■直近1年間ファミリーレストラン利用者の重視点は「価格」「料理の味」が各7割弱、「メニューの内容」「店までのアクセスのよさ」が各40%台、「メニューの豊富さ」が3割強。「ドリンクバーの充実度」は利用頻度が高いほど、比率が高い傾向。
■直近1年間ファミリーレストラン利用者の、利用決定時の経緯は「食べたいメニューがある」が5割弱、「その日の気分」「安くておいしい店に行きたい」「駐車場がある店舗」「クーポンやキャンペーン・プレゼントなどがある」が各20%台。
-
- 調査時期:
- 2024年11月
- 設問項目:
-
からだにいい食事に関する考え方/からだにいい食べ物・飲み物の摂取に対する意識/からだにいい食べ物・飲み物の摂取にあたり気をつけていること/からだにいいと思って習慣的に摂取している食べ物/からだにいいと思って習慣的に摂取している飲み物/からだにいい食べ物・飲み物に期待する効果/からだにいい食べ物・飲み物に関する情報源/からだにいいと思って摂取している食べ物・飲み物の名称と摂取理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■からだにいい食べ物・飲み物をとるよう気を付けている人は半数弱。気を付けていない人は約25%で、2015年調査より増加。気を付けていることは「野菜を多くとる」「必要な栄養素をバランスよくとる」「量を食べすぎない」が各50%台、「発酵食品」「旬のものを食べる」が各40%台。一方「栄養機能食品」「機能性表示食品」「小麦などグルテンの摂取を減らす食生活」「標準的に必要なカロリーよりも少なめに摂取」はそれぞれ約5~6%と低い。
■からだにいいと思って習慣的に摂取している食べ物は「野菜」が6割強、「きのこ類」「大豆加工品」「乳製品」「豆類」などが各40%台で上位。飲み物は「お茶、お茶系飲料」が5割強、「牛乳」「コーヒー、コーヒー飲料」が各3割強、「水・ミネラルウォーター」「野菜ジュース」が各2割前後。
■からだにいい食べ物・飲み物に期待する効果は「健康維持」が6割弱、「免疫力を高める」「便通改善、おなかの調子を整える、整腸効果」などが各3割弱で、高年代層で高い傾向。「体調不良の改善、病気の改善・悪化防止」「体質改善」などは男性10~40代、女性30~40代での比率が高い。
■からだにいい食べ物・飲み物に関する情報源は「テレビ番組・CM」が5割弱、「家族や友人・知人」が20.5%、「新聞記事・広告」「健康関連の情報サイト」「SNS、動画共有サイト」「商品パッケージの説明」が各10%台。「SNS、動画共有サイト(YouTubeなど)」は若年層で高く、「テレビ番組・CM」「新聞記事・広告」などは、高年代層で高い。
-
- 調査時期:
- 2024年11月
- 設問項目:
-
発酵食品に対する関心度/発酵食品であるということを知っていたもの/飲食している発酵食品/発酵食品の摂取意識度合い/健康のために意識して摂取している発酵食品/発酵食品飲食のきっかけ・理由/発酵食品に期待する効果/発酵食品の摂取意識意向/発酵食品で気に入っているもの/摂取しない理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■発酵食品関心層は全体の6割強、女性や高年代層での比率が高い。普段の食事での発酵食品の摂取について、意識層は約46%、非意識層は3割強。発酵食品摂取意向者は約74%、発酵食品を意識的に摂取している人では9割弱、意識的に摂取していない人では4割弱。
■発酵食品であることを知っていたのは「納豆」「味噌」が各9割強、「ヨーグルト」「チーズ」「醤油」「キムチ」などが各8割前後。下位は「くず餅」「ナタデココ」「ドライソーセージ(サラミ)」など。発酵食品飲食者が健康のために意識して摂取する発酵食品は「納豆」6割弱、「ヨーグルト」5割弱、「味噌」3割強、「チーズ」2割強。
■発酵食品飲食者のきっかけ・理由は「健康によい」が6割弱、「おいしい」が4割強、「手軽に摂取できる」「旨味がある」がそれぞれ約25~26%。
■発酵食品飲食者が期待する効果は、「整腸作用」が5割弱、「免疫力向上」が4割強、「うま味成分が高まる」「栄養価が高まる」が各3割強、「高血圧など、生活習慣病予防」が3割弱。
-
- 調査時期:
- 2024年11月
- 設問項目:
-
行っている運動の程度/直近1年間でのプロテイン利用状況/直近1年間プロテイン利用頻度/プロテイン利用のきっかけ・理由/プロテイン選定時の情報源/プロテイン利用による効果を感じたか/プロテイン利用意向/プロテイン利用時に重視すると思う点/プロテイン利用意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■プロテイン直近1年間利用者は2割弱で、若年層での比率が高い傾向。プロテイン直近1年間利用者のうち「粉末」6割弱、「液体、飲料」「棒状・バータイプ」各3割前後、「ゼリー飲料」2割弱。週1日以上利用者は直近1年間利用者の7割弱。
■プロテイン直近1年間利用者のきっかけ・理由は「筋肉や筋力の維持・増強」「健康維持」「たんぱく質の摂取」が各40%台。「筋肉や筋力の維持・増強」「筋肉質な体を目指す」は男性の方が比率が高い。女性は「たんぱく質の摂取」が1位。直近1年間利用者のうち効果を感じた人は3割強。女性50代では、効果を感じなかった人の比率が高い。
■プロテインの利用意向率は全体の2割弱、非利用意向率は約55%。利用意向率は若年層で高い。プロテイン直近1年間利用者では利用意向率は7割強、利用未経験者では約5%。
■利用意向者の重視点は「味、おいしさ」が7割弱、「飲みやすさ」が6割弱、「価格」「風味・フレーバーの種類」が各40%台、「品質」「たんぱく質の種類」が各4割弱、「たんぱく質含有量・含有率」「安全性」「手軽に摂取できる」が各3割強。
-
- 調査時期:
- 2024年11月
- 設問項目:
-
味噌の嗜好度/味噌を料理に使う頻度/使用する味噌のタイプ/自宅にある味噌の種類数/味噌を使う料理/使用している味噌のメーカー/味噌購入時の重視点/市販の味噌のこだわり・気を付けていること(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■味噌が好きな人は全体の約85%。味噌を料理に週4~5回以上使う人は約35%、週1回以上利用者が7割弱で、2021年調査より減少。東北や北陸では利用頻度が高い傾向。
■味噌使用者が使う味噌のタイプは、「米みそ・こうじみそ」が6割弱、「合わせみそ」が約26%、「赤みそ」「だし入り」「白みそ」が各2割弱。北海道では「だし入り」、中部では「赤みそ」などの比率が高い。味噌使用者の自宅にある味噌は「1種類」が約56%。2種以上使用者は中部や近畿での比率が高い。
■味噌使用者が味噌を使う料理は「味噌汁」が約95%、「鍋物」「炒め物」「煮物、煮込み料理」などが各20%台。東北では「おにぎり」、中部では「揚げ物」「煮物、煮込み料理」「味噌だれ」などが他の地域よりやや高い。
■味噌使用者の購入時の重視点は「味」が7割弱、「価格」が4割強、「味噌の種類」が3割強、「原材料」「容量、サイズ」が各20%台。
-
- 調査時期:
- 2024年11月
- 設問項目:
-
直近1年間に利用・摂取する食用油/自宅にある食用油の種類数/食用油利用場面/食用油利用頻度/食用油購入時の重視点/効能・効果を期待して利用している食用油/食用油に期待する効能・効果/食用油の使い分け(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■直近1年間に利用・摂取する食用油は「オリーブオイル」「ごま油」が各7割弱、「サラダ油」が6割弱。自宅にある食用油の種類数は「3~4種類」が半数。
■食用油直近1年間利用者の利用頻度は週4~5回以上利用者が6割強。食用油利用シーンは「加熱調理する料理」が直近1年間利用者の約95%、「加熱しないで料理に使う」が4割強、食べるものにそのままかける」が3割弱。
■食用油購入時の重視点は「油の種類」が6割強、「価格」が約46%、「味」「原材料」「容量、サイズ」が各3割前後。
■食用油直近1年間利用者が効能・効果を期待している食用油は「オリーブオイル」が4割弱、「ごま油」が2割弱、「サラダ油」「亜麻仁(アマニ)油」が約11%。期待する効果・効能は「悪玉コレステロールを下げる」「生活習慣病予防」が各2割弱。