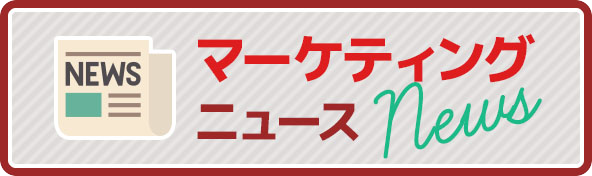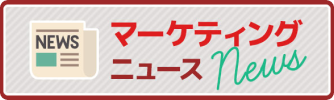- 検索
-
- テーマ別実施時期一覧
- カテゴリー別一覧
-
-
アルコール飲料・嗜好品147
-
非アルコール飲料210
-
その他19
-
-
住宅・住宅設備219
-
-
家電126
-
パソコン・カメラ・AV機器113
-
その他10
-
-
家庭用品・トイレタリー91
-
自動車・関連用品76
-
-
インターネット・情報通信328
-
携帯電話・スマートフォン180
-
メディア・広告66
-
その他7
-
-
ファッション69
-
交通・レジャー・娯楽161
-
季節行事・イベント241
-
時事・ニュース・トレンド51
-
企業ブランドイメージ250
-
広告・CM51
-
WEBサイトの利用91
-
顧客満足度100
- 実施時期別一覧
-
- 調査時期:
- 2024年08月
- 設問項目:
-
直近1年間に利用した家事代行サービスの内容/家事代行サービス定期利用時の利用頻度/直近1年間に利用した家事代行サービス名/家事代行サービスに関する情報収集方法/家事代行サービス利用意向/利用してみたい家事代行サービス/家事代行サービス選定時の重視点/家事代行サービスを利用したい場面/家事代行サービス利用意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■直近1年間家事代行サービス利用者は全体の約5%、男性10~30代では各1割強。家事代行サービス利用者のうち「掃除代行、ハウスクリーニング」利用者は男性約56%、女性6割強。直近1年間利用者のうち、定期的な利用は6割強で、男性の方が比率が高い。スポット・単発利用のみは3割強で女性の方が比率が高い。
■家事代行サービス利用意向者は全体の約16%、非利用意向者は約54%。利用意向者の比率は女性の方が高い。直近1年間家事代行サービス利用者では7割弱の利用意向、非利用者では1割強。
■家事代行サービス利用意向者の重視点は、「価格」が7割弱、「料金体系のわかりやすさ」が5割強、「スタッフの対応・技術力」「サービスの種類やプランの充実度」が各40%台、「希望日に対応」「会社の信頼性」が約34%。
■サービス利用意向者が、利用したいサービスは「掃除代行、ハウスクリーニング」約76%、「片づけ、整理整頓」約24%、「日常家事全般」が2割弱。利用したい場面は「自分ではできない・難しいところ」が6割強、「プロに本格的にやってほしい」が約46%、「自分が苦手な家事」が36%。
-
- 調査時期:
- 2024年08月
- 設問項目:
-
意識して摂取している栄養素・成分/たんぱく質摂取の意識度合い/たんぱく質摂取量についての意識/たんぱく質摂取のために意識的に摂取している食品/たんぱく質摂取のために直近1年間に購入した商品/たんぱく質を意識的に摂取するきっかけ・理由/たんぱく質の摂取による効果の度合い/たんぱく質の摂取について意識的に行っていること/行っていない理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■たんぱく質の摂取を意識している層は4割強、意識していない層は4割弱。意識している層の比率は女性の方が高く、女性60~70代では各6~7割。男性30~60代では意識していない層の比率が高い。たんぱく質を摂取している方だと思う人は約35%、摂取している方ではないと思う人は2割強。
■たんぱく質摂取のために意識的に摂取する食品は「卵」「精肉類:鶏肉」「豆腐」「納豆」が各4割弱、「ヨーグルト、飲むヨーグルト」「精肉類:豚肉」がそれぞれ約34~35%、「牛乳」「魚介類」「チーズ」が各3割弱。たんぱく質摂取のための直近1年間購入商品は「サラダチキン」が1割強、「プロテインの粉末・錠剤」が約9%。
■たんぱく質を意識的に摂取している人の、きっかけや理由は「健康維持」が7割強、「筋力維持」が4割強、「免疫力・抵抗力向上」が3割強、「人体に欠かせない基本的な栄養素」「加齢に伴う衰えが気になる」「筋肉をつける」がそれぞれ約24~26%。
■たんぱく質の摂取を意識している層のうち、効果を感じる人は3割強。男性若年層では効果を感じる人の比率が高い。女性30~50代では効果を感じない人がやや高い。
-
- 調査時期:
- 2024年08月
- 設問項目:
-
夕食を外食でとる頻度/夕食時の外食回数の1年前からの変化/夕食時に外食する回数が減った理由/自宅での夕食時のお惣菜・レトルト食品・半調理品・テイクアウトなどの直近1年間利用状況/自宅で週5日以上食べる食事/自宅での食事に関して直近1年間で増えたこと/直近1年間の自宅での食事にかける費用の変化/自宅での食事について大切にしていること・こだわり(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■夕食を外食でとる頻度は「年に数回程度」が2割強、週1回以上が4割強。「ほとんど外食はしない」は3割弱で、コロナ禍の2021年調査より減少。
■1年前より夕食の外食回数が減った人は2割強、「変わらない」が7割強。夕食の外食回数が減った理由は「節約」が38.6%、「物価上昇」「外食をするお金の余裕がない」が各3割前後、「家でゆっくり食事をしたい」「飲み会などの夜のつきあいの機会が減った」が各2割強。
■自宅での夕食で直近1年間に利用したものは、「店で購入したお惣菜」が5割弱、「レトルト食品、インスタント食品、レンジアップ商品など」が3割弱、「カット野菜、袋入りサラダ」「市販のあわせ調味料、料理の素」「店で購入したお弁当」「調理済みの冷凍食品(温めるだけのもの)」が各2割強。
■自宅での食事で直近1年間に増えたことは「食費を安く済ませる(節約)」「簡単に調理できる・短時間で調理できるものを準備する」「夕食を自宅で食べる」が各1割強。自宅での食事にかける費用が直近1年間に増えた層は全体の3割弱、「変わらない」が5割強。
-
- 調査時期:
- 2024年08月
- 設問項目:
-
甘いものの嗜好度/自宅で使う砂糖・甘味料/砂糖・糖分に関する考え方/砂糖・糖分の摂取量・頻度について気をつける度合い/砂糖・糖分の摂取について気をつけていること/甘さ控えめの商品を選ぶことが多いもの/甘さ控えめの商品を選ぶ理由/砂糖・糖分摂取量についての意識/砂糖・甘味料選定時や糖分摂取時に気を付けること・こだわり(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■甘いものが好きな人は8割強。自宅で使う砂糖・甘味料は「上白糖」が5割弱、「ハチミツ」が3割強、「三温糖」「グラニュー糖」が各2割前後。砂糖・糖分の摂取量がちょうどよいと思う人は4割強、多い方だと思う人は女性30~50代で5割強と高い。
■「糖分をとりすぎると生活習慣病になりやすい」「糖分をとりすぎると太る」と思う人が各6割前後、「糖分は脳の働きに必要」「糖分をとりすぎると虫歯になりやすい」が各40%台。「糖分は疲労回復に役立つ」は約36%で過去調査より減少傾向、「人工甘味料は体によくない」は約34%で過去調査より増加傾向。
■砂糖・糖分の摂取量・頻度に気をつけている人は約54%。気をつけていることは「糖分控えめ、微糖、低糖、無糖などの商品を選ぶ」が4割弱、「砂糖・糖分が多い食べ物・飲み物を控える」「料理や飲み物に入れる砂糖・糖分の量を控える」が各20%台。
■糖分控えめの商品利用者が選ぶ食べ物は「ヨーグルト」が3割強、「チョコレート類」が2割強。飲み物では「コーヒー飲料」が6割弱、「炭酸飲料」「紅茶飲料」などが各20%台。甘さ控えめ商品を選ぶ理由は「健康維持、病気予防」が7割弱、「太らないようにする・ダイエット」が5割弱、「糖尿病などの病気」「甘さ控えめの方がおいしい」などが各3割前後。
-
- 調査時期:
- 2024年08月
- 設問項目:
-
直近1年間での市販の青汁利用状況/直近1年間での青汁利用頻度/直近1年間に利用した市販の青汁の特徴/直近1年間に利用した青汁のメーカー/直近1年間での青汁購入場所/青汁利用理由/青汁利用意向/青汁を購入する場合の重視点/利用したい青汁のタイプ・特徴/青汁利用意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■市販の青汁利用経験者は全体の4割、直近1年間利用者は2割強。直近1年間青汁利用者のうち「粉末タイプ」利用者は8割強、「ストレートタイプ」は2割強。週1回以上利用者は約56%。70代での利用頻度が高い傾向。
■市販の青汁直近1年間利用者のうち「大麦若葉が主原料」利用者が5割弱、「ケールが主原料」が約26%。青汁直近1年間利用者の購入場所は「スーパー」「インターネット通販」が各3割弱、「ドラッグストア」が2割強。青汁利用頻度が週2~3回以上と高い層では「インターネット通販」が最も多い。
■市販の青汁直近1年間利用者の青汁利用理由は「健康のため、健康維持」が約66%、「野菜不足を補うため」「なんとなく体によさそう」が各3割前後、「食物繊維がとれる」「栄養がある、栄養素の摂取・補給」「体質改善」が各10%台。
■青汁利用意向は2割強、非利用意向者は約55%。青汁直近1年間利用者の利用意向率は7割強、非利用者(利用経験あり)では2割強、利用未経験者では約5%。青汁利用意向者のうち「粉末タイプ」利用意向が約75%、「ストレートタイプ」が3割。今後青汁購入時の重視点は「飲みやすさ」が全体の4割弱、「味」約35%、「価格」3割弱、「安全性」「効能・効果」「国産かどうか」などが各2割弱。
-
- 調査時期:
- 2024年08月
- 設問項目:
-
炭酸入り飲料の嗜好度/普段よく飲む炭酸入り飲料/直近1年間の市販の炭酸水飲用頻度/直近1年間に飲んだ炭酸水の銘柄/直近1年間に最もよく飲んだ炭酸水の銘柄/市販の炭酸水飲用場面/市販の炭酸水選定時の重視点/市販の炭酸水飲用意向/市販の炭酸水の不満点/非飲用者の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■炭酸が入った飲料が好きな人は約65%、好きではない人は2割弱。普段よく飲む炭酸入り飲料は「コーラ炭酸飲料」が4割弱、「炭酸水」が3割強、「透明炭酸飲料:香り・フレーバーつき」が3割弱、「果汁系炭酸飲料・果実着色炭酸飲料」「ジンジャーエール」が各2割強。
■市販の炭酸水直近1年間飲用者は全体の6強弱。週1回以上飲用者は全体の3割強、市販の炭酸水飲用者の5割強。市販の炭酸水飲用意向者は全体の約44%、週1回以上飲用者では8割以上、月1回以下飲用者では5割弱、飲用未経験者では約3%。
■市販の炭酸水直近1年間飲用者の飲用場面は「のどが渇いたとき」が3割強、「お風呂あがり」が3割弱、「スッキリしたいとき」「休憩中・休み時間」が各2割強。サンペレグリノ主飲用者、ペリエ主飲用者では「食事と一緒に」が1位。
■市販の炭酸水直近1年間飲用者の重視点は「価格」が4割強、「味、飲み口」「強炭酸」が各30%台、「商品ブランド」「容量」「飲み慣れている」「メーカー名」などが各2割弱。炭酸水が好きな層や飲用頻度が高い層では「強炭酸」の比率が高い傾向。
-
- 調査時期:
- 2024年07月
- 設問項目:
-
環境問題への関心度/使い捨てプラスチック製品の利用についての意識度/利用する使い捨てプラスチック製品/使い捨てプラスチック製品であった方がよいと思うもの/使い捨てプラスチック製品に関して実施していること/レジ袋有料化で不便に感じる度合い/プラスチックごみ削減のための国際的ルールとして賛同する内容/環境問題の意識・行動の直近3年間での変化/使い捨てプラスチック製品に関して意識していることや取り組み(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■使い捨てのプラスチック製品利用を意識する人は6割強、女性や高年代層で高い傾向。使い捨てプラスチック製品に関する実施内容は「エコバッグ・マイバッグを使う」「有料レジ袋は買わない」が各6~7割、「詰め替え用を買う」が5割弱、「プラスチックのゴミを分別、洗浄し、リサイクルできるようにする」「プラスチック製のスプーン・フォーク、ストローなどはもらわない」が各30%台。
■使い捨てのプラスチック製品や容器で普段使う・もらうものは、「ペットボトル」「食品トレイ」が各70%台、「プラスチック製の容器・袋の商品」が約66%、「無料のポリ袋」が約56%。
■使い捨てのプラスチック製品のうち、あった方がよいと思うものは「ペットボトル」が5割強、「無料のポリ袋」が4割強、「食品トレイ」「無料レジ袋」が各30%台。レジ袋有料化で不便に感じる・感じない人は、いずれも4割強。
■環境問題に関する3年前と比べた意識・行動の変化は「ゴミの分別やリサイクルの意識が高まった」が3割強、「ゴミを減らす意識が高まった」が約24%。プラスチックごみ削減の国際的な条約・ルールがあった場合に賛同するものは「リサイクルできないプラスチック製品の生産を禁止」「プラスチック製品は、再生プラスチックにすることを義務」がそれぞれ約37%。
-
- 調査時期:
- 2024年07月
- 設問項目:
-
直近1年間に利用した屋内アミューズメント施設/屋内アミューズメント施設に対する関心度/直近1年間屋内アミューズメント施設利用頻度/最も好きな屋内アミューズメント施設のタイプ/最も好きな屋内アミューズメント施設利用時の同行者/最も好きな屋内アミューズメント施設利用理由/屋内アミューズメント施設選定時の重視点/今後利用したい屋内アミューズメント施設/好きな屋内アミューズメント施設の種類・理由等/今後利用したい屋内アミューズメント施設(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■屋内アミューズメント施設(屋内でゲームやスポーツ、カラオケなどができ、大人子ども問わず近場で予約なしでも利用できる施設)の直近1年間での利用は、「カラオケボックス」が全体の約14%、「ゲームセンター」が1割弱、「ボウリング場」が約6%、「複合アミューズメント施設」が約5%、「複合スポーツ・アミューズメント施設」が約3%。これらの屋内アミューズメント施設関心層は約25%、10・20代では6割弱と高い。
■屋内アミューズメント施設直近1年間利用者の利用頻度は「2~3ヶ月に1回」「半年に1回」「年に1回以下」がボリュームゾーン。
■屋内アミューズメント施設直近1年間利用者が、最も好きな屋内アミューズメント施設に行く理由は「気分転換・リフレッシュ」が6割強、「ストレス解消」が4割強、「楽しい気持ちになりたい」「暇つぶし」が各20%台。ボウリング場が好きな人は「気分転換・リフレッシュ」「体を動かしたい」、ゲームセンターが好きな人は「気分転換・リフレッシュ」「暇つぶし」が上位2位。
■屋内アミューズメント施設直近1年間利用者の重視点は「アクセス・立地」「料金が手頃」が各6割半ば~7割弱、「施設や設備がきれい・清潔」「会員特典などお得なサービスの充実度」が各2割強。今後利用したい施設は「カラオケボックス」「ボウリング場」が各20%台、「複合アミューズメント施設」が2割弱、「ゲームセンター」「複合スポーツ・アミューズメント施設」がそれぞれ約13~14%。
-
- 調査時期:
- 2024年07月
- 設問項目:
-
紫外線対策への関心度/紫外線が気になる箇所/紫外線対策有無・季節/紫外線対策の内容/紫外線対策を行うかどうか判断する条件・基準/紫外線対策をする理由/使用している日焼け止めのタイプ/日焼け止めの選択基準/紫外線について困っている・気になること(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■紫外線対策をする人は全体の6割強、男性4割強、女性9割弱。対策を行うのは「夏」が4割強、「春」が約17%、「秋」が1割強。「季節を問わず1年を通して」は全体の2割強、女性の4割強。紫外線が気になる箇所は「顔」が約65%、「腕」「首」「手」「目」などが各3~4割。
■紫外線対策実施者のうち、「日焼け止めを使用」が約64%、「帽子」が6割弱、「日傘」が4割強、「UVカット効果のあるスキンケア商品」「UVカット効果のある基礎化粧品」「なるべく肌を露出しない」が各30%台。「帽子」は高年代層、「サングラス」は男性や高年代層での比率が高い傾向。
■紫外線対策実施者が対策を行う判断基準は、「日差しの強さ」が5割強、「日に当たる時間の長さ」「屋外にいる時間の長さ」「天候」「屋外にいる時間帯」などが各40%台。紫外線対策をしている人の理由は、「しみ、そばかすなどの予防」「肌の老化の予防」が各50%台、「肌を白く保ちたい、日焼けをしたくない」が3割強、「肌が弱い、日焼けによる肌トラブルが出る」が約26%。
■直近1年間の日焼け止め使用者は6割弱、男性約36%、女性約86%。「クリームタイプ」「乳液タイプ」が20%台。塗る・スプレータイプの日焼け止め直近1年間使用者の選定基準は「SPF値、PAの高さ」が約64%、「付け心地のよさ」「価格」「肌への負担の低さ」「のびがよい、ムラにならない」が各30%台。
-
- 調査時期:
- 2024年07月
- 設問項目:
-
自転車利用頻度/自転車保険加入状況/加入自転車保険のタイプ/自転車保険加入のきっかけ/加入自転車保険の種類/自転車保険加入経路/自転車保険非加入理由/自転車保険加入時の重視点/自転車保険への要望(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■自転車利用率は約45%。自転車保険加入率は自転車利用者の6割強、中部や近畿でやや高い。加入者のうち契約者本人対象が約36%、家族型が6割強。保険の種類は「自転車保険※特約以外」「自動車保険・火災保険などの特約」がそれぞれ約34%。自転車保険加入者の加入経路は「インターネット」が約35%。
■自転車保険加入のきっかけは「保険加入が義務化」が加入者の4割強、「事故にあった時の備えとして加入したいと思った」「自動車保険や火災保険、家財保険、共済などの加入・見直し」「自転車を購入した・買い替えた」が各2割弱。TSマーク付帯保険加入者では「自転車を購入・買い替え」「自転車店の店員の勧め、保険会社からの勧め」などが高い。
■自転車保険加入時の重視点は、「保険料が手頃」「補償内容の充実度」が各5割弱、「商品のわかりやすさ」が3割強、「補償金額」「事故時の対応力」「自転車事故時の自分のケガ・後遺症などの補償有無・内容」が各2割前後。
■自転車保険非加入者の非加入理由は「自転車にあまり乗らない」が4割弱、「必要性を感じない」が2割強、「保険料が高い」が16%。
-
- 調査時期:
- 2024年07月
- 設問項目:
-
生命保険会社の認知/主加入生命保険/加入生命保険商品の種類/生命保険申込み方法/1か月あたりの生命保険料/生命保険加入・見直し時に、候補として検討した生命保険会社/生命保険に関する情報入手経路/加入したい生命保険会社/生命保険の加入・見直し意向/主加入生命保険の加入理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■生命保険加入者は全体の8割弱。生命保険加入者の申込み方法は「知り合いや紹介を受けた営業職員、保険外交員」が3割強、「自宅や勤務先に訪問してくる営業職員、保険外交員」が2割強。「インターネットで申込み手続き」は楽天生命主加入者で比率が高い。
■生命保険加入者のうち、加入時に他社を候補として検討した人は、生命保険加入者の4割弱。比較した会社では「県民共済」「アフラック」「かんぽ生命」「こくみん共済coop」が各3~4%で上位。
■生保関連の情報入手経路は「テレビ番組、CM」が3割強、「家族や友人、知人」「営業職員、保険外交員」がそれぞれ約15%、「保険商品のパンフレット、説明資料」「保険を取り扱っている企業のホームページ」などが各1割強。
■生命保険の加入・見直し意向は、「現在加入の生命保険を継続」が4割弱、「現在加入の生命保険に追加して加入」が4%。「現在加入しておらず、生命保険には当面加入しない」が1割強、「わからない」が4割弱。加入したい生命保険会社は、「県民共済」が約9%、「アフラック」が約6%。
-
- 調査時期:
- 2024年07月
- 設問項目:
-
利用している飲用水/家庭用ウォーターサーバーの利用実態/ウォーターサーバーを利用し始めたきっかけ/ウォーターサーバー非利用理由/ウォーターサーバーの利用中止理由/主利用家庭用ウォーターサーバーのタイプ/主利用家庭用ウォーターサーバー/主利用ウォーターサーバーの満足度/ウォーターサーバー利用意向/主利用ウォーターサーバーの選定理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■家庭用ウォーターサーバー利用経験者は全体の約14%、現在利用者は約5%。現在利用者ののうち、「宅配型:ワンウェイ方式のボトル・パック」利用者は4割弱、「宅配型:リターナブル方式のボトル」は2割強、「水道水補充型」は約16%。利用中止者(利用したことがあるが現在は利用していない)では「宅配型:リターナブル方式のボトル」が4割強で最も多い。
■利用のきっかけは、利用者・利用経験者全体では「無料お試し期間」「店頭、街頭などでのキャンペーンやデモ」が各20%台。現在利用者では「店頭、街頭などでのキャンペーンやデモ」が1位。利用中止者では「無料お試し期間があった」の比率が高い。
■非利用理由、利用中止理由とも「維持費がかかる」「設置スペースをとられる」が上位2位。水道水やミネラルウォーターなどで十分/満足なども上位にあがっている。
■家庭用ウォーターサーバー利用意向者は全体の約9%、非利用意向者は約76%。利用意向者の比率は、現在利用者の8割強、利用未経験者の約4%。水道水補充型主利用経験者では利用意向者の比率が他の層より高い。
-
- 調査時期:
- 2024年07月
- 設問項目:
-
ご飯を食べる頻度/おかずの品数/ご飯のおともとして食べるもの/最も好きなご飯のおとも/ご飯のおともを食べる場面/市販のご飯のおともの購入場所/市販のご飯のおとも購入時の重視点/ご飯のおとものこだわり・おすすめ(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■毎日ご飯を食べる人は全体の7割強。自宅でご飯を食べる人のおかずの品数は、「3品」が4割強でボリュームゾーン。4品以上の比率は3割弱。
■自宅でご飯を食べる人のうち、「納豆」をご飯と一緒に食べる人は6割強、「ふりかけ」「焼き海苔・味付け海苔」「明太子、たらこ」「キムチ」が各30%台。最も好きなご飯のおとも上位2位は「納豆」「明太子、たらこ」。「納豆」は北海道、東北、関東など、「とろろ芋」「いくら、すじこ」などは北海道、東北で高いなど地域差がみられる。
■ご飯のおともを食べる人のうち、「夕食」で食べる人が6割強、「朝食」が4割弱、「昼食」「おかずが少ないとき」が各20%台。東北では「朝食」が他の層より高く「夕食」が低い。
■市販のご飯のおともを食べる人の重視点は「味」が約74%、「価格」5割強、「容量、サイズ」「賞味期限・消費期限」「原材料」などが各20%台。ご飯のおともを食べる人の購入場所は「スーパー」が約85%、「ドラッグストア」が1割強。
-
- 調査時期:
- 2024年07月
- 設問項目:
-
料理をする頻度/直近1年間に利用した料理の素のジャンル/利用する料理の素のタイプ/料理の素の利用頻度/料理の素を利用する理由/料理の素を購入する場面/料理の素購入時の重視点/料理の素利用意向/気に入っている料理の素/利用しない理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■料理の素直近1年間利用者は、料理をする人の7割強、男性約66%、女性8割弱。利用意向者の比率は、直近1年間の料理の素利用者の9割弱、非利用者の2割弱。
■料理の素利用者のうち週1回以上利用者は約25%、月数回以上利用者は6割強。料理の素の利用理由は「おいしい」「失敗がない」が各40%台、「調理に時間がかからない」「素を使ったほうが上手にできる」「面倒な工程がない」が各30%台。
■料理の利用者の購入場面は「食べたいメニューがあるとき」「料理を手早く済ませたいとき」「あらかじめ買うと決めているとき」などが各3割強。料理の素利用頻度が高い層では「あらかじめ買うと決めているとき」「家にある材料を活用したいとき」が上位2位。
■料理の素購入時の重視点は「味」が8割強、「価格」が5割強、「手順の簡単さ」が4割強、「容量、サイズ」「保存がきく」「少ない材料で作れる」などが各2割強。
-
- 調査時期:
- 2024年07月
- 設問項目:
-
夏にアイスクリーム類を食べる頻度/冬にアイスクリーム類を食べる頻度/アイスクリーム類・氷菓の食べ方等の、季節による違い/アイスクリーム類を食べる場面/アイスクリーム類の購入場所/市販のアイスクリーム類購入時の重視点/直近1年間に購入した市販の健康・美容系アイスクリーム/好きな市販のアイスクリーム類・氷菓/市販のアイスクリームで好きなもの(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■夏にアイスクリーム類を週1回以上食べる人は6割弱。冬に週1回以上食べる人は2割強。アイスクリーム類を「主に暑い季節に食べる」は4割強、「季節を問わず、一年を通して食べる」は3割弱。
■アイスクリームを食べる人のうち、「間食・おやつ」に食べる人が約45%、「暑いとき」「くつろいでいるとき」が各20%台、「お風呂あがり」「甘いものが欲しいとき」などが各2割弱。食べる頻度が高い層では「お風呂あがり」の比率がやや高い傾向。
■アイスクリーム類を食べる人の購入場所は「スーパー」が約85%、「コンビニエンスストア:市販のアイス」が4割強。「ドラッグストア」は2割強で過去調査と比べ増加傾向。アイスクリーム類購入者の重視点は「味」8割強、「価格」6割弱、「食感」3割、「食べ慣れている」「食べやすさ」「甘すぎない」「内容量」「濃厚」などが各2割前後。
■アイスクリーム類購入者が直近1年間に購入した健康・美容系アイスクリームは「低糖質、糖質オフ」「低カロリー」が各1割強、「高カカオチョコレートを使用」が約6%。市販のアイスクリームを食べる人が好きな銘柄は1位「ハーゲンダッツ」5割強、2位「チョコモナカジャンボ」4割弱。
-
- 調査時期:
- 2024年07月
- 設問項目:
-
コーヒーの飲用頻度/飲んでいるコーヒーのタイプ/最もよく飲むコーヒーのタイプ/好きなコーヒーの飲み方/コーヒーを飲む場所/コーヒーを飲む場面/コーヒーに期待する効果/コーヒーの楽しみ方(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■コーヒーを毎日飲む人は全体の7割強、高年代層での比率が高い傾向。「1日に2~3回」飲む人が4割弱。コーヒー飲用者のうち「インスタントコーヒー」が5割強、「レギュラーコーヒー」が4割強。「ペットボトル入りコーヒー」は3割強で過去調査と比べ増加傾向。「レギュラーコーヒー」「缶コーヒー」などは過去調査より減少傾向。
■好きなコーヒーの飲み方は「ホット/ブラック」が飲用者の5割強。カフェ・オレ、カフェ・ラッテは、女性や若年層での比率が高い傾向。ブラックは、ホットは男性や高年代層、アイスは男性や若年層での比率が高い傾向。
■コーヒー飲用者のうち「自宅」で飲む人は9割弱、「職場」が3割強、「コーヒーチェーン店」「喫茶店 ・カフェ」「車の中」などが各2割前後。コンビニコーヒー主飲用者では「車の中」が5割弱で、他の層より高い。
■コーヒーを飲む場面は「朝食時」「おやつの時」が各40%台。「休憩中・休み時間」「仕事・勉強・家事をしながら」「リラックスしたいとき」が各3割前後。コーヒー飲用者が期待する効果は「気分転換」「リラックス効果」が各5割強、「眠気を覚ます」が3割強、「集中力を高める」が2割弱。
-
- 調査時期:
- 2024年07月
- 設問項目:
-
豆乳の嗜好度/直近1年間での豆乳の摂取方法/豆乳摂取理由/豆乳に期待する効果/豆乳購入時の重視点/豆乳飲用頻度/豆乳飲用場面/豆乳飲用意向/豆乳の飲用・利用状況/豆乳非飲用・非利用理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■豆乳が好きな人は全体の約36%、女性若年層で高い。直近1年間豆乳・豆乳飲料摂取者(飲用や食品での摂取)は全体の5割強。「市販の豆乳をそのまま飲む」は全体の3割強。
■直近1年間豆乳摂取者の摂取理由は「健康に良い」が5割弱、「栄養価が高い」が4割強、「おいしい」「大豆イソフラボン摂取」「牛乳の代わり」が各30%台。期待する効果は「コレステロールの低減」「高血圧や高脂血症、動脈硬化などの予防」がそれぞれ約27%、「便秘を防ぐ・便通をよくする」「美肌」「カルシウムの摂取」などが各2割弱。
■直近1年間豆乳摂取者の購入時の重視点は「味」が6割弱、「価格」「飲みやすさ」が各30%台、「調製、無調整」「成分、添加物」「原材料」が各20%台。
■直近1年間豆乳飲用者(全体の約45%)のうち、週1~2回以上飲用者は4割強。飲用場面は「朝食時」が4割弱、「おやつの時」が約26%、「昼食時」が1割強。豆乳飲用意向者は全体の4割強、男性3割強、女性5割。豆乳・豆乳飲料飲用者では8割弱、非飲用者では約6%。非飲用者では非飲用意向が6割強を占める。
-
- 調査時期:
- 2024年07月
- 設問項目:
-
炭酸飲料の飲用頻度/炭酸飲料の飲用場面/炭酸飲料選定時の重視点/直近1年以内に飲んだ炭酸飲料/直近1年以内に最もよく飲んだ炭酸飲料/炭酸飲料購入場所/今後飲みたい炭酸入り飲料の種類/直近1年間最頻飲用炭酸飲料の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■炭酸飲料飲用者は全体の約74%、過去調査と比べ減少傾向。週1回以上飲用者は3割弱。男性10~30代の炭酸飲料飲用者のうち、週1回以上飲用者は各5割強~6割強で、飲用頻度が高い。
■炭酸飲料飲用者が飲む場面は「のどが渇いたとき」が4割強、「休憩中・休み時間」「スカッとしたい」が各3割強。「食事と一緒に」「食後」「おやつ」などは若年層での比率が高い傾向。飲用頻度が高い層では「お風呂あがり」「食事と一緒に」「食後」などの比率が高い。
■炭酸飲料飲用者の選定時の重視点は「味、飲み口」「価格」が各5~6割、「商品ブランド」が約35%、「飲み慣れている」「メーカー名」がそれぞれ約25%。購入場所は「スーパー」が7割強、「コンビニエンスストア」が3割強。「ドラッグストア」は2割強で、過去調査と比べ増加傾向。
■炭酸入り飲料の飲用意向は「炭酸飲料」が5割強、「炭酸水」が約26%。「炭酸飲料」は男性や若年層で高く、男性10~50代では各60%台。
-
- 調査時期:
- 2024年06月
- 設問項目:
-
今年のゴールデンウィークの休日数/今年のゴールデンウィークの連休日数/今年のゴールデンウィークに出かけた行楽・レジャー・帰省など/今年のゴールデンウィークに出かけた行楽・レジャーの予定をたてた時期/ゴールデンウィークの行楽・レジャーに使ったお金/今年のゴールデンウィークの自宅での過ごし方/ゴールデンウィークの休みの外出・在宅の割合/ゴールデンウィークの過ごし方/今年のゴールデンウィークの満足したこと・不満だったこと(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■今年のゴールデンウィーク休日数は「12日以上」が約17%、「7日」が約15%、「5日」が約10%。2日以上休みがあった人のうち12日以上連休した人が2割弱、4日が約25%。
■ゴールデンウィークに出かけた人は全体の5割弱。「ショッピング」「グルメスポット、外食」にでかけた人がそれぞれ約13~15%、「ドライブ」が約9%、「自然名所(山・湖・高原など)」「公園」「帰省」がそれぞれ約7%。
■ゴールデンウィークの自宅での過ごし方は「テレビ」が6割弱、「インターネットの閲覧・検索、SNS・アプリの利用など」が約50%、「録画していたテレビ番組」「動画共有サイト(YouTubeなど)などを見る」「部屋の片付け・掃除」などが各3~4割。ゴールデンウィークに休みがあった人のうち、家で過ごすことが多かった人は約74%。
■ゴールデンウィークに休みがあった人の過ごし方は、「のんびりすごした」が5割弱、「「心身を休めるために使った」「普段の休みの日と変わらない」がそれぞれ約24~25%、「家族とのコミュニケーションを楽しんだ」「自分の好きなことをして、リフレッシュした」が各1割強。
-
- 調査時期:
- 2024年06月
- 設問項目:
-
免疫力向上についての意識度/5年前と比べた免疫力の向上・低下/免疫力低下時の症状として直近1年間に気になるもの/免疫力向上のために行っていること/免疫力を向上したい理由・きっかけ/免疫力向上のために食事・飲食物で気を付けていること/免疫力向上のために摂取している飲食物/免疫力維持・サポート等を目的とした健康食品・サプリメント・機能性表示食品の直近1年間利用状況/免疫力の維持・向上のための利用商品・サービスや意識していること(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■免疫力の向上について意識している人は5割強で女性や高年代層で高い。5年前と比べて免疫力が向上したと感じる人は約9%、低下したと感じる人は約34%、「変わらない」は6割弱。免疫力低下に関して直近1年間に気になる症状は「疲れやすい、だるい」が3割強、「風邪や病気の治りが悪い」「肌が荒れる・かゆみ・湿疹など」「ケガの治りが悪い」などがそれぞれ約14~16%。
■免疫力向上のために行っていることは「バランスのよい食生活」が4割強、「腸内環境を整える」「手洗い・うがいをする」が各3割強、「適度な運動」「なるべく動いたり歩いたりする」が各3割弱。免疫力維持・サポート等を目的とした健康食品・サプリメント・機能性表示食品の直近1年間利用者は2割強。
■免疫力を向上したいと思った理由・きっかけは「健康維持・向上のため」が5割強、「風邪やインフルエンザの予防」「新型コロナウイルスの予防」「病気の予防や早期回復」が各20%台。免疫力向上のために食事・飲食物で気を付けていることは「栄養バランス」「一日三食食べる」が各4割前後、「発酵食品を摂取」「乳酸菌を摂取する」「食物繊維を摂取」がそれぞれ約27~29%。
■免疫力向上のために摂取している飲食物は「野菜」「ヨーグルト、飲むヨーグルト」「納豆」が各30%台、「きのこ類」「魚介類」「海藻類」「味噌」「豆類、ナッツ類」「卵」が各20%台。飲み物では「牛乳」「コーヒー」「緑茶」などが各2割弱。
-
- 調査時期:
- 2024年06月
- 設問項目:
-
美容に対する関心度/美容のために意識していること/美容のために食生活で意識していること/美容について意識して行う理由/美容のために使っているアイテム/美容にかける費用(1ヶ月あたり)/直近1年間に利用したことがある美容関連サービス/美容に関して気になること/美容のために気を付けていること・こだわり(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■美容関心層は全体の約36%、男性2割弱、女性6割弱。男性10~30代では約36%と高い。美容のために意識していることは「ウォーキングなど軽い運動」「食生活」「スキンケア・肌の手入れ(顔)」「水分補給」などが各3割前後。食生活を意識する人のうち「栄養バランス」「野菜を多くとる」を意識する人が各7割前後、「食べ過ぎない」が5割強、「寝る直前に食べない」「たんぱく質を意識してとる」「三食きちんと食べる」などが各4割弱。
■美容のために意識して行っている人の理由は「身だしなみを整える、清潔感」が54%、「若々しく見られたい」「よい印象を与えたい」「若さを維持するため」が各20%台。「よい印象を与えたい」は10~30代の若年層での比率が高い傾向。女性10~30代では「身だしなみを整える、清潔感」「自分に自信をつけたい」が上位2位。
■美容に関して気になることは「顔のくすみ、しみ、そばかす、毛穴など」「顔のしわ、たるみ、筋肉のゆるみなど」が各3割強、「体重」「肌の乾燥」「体型、スタイル」が各2割強。「肌の乾燥」「顔の肌荒れ・肌のトラブル」「ヒゲや鼻毛、うぶ毛」「体のムダ毛」などは若年層、「顔のしわ、たるみ、筋肉のゆるみなど」は高年代層での比率が高い傾向。
■美容のために使うアイテムのうち「スキンケア用品」「洗顔料」は女性では各70%台、男性10~30代では各3~4割で上位2位の項目。美容関連サービスの直近1年間利用経験は「美容室・ヘアサロン」が女性の8割弱。「理容院」が男性の4割弱で男性高年代層での比率が高い傾向。
-
- 調査時期:
- 2024年06月
- 設問項目:
-
スポーツクラブ会員登録・利用登録状況/スポーツクラブ会員登録・利用登録理由/主利用スポーツクラブ/スポーツクラブ利用頻度/スポーツクラブ関連の1ヶ月あたり支払い額/民間スポーツクラブ非利用理由・スポーツクラブ非利用理由/民間スポーツクラブの利用意向/民間スポーツクラブ選定時の重視点/民間スポーツクラブの利用意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■スポーツクラブ会員登録経験者は全体の3割強。会員登録経験者のうち、現在利用者は4割弱(回答者全体の1割強)。現在利用者のうち週1回以上利用者は8割強、週2~3回以上利用者は6割弱。
■スポーツクラブ・ジムの会員登録経験者の登録理由は「健康維持」が7割弱、「体力維持・向上」「運動不足解消」が各5割弱、「ダイエット、体型を整える」「筋トレ、筋力維持・向上」がそれぞれ約35%、「気分転換、ストレス解消」「体質改善、症状緩和・改善」が各20%台。
■民間スポーツクラブの利用意向者は全体の2割強。スポーツクラブ(公共施設含む)現在利用者の利用意向率は7割強、退会者の約25%、未経験者の約9%。利用意向者のスポークラブ重視点は「アクセスのよさ」「入会費・月会費が手頃、割安」が各7割強、「設備が充実」「施設が清潔」「気軽に行ける」が各4割強、「一人で利用しやすい」「混んでいない」が各30%台。
■スポーツクラブ利用経験者のうち、民間のスポーツクラブ非利用者(公共施設主利用者、退会者)の理由は「会費が高い」が約35%、「通うのが面倒」「通う時間がない」「月に通える回数が限られ割高」などが各2割前後。
-
- 調査時期:
- 2024年06月
- 設問項目:
-
髪の長さ/髪や頭皮の悩み・気にしていること/シャンプーでの洗髪頻度/シャンプー購入時の重視点/シャンプーに期待する効果/シャンプーの銘柄を変えるタイミング/シャンプー購入時の選定基準/シャンプー選定時の重視点・気にすること・こだわり(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■髪や頭皮の悩み・気にしていることは、全体では「白髪」「髪の量」「髪のハリ、コシ、ツヤ」「抜け毛、脱毛」などが上位。「髪の毛の痛み・ダメージ」「髪質」は女性若年層、「白髪」「髪のハリ、コシ、ツヤ」などは女性50~70代で高い。
■シャンプーで洗髪する頻度は「ほとんど毎日・1日2回以上」が1割弱、「ほとんど毎日・1日1回」が5割強、毎日洗髪する人が6割強。
■シャンプー使用者の重視点は「髪質に合う」「価格」が各4割弱、「メーカー・ブランド」が3割弱、「洗浄力」「香り」などが各2割弱。「髪質に合うこと」「髪のまとまり感」などは女性での比率が高い。期待する効果は「汚れを落とす」が5割強、「頭皮や地肌ケア」「髪や頭皮のにおいを防ぐ」「髪のダメージのケア」などが各20%台。
■シャンプー使用者が銘柄を変えるタイミングは「使っていたシャンプーを使い切った」「使っていた銘柄が手に入らない・販売終了した」が各2割前後、「魅力的な商品があった・発売された」が約14%。シャンプー使用者のうち「だいたい決まった商品を買うことが多い」は6割強で女性高年代層で高い。「決まった銘柄はなく、効果や種類で選ぶことが多い」は1割強。
-
- 調査時期:
- 2024年06月
- 設問項目:
-
自宅の洗濯機のタイプ/主利用洗濯機のメーカー/主利用洗濯機メーカーの満足度/洗濯機の容量/洗濯機の使用頻度/洗濯をする時間帯/洗濯機購入・買い替え予定時期/洗濯機購入時に重視する機能・製品特長/主利用洗濯機メーカーの選定理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■自宅の洗濯機のタイプは「ドラム式洗濯乾燥機」が16%、「縦型洗濯乾燥機」が約24%、「全自動洗濯機」が約55%。パナソニック主利用者での満足度が他の層より高い。「7kg台」「8kg台」がボリュームゾーンで、過去調査と比べ「10kg台以上」が増加傾向。
■洗濯機所有者が自分で使う頻度は「ほぼ毎日」が4割弱。女性40~50代で各50%台、男性40~70代で各30%台。「自分では使わない」は2017年調査以降微減傾向。
■洗濯をする時間帯は「8時台~11時台(午前中)」が洗濯機使用者の5割弱。「19時台~22時台(夜)」は若年層、「8時台~11時台(午前中)」は高年代層での比率が高い傾向。
■洗濯機購入・買い替え予定者(4割強)が、洗濯機購入時に重視する点は「省エネ」が6割強、「大きさ・容量」「洗浄力」がそれぞれ約54~55%、「使い勝手(フタの開閉、ボタン操作等)」「運転音の静かさ」が各4割強。
-
- 調査時期:
- 2024年06月
- 設問項目:
-
契約している電力会社/電力会社変更状況/新電力会社選定理由/電力会社を変更しない理由/電力会社の契約意向/契約しているガス会社/ガス会社変更状況/新規参入ガス会社選定理由/ガス会社の契約意向/電力会社契約意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■新電力会社利用者は3割弱。関東では4割弱、近畿では3割強。電力自由化後、「大手電力会社から、新電力社へ変更」が3割弱。契約会社での料金プラン変更者は約5%。
■新電力会社利用経験者の会社選定理由は「いままでより安くなる、安い料金プラン」が6割弱、「電気料金を節約できる」が約34%、「ポイント還元率やキャッシュバック、割引特典、節電によるポイント付与などがお得」「他の商品・サービスとのセット割」が各20%台。電力会社を変更していない人(全体の6割強)の理由は「利用会社に特に不満がない」が約46%、「現在の契約会社の方が安心」が3割弱、「メリットが感じられない」「料金がさほど安くならない」などが各2割前後。
■新規参入の電気小売事業者契約意向者は約15%、大手電力会社契約意向者は全体の約45%。現在大手電力会社利用者のうち、新規参入事業者契約意向者は約3%。新電力会社利用者のうち新規参入事業者との契約意向は4割強、「どちらともいえない」が5割弱。
■新規参入の都市ガス会社契約者は6%、従来の都市ガス会社は5割強。ガス自由化後の会社変更者はガス使用者の1割強。新規参入ガス会社選定理由は「いままでより安くなる、安い料金プラン」が利用者の約55%、「ガス料金を節約できる」が約35%、「ポイント還元率やキャッシュバック、割引特典などがお得」「他の商品・サービスとのセット割」が各20%台。新規参入都市ガス契約意向者は全体の約6%、新規参入都市ガス利用者の6割強。
-
- 調査時期:
- 2024年06月
- 設問項目:
-
食の安全に対する不安/食の安全に関して不安を感じている事柄/食の安全に関する不安を感じている食品・飲料/食品の品質表示等への信頼度/食品購入時に品質表示やパッケージの説明書きで注意して見ること/飲食店での外食時の食の安全性への不安/直近2~3年での、食の安全の意識・行動/食の安全に関して気をつけていること・工夫(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■食の安全に対して不安を感じている人は全体の5割強。2015年調査以降減少していたが2021年調査と比べて微増。不安を感じる上位3位は「添加物」が約64%、「輸入食品の安全性」「残留農薬」が各5割前後。2021年調査と比べ、「異物・毒物の混入」が増加、「残留農薬」は減少。飲食店での外食に不安を感じる人は4割強。
■食の安全性に不安を感じている人が、不安に感じる食品・飲料の上位は「肉の加工品」が6割弱、「魚介類」「精肉類」が約45~46%、「水産加工品」「野菜」などが各4割弱。
■食品の品質表示等について信頼している人は約84%。品質表示等で注意して見ることは「期限表示」「原産国、生産地」が各6~7割、「原材料」「製造年月日」が各40%台、「値段」「食品添加物の有無」が各30%台。
■ここ2~3年の食の安全性に関する意識・行動は「賞味期限・消費期限を気にする」が5割強、「原産地を気にする」が4割強、「国内産の食品を買うようにしている」が約35%、「食品添加物を気にする」「食品表示やパッケージの説明をよく読む」が各3割弱。
-
- 調査時期:
- 2024年06月
- 設問項目:
-
間食の頻度/間食をとる時間帯/間食をとる場面/間食でよく食べるもの/間食でよく飲むもの/間食で飲食するものを購入する時の重視点/間食をとる理由/間食の分量・頻度の多さ/間食をとる時に気を付けていること/間食をとらない理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■間食をとる人は全体の7割、男性の6割強、女性の8割強。1日1回以上食べる人は全体の3割強、間食をとる人の5割弱。間食をとる人のうち「昼食から夕方の間」が7割弱、「夕食後」が3割強。間食をとる人のうち、分量・頻度が多い方だと思う人は約45%、ちょうどよいと思う人は約43%。
■間食をとる人のうち「くつろぎながら」「おやつの時間」に間食をとる人が各4割強、「仕事・勉強・家事の合間」が3割、「テレビやDVD・BD、動画配信サービスなどを見ながら」が約24%。間食をとる理由は「お菓子など甘いものが好き」が5割弱、「なんとなく口さびしい」「おなかがすく」が各4割前後、「気分転換」「リラックスしたい」が各3割弱。
■間食をとる人のうち「チョコレート、チョコレート菓子」を食べる人が約55%、「スナック菓子」「せんべい・あられなどの米菓」「クッキー、ビスケット」が各5割弱、「アイスクリーム類」「ケーキ類、シュークリーム、ドーナツ、マドレーヌ等」「和菓子」などが各30%台。よく飲むものは「コーヒー、コーヒー飲料、カフェオレなど」7割弱、「お茶、お茶系飲料」6割弱、「紅茶、紅茶飲料」が約26%。
■間食をとる人の、購入時の重視点は「価格」が4割強、「すぐ飲食できる、手間がかからない」「買い置き・ストックしておける」「食べきりサイズ」などが各20%台、「甘い」「分けて食べられる容器・包装」がそれぞれ約19%。
-
- 調査時期:
- 2024年06月
- 設問項目:
-
果物の嗜好度/好きな果物/果物の摂取方法/果物摂取理由/果物摂取頻度/生鮮果物摂取場面/生鮮果物購入時の重視点/好きな果物の理由、こだわりなど(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■果物が好きな人は全体の9割弱。好きな果物上位は「いちご」「もも」「梨」「ぶどう、マスカット」「みかん」「りんご」などが各6~7割。ほぼ毎日食べる人は、果物摂取者の3割弱、週1回以上は約75%。「ほぼ毎日・1日1回」「週2~3回」がボリュームゾーン。
■果物の食べ方は「生鮮果物をそのまま」が全体の約94%、「生鮮果物を何かにのせる・まぜる」が3割弱。摂取場面は「間食、おやつ」が摂取者の5割弱、「夕食後」「朝食のメニューとして」が各4割弱。過去調査と比べ「間食、おやつ」が増加傾向。
■果物摂取理由は「おいしい」が9割弱、「好き」が約56%、「健康によい」「ビタミン」が各4割弱、「甘い」「手軽」がそれぞれ約25%。
■果物購入時の重視点は「価格」が7割弱、「鮮度」が4割強、「季節感・旬のもの」「産地」などが各4割弱。
-
- 調査時期:
- 2024年06月
- 設問項目:
-
自宅でのお酒飲用頻度/自宅での飲酒時おつまみを食べるかどうか/自宅での飲酒時によく食べるおつまみ/自宅でおつまみを食べながら飲むお酒の種類/自宅で飲酒時のおつまみ準備方法/自宅での飲酒時に食べる市販のおつまみ選定時の重視点/自宅での飲酒時に食べる市販のおつまみ購入場所/自宅での飲酒時に食べるおつまみで気に入っているもの・食べるシチュエーション(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■自宅でお酒を飲む人は7割弱、男性7割強、女性6割弱。「ほぼ毎日」は2割強、週1回以上が半数弱。自宅での飲酒者のうち、おつまみを食べる人は9割弱。「必ず食べる」は7割弱で、高年代層での比率が高い。
■自宅でおつまみを食べる人のうち「食事のおかずをおつまみとして食べる」は7割強、「市販のスナック、菓子、乾きものなど」は5割弱、「出来合いのおかず・惣菜」は3割強、「おかずを作る・用意する」は2割強。自宅でおつまみを食べる人では「チーズ」「スナック菓子」「刺身、たたき」が各40%台、「ナッツ類」「揚げ物」「枝豆」「ギョウザ、シューマイ」「食肉加工品」などが各4割弱。
■自宅でおつまみを食べる人のうち「ビール」を飲む人が7割弱、「チューハイ、サワー」「発泡酒、新ジャンルビール」が各4割前後、「ワイン」「日本酒」「焼酎・泡盛」が各3割前後。女性20~40代では「チューハイ、サワー」が1位。
■自宅での飲酒時のおつまみ購入時の重視点は「味」7割強、「価格」4割強、「すぐ食べられる」3割弱。購入場所は「スーパー」が購入者の9割強、「コンビニエンスストア」3割強、「ドラッグストア」2割強。
-
- 調査時期:
- 2024年06月
- 設問項目:
-
焼酎飲用頻度/焼酎を飲む場所/直近1年間に飲んだ焼酎の種類/最も好きな焼酎の飲み方/焼酎を選ぶ際の重視点/焼酎を飲みたいシーン/焼酎をあまり飲まない理由/焼酎飲用意向/焼酎を飲みたいシーン・飲み方など/焼酎を飲みたいと思わない理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■焼酎飲用者は4割強で過去調査より減少傾向。週1~2日以上飲用者は全体の2割弱、男性高年代層での比率が高い傾向。家で飲む人は焼酎飲用者の7割弱で、2022年調査より減少。アルコール飲用者のうち、焼酎飲用意向率は約46%、週1~2日以上飲用者では9割強、非飲用者では約4%
■最も好きな焼酎の飲み方は「水割り」「お湯割り」「ロック」「柑橘類味+炭酸水割り」が、飲用者の各2割前後。焼酎を飲みたいシーンは「平日」「休日の前日」「休日の夜」「普段の食事のとき」などが各3割弱。
■焼酎を選ぶ際の重視点は「味・おいしさ」が飲用者の約66%、「飲みやすさ」4割強、「価格」3割強、「主原料」「香り」「アルコール度数」が各20%台。
■焼酎非飲用者・月1日以下飲用者があまり飲まない理由は、「味が好きではない」が3割弱、「焼酎を飲む機会がない」「アルコール度数が高い」「匂いが好きではない」などが各10%台。