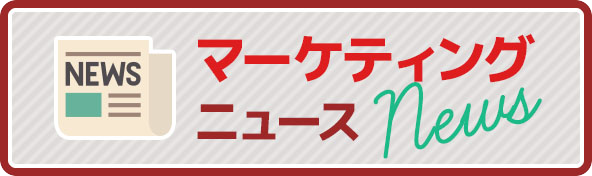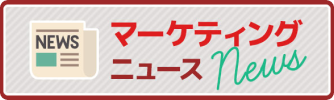- 検索
-
- テーマ別実施時期一覧
- カテゴリー別一覧
-
-
アルコール飲料・嗜好品146
-
非アルコール飲料209
-
その他19
-
-
住宅・住宅設備218
-
-
家電126
-
パソコン・カメラ・AV機器113
-
その他10
-
-
家庭用品・トイレタリー91
-
自動車・関連用品76
-
-
インターネット・情報通信327
-
携帯電話・スマートフォン180
-
メディア・広告66
-
その他7
-
-
ファッション69
-
交通・レジャー・娯楽161
-
季節行事・イベント241
-
時事・ニュース・トレンド51
-
企業ブランドイメージ249
-
広告・CM51
-
WEBサイトの利用91
-
顧客満足度100
- 実施時期別一覧
-
- 調査時期:
- 2025年12月
- 設問項目:
-
ワイン飲用頻度/よく飲むワインの種類/直近1年間でのワイン飲用場所/直近1年間でのワイン飲用場面/直近1年間のワイン購入場所/よく購入するワインの容量(直近1年間)/購入するワイン1本あたりの金額(直近1年間)/ワイン購入時の重視点/ワインを飲む気分・タイミングなど(自由回答設問)
- 結果概要:
-
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
ワイン飲用者は5割強。ワイン飲用者の飲用場面は「親しい友人や家族と一緒」の他、「ひとりでゆったり」「季節行事」「普段の食事」などが上位。
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
■ワイン飲用者は全体の5割強、過去調査と比べやや減少傾向。若年層での比率が低く、高年代層との差が大きい。飲用頻度は「年に数回」がボリュームゾーン、週1回以上飲用者はワイン飲用者の2割弱。ワイン飲用者がよく飲む種類は「赤ワイン」8割弱、「白ワイン」6割弱。「スパークリングワイン」は3割強で、過去調査と比べ増加傾向。
■ワイン飲用者の直近1年間飲用場面は「親しい友人や家族と一緒」5割弱、「ひとりでゆったりとした気分で」「季節行事の時」「普段の食事」「料理に合わせて」が各20%台。ワイン飲用者のうち直近1年間に「自宅で飲むことの方が多い」は7割弱、「外食で飲むことの方が多い」は2割強。2021年調査以降「自宅で飲む」が多い人は減少しコロナ禍前の水準となっている。
■ワイン飲用者の直近1年間購入場所は「スーパーマーケット」6割弱、「ディスカウントストア」2割強。飲用頻度がほぼ毎日・週に3~4日と高い層では「ネット通販」の比率が高い。ワイン飲用者がよく購入するサイズは「フルボトル」8割弱、「ハーフボトル」2割。
■ワイン飲用・購入者の重視点は「種類」「味」各6割台前半、「価格」約56%、「生産地」約36%、「銘柄」約25%。飲用・購入者の購入ワイン1本あたり平均金額は「500円~1000円未満」「1000円~1500円未満」がボリュームゾーン。
-
- 調査時期:
- 2025年12月
- 設問項目:
-
好きなスープ・汁物/スープ・汁物摂取の積極度/スープ・汁物を食べる頻度/スープ・汁物を食べる場面/スープ・汁物を食べる理由/直近1年間に食べたスープ・汁物のタイプ/直近1年間に食べた市販のスープ・汁物の種類/市販のスープ・汁物購入時の重視点/市販のスープ・汁物で好きな商品・よく食べる良品と理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
好きなスープは味噌汁が8割強、豚汁7割強、コーンスープ、クリームシチュー、ビーフシチューが続く。
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
■好きなスープ・汁物は「味噌汁」8割強、「豚汁、けんちん汁」7割強、「コーンスープ(洋風)」6割弱、「クリームシチュー」「ビーフシチュー」「たまごスープ」「ポタージュ」などが各5割前後。スープ・汁物を毎日1回以上食べる人は全体の4割弱、2021年調査以降減少傾向。
■スープ・汁物飲食者の飲食場面は「夕食」8割弱、「朝食」「昼食」各30%台。食べる理由は「スープ・汁物が好き」5割、「体が温まる」4割弱、「野菜をたくさん食べられる」3割強、「習慣になっている」「いろいろな食材を一度に摂取できる」が各2割台半ば。
■スープ・汁物飲食者のうち、市販のスープ・汁物を食べる人は7割強で、「インスタントの袋入り」が6割弱、「インスタントのカップ入り」が3割強。市販品を直近1年間に食べた人では食べた市販の商品は、「味噌汁」8割強、「コーンスープ(洋風)」5割弱、「お吸い物」「わかめスープ」「たまごスープ」「豚汁、けんちん汁」が各30%台。
■市販のスープ直近1年間飲食者の購入時の重視点は「味」8割弱、「価格」5割強、「具だくさんである」3割強、「野菜が多い」「一緒に食べる食品との相性」「粉末、フリーズドライ、生タイプなど」が各2割強。
-
- 調査時期:
- 2025年12月
- 設問項目:
-
直近1年間に食べた海藻類/海藻類の嗜好度/海藻類の意識的摂取度合い/直近1年間に食べた海藻類の加工品/海藻類の食べ方・用途/海藻類・海藻類加工品の直近1年間摂取頻度/海藻類に期待する効果・効能/海藻類・海藻類加工品購入時の重視点/よく食べる海藻類/海藻類を食べない理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
海藻を意識的に食べている人は半数弱で、女性や高年代層ほど高い傾向。期待する効果は「健康維持」の他、「栄養の摂取」「生活習慣病予防」が上位。
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
■海藻類や海藻類の料理が好きな人(TOP2)は8割強、「好き」は5割弱。海藻類を週2~3回以上食べる人は6割弱で、高年代層での頻度が高い傾向。普段の食生活で海藻類を意識的に食べている人は半数弱、女性や高年代層で高く、年代差が大きい。
■直近1年間に食べた海藻類は「海苔」約85%、「わかめ」約76%、「昆布、とろろ昆布、切り昆布、塩昆布など」約66%、「ひじき」6割弱、「もずく」5割弱。海藻類直近1年間摂取者が食べた市販の加工品は「焼き海苔、味付け海苔、韓国海苔」7割強、「塩昆布」「とろろ昆布、おぼろ昆布」「もずく加工品」「わかめ加工品」各4割強。
■海藻類直近1年間摂取者の、海藻類や加工品の食べ方・用途は「ご飯やおにぎり、お寿司などに混ぜる・巻く」7割強、「みそ汁・汁物・スープに入れる」7割弱、「そのまま食べる」6割強、「酢の物、和え物」4割強、「トッピングとして、完成した料理にかける」「サラダ、野菜類に混ぜる・かける」各30%台。
■海藻類直近1年間摂取者が期待する効果・効能は「健康維持」5割強、「栄養の摂取」3割強、「生活習慣病予防」2割強、「血液サラサラ効果」「腸内環境改善、便通改善」約16%。購入時の重視点上位は「味」「価格」が全体の各5割強~6割弱、「国産である」4割弱、「品質」3割弱、「原材料、成分、添加物」約25%。
-
- 調査時期:
- 2025年12月
- 設問項目:
-
おでんを食べる季節/冬におでんを食べる頻度/好きなおでんの具/自宅で食べるおでんのタイプ(準備方法)/自宅で最もよく食べるおでんのタイプ/自宅でおでんを食べる場面/市販のおでん購入時の重視点/自宅でおでんを食べるときの、楽しみ方・こだわり(自由回答設問)
- 結果概要:
-
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
冬におでんを食べる人は約65%。おでんを食べる人のうち、自宅調理は「市販の素利用」が46%で増加傾向。
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
■おでんを冬に食べる人は全体の約65%。「一年を通して食べる」約11%、「特に季節は決まっていない」約15%。冬におでんを食べる頻度は「月に2~3回」「月に1回程度」がボリュームゾーン。月1回以上は約65%、月2~3回以上は3割強、北海道での頻度が低い傾向。
■おでんを食べる人が好きなおでんの具は「大根」8割強、「たまご」7割強、「こんにゃく」5割、「厚揚げ」「もち入りきんちゃく」「さつまあげ」「ちくわ、焼きちくわ」などが各3割台。「厚揚げ」「牛すじ」などは西日本での比率が高く、
「ちくわぶ」は関東、「しらたき、糸こんにゃく」は北海道などでの比率が高い傾向。"
■自宅で食べるおでんの準備方法は「具材と、おでんの素や市販のつゆを購入し、自宅で調理」が46%で、過去調査と比べ増加傾向。「具材を購入し、つゆ・スープは自宅で作ったもので調理」が4割弱。「コンビニエンスストアの、店頭で調理されているおでんを購入する」は2割弱。
■自宅でおでんを食べる人の食べる場面は、「温まりたい」5割強、「いろいろな食材を食べたい」3割強、「鍋料理を食べたい」3割弱、「家族がそろう」2割弱。市販のおでん購入時の重視点は「味」6割弱、「価格」5割弱、「容量、サイズ」「具材の種類」各3割弱、「原材料」2割弱。
-
- 調査時期:
- 2025年12月
- 設問項目:
-
コンビニ調理品購入頻度/直近1年間に購入したコンビニ調理品/コンビニ調理品購入場面(直近1年間)/コンビニ調理品購入時の重視点/直近1年間でコンビニ調理品を購入したことがあるコンビニエンスストア/直近1年間でコンビニ調理品を最もよく購入したコンビニエンスストア/調理品が最もおいしいと思うコンビニエンスストア/コンビニ調理品の不満点(自由回答設問)
- 結果概要:
-
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
コンビニ調理品購入者の直近1年の購入は中華まん4割強、から揚げ3割強が上位。美味しさ評価はセブンが3割弱で1位、北海道ではセイコーマートが1位と地域差も。
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
■コンビニ調理品購入者は全体の8割強。月1回以上購入者は約36%、週1回以上購入者は全体の1割強。購入経験者が直近1年間に購入したものは「中華まん」4割強、「から揚げ」3割強、「フライドチキン」2割強、「コロッケ」「おでん」「店内調理のお弁当」「店内調理のおにぎり」各2割弱。
■コンビニ調理品直近1年間購入者の購入場面は「ちょっとおなかがすいたとき」3割強、「温かいもの、冷たいものが食べたい」3割弱、「食事のおかず・一品として」「すぐ食べたい」「食事を軽く済ませたい」各2割強。
■コンビニ調理品直近1年間購入者の重視点は「味」「価格」が各6~7割、「分量、サイズ」3割強、「品揃え(調理品目の種類)」「持ち歩きしやすい、手で持って飲食しやすい」「原材料」が各1割強。
■調理品が最もおいしいと思うコンビニは、全体では「セブン‐イレブン」が3割弱、「ローソン」「ファミリーマート」各1割前後、「わからない」が4割弱。北海道では「セイコーマート」、四国では「ローソン」が1位。直近1年間最頻購入店舗が最もおいしいと回答した人の比率は、セイコーマート主利用者が7割強、セブン‐イレブン主利用者が6割強。
-
- 調査時期:
- 2025年12月
- 設問項目:
-
コンビニエンスストア利用頻度/商品・サービスをよく利用するコンビニエンスストア/信頼性・安心感があると思うコンビニエンスストア/商品開発力や企画力があると思うコンビニエンスストア/独自性があると思うコンビニンスストア/革新的・先進的であると思うコンビニエンスストア/顧客サービスが充実していると思うコンビニエンスストア/最も利用したいコンビニエンスストア/最も利用したいコンビニエンスストアの理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
商品開発力はセブンが約46%で1位だが、他社との差は縮小傾向。
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
■『信頼性・安心感』があると思うコンビニは全体では「セブン‐イレブン」(約56%)が1位、「ローソン」5割弱、「ファミリーマート」4割強。近畿・四国では「ローソン」、北海道では「セイコーマート」が1位。『商品開発力や企画力』は「セブン‐イレブン」(約46%)が1位だが2022年調査より減少し、続く「ローソン」4割強、「ファミリーマート」3割強との差が縮小。
■『独自性がある』は「セブン‐イレブン」「ローソン」が各20%台。「セブン‐イレブン」は2017年調査以降微減傾向で、増加傾向の「ローソン」と僅差となっている。「ファミリーマート」2割弱。北海道では1位「セイコーマート」が約65%と特に比率が高い。
■『革新的・先進的である』『顧客サービスが充実している』と思うコンビニは、全体では「セブン‐イレブン」が各3割強で1位、「ローソン」「ファミリーマート」が各2割弱~3割弱で続く。「特にない」が各5割前後と高い。北海道では「セイコーマート」の比率が高く、『顧客サービスが充実している』の1位、『革新的・先進的である』の2位。
■生活圏にあった場合最も利用したいコンビニは「セブン‐イレブン」が3割強だが2022年調査よりやや減少。「ローソン」2割強、「ファミリーマート」約15%。北海道では「セイコーマート」、四国では「ローソン」がそれぞれ1位。
-
- 調査時期:
- 2025年12月
- 設問項目:
-
家電量販店の利用頻度/直近1年間に利用した家電量販店/直近1年間の最頻利用家電量販店/直近1年間の最頻利用家電量販店の利用理由/家電量販店利用目的/直近1年間に家電量販店の店頭で購入したもの/家電量販店店頭で商品購入時の、事前の情報収集手段/家電製品購入場所/家電量販店を利用してよかった点・理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
家電製品購入場所は量販店店頭が7割弱で根強い一方、外部オンラインショッピングサイト利用も4割弱まで拡大
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
■家電量販店月1回以上利用者は1割強で、過去調査と比べて減少傾向。家電量販店直近1年間利用者の利用目的は「家電製品や関連用品を購入」7割強、「実物を見る」6割弱、「価格を確認」3割強、「家電に関する情報収集」2割弱。
■家電量販店直近1年間利用者の最頻利用店利用理由は「家から近い」5割強、「ポイントカードなどのお得なサービス」「交通アクセスがよい」各3割強、「駐車場」3割弱、「品揃えが豊富」「価格が安い」が各2割前後。ビックカメラ主利用者、ヨドバシカメラ主利用者では「交通アクセスがよい」「ポイントカード・会員特典などのお得なサービス」「品揃えが豊富」が上位3項目。
■直近1年間に家電量販店店頭で家電を購入した人の事前情報収集は、「店頭の商品、商品情報」3割弱、「店員の説明」2割強、「メーカーの公式ホームページ」「折込チラシ、ダイレクトメール」各2割弱。
■家電製品・関連用品購入場所は「家電量販店の店頭」が全体の7割弱、「家電量販店や家電メーカー以外のオンラインショップ」が4割弱、「家電量販店のオンラインショップ・通販サイト」が2割強。
-
- 調査時期:
- 2025年12月
- 設問項目:
-
医療保険加入状況/主加入医療保険会社/主加入医療保険の満足度/医療保険加入時の申し込み経路/医療保険加入・見直し意向/加入したい医療保険会社/医療保険加入時の商品選定の決め手/医療保険加入時のインターネット利用意向/主加入医療保険の加入理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
生保申込みまでネット完結を望む人は全体の3割強。
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
■医療保険加入者は全体の7割弱、医療保険単独加入が4割弱、特約が2割弱。医療保険加入者の商品加入継続意向は6割強。未加入者の新規加入意向は1割強。
■医療保険加入経路は「知り合いや紹介を受けた営業職員、販売員を通じて」が加入者の2割強。ライフネット生命主加入者、楽天生命主加入者などでは「インターネットで申込み手続き」が各6割前後と高く1位。プルデンシャル生命主加入者では「知り合いや紹介を受けた営業職員、販売員を通じて」の比率が他の層より高い。
■医療保険商品選定ポイントは「月々の保険料が安い」が全体の6割弱、「病気での入院給付金日額が十分」「十分な額の手術給付金がある」が各2割強、「商品内容がわかりやすい」「日帰り入院も保障」「払込期間が終身」などが各2割弱。
■医療保険加入時「情報収集から申し込みまですべてインターネットを利用したい」は全体の3割強で、ライフネット生命主加入者、楽天生命主加入者、県民共済主加入者などで比率が高い。「ネットで情報収集し最終的には販売員などに相談」は約24%。
-
- 調査時期:
- 2025年12月
- 設問項目:
-
知っている生命保険会社/生命保険加入状況/加入している生命保険会社/「信頼性や安心感がある」と思う生命保険会社/「商品開発力や企画力がある」と思う生命保険会社/「独自性がある」と思う生命保険会社/「革新的・先進的である」と思う生命保険会社/契約したいと思う生命保険会社/最も契約したい生命保険会社の選定理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
信頼性・安心感では日本生命、県民共済が各20%台で上位。商品開発力はアフラックが約16%で最も高い。
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
■生命保険加入率は全体の7割強。「現在の会社との契約を継続したい」が7割弱。最も契約したい生命保険会社は「県民共済」「アフラック」「日本生命」「ソニー生命」などが上位。
■『信頼性・安心感がある』生保は、「日本生命」「県民共済」が各20%台、「第一生命」約17%、「アフラック」約15%、「明治安田生命」「住友生命」「こくみん共済coop」「かんぽ生命」約12~14%。
■『商品開発力・企画力』があると思う生保は「アフラック」約16%、「日本生命」約8%、「ソニー生命」7%、「ライフネット生命」「第一生命」それぞれ約5%台。「いずれもない」は約55%。
■『独自性がある』『革新的・先進的』と思う生保はどちらも「アフラック」が最上位。2位以下は『独自性』は「県民共済」「ライフネット生命」「ソニー生命」などが続く。『革新的・先進的』は「ライフネット生命」「ソニー生命」などが続く。『革新的・先進的』は「いずれもない」が6割強と高い。
-
- 調査時期:
- 2025年12月
- 設問項目:
-
サプリメント利用状況/サプリメントで摂取している成分・素材/サプリメントの摂取頻度/サプリメントの利用目的/サプリメントの効果/サプリメント直近1年間購入場所/サプリメント選定時の重視点/サプリメント利用意向/サプリメント利用意向の理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
サプリメント利用者は約36%。効果を実感している人は5割で、非実感は約15%。
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
■サプリメント現在利用者は全体の約36%、女性の方が高く、10・20代で低い傾向。利用者が直近1年間に購入した場所は「インターネット通販サイト、オンラインショッピング」約46%、「ドラッグストア」3割強、「メーカーに直接注文」2割強。
■サプリメント現在利用者の摂取成分・素材は「ビタミンC」3割強、「ビタミンB群」約24%、「DHA」「亜鉛」各2割前後、「ビタミンE」「ルテイン」約16%。過去調査と比べ「亜鉛」などが増加傾向、「ブルーベリー」などが減少傾向。
■サプリメント現在利用者の利用目的は「健康維持」7割強、「免疫力・抵抗力向上」2割強、「目の健康の維持・改善」「疲労回復」各1割台後半。利用者の重視点は「効果・効能」7割弱、「価格」「成分」各5割前後、「メーカー・ブランド」4割強、「安全性」3割弱、「飲みやすさ」が2割強。
■サプリメント利用者のうち、求める効果を実感している人は5割、実感していない人は約15%。サプリメント利用意向者は全体の約36%。女性30代では5割強と高い。
-
- 調査時期:
- 2025年12月
- 設問項目:
-
風邪をひいた時の対処方法/風邪薬の利用状況/直近1年間に利用した風邪薬/直近1年間の最頻利用風邪薬/風邪薬の購入場所/市販の風邪薬選定時の重視点/市販の風邪薬を利用するタイミング/市販の風邪薬の不満点(自由回答設問)
- 結果概要:
-
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
市販の風邪薬利用者は8割弱、直近1年利用は5割弱。利用タイミングは軽い症状時が7割弱。
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
■風邪をひいた時の対処方法は「睡眠を十分とる」「市販の風邪薬を利用」が各6割弱、「病院・診療所などの医療機関に行く、処方薬を利用する」「安静にする」が各4割台半ば。
■市販の風邪薬利用者は8割弱。直近1年間利用者は5割弱で、2021年調査よりやや増加。
■市販の風邪薬直近1年間利用者の重視点は、「効能・効果」約65%、「価格」約35%、「成分」3割弱、「飲みやすさ」「錠剤、粉末、液体など、形状」が各2割強。購入場所は「ドラッグストア」85%で2021年調査より増加。「薬局」は過去調査より減少傾向。
■市販の風邪薬直近1年間利用者が利用するタイミングは、「軽い鼻水、せき、のどの痛み、だるさなどを感じる」7割弱、「鼻水、せき、のどの痛み、だるさなどがひどい・つらい」5割弱、「熱がある」3割強。
-
- 調査時期:
- 2025年12月
- 設問項目:
-
よく身につけるスポーツブランド/スポーツブランドへの関心度/よく身につけるスポーツブランドのアイテム/スポーツブランドのアイテムを身に着ける場面/スポーツブランドのアイテム購入頻度/スポーツブランド選定時の重視点/一番好きなスポーツブランド/好きなスポーツブランドのイメージ/気に入っているスポーツブランドのアイテム・気に入っている点(自由回答設問)
- 結果概要:
-
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
スポーツブランド関心層は2割強。好きなブランドはアディダス、ナイキ、ニューバランスが上位。
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
■スポーツブランド関心層は全体の2割強、非関心層は56%。スポーツブランドのアイテムを身に着ける人は全体の約64%。「靴・シューズ、スニーカー、ブーツ、サンダル」7割弱、「Tシャツ」「ジャージ、スウェット」各3割強、「スポーツ用ウエア」「アウター」各3割弱。
■スポーツブランドを身に着ける人のうち「日常のファッション」「スポーツ・運動」の場面で着る人が各40%台、「動きやすい服装がよい時」が3割弱、「アウトドア」「家にいる時」がそれぞれ約20%。過去調査と比べ「スポーツ・運動をする時」「アウトドア」などが減少傾向。
■スポーツブランドのアイテム購入者は全体の8割弱。スポーツブランド選定時の重視点は「デザイン」「品質」「価格」各5割前後、「サイズ」4割強、「動きやすさ、伸縮性」「耐久性」「色・生地の柄」が各3割前後。
■一番好きなスポーツブランドは、「アディダス」「ナイキ」「ニューバランス」が上位。一番好きなブランドの上位3位(アディダス、ナイキ、ニューバランス)のイメージは、いずれも「信頼性・安心感がある」「品質・技術が優れている」が上位2位。ナイキは「デザイン性が高い」、アディダス、ニューバランスは「親しみやすい」が続く。
-
- 調査時期:
- 2025年11月
- 設問項目:
-
市販のコーヒー飲料の飲用タイプ/チルドコーヒーの飲用頻度/チルドコーヒーを飲む場面/直近1年間に飲んだチルドコーヒーの銘柄/直近1年間に最もよく飲んだチルドコーヒーの銘柄/チルドコーヒー購入時の重視点/チルドコーヒー飲用理由/チルドコーヒー飲用意向/チルドコーヒーを飲むシーン(自由回答設問)
- 結果概要:
-
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
チルドコーヒーの飲用者は全体の約46%、
重視点は「価格の手頃さ」と「ミルクとコーヒーのバランス」が上位。
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
■チルドコーヒーの飲用者は全体の約46%。飲用者のうち週1本以上飲用者は2割強、若年層での飲用頻度が高い傾向。飲用者では「おやつの時」「ちょっと一息つきたい時」「仕事・勉強・家事の合間」「気分転換したい時」に飲む人が各20%台。
■チルドコーヒー飲用者の飲用理由は「おいしい」が5割弱、「価格が手頃」が約25%、「好きな味のタイプがある」「味が本格的」「ストローがついていて飲みやすい」などが各2割前後。マウントレーニア主飲用者では「好きな味のタイプがある」の比率が高い。
■チルドコーヒー飲用者の重視点は「価格の手ごろさ」4割強、「ミルクとコーヒーのバランス」4割弱、「コーヒーの味の強さ」3割強、「飲み慣れている」2割強。マウントレーニア主飲用者では「ミルクとコーヒーのバランス」が1位。
■チルドコーヒー飲用意向者・非飲用意向者はいずれも全体の4割弱。飲用意向者の比率は女性10~50代で高く、飲用頻度が2~3か月に1本以上の層では80~90%台、非飲用者では約5%。
-
- 調査時期:
- 2025年11月
- 設問項目:
-
自宅でパスタ料理を食べる頻度/自宅で食べる際の好きなパスタの種類・ソース/パスタソースの準備方法/市販のパスタソース利用頻度/自宅で利用した市販のパスタソースの種類/市販のパスタソース利用場面/パスタソース購入時の重視点/自宅でパスタを食べる際の、市販のパスタソース利用意向/市販のパスタソースのお勧め/利用しない理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
市販パスタソースは自宅でパスタを食べる人の約74%が利用、
食事を簡単に済ませたいときやすぐに食べたいときに利用
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
■自宅でパスタ料理を食べる人は全体の9割弱、週1回以上食べる人は2割強。市販のパスタソース利用者は、自宅でパスタを食べる人の約74%。利用するタイプは、レトルトパウチ入りのパスタソースの「ペースト状:温める」が5割強、「ペースト状:温めない」が約24%。
■自宅で食べるパスタで好きな種類は「ミートソース、ボロネーゼ」が6割強、「ナポリタン」が約55%、「たらこ・明太子」「トマトソース」が約44%、「カルボナーラ」「ペペロンチーノ」が各4割弱、「和風、しょうゆ味など」が3割強。市販のパスタソース利用者が直近1年間に利用した市販のソースは「ミートソース、ボロネーゼ」が6割弱。
■市販のパスタソース利用者について、利用頻度は「月に1回未満」「月に2~3回」がボリュームゾーン。利用場面は「自宅でパスタを食べる時はだいたい利用」5割強、「食事を簡単に済ませたい」「すぐに食べたい・すぐに準備する」が各30%台、「自分では作れないパスタソースを食べたい」2割強。
■市販のパスタソース利用者の重視点は「味」8割強、「価格」6割強、「容量、サイズ」3割強。市販のパスタソース利用意向者はパスタソース現在利用者の9割強、非利用者の約25%。
-
- 調査時期:
- 2025年11月
- 設問項目:
-
大豆食品に対する関心度/大豆食品として知らなかった商品/健康のために意識して飲食している大豆食品/食事における大豆食品の摂取度合い/大豆食品を意識して取り入れている理由/大豆食品購入時に気になること/大豆食品の魅力点/大豆食品で気に入っているもの(自由回答設問)
- 結果概要:
-
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
大豆食品の魅力は「手軽」「手頃な値段」が6割超で、
たんぱく質の豊富さも4割弱が評価。
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
■大豆食品の関心層は全体の67%で過去調査と比べ減少傾向。女性や高年代層で高い傾向。健康のために意識して飲食している大豆食品は「納豆」「とうふ」各6割強、「味噌」約35%、「油揚げ類」約25%。
■大豆食品の魅力は「手軽に食べられる」「値段が手頃」各60%台、「たんぱく質が豊富」4割弱、「安心して食べられる」「低カロリー」各2割強。
■普段の食事で大豆食品の摂取意識層は6割強。意識して取り入れている人の理由は「健康によい・よさそう」9割弱、「高たんぱく低カロリーだから」5割強、「ふだんの食事に取り入れやすい」3割強。
■大豆食品購入時に気になることは「価格」「味」各40%台、「原産国」4割弱、「遺伝子組み換え」「消費期限、製造年月日」各2割強。過去調査と比べ「価格」が増加傾向。
-
- 調査時期:
- 2025年11月
- 設問項目:
-
ビタミン類摂取の意識度合い/意識的に摂取しているビタミン類/ビタミン類の摂取量の状況/ビタミン類摂取のために意識的に摂取・利用しているもの/ビタミン類摂取のために意識的に利用している食材・食品・飲料/ビタミン類を意識して摂取する理由・きっかけ/ビタミン類の摂取による効果の度合い/ビタミン類の摂取について意識して行っていること/行っていない理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
ビタミン類摂取者が意識的に利用・飲食している食材・食品は
野菜類(緑黄色野菜など)7割弱、果物類5割強。
ビタミン摂取の効果実感は3割強、半数は「どちらともいえない」。
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
■ビタミン類の摂取意識層・非意識層はそれぞれ4割前後。女性では意識層が約半数、男性は非意識層が意識層を上回る。普段の生活でビタミン類を摂取していないと思う層は約34%で、摂取していると思う層(約26%)を上回る。
■意識して摂取しているビタミン類がある人は約54%。摂取内容は「ビタミンC」3割強、B1、D、B2、A、Eが各1割強。ビタミン類摂取者が利用しているものは「ビタミンが多く含まれる食材、生鮮・加工食品、飲料」約54%、「サプリメント、ビタミン剤、健康食品・飲料」5割弱、「栄養補助食品・飲料」15%。
■ビタミン類摂取者が意識的に利用・飲食している食材・食品は「野菜類(緑黄色野菜など)」7割弱、「果物類」5割強、「きのこ類」「豆類、ナッツ類」各4割弱、「大豆加工品」「精肉類:豚肉」「乳製品」「魚類」「卵」が各3割前後。
■ビタミン類摂取者の理由・きっかけは「健康維持」7割強、「免疫力維持・向上」5割強、「風邪予防、感染予防」4割弱、「肌、髪、爪などの健康のため」「疲労回復のサポート」各2割強。ビタミン類摂取者のうち、効果を感じた人は3割強、効果を感じない人は約15%で、「どちらともいえない」が半数。
-
- 調査時期:
- 2025年11月
- 設問項目:
-
薄型テレビ所有タイプ/薄型テレビ購入時期/薄型テレビ購入のきっかけ/主利用薄型テレビのメーカー/薄型テレビ画面で見るもの/薄型テレビ購入時に重視すると思う点/薄型テレビ購入予定時期/チューナーレステレビ所有状況・意向/主利用薄型テレビ選定理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
薄型テレビ所有者のうち、テレビ画面でDVD・BDを視聴する人は4割強、
YouTubeや映像配信サービスの利用も増加傾向
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
■「液晶テレビ」所有者は約84%、「有機ELテレビ」は約7%。購入のきっかけは「故障した」が購入者の4割強、「テレビが古くなった」約26%、「地上放送のデジタル化」「もっと大きい画面で見たい」各1割強。過去調査と比べ「故障した」が増加、「地上放送のデジタル化」「価格が安くなった」などが減少傾向。
■薄型テレビ所有者が、テレビ番組以外で見るものは「DVDやBD」4割強。「YouTubeなど動画共有サービス」「映像配信サービス」は各3割強で2019年調査以降増加傾向、若年層での比率が高い。
■今後の薄型テレビ購入予定者は全体の4割弱。薄型テレビを購入する場合の重視点は「価格」「画面サイズ」が各6~7割、「メーカー・ブランド」「画質のよさ」が各4割前後、「国内製品」「耐久性・故障のしにくさ」が各20%台。過去調査と比べ「画質のよさ」「ハイビジョン対応」などが減少傾向。
■チューナーレステレビ所有者は約4%、非所有・購入検討者は約8%。
-
- 調査時期:
- 2025年11月
- 設問項目:
-
美容家電への関心度・購入検討度合い/利用している美容家電/美容家電購入時の参考情報/直近3年間に購入した美容家電/美容家電購入場所/購入したい美容家電/美容家電購入時の重視点/おすすめの美容家電(自由回答設問)
- 結果概要:
-
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
美容家電関心層は約35%。
購入チャネルはインターネットショップが増加傾向。
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
■美容家電関心層は約35%、美容家電利用状況は、女性では「ヘアードライヤー」8割強、「ヘアーアイロン」3割弱、「電気シェーバー」約16%。男性は「ヘアードライヤー」約45%、「鼻毛シェーバー」約17%。男性30~70代では「利用していない」が各40%台。
■美容家電利用者の購入時の参考情報は「店頭で実物をみて」約35%、「通販サイト・ネットショップの商品情報、口コミ」「テレビ番組・CM」「商品比較サイト、家電レビュー・評価サイト」約22~25%、「メーカーのホームページ」2割弱。
■美容家電利用者のうち、直近3年間美容家電購入者は4割強。「ヘアードライヤー」購入者が約26%、「ヘアーアイロン」が約6%。若年層での比率が高い傾向。3年以内の美容家電購入者のうち「家電量販店の店頭」「インターネットショップ」での購入者が約43~44%。過去調査と比べ「インターネットショップ」が増加、「家電量販店の店頭」が減少傾向。
■今後購入したい美容家電は「ヘアードライヤー」2割弱。男性では「ヘアードライヤー」「鼻毛シェーバー」が上位2位。「ヘアーアイロン」「美顔器」「脱毛・除毛器」などは女性若年層での比率が高い傾向。購入意向者の重視点は「価格が手頃」「メーカー・ブランド」「性能・パワー」「大きさ、重さ」「操作のしやすさ」「手入れのしやすさ」などが上位。
-
- 調査時期:
- 2025年11月
- 設問項目:
-
マスク着用に関する意識/直近1年間でのマスク使用状況/外出時にほとんどいつもマスクを使う理由/直近1年間でのマスク使用場面/直近1年間に使用したマスクのタイプ/最もよく購入する市販のマスクの枚数(何枚入り)/マスク選定時の重視点/マスクに期待する効能・効果/マスクを使うときの工夫・こだわり(自由回答設問)
- 結果概要:
-
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
外出時のマスクは5割強が状況に応じて着用。
直近1年間のマスク使用場面は感染症流行時や人が密集する場所。
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
■マスク着用について「外出時、状況に応じて使う・使わないときがある」は5割強。「外出時はほとんどいつも使う」は約25%で、その理由は「新型コロナウイルスの感染予防」8割強、「(コロナ以外の)感染症の予防」約76%、「風邪の予防」6割弱などが上位で、「マスクをすることが習慣になっている」「花粉症などのアレルギー対策・予防」などが続く。
■直近1年間のマスク使用者の使用場面は、「インフルエンザ、新型コロナウイルスなど感染症流行時期」「人が密集する場所、大勢で集まる」が各50%台、「風邪など人に感染する症状や病気の人がいる」「自分が風邪など人に感染する症状や病気」が各40%台。2022年調査と比べ「人と会話する」「周りの人がマスクをしている」「他の人と食事をする」「人が密集する場所、大勢で集まる」などが減少。
■直近1年間マスク使用者のうち、「不織布マスク」9割弱、「プリーツマスク」「立体型マスク」「色つき・カラーのマスク」約13~16%。「大容量」購入者は約46%。
■直近1年間マスク使用者の重視点は「使い捨てタイプ」8割強、「価格」4割弱、「大きさ」「フィット感」「素材」が各20%台。期待する効能・効果は「細菌やウイルス、花粉、ハウスダストなどのカット率が高い」約66%、「息苦しくない」4割強、「耳が痛くならない」「フィットする」が各30%台。
-
- 調査時期:
- 2025年11月
- 設問項目:
-
自動車運転頻度/車を利用する場面/車を運転するのが好きか/車の所有率/所有している車のタイプ/車を持っていない理由/車購入時の重視点/今後車を購入する時の重視点/あなたにとって車とは/車を運転するのが好き・好きではない理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
運転が好きな人は6割弱。
車非所有の理由は「車を使う必要がない」「維持費がかかる」各4割弱。
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
■プライベートで自動車を運転する人は全体の約67%で、そのうちほとんど毎日運転する人は約36%、週1回以上運転する人は8割強。運転する人の利用場面は、東北、北陸では「通勤・通学」が他地域より高い。週に1~2回・3~4回程度運転する人では「日常の買い物」が最も多い。
■世帯の自動車所有率は7割強。車所有者のうち軽自動車所有者は3割強で、女性10~50代での比率が高い。車非所有の理由は「車を使う必要がない」「維持費がかかる」各4割弱、「免許を持っていない」「購入費用がかかる」各3割弱。
■車所有者の購入時・今後の購入時の重視点は「車両価格」「ボディタイプ」「メーカー、車種」「燃費のよさ」が上位。
■車を運転する人のうち、運転が好きな人は6割弱、好きではない人は2割弱。自分にとっての車とは「移動手段」7割弱、「生活必需品」「行動範囲を広げてくれる」各3割前後。運転が『好き』と回答した人では「プライベートな空間」「気分転換の一つ」「楽しみやワクワクを感じるもの」「自分の趣味やこだわりを表現するもの」も上位にあがっている。
-
- 調査時期:
- 2025年11月
- 設問項目:
-
宅配ピザチェーン直近1年間利用頻度/直近1年以内に利用したことがある宅配ピザチェーン/直近1年間での最頻利用宅配ピザチェーン/直近1年間の宅配ピザの利用場面/宅配ピザにネットで注文する理由/宅配ピザチェーン店利用時の重視点/最もおいしいと思う宅配ピザチェーン/宅配ピザの嗜好度/宅配ピザチェーン店の不満/利用しない理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
宅配ピザを好む人は全体の4割強で、
女性若年層で比率が高い傾向。
ネットでの注文者は約85%で過去調査より増加傾向
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
■宅配ピザが好きな人は全体の4割強、女性若年層での比率が高い。宅配ピザ直近1年間利用者は約25%、そのうち年1~2回利用者は約64%、月1回以上利用者は約14%。宅配ピザ直近1年間利用者が最もおいしいと思うのは「ドミノ・ピザ」(3割強)。北海道や東北では「ピザハット」が1位。
■宅配ピザ直近1年間利用者の利用場面は「家族といるとき」が5割弱、「ピザが食べたくなった」4割強、「大勢で集まる」「家でゆっくり過ごす」「クーポンがある」「夕食として」が各2割前後。
■宅配ピザ直近1年間利用者の利用時の重視点は「味が好み」6割弱、「価格」約46%、「生地がおいしい」「メニューが豊富」各30%台、「店が近い」「割引やおまけサービスが充実」が各2割強。
■宅配ピザ直近1年間利用者のうち、インターネットでの注文者は約85%、過去調査より増加傾向。ネットで注文する理由は「割引サービス、クーポンなどがある」が5割弱、「スマートフォンやパソコンから手軽に注文できる」「メニューを選びやすい・探しやすい」が各3割前後、「クレジットカードやスマホ決済などで支払える」「配達時間・状況がわかる」が各2割前後。
-
- 調査時期:
- 2025年11月
- 設問項目:
-
SNSの認知・登録状況/利用しているSNSサイト/SNS利用頻度/最頻利用SNS/SNS利用場面/SNSを利用する機器/SNSの利用内容/今後利用したいSNS/閲覧しているSNS/あなたにとってSNSとは(自由回答設問)
- 結果概要:
-
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
SNS登録者で1日2回以上利用者は約55%、
8割弱が毎日アクセスしている。
女性や若年層で利用頻度が高い傾向。
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
■SNS現在登録者は7割強。回答者全体に占める利用者は「LINE」約65%、「X」約36%、「Instagram」約33%、「Facebook」約27%。今後利用したいSNSは「LINE」5割弱、「X」「Instagram」約24~25%、「Facebook」約14%、「TikTok」8%。利用者・利用意向者とも、過去調査と比べ「Facebook」が減少傾向。
■SNS登録者のうち、1日2回以上利用者は約55%で、8割弱が毎日アクセスしている。女性や若年層で利用頻度が高い傾向。「スマートフォン」でアクセスする人はSNS利用者の9割強。
■SNS利用者の利用場面は「自宅でくつろいでいるとき」約56%、「暇なとき」「すきま時間」各3割台半ば~後半。10~30代では、複数の場面で他の年代より比率が高い傾向がみられる。
■SNS利用者の利用内容は「他人の投稿を読む」が約56%、「メッセージやチャット、DM等を個人同士・グループ内で送信・受信」36%、「他の人の画像や動画を見る」「他人の投稿にコメントやいいね!をする」が各3割弱。SNS認知者のうち投稿せず閲覧だけしているSNSは、「Instagram」「X」がそれぞれ約27%、「LINE」が2割強。
-
- 調査時期:
- 2025年11月
- 設問項目:
-
スキンケアに対する関心度/肌のトラブル・悩み事/肌のためにしていること/現在使用しているスキンケア用品/スキンケア用品に期待する効果/スキンケア用品購入時の重視点/スキンケア用品の1ヶ月あたり購入費用/スキンケア用品購入場所/スキンケア関連用品について困っていること・不満(自由回答設問)
- 結果概要:
-
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
スキンケア関心層は5割弱、女性は7割超。
スキンケア用品使用者が期待する効果は
「保湿効果」「アンチエイジング」「肌のハリ・ツヤのアップ」が上位。
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
■スキンケア関心層は全体の5割弱、女性約74%。男性では3割強で、男性30代が最も高い。悩み事は「シミ・そばかす」4割弱、「乾燥」「しわ」各3割弱、「たるみ」2割台半ば、「ハリがない」「くすみ」「クマ」「毛穴が目立つ」が各15~17%。
■肌のためにしていることの上位3位は「スキンケア用品を使用」4割、「紫外線対策」約25%、「規則正しい生活」「睡眠を十分とる」各2割前後で、いずれも女性が男性を大きく上回る。女性の上位項目は「スキンケア用品を使用」6割強、「紫外線対策」5割弱、「肌の保湿」3割強、「肌に負担のかからない化粧品を使用」「規則正しい生活」「睡眠を十分とる、夜更かししない」などが各3割弱。
■スキンケア用品使用者は全体の7割強、男性約55%、女性94%。男性の中では男性30代での比率が高い。「洗顔料・メイク落とし、クレンジング」「化粧水」は男性10~30代で各3割弱~4割弱。使用者が期待する効果は「保湿効果」4割弱、「アンチエイジング」「肌のハリ・ツヤのアップ」各3割弱、「紫外線対策、日焼け予防」「肌荒れ防止」「肌をなめらか・つるつるにする」「しわ改善・予防」「しみの改善・予防」が各2割前後。
■スキンケア用品使用者の購入時の重視点は「効能・効果」5割強、「肌との相性」4割強、「使用感」「品質・成分」各4割弱。購入場所は「ドラッグストア」がスキンケア用品購入者の6割強、「インターネット通販、オンラインショップ」が3割強、「スーパー」が1割強。
-
- 調査時期:
- 2025年11月
- 設問項目:
-
直近1年間にギフトを贈った回数/直近1年間にギフトを贈った機会/直近1年間にギフトを贈った相手/ギフト選定時の重視点/直近1年間のギフト選定時の参考情報/直近1年間に贈ったギフトを届けた方法/直近1年間に贈ったギフトの購入場所/直近1年間にプチギフトを贈った経験/直近1年間に贈ったプチギフトの内容・場面(自由回答設問)
- 結果概要:
-
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
直近1年間に贈り物をした人は6割強。
購入場所は「インターネットショップ、ネット通販」5割弱、
「デパートの店頭」「専門店・小売店」各3割弱
∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺∺
■直近1年間に何らかの贈り物をした人は6割強、過去調査より減少傾向。女性の方が比率が高い。贈った回数は年間「2~3回」がボリュームゾーン。直近1年間贈答者のうち「誕生日」に贈った人は約55%、「お中元・お歳暮」4割弱、「手土産・ご挨拶」「ちょっとしたお礼・お返し、プチギフト」「母の日」各2割強~3割強。
■直近1年間ギフト贈答者について、重視点は「相手の好みにあうか」約64%、「もらった人が喜ぶか」「贈り物の内容が状況にふさわしいか」が各5割弱、「価格が高すぎたり安すぎたりしないか」4割強。参考情報は「店頭の商品・説明」3割強、「相手の希望」「オンラインショップの商品情報、口コミレビュー」「家族・友人・知人の意見」各2割前後。「SNS、ブログ、YouTubeなど」は若年層での比率が高い。
■直近1年間ギフト贈答者の購入場所は「インターネットショップ、ネット通販」5割弱、「デパートの店頭」「専門店・小売店」各3割弱、「スーパーの店頭」「ショッピングセンター・モール」各2割弱。直近1年間にギフトを贈った人のうち、「直接会って渡す」は7割弱で、「宅配便や郵送、振込など」(6割弱)は2022年調査以降減少傾向。
■直近1年間にプチギフト実施経験者は、全体の約54%。女性の方が比率が高い。プチギフトの場面は「ちょっとしたお礼・お返しとして」3割弱、「訪問時や会うときの手土産として」「ちょっとしたお祝いとして」はそれぞれ約15%。
-
- 調査時期:
- 2025年10月
- 設問項目:
-
冷たい飲み物・温かい飲み物の嗜好度/冷たい飲み物飲用状況の時期による違い/冷たい飲み物の年間を通しての飲用状況/冷たい状態のものをいつも選ぶ飲み物/寒い時期に冷たいものを飲む頻度/寒い時期に冷たい状態で飲む物/寒い時期に冷たい状態のものを飲む場面/寒い時期に冷たい状態のものを飲む理由/冷たい飲み物の年間を通しての飲用実態・理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■冷たい飲み物派は4割強、温かい飲み物派(約25%)よりも多い。男性は冷たい飲み物派が約半数、女性は温かい飲み物派が約35%で冷たい飲み物派よりやや多い。冷たい飲み物を「主に暑い時期の方がよく飲むが、寒い時期にも飲む」は約45%で、男性の方が比率が高い。「主に暑い時期によく飲み、寒い時期にはほとんど飲まない」は4割弱で、女性や高年代層で高い。
■「年間を通して冷たいものを習慣的に飲む」は4割弱で、男性や若年層での比率が高い。「特定の時期や状況では飲むが、年間を通してではない」は5割弱。冷たい飲み物飲用者が、時期によらず冷たい状態で飲むものは「水、ミネラルウォーター」4割強、「麦茶、ウーロン茶」「緑茶、ほうじ茶、煎茶など」「コーヒー、コーヒー系飲料」「牛乳」各30%台。
■冷たい飲み物飲用者のうち、寒い時期に「ほとんど毎日」飲む人は4割弱、週1回以上は7割弱。寒い時期に冷たいものを飲む人が、冷たい状態で飲むものは「水、ミネラルウォーター」が3割強、「緑茶、ほうじ茶、煎茶など」「麦茶、ウーロン茶」「牛乳」「コーヒー、コーヒー系飲料」「炭酸飲料」「果汁飲料・ジュース、野菜ジュース」が各20%台。
■寒い時期に冷たいものを飲む人の飲用場面は「自宅でくつろいでいる」「お風呂あがり」「朝食時」「昼食時」「夕食時」「おやつ、間食」などが各2割強~3割強。冷たいものを飲む理由は「水分補給」「のどの渇きをすぐに解消したい」各4割前後、「冷たいものが好み」3割弱、「冷たくした方がおいしい」「体が暑いときに冷やしたい」「リフレッシュしたい」「ごくごく飲みたい」などが各2割強。
-
- 調査時期:
- 2025年10月
- 設問項目:
-
アルミパック入りゼリー飲料の飲用頻度/直近1年以内に飲用したアルミパック入りゼリー飲料銘柄/直近1年以内に最もよく飲用したアルミパック入りゼリー飲料/アルミパック入りゼリー飲料飲用理由/アルミパック入りゼリー飲料飲用場面/アルミパック入りゼリー飲料購入時の重視点/アルミパック入りゼリー飲料の飲用意向/アルミパック入りゼリー飲料の不満点・非飲用理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■アルミパック入りゼリー飲料飲用者は全体の約36%、そのうち週1回以上飲用者は15%。今後の飲用意向は全体の3割強で2019年以降微増傾向。若年層の飲用意向が高い傾向。
■アルミパック入りゼリー飲料飲用者の理由は「エネルギー補給ができる」4割弱、「摂りたい栄養成分が入っている」「味が好き」各3割弱、「食欲がない時や体調が悪い時でも飲みやすい」「すばやく短時間で飲める」「価格が手頃」が各2割強。1日分のビタミンゼリー主飲用者、カロリーメイト ゼリー主飲用者では「摂りたい栄養成分が入っている」が1位。
■アルミパック入りゼリー飲料飲用者の飲用場面は「体調が悪いとき、食欲がないとき」「おやつ、間食」が各20%台、「小腹がすいたとき」「疲れたとき」が約14~15%。アミノバイタルゼリー主飲用者やヴァーム主飲用者などでは、運動・スポーツの前後や途中の比率が高く、蒟蒻ゼリータイプを飲む人では「おやつ」「小腹がすいた」などの比率が高い。
■アルミパック入りゼリー飲料飲用者の購入時重視点は「味」6割強、「価格」5割弱、「フレーバー」「効能」が各30%台、「栄養素」「成分、添加物」などが各20%台。過去調査と比べ「カロリー」が減少傾向。
-
- 調査時期:
- 2025年10月
- 設問項目:
-
冷凍食品利用頻度/直近1年間に利用した冷凍食品の種類/自宅に常備してある冷凍食品の種類/冷凍食品利用場面/冷凍食品利用理由/冷凍食品購入時の重視点/直近1年間に購入した冷凍食品メーカー/冷凍食品の積極的利用意向/気に入っている冷凍食品・気に入っている理由/利用しない理由(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■冷凍食品利用者は全体の85%。週1回以上利用者は5割強。今後の積極的利用意向者の比率は5割強(「できるだけ幅広く、積極的に利用したい」約13%、「便利な部分は積極的に利用したい」4割強)、女性30~50代での比率が高い。「時々、必要な時だけ利用したい」は3割強、「あまり積極的には利用したくない」約6%。
■冷凍食品利用者が直近1年間に利用した種類は「麺類」「中華系の軽食・おかず」が各6割弱、「米飯類」が5割強、「あげもの類」「野菜類」「洋食系の軽食・おかず」が各30%台。自宅に常備してある冷凍食品は「麺類」4割強、「米飯類」「中華系の軽食・おかず」各3割強、「野菜類」3割弱、「あげもの類」2割強。
■利用場面は「夕食」6割強、「昼食」5割強。「食事を簡単に済ませたい」約25%、「料理を作るのが面倒」「すぐ食べたい」「お弁当」「ふだんの食事のメニューとして」「おかずの品数を増やしたい」などが各2割前後。冷凍食品利用者の理由は「保存がきく」約55%、「すぐにできあがる」「手順が簡単」各5割弱、「調理や後片付けの手間が省ける」「少量必要なときに便利」各30%台。
■冷凍食品利用者の購入時重視点は「味」「価格」各7割弱、「容量、サイズ」4割強、「原材料」「生産国・地域」「電子レンジ対応かどうか」などが各2割強。
-
- 調査時期:
- 2025年10月
- 設問項目:
-
ふだんの食生活/栄養バランスに対する意識/栄養バランスがとれている度合い/栄養バランスのとれた食生活の実施状況/栄養バランスのとれた食生活を実施している・したいと思うきっかけ・理由/栄養バランスのとれた食生活のために実施していること/栄養バランス維持にあたり困難・大変なこと・不満/栄養バランス維持のために直近1年間に利用した商品/栄養バランス維持のために気を付けていること・実施していること(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■栄養バランスについて気を付けていないと回答した人の食生活は、「一人で食事をする」「同じようなメニューを食べる・繰り返す」に加え、「炭水化物が好きでよく食べる」「インスタント・レトルト食品を食べる」「1日3食きちんと食べない」「食べる食材がほぼ決まっている、同じ食材をよく食べる」「野菜をあまり食べない」などが上位。
■食生活での栄養バランス意識層は5割強で、女性や高年代層で高い傾向。食生活で栄養バランスがとれている層は4割強で、60~70代で高い傾向。栄養バランスがとれていない層は約26%。
■栄養バランスのとれた食生活のための取り組み実施者は約35%、「実施したいと思っているが実施していることはない」は3割強。実施者のうち「野菜を中心に、肉・魚・乳製品などのバランス」が55%、「適度な量」「主食・主菜・副菜を組み合わせた食事」「毎日3食きちんと食べる」が各5割強、「たんぱく質・脂質・炭水化物などの栄養素のバランス」が46%。栄養バランス維持のために直近1年間に「サプリメント、健康食品」利用者は3割弱。
■栄養バランス維持にあたり困難なことは「栄養バランスに配慮した食事の準備や、メニューを考えるのが面倒・時間がかかる」「お金がかかる」各3割強、「どの栄養素が不足しているかがわからない」2割弱、「モチベーションを保つのが難しい」約16%。
-
- 調査時期:
- 2025年10月
- 設問項目:
-
魚介類の料理の嗜好度/魚介類の料理を食べる頻度/魚介類・魚料理を意識的に食べる度合い/好きな魚介類/魚介類購入時の重視点/魚介類の料理で好きなもの/魚介類のイメージ/魚介類に関して健康効果で期待していること/魚介類に関する不満点(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■魚介類の料理が「好き」は約46%で、調査開始以来最も低い数値。魚介類や魚介類の料理を食べる頻度が週2~3回以上の人は5割強で、過去調査より減少傾向。普段の食生活で魚介類・魚料理を意識的に食べている人は約半数、女性や高年代層で高い傾向。
■魚介類を食べる人が食べるのが好きな魚介類は「サケ」7割強、「サバ」「マグロ」「エビ」「サンマ」「アジ」各5割台半ば~後半、「イカ」「ウナギ」各5割強。魚介類をを食べる人が好きな料理は「刺身」「寿司」が各8割弱、「塩焼き」が7割弱、「フライ、唐揚げ」「天ぷら」各5割強、「照り焼き」「干物」各4割台半ば。
■魚介類を食べる人の購入時の重視点上位は「価格」「鮮度」各6割弱、「種類」「品質」各4割弱、「国産・外国産」「季節感・旬のもの」などが各3割前後。
■魚介類のイメージは「おいしい」「健康によい」各7割弱、「ヘルシー」4割弱、「季節感がある」「価格が高い」「栄養価が高い」各3割前後。魚介類の健康効果での期待は「生活習慣病の予防」5割強、「血液中の中性脂肪やコレステロールの改善」4割強、「脳の活性化、脳の健康維持」「カルシウムが豊富で骨や歯を丈夫にする」「良質のたんぱく質が豊富で体に良い」が各3割前後。
-
- 調査時期:
- 2025年10月
- 設問項目:
-
和食の嗜好度/好きな和食のメニュー/和食を食べるシーン/和食を食べる頻度/自宅で和食のおかずを食べる際の重視点/和食を意識して多く食べるか/和食を食べる割合が多い理由/和食のイメージ/和食の魅力(自由回答設問)
- 結果概要:
-
■和食が「好き」は6割弱で、過去調査と比べ減少傾向。好きな和食メニューは「寿司」8割弱、「刺身」「天ぷら」「うどん、そば」「ごはん」が各7割前後。和食のイメージは「庶民的」5割弱、「季節感がある」「ヘルシー」「素朴」「伝統的」各4割弱。過去調査と比べ「低カロリー」などが減少傾向。
■和食を毎日1回以上食べる人は5割弱、2022年調査より減少。東北、北陸では食べる頻度が高い傾向。和食を食べるシーンは「夕食」が8割強、「昼食」約45%、「外食」「旅行先」「朝食」が各30%台。「朝食」は東北で高く、近畿で低い。
■和食を食べる人のうち「意識して和食を多めにしている」は1割強、「特に意識していないが和食が多め」は4割弱、「和食と、和食以外が同じくらい」は3割弱。和食を食べる割合が多い人の理由は「和食が好き」7割強、「ご飯(お米)が好き」6割弱、「健康に良い」「ダシや味付けが好き」各4割弱、「栄養バランスが良い」「季節感が感じられる」「体にあっている」各3割前後。
■自宅で和食を食べる人の重視点は「味、おいしさ」7割強、「価格」4割弱、「栄養バランス」「季節感」「原材料」が各3割前後。